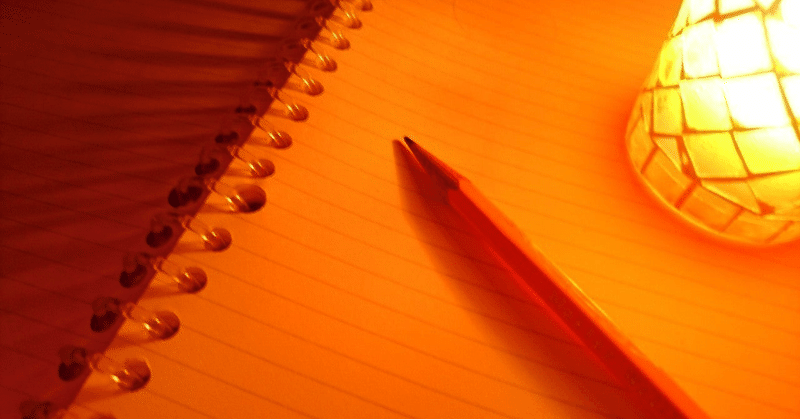
【書評】書きたいものを見極める『べらぼうくん』(万城目学)
変わった人だなあというのが読み始めた印象だった。
万城目学が小説家になるまでの紆余曲折が綴られたエッセイ集なんだけど、浪人したり(京大生だったことに驚き!頭いい!)、工場勤務したり、工業勤務で貯めたお金を引っ提げて上京して小説家を目指したり、行動力が半端ない。うらやましい。
でも節々に感じる「この人きっとおもしろい人なんだろうな」というテンション。関西人だからだろうか。独特のノリというものを文章から感じる。
実は私は彼の著書を一冊も読んだことがない。一昨年ぐらいに「バベル九朔」を読みかけたのだけど、結局読了せずに積ん読にまた戻ったままだ(本当にすみません。決しておもしくろくなかったわけではないです)。
だというのにこのエッセイを手に取ったのは、別の本で紹介されており、なんとなーく興味を持ったのだ。そしたら止まらなくなり、あっという間に読了してしまった。
おもしろいエッセイを書く作家と言えば、穂村弘とか三浦しをんとかがいるけれど、万城目学も決して負けていない。
京大に落ちて帰宅したら、ご飯の横に予備校のパンフレットが置いてあったくだりなんてちょっと吹き出してしまった。お母さん、お仕事が早いことで。
就職して寮で同室になった東大生との会話も、嫉妬が混じったような不愉快さに思わずうなずく。
おもしろいエピソードにこと欠かないエッセイだったけれど、なかでも私が印象に残った言葉がある。
私が自分が書きたいものを書きたい。
このシンプルな欲求があるだけで、書く仕事全般を志望していたわけではない。それこそ外為のように、それまでまったく興味のない分野の記事を書きたいかと問われたなら、さほど書きたくないというのが正直な心情である。
確かに文章に訓練にはなるだろう。でも訓練ならひとりでできる。
書評ライターをやっていたとき、この呼称に違和感があった。私はライターになりたいわけではなかった。書評が書きたくて仕事をもらっていたのにえいえんとリライト記事を書かされたこともあったからだ。
「これは呼称にライターがつくからなのか」と思い、脱却すべく努力をしたけど難しかった。ゆえに、書評の仕事は開店休業中なのである。
私は書評が書きたいのだ。ライターみたいに、様々な分野の記事は書くことはできない。わがままと思われるかもしれないけど、書く仕事すべてをしたいわけではないのだ。
そんな私の思いは万城目学がエッセイで肯定してくれた。
と、同時に、自分が何を書いていきたいかを見直すきっかけにもなった。
書評が書きたい。もしかして、ずっと未練のある小説も本当は書いていきたいのではないのか……?いろんな「書くこと」への思いがこの文章を読んで駆け巡った。
小説家とは特殊な職業である。
物語を書いて、それを読んでもらって、お金をいただく。
でもいちばんは、小説家自身が「書きたい」と思う文章を熱意を持って書いているからこそ、読者は心から楽しめるのだろうなと思った。
とりあえず私は積ん読の万城目学の小説を読もうと思う。
西桜はるう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
