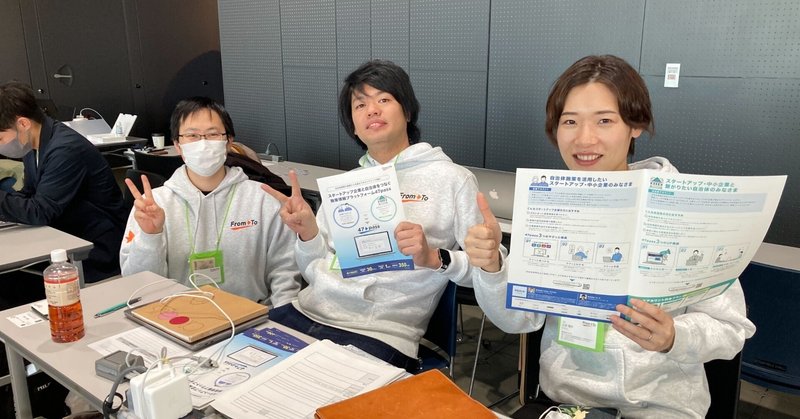
ALL JAPANで日本を元気に!スタートアップ創出の課題とは。
こんにちは!FromToの八木です^^
先日、2/2(木)@渋谷QWSにて、「JAPAN STARTUP SELECTION(以下、JSS)」に浜松代表としてイベント参加をしました。
「JSS」とは各地域のスタートアップ企業と全国の大手企業・投資家などとの協業促進を目的としたビジネスマッチングイベントです。
コロナ禍でオンラインで開催していましたが、3年ぶりのリアル開催となり、当日は200名を超える自治体職員や、企業の方々がご来場され、熱気に満ち溢れていました!
弊社もイベント出展のために、プロモーション動画を作り、パンフレットを作り、ピッチ資料も作りと、満を持しての参加となりました。

追い込まれるとやる典型的なパターンですね笑
当日にピッチ登壇した代表宮城の記事はこちら
今回は、本イベントを通して感じた、
スタートアップの成長に関する課題感と私自身で感じた使命感を徒然なるままに書いていこうと思います。
やっぱりすごいぞ福岡
本イベントでは日本を代表するスタートアップフレンドリー都市の福岡市 市長 高島 宗一郎氏もセッションに登壇されました。
福岡市は10年前からチャレンジを軸に経済発展をさせたいとスタートアップの創出・育成に力を入れ、実際にさまざまな施策を開始しました。
お互いのチャレンジを応援することで雰囲気が作られ、それが風土となり、仲間のチャレンジを讃えながら、刺激されながら、自分もチャレンジをしていく。
大事なのが、目には映らない雰囲気づくりがとても大事だということ。
そのコミュニティの場そのものがつくるリアルな熱量や生っぽさ。
その雰囲気が積み重なって風土となり、ビヘイビアチェンジ=行動の変革に繋がっていきます。
福岡は今や「スタートアップがアツい街」
まさに行動変革が起こっている街だと思います。
(その軌跡はとてつもないチャレンジだったと思いを馳せます)
福岡市のスタートアップコミュニティ形成について、福岡に移住した弊社の中田がnoteにまとめていますので、ぜひお読みください。
既存の法律がスタートアップを苦しめてる問題
スタートアップは、これまでに無かった概念や技術を社会に投入する企業です。
よって今存在している既存のルール・法律では立ちゆかないことも当然出てきますよね。
同イベントで登壇したつくば市 市長 五十嵐 立青氏も
「今はロボットが歩く後を人間が付いていかないといけない法律になっている。これでは新しい産業の芽が生まれない」
とおっしゃっていました。
つくば市では日本では実証実験ができないと、シンガポールに進出した企業もいるそうです。
新たな技術の登場により、社会の価値観が変われば、ルールの変更は必須になってきます。スタートアップが新技術で新市場をつくるためには、事業の成長だけでなく、社会の慣習や規則とどう折り合いをつけるかもとても重要です。
まさにこの部分は行政と一緒になって向き合っていかなければいけない部分です。
2022年6月経済産業省は、
スタートアップなどが技術の浸透に向け、規制改革に動くための枠組みとして、以下を紹介しています。
・期間や地域を限定した実証実験を通じて事業化の可能性検証や規制緩和につなげる「規制のサンドボックス制度」
・規制適用の有無を所轄官庁に確認できる「グレーゾーン解消制度」
・規制の特例措置を求める「新事業特例制度」
まだまだ利用数は圧倒的に少ない状況です。
スタートアップと自治体と一緒に進めていきたいですよね。
そもそも人材流動が起きていない
日本の定年雇用の文化、
挑戦の機会損失によるストレス耐久と自己肯定感の低さ、
マネーリテラシーやキャリアリテラシーの低さ、
女性の社会進出の低さ、
などなど様々な要因はあると思うものの、
まず、人の流動が市場で起きていません。
人が流れるから、新産業が成長していくのであって、
逆にいうと、どんどんスタートアップやスタートアップを支援するような市場へ人が流れていかないと伸び代がないといったことになります。
日本のエンゲージメントの低さは世界でもトップクラスに悪いのに、
転職市場の顕在化している母集団約300万人(潜在母集団は600万人と言われている)に対し、実際に転職を実行しているのはその内の5%です。
好きでも何でもない、かつモチベーションもない会社に勤め続けている人が
どんなに多いのか。数字だけ見れば悲しくなるのですが、
それは先に記載したように様々が紐が絡まって起きている事実です。
個人からALL JAPANへ
人材流動のためには、やっぱり挑戦する人に触れていくことが大事だと思います。
これは、単にスタートアップ同士がつながることだけはありません。
例えば企業に勤めていて、その後独立した先輩を囲んで飲み会を行う、起業家を多く輩出する大学を覗いてみるなど、非公式なものも多く含んだコミュニティが形成されることによって、
起業が身近になる→まずは知人のスタートアップに転職してみよう→次は自身で起業をしてみようといった好循環が生まれてきます。
地方においてはまだまだ起業する人が少ないですよね。
私も地方で大企業からスタートアップへキャリアチェンジをした時はもう、周りから「大丈夫?!」という意見を散々もらいましたが、元同僚は影響を受けて副業を始め、今では起業も考え始めています。
同僚から始まり、地域内へ、そこからプレイヤーの壁や、地域の壁を超えて、より幅広いコミュニティ形成につながっていき、結果として、個人の成長と共に新産業への流動も起こっていくのだと考えます。
個人からALL JAPANで日本を元気にすることへ繋がっていく大きなうねりになっていくのでしょう。
これがイノベーションですよね。
最後に
ALL JAPANという言葉がイベントの中でとても気に入りまして。
熊本市長が、「ALL 熊本、ALL九州、ALL JAPANで挑戦していく」とおっしゃっていて「これもらい」と早速使ってみました。
「日本全国に新たなビジネスエコシステムを創る」をビジョンに掲げている弊社。まさに地方からALL JAPANを元気にしていきたいと思っています。
そしてそのために弊社も私も挑戦していきます!
イベント後はイベント出演者と懇親会でした。
たくさんの起業家の方と話せてとても有意義な時間でした。
やっぱり皆さんとても楽しそう!楽しいは最高ですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
