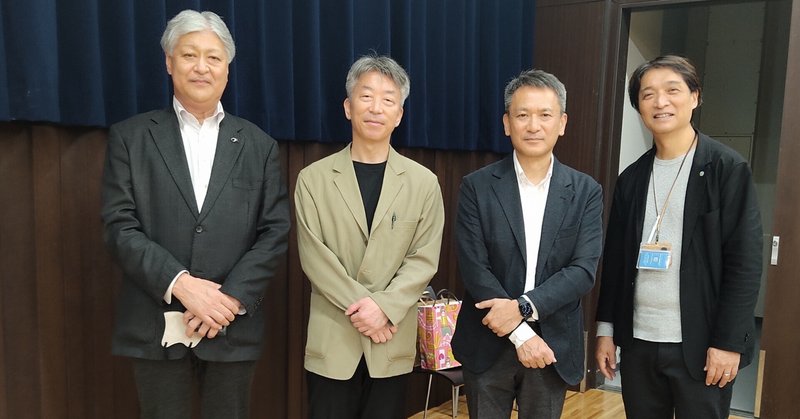
これが横浜創英 #センセイを捨ててみる。
住宅街の中にある小高い丘につながる坂道を少し上ると、その学校はあった。
受付時刻まで、まだ30分近くある。5分くらい門の外から校舎をジロジロ見ていたら、当然のように入口にいた警備の方と目が合った。
用件を伝えると、幸い、中に入れてもらうことができた。
校舎に入ってすぐ右側に、応接室。学校のパンフレットや賞状、トロフィーが飾られたガラスケース。広く、明るく、小ざっぱりとしたその部屋に30分近く座っているのは何となく落ち着かず、窓のすぐ外に見える、人工芝のピッチへ出てみる。
30年の教員生活のうち、縁あって半分の年数をサッカー部顧問として務めてきた私にとって、サッカーグラウンドはたくさんの思い出が詰まった場所だ。サッカー用具を眺めながら外周をゆっくりと歩くと、穏やかな気持ちになれる。

そうしている間にも、生徒はどんどん登校してくる。誰もが高台にある校舎の生徒玄関を目指して、坂道を上る。
8:30近くになると、生徒の姿がほとんど見えなくなってきた。この時間が始業だろうか? こちらのスケジュールも同じ時刻がスタートだ。応接室へ戻ると、大勢の教員が「その時」を待っていた。
今日は、横浜創英中学高校の教職員向け学校視察日。
月1回の実施で年内最後の日とあって、視察参加者は約70名。その範囲は東北から九州に及ぶ。
そこに集まった教師たちすべてが、「何か」に期待している。噂では聞いている。校長は著書も多い。基本的な考え方は誰もが事前学習済みだろう。
でも、実際に足を運んでみないとわからないことが、世の中にはたくさんある。私が休暇を取って参加したのも、「この目で見たい」と強く思ったからだ。でも、「見たい」のは授業風景じゃない。生徒の様子でもない。
見たかったのは「人」であり、聴きたかったのは「人の言葉」。
私は「人」に会うためにここへ来た。

視察参加者は講堂に集められた。
ここから先は、私のメモをもとにキーワードのみを書き連ねる。
8:55
山本崇雄・校長補佐の話が始まる。
テーマは、「自律を目指した横浜創英の学び」
・公務員の限界を感じ、私学へ
・「教えない授業」を目指す
・生徒中心を実践するため「引率のないスタディ・ツアー」を実施
・視覚障碍者に視力を提供するアプリ「Be My Eyes」の紹介
・場面緘黙当事者をサポートするアプリ「Be Free」を開発した上田蒼大くん(小5)の紹介と生徒の可能性
・ImpossibleをPossibleに変える
・生徒に身につけさせたいスキルは、①助けてもらう、②行動する
・インクルージョン社会を目指すのは学校から
・ワクワクを大切にする、ノルマやルールがない場をつくる
・サボるわけではなく、楽しそうに働く
・「自分で見つけた方法」で学ぶ
・スタバのような、「認め合いと居場所づくり」を大切にする
・ネット動画の誘惑を超えるセルフコントロールを生徒育成の幹にする
・目標を達成する。プロセスは自由に
・繰り返すことで「そのこと」「その回路」が太くなる
・生徒は「教える」「対話する」「個人で」「企業を」の、いずれかの教室で学ぶ
・教師が介入するのは「誰かの邪魔をするとき」だけ

9:20-10:10 英語の授業見学
10:10
本間朋弘・副校長の話。
テーマは、「新しい学校像を求めて 働き方改革」
・「人権宣言」を行い、校則ゼロを目指す
・生徒と社会をつなげる
・先端的かつ組織的に学校改革を進め、1年で終えた
・工藤校長の「しんどさや苦しみをオープンにしていこう」に共鳴
・2020年5月からテレワーク
・最上位目標は「教職員と家族の命を守る」
・2020年10月「先進的働き方推進メンバー」を構成
・「生徒のため」と言っているうちは働き方改革は進まない
・まず最初は「会議改革」
・「会議のやり方」をレクチャー
・分掌のトップが輪番で会議を回す
・情緒主義的学校観から、権利主義的学校観へ
・変化に立ち向かう子どもを教える教員は、社会に出なくてはならない。
・支え、させられる関係が大切
・理不尽を認め合う職場
・強みや好きを生かす職場
・オールマイティでなくていい
・私学の働き方は「労働基準法」に拘束される
・アラームが鳴り退勤時刻を知らせる勤怠システムの導入
・学校を軸として生徒を社会に解き放つ
・学校を通して社会をデザインする
・カリキュラムは自由選択制
・学年制の撤廃

11:15
工藤勇一・学校長の話
テーマは、「横浜創英中高が目指す教育」
・Agency(生徒主体の運営)
・実学教育(社会とリアルにつながる)
・衝突を恐れずに学校改革メンバーを構成する
・「見えない教育課程(ヒドゥン・カリキュラム)」がすべて
・日本教育の失敗は「当事者意識と主体性の欠如」
・2023年時点の大学数は622だが、2040年には240まで減少する
・「勝ち切る」ために、今までにない教育を志向する
・「痛みを覚悟する人材」を輩出していかなければならない
・主体性を与えないまま「知徳体」を教えようとする従来型学校教育
・教え込まれ続けるから日本の労働生産性が低いのは当たり前
・欧米の人間が主体的な理由
・日本の教育は、子どもが積むべき経験をすべて奪ってしまっている
・子どもに「聖人君子」を求める大人
・対話は、ピンチの時にしかできない
・しかし教職員はその「ピンチ」を避けようとする

その後、学校長・副校長・校長補佐の3人で鼎対談
これからの横浜創英の目標
〇在籍生徒1,600人分のカリキュラム作成
〇生徒の所在確認のためのQRコードシステム構築
〇成績管理システム構築
3人とも話好きな方々ばかりで、時間が許せばずっと持論を展開していくだろうと思われた(笑)。批判ではなく、理想とそれを実現するための方法論を終始述べているので、聴いている側の顔も自然に紅潮してくる。参加者の多くが、その場に居合わせたことを嬉しく感じていただろう。
全日程が終了したのは、予定通り12:30。
しかし、そのあとは想像通りで、多くの参加者が3人の前に列をなし、その場で聞きたかったことを直接、ぶつける時間に。
質問の時間が取れなかったのはご愛敬だ。私もいくつか質問を用意していたが、まず考えるのは、自分の質問が同時に他の多くの参加者のニーズを満たしているかどうか、だ。個人的でレアなケースを大勢の前で持ち出しても、誰も喜ばない。
何より、今回の視察の目的は、横浜創英を牽引するリーダーたちのパフォーマンスを体感することにあった。「誰が、何を言うか」。参加者はそれだけを聞くために集まっているからだ。

私は折を見て列に並んだが、すぐに後ろに何人かが並んだ。
当初聞きたかったことは5つ。
①中高一貫校は6年という短期間で結果が求められる。結果を出すことと学校改革をどのように合流させていくのか?
②経営サイドが変わった場合の理念継承について
③ヒドゥン・カリキュラムの原型になる考え方
④授業を通じて理念を伝えることはしていないのか?
⑤卒業生とどんな形でつながりを継続していくか?
だが、もう予定の終了時刻を40分近くも過ぎている。私の後ろにはまだ数人が並んでいる。結局、上記①から③に絞っての質問を工藤校長に。
3人のリーダーはみなそうだったが、質問を待たせている人たちに配慮しながら、しかし目の前の相手に対して端的に、真摯に、熱のこもった回答をしていた。これだけでも参加した甲斐があったと思う。
質問を終えた後、今回の視察の機会を作ってくれた本間副校長に挨拶して帰りたいと思い、山本校長補佐や他校の参加者と一緒に椅子を片づけ、結局会場を出たのが13:40。「70分の延長戦につきあうことが本当の仕事だ」というリーダーたちの信念がうかがえる。

こんな管理職に出会うと、いつも思い出すことがある。
✔ビジョンを示し、
✔フォロワーの力を最大限に発揮させること。
リーダーの仕事とは、究極的にはこの2つしかないと思う。
ビジョンとは、現状の閉塞感を打破するものだから、イノベーティブでなければならない。
マーケティング理論において、わずか2.5%しかいないイノベーターは「革新者」と呼ばれる。最初の提案者であり、ファースト・ペンギンだ。すぐに理解されることはないが現状を大きくプラスに転じる提案をして、マジョリティに希望をもたらす。
イノベーターの動きを感知して、いち早くそれに追随するのがアーリー・アダプター。彼らは次に追随するアーリー・マジョリティにイノベーションをわかりやすく「翻訳」するポジションにある。イノベーターの理念がマジョリティに浸透するかどうかは、アーリー・アダプターにかかっている。
視察参加者をアーリー・アダプターと考えるなら、次に乗り越えるべきは「キャズム」だ。
アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には大きな溝(=キャズム)があるとする考え方です。
イノベーターとアーリーアダプタ―は「新しい」というニーズを求めますが、他の層では「安心感」を求めるため、マーケティング方法を変える必要があります。この理由により商品やサービスが革新的なほど、残りの層では普及しにくく、この溝のことをキャズムと呼んでいます。
キャズムを乗り越えるためには84%の他の層のニーズである安心感を満たすことができるように商品やサービスの品質や信頼の高さをアピールしていくことが大切です。
学校教育がこのキャズムを乗り越えるには、大きな意識改革を伴うはずだ。それでも、横浜創英のビジョンが単に「新しい」ものとしてだけでなく、「それが自然で人間が成長するうえでの本質を捉えた試み」である限り、アーリー・アダプターは使命を感じ、「翻訳」を続けるべきだろう。

リーダーの仕事の2つ目は、フォロワーの力を最大限に発揮すること。
学校を変える、というのは、生徒を変えることではない。
生徒に影響力を行使する教師に働きかけることだ。
いつの時代も学校管理職に突きつけられてきた問いがある。それは、自身が受けてきた教育が(良くも悪くも)ベター(ベストと言い切れない点が切ない)だと思い込んでいる教師たちを、どのようにしたらビジョンに向かわせることができるのか?
という問いだ。
進学実績や部活動の実績のどちらを選ぶかという二項対立をはるかに超えた、多様な価値観と言う尺度が学校教育に入り込み、教師だけでなく生徒も保護者も戸惑っている時代。
おそらく、多くの教師たちは「これでよかったのか?」と疑念を抱きながら、過去の成功体験にすがりながら自身の殻に籠らざるを得ない。
元来、教育とは保守的なものだ。ならば教育に携わる人間も保守的にならざるを得ない。結果として、自身の成功体験か、自校とはまったく条件の異なる他校の成功例を参考に、授業を、進路指導を、部活動指導をやっていくことになる。

教職員は、一枚岩にはなれない。
経験だけで言わせてもらえば、これは動かせない事実だ。
だから、ビジョンが必要になる。それは最上位の目標としてメンバーの結束を促す。そしてリーダーは、フォロワーがそのビジョンに乗っかれるように働きかけなければならない。
凸凹のある教師たちをビジョンに向かわせる。
ならば、その凸凹を、そのまま受け取ることだ。
すべての教師が、自身の「好きで得意」に専念する。そういう環境を作る。
そのために何ができるのかを考えるのが、リーダーの仕事だ。
指示するのではない。
自由にさせるのでもない。
仲良くやるのとも違う。
リーダーの仕事は、フォロワーの能力を解き放つこと。
それさえ実現すれば、職員室の雰囲気は常にポジティブになるはずだ。
学校が目指すビジョンを実現させるために、自身の力を最大限に発揮しようとする。多くの教師は、そんな職場で働きたいと願うんじゃないだろうか。

現在、定時制高校に勤務している私の懸案は、横浜創英の取り組みとはほとんど重なることがない。
でも、「人を育てる」点では同じだ。「その子に合った将来を見せてやろうとする」ことも。
だから、こんな機会は無駄どころじゃない。
定時制をよくするために定時制を視察することも、
進学率を上げるために進学校へ視察に行くことも、
従来の思考から抜けきれない選択と言える。
そうではなく、まったく異なる「相手」から自身に必要な学びを引き出すことにこそ、イノベーティブな価値がある。
横浜創英がビジョンを叶えるプロセスを見続けながら、私は私のビジョンを叶えることにしたい。他の視察参加者も、アーリー・アダプターとして全国へ散っていき、与えられた場で各自の使命を展開することになる。
そう思うと、ワクワクしてくるんだ。

現役高校教師
協会ページ
https://t-c-m.my.canva.site/
ブログサイト
https://sensei.click/
ポッドキャスト(Spotify)
https://open.spotify.com/show/2pCy8yUiGRk3jKoVJo72VF
note
https://note.com/harukara1968
FBコミュニティ
https://www.facebook.com/groups/unlearnteachers
udemy
https://www.udemy.com/course/kqfpehod/
Amazon Kindle
https://www.amazon.co.jp/%25E3%2582%25BB%25E3%2583%25B3%25E3%2582%25BB%25E3%2582%25A4%25E3%2581%25AE%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25A2%25E3%2582%2592%25E6%259C%25AC%25E6%25B0%2597%25E3%2581%25A7%25E8%2580%2583%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B%25E5%258D%2594%25E4%25BC%259A/e/B0BPPDYHYD%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
オン&オフラインセミナー講師
心理学修士(学校心理学)
NPO法人日本交渉協会認定「交渉アナリスト」1級
https://nego.jp/interview/karasawa/
一般社団法人7つの習慣アカデミー協会主催
「7つの習慣®実践会ファシリテーター養成講座」修了
思いつきと勢いだけで書いている私ですが、 あなたが読んでくれて、とっても嬉しいです!
