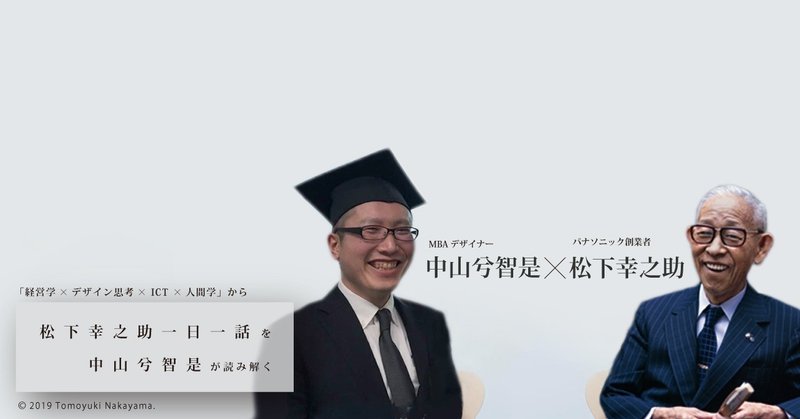
部下のために死ぬためには
松下幸之助 一日一話
11月 6日 部下のために死ぬ
経営者に求められるものはいろいろありましょうが、自分は部下のために死ぬ覚悟があるかどうかが一番の問題だと思います。そういう覚悟ができていない大将であれば、部下も心から敬服して、ほんとうにその人のために働こうということにはならないでしょう。経営者の方も、そういうものを持たないと、妙に遠慮したり、恐れたりして社員を叱ることもできなくなります。それでは社内に混乱が起こることにもなってしまいます。
ですから、やはり経営者たるものは、いざというときには部下のために死ぬというほどの思いで、日々の経営に当たるのでなければ力強い発展は期し得ないと思うのです。
https://www.panasonic.com/jp/corporate/history/founders-quotes.html より
松下翁は、経営者に必要となる覚悟のひとつとして、戦国時代の武将が、自分の命を捨てて部下の命を救うのが当然であったように、今の時代ならば、みずからの「職」をかけて事に臨ようでなければ経営者の資格はないとし、1976年に以下のような問答をしています。
――今春、経営トップに就任する予定です。そこでぜひ、指導者が備えておくべき要件についてお教えいただきたいのですが。
松下
ひと言でいって、指導者とは責任をとるということですな。責任をとれない人は、指導者たる資格はない。昔は、指導者の心得というのは、みんなのために死ぬということでしたわな。高松城水攻めの話はそのいい例です。
秀吉の毛利攻めで、水攻めにされた高松城は、食糧もだんだん尽きはてていき、城兵はただ死を待つのみとなった。
そのとき、城の守りの大将、清水宗治(むねはる)は、「わしの首と引き換えに、城兵を助けてくれ」と秀吉に申し出たんやな。秀吉は宗治の態度に感服し、”待ってました”とばかりそれを聞き入れた。
宗治は、みずから船をこぎ出して、船の上で従容として切腹したでしょう。それを見守っていた敵、味方の将兵はみんな拍手をした。自分の命を捨て、部下の命を救うというのが、戦国の武将の心がまえやったんですな。この宗治の精神が、指導者の精神だと思うな。「一将功なりて万骨(ばんこつ)枯る」というが、「一将死して万卒生きる」というのも一面の真理です。
一国の首相であれば国民のため、会社の社長なら社員のため、部長や課長なら部下のために、大事に際しては自分の命を捨てるんだ、という心意気をもたないとあかん。今はそういう指導者が出なければいかんですよ。
命をかけるといえば多少ウソになるというなら、命をかけんでも職をかける、指導者は当然、それをやらないといかん。その気がまえで臨めば、そのことに誤りがなければ成功しますよ。
(松下幸之助述「社長になる人に知っておいてほしいこと」)
上記の清水宗治が切腹したのが1582年。そこから約1,700年前中国前漢の武帝の時代に司馬遷によってまとめられた中国の歴史書である「史記」には次の言葉があります。
「士は己を知る者の為に死す」(史記)
この言葉は史記がまとめられる約300年前の戦国時代、晋の豫譲(よじょう:紀元前453年頃没)のお話が元であり、「自分のことをよくわかっていてくれる人。親友。知音。」という意味で使われる「知己(ちき)」の語源とされます。
松下翁の「部下のために死ぬ」覚悟とは、史記に擬えるのであれば「上司は己を知る部下の為に死す」とも換言できます。
この松下翁の「部下のために死ぬ」という思いは、部下の中でも特に、松下翁を支え続けた名補佐役であり、大番頭でもあった高橋荒太郎さんのことを思い浮かべて仰っているのではないでしょうか。高橋さんは松下翁から「松下電器の伝統の精神というものは、私以上に高橋さんがつくってくれた」という最大の賛辞を贈られたほどの人物だったそうです。
何故、高橋さんは松下翁から「知己」とまで認められていたのでしょうか?高橋さんは、ご自身の著書にて以下のような言葉を残されています。
私が一貫して確固たる”よりどころ”としてきたものは、松下幸之助創業者の経営理念に基づく基本方針であった。ほかに類をみないこの基本方針こそ、松下電器発展の大きな要素であると確信したからである。
以来、私は自分の小さな知恵才覚でものごとを判断するのではなく、松下電器の基本方針に沿って仕事をし、やった仕事をまたそれに照らして謙虚に反省し、検討するというやり方を通してきた。だからこそ、私のような者でも、そのときどきの重責を果たすことができたのだと思う。…
高橋さんは、松下翁の考え方と「経営理念」に感銘を受け、それを自らの行動判断の規矩とし任務を全うされたと謙虚に語っておられます。
他方で松下翁は、「経営理念」の大切さについて1980年に以下のような問答をしています。
――経営トップに就いて数年が過ぎました。しかしいまだに自分は経営者としての資質に欠けているのではと思うことがあります。経営者がもつべき資質や条件はたくさんあろうかと思いますが、松下さんが特に大切だとお考えになるものは何でしょうか。
松下
経営者として必要な資質・条件はいろいろ考えられますね。たとえば統率力、決断力、実行力、あるいは先見性、さらには徳というような人格的なものなど。
経営者である以上、完全無欠はもちろん望めないにしても、そういう要件はある程度ずつはもっていなくてはならないと思うんです。先見性はあるけれど、決断力に乏しいというようなことでは経営者としては失格ですから。
しかし、何がいちばん大切かということになると、私は経営理念やないかと思うんですな。企業は存在することが社会にとって有益なのかどうかを世間大衆から問われていますが、それに答えるものが経営理念です。つまり、経営者はほかから問われると問われざるとにかかわらず、この会社は何のために存在しているのか、そしてこの会社をどういう方向に進め、どのような姿にしていくのかという企業の基本のあり方について、みずからに問い、みずから答えるものをもたなくてはならない。いいかえれば、確固たる経営理念をもたなくてはならないということです。
さきに経営者として必要な条件をいくつかあげましたが、結局そうしたものも、正しい経営理念があってこそほんとうに生きてくるのではないでしょうか。たとえば決断力です。最高経営者にとって、次々と起こってくる問題に適切な決断を下していくことは不可欠の重要事です。経営者が決断しなくては物事が進まないし、誤った決断をすれば会社そのものを危うくすることもあります。けれども、経営者として最後の決断を下すのは実に孤独な仕事ですね。
それほどの孤独感を味わいながら決断を下していく根拠は何かということですね。もちろん、損得といいますか、いわゆるソロパン勘定はするでしょう。しかし、日常の小さな決断はそれでもいいけれど、最高戦略はそれだけではいけない。やはり何が正しいかということに立脚することが大切ですし、その根底をなすものは正しい経営理念ですね。常にそれに照らして判断を下すということです。
これは頭で考えたものでは本物にはなりませんね。やはり、その人の人生観なり、人間観、世界観といった奥深いところに根ざしたものであることが大切です。つまり、その人の人間そのものから生まれてきたといいますか、いわば血肉と化しているというほどでなくてはいけません。どんな立派な内容でも、単に言葉のうえでのお題目にすぎない経営理念では、生きた経営力には結びつかないと思いますな。
(松下幸之助述「社長になる人に知っておいてほしいこと」)
高橋さんの立場からみた「経営理念」、松下翁の立場からみた「経営理念」。両者の間には、共有する「経営理念」によって結ばれた固い絆があったからこそ「知己」となり、松下翁には「部下のために死して可なり」という覚悟が生まれ、また同時に高橋さんには恐らく「上司のために死して可なり」という覚悟もあったのではないかと私は考えます。
中山兮智是(なかやま・ともゆき) / nakayanさん
JDMRI 日本経営デザイン研究所CEO兼MBAデザイナー
1978年東京都生まれ。建築設計事務所にてデザインの基礎を学んだ後、05年からフリーランスデザイナーとして活動。大学には行かず16年大学院にてMBA取得。これまでに100社以上での実務経験を持つ。
お問合せ先 : nakayama@jdmri.jp
頂いたサポートは、書籍化に向けての応援メッセージとして受け取らせていただき、準備資金等に使用させていただきます。
