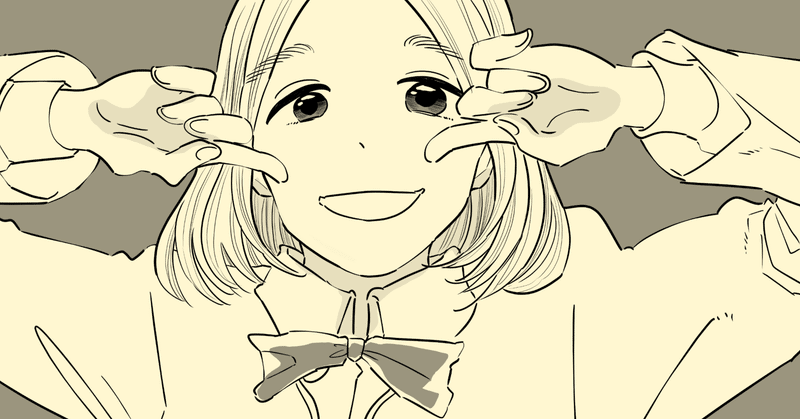
【小説】 ハッピーアイスクリーム・①なぞのシャウト
ハッピーアイスクリーム ①
帰るメンバーのいない高校生葛飾塔子が、校庭でなぞの言葉を叫ぶ声を聞いた。一人の帰り道、葛飾は光るモノを掲げる男に遭遇する。
(一応続きものなんですけど、
どこから読んでも問題ないような気がしてきました)
誰かに肩を叩かれたような気がして、窓際の後ろから二番目の席で眠っていた葛飾塔子は机に投げ出していた半身を起こした。
世界史教師は第一次世界大戦のころにスペイン風邪が大流行したという話をしている。
開け放たれた窓に顔を向けると、変に間延びした高い声が聞こえてきたが、何と言っているのかはわからない。葛飾は寝起きでこわばった身体を伸ばして窓の外を覗き込んだ。校庭の体育はたぶんテニスだと思うが、誰かが派手にボールを打ち上げでもして、今のかん高い声が出たのだろうか。目をとじて耳に神経を集中させると、葛飾は声がなんと言っているのかを聞き取ろうとした。
はじめの声は、おそらく「は」だろう。それに、小さい「っ」がついているから、「はっ」だ。
次は?「い」にも「き」にも「ひ」にも聞こえたんだけど、そのあとに続いた単語だけは、はっきりと聞こえた。
「あいすくりいむ」だ。そう、たしかにその声は、アイスクリームと言ったのだ。
ふたつの言葉をつなげると、「はっ」なんとか「アイスクリーム」か。
葛飾は、それをノートの端に書きとめた。世界史の教師がちらりと窓際の列に目をやったが、すぐに黒板に向き直った。真夏のもったりとした風が頬を撫でて、次の声がした。葛飾は電子レンジで白飯を温めながら耳だけで二時間サスペンスのストーリーを追いかけているときみたいに、窓際に向いている左耳に全神経を集め、ようやく、すべてをはっきりと聞き取ることができた。
はっぴい あいすくりーむ。
声は、「ハッピーアイスクリーム」と言っていた。
すぐにその言葉を書き留める。さて、ハッピーアイスクリームとはなんだ?
アイスの名前なのか。そんなアイスがあるかどうかは知らないが、まあ校庭で女子高生が連呼しているというだけなので、存在しているアイスとは限らない。
世界史教師ではない視線を感じ、葛飾がさり気なく教室を見渡すと、廊下側のいちばん前の席にいる片田さんがこちらを見ている。視線を合わせると、片田さんはさっと前を向いてしまったが、その前に、彼女の顔に疑問符が浮かんでいたのを葛飾は見逃さなかった。
彼女もまた、ハッピーアイスクリームを聞いていたのかもしれないと葛飾は思った。
このクラスで自分から誰かに話しかけたことはほとんどないけれども、昼休みになったら彼女に聞いてみようと葛飾は決心して前を向く。世界史教師が第一次世界大戦がスペイン風邪をより一層流行らせた、それは少し前に世界を駆け巡ったウイルスとちがって若い人をたくさん死なせたのだ、と言って話を締めくくった。
休み時間になると葛飾は片田さんのところに行き、ハッピーアイスクリームの話をしようとしたが、片田さんはすぐさま立ち上がって教室を出ようとしたので、向かう先は多分トイレだと目星をつけた葛飾も、連れ合うことにした。
「え、葛飾さんもトイレ?」
誰かとトイレに行くのも葛飾には珍しいことだったので、片田さんは少しばかり驚いている。
「うん、トイレ」
そっか、と頷きながら片田さんは歩き続ける。廊下の窓から、さっきと同じ生ぬるい風が流れてきて葛飾は目を薄めた。トイレに着く前に、ぜひともあれについて聞かなければならない。
「あのさ、ハッピーアイスクリームのことなんだけど」
「え。なに?」
振り向いた片田さんに向かって、ひるまず一気に打ち明ける。
「さっき校庭で、誰かハッピーアイスクリームって言ってたでしょ。それ、片田さんも聞いてたかなと思って」
片田さんは何を急にという顔で葛飾を見ると、
「ハッピーアイスクリームって、なに?」と言う。
「や。べつに。片田さんも聞こえたのかと思って」
なんかへんな顔してたし、という言葉を葛飾がかろうじて呑み込んでいると、片田さんは何かを考え込むような顔をしたものの、特にコメントはせず個室に入っていった。葛飾はそのままトイレから出た。今の片田さんの反応はおかしかった。普通ならハッピーアイスクリームって一体なんなの、それ葛飾さん聞こえたのとかなんとか、追求してくるはずではないか。
廊下をもと来た方向に歩きながら、片田さんも絶対に聞いたなと葛飾は改めて確信した。
★
葛飾の帰り道は、いつでも一人だ。帰るメンバーの友達がいないからだ。
帰るメンバーというのは、学校から駅までの帰り道を同行する生徒のことで、一度一緒に帰ると決めたメンバーは三年間代えることができない。仮にクラス替えのあとで新規に仲良くなったとしても、その友達と帰り道のルートが同じという保証はない。部活や文化祭の準備なんかで下校時刻が変動したような場合をのぞいて、帰るメンバーは基本、三年間変わらない。
葛飾は入学してしばらく、近くの高校に入学した中学時代の友達と自転車通学をしていたために、帰るメンバーを見つけ損なった。中学の友達は、いまの高校の友達と通学するからと言ってルートごと変えてしまった。
靴をはきかえていると、三人の男子生徒が走って自転車乗り場に行くのが見えた。入学してから半年後に親が離婚して引っ越しをしたせいで、今では葛飾も電車通勤になってしまった。自転車ならせめて一人でいることが目立たないのにと三人を横目に見ながら、道幅いっぱいに広がる生徒たちの姿がぼやけるように目を薄めてみたものの、すぐにこけそうになったのでかわりに耳にイヤホンを押し込む。沖縄のどこかの海の波の音が、盛大に鳴りわたる。
さすがに電車から降りれば帰るメンバーもばらけて、あちこちに一人で歩く生徒を見かける。葛飾は錆びた歩道橋をくぐり、郵便局の角を右に曲がる。解体中の家に丸太を差し込んで、それをクレーンで叩いて横木をぶっ壊している。新聞配達所、保育園、黒猫のいる家、接骨院といつもより大股で進んだせいか、気づけば小学校のころ少しだけ仲が良かった子の家の前にきていた。
ベランダに、端から端まですごく効率よく洗濯物が干してあるけれども、いまは午後三時過ぎなので取り込んだほうがいいんじゃないかなどと考えていると、背後に視線を感じ、葛飾は振り返った。ねずみ色のパーカーを着た若い男の人が、両手をジーンズのポケットに窮屈そうに突っ込んで立っている。
人の家の洗濯物を阿呆みたいに眺めていた姿を見られたと思っていると、男の人が歩き出し、友達だった子の家の脇道からおばあさんが出てきて、葛飾のそばにくると、「バス停はどこでしょうか」と尋ねてきた。
「すぐそこです」
バス停の看板を指さす葛飾の横を、若い男の人がなぜか焦った感じで通り過ぎて行く。葛飾が男の様子にとらわれていると、おばあさんはこちらの意識を引き戻すようにせり出してきた。
「始発のバス停を探してましてね。その近くに友達の家があるもんだから」
「それなら、この道を真っ直ぐ行くとコンビニがありますから、そこを左に曲がって少し歩いたところにあります」
おばあさんは葛飾の言った道順を復唱すると、礼を言って歩き出した。
信号を渡って反対側の歩道をおばあさんと同方向に歩きながら、そういえばコンビニの隣は駐車場で、曲がり道はもう少し先だったと思い出し、あわてて向かい側の道を見た。
ちょうどコンビニ前に大きなトラックが止まっていて、おばあさんの姿は見えない。そのかわりに、少し先の場所からさきほどのパーカー男がコンビニから出てくるのが見えた。手には何か光るものが握られている。水のボトル?それにしては細い。
トラックが動き出した。おばあさんはコンビニ横の駐車場を見て首を傾げていた。葛飾が、そこをもう少し先ですと叫ぶと、おばあさんがこちらを振り返る。それはよかったのだが、かわりに男に背を向けることになり、葛飾はにわかに鼓動が速くなるのを感じた。男が後ろに立った瞬間、おばあさんの身体がほんの少しぶれて男ははじかれたように体を回転させて、駐車場の奥に走って行った。
おばあさんは葛飾に向かって手を振ると、角を曲がって行った。
葛飾は同じ場所に立ったまま、心臓が脈打つのを感じていた。男が握っていた光るものがナイフだと思った自分はどうかしている。それからは何も考えずに機械的に歩き続け、気がつくと玄関の前に着いていた。
ハッピーアイスクリーム ②に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
