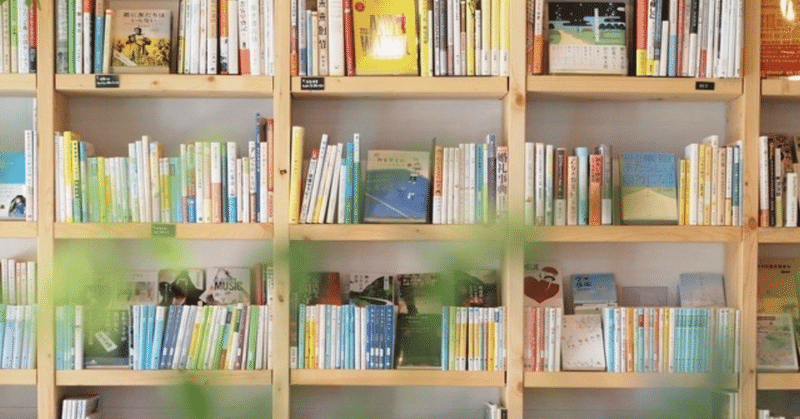
文庫本を手に取る理由。②
文庫本を手に取る理由。
前回は、私が中学2年生で初めて小説が娯楽になったときのお話をしました。
当時は、周囲に本読む子はいなかったので、母親のおすすめ本をよく読んでいました。
例えば、赤川次郎とかよしもとばななとか。
あとは、ドラマや映画の原作。「書店ガール」、「図書館戦争」も読みました。
家の近くにブックオフがあって、週末はそこで100円の本を買ってたな。
懐かしい。
中学3年生に上がると、プツンと糸が切れたように学校に行けなくなりました。
教室に入ろうとすると、体がこわばって、とてつもない緊張感で頭が痛くなる日々が続いた後でした。
そのあとは、高校受験。
幸い別室登校しながら、何とか志望校に合格。
それ以降は次のマイブームが来るまで読んでません。
あれです。タピオカが定期的にはやるのと一緒。
ガガガっとブームきて、楽しんで、終わったら積読になる。
文庫本とはそんなお付き合いばかりでした。
晴れて高校に入っても、苦悩の日々は続きます。
高校に入っても教室への嫌悪感というのか。
数年たった今でも形容に困るけれど、教室の中身なのか物理的な距離の近さなのか本当に全身に針を刺すような緊張が拭えなくて。
部活を生きがいに何とか学校に行っていました。
最初はごまかしごまかし行ってましたが、日に日に体が悲鳴を上げ始めました。
「あ、私、教室にいるの向いてない。」
気付いちゃった。
当時、高校は進学クラスにいました。
とにかく勉強漬けの日々。昼休みも土曜日も。
今となってはあまり当時の記憶がありません。
でも、勉強や部活それ自体は全然苦じゃなくて。
先生方がとても親身にサポートしてくださったこと、部活に友達がいたことでポジティブな気持ちがあったように思います。
教室外で、勉強に部活に。生き生きしている自分を見るたびに、休暇明けの教室が檻のように感じてきて余計に辛く感じました。
そんな中、夏休みの読書感想文を機に、再度本を読むようになりました。
第2次読書ブームとでもいうべきでしょうか。
このころは、ちょっと猟奇的な内容だったり、テーマが社会問題のような重いものだったり、ハッピーエンドでない小説ばかりを読んでいたと思います。
背景は重たくて、退廃的そして絶望感。
いっぽうで、登場人物たちは無垢で愁いを帯びたキラキラ感とした視点の内容がほとんど。
子どもの無力さや与えられた環境で健気に生きる様子、どうしようもない結末に折り合いをつけながら、楽しく生きようとする人々の様子。
大なり小なり程度はあれど、どこか自分の姿に投影していたのだと思います。
あの頃は、もう教室が牢獄のようにしか思えなくなっていました。
大学生になって、クラス制とか教室とかそういったものから離れてみてわかるのですが、あそこからあぶれたくらいで人の価値にキズなんてつくもんじゃありません。
今の私だったら外にコミュニティを求めるとか思いつきます。
けれど、高校生、もっといえば中学生にそんな視野の広さはまだないんですよね。
「小さな箱の中の、たまたま地域が近くて同い年の、ランダムな30人の世界」そこから離れたら「イレギュラー」扱い。
だから、できる限りぎりぎりまでそこで生き抜くしかない。
当時は学校という世界がすべて。(見渡せば外にも居場所はあったんだろうけど)
だからせめて、この中でサバイブする気持ちを誰か(なんていないから本で)と共有したかったんじゃないかな。なんて今では思います。
大人は転職したり、自分で事業したり、趣味仲間つくったり居場所は自由なのにね。
そんな感じで、本に共感を求めた「第2次読書ブーム」でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
