
わかりやすい!漢方薬 Vo.1〜漢方薬はメーカーによる違いがあるの?〜
今回から、ご家庭で実際に『漢方薬』を病気の時や不調のサポートとして利用することを前提に、漢方薬や生薬について解説していきたいと思います。
漢方薬をご購入する際には、専門家にご相談の上ご購入いただくことが大切ですが、ご自身である程度知識を持っていると、家にある漢方薬や病院でもらった漢方薬を服用するときに役立ちます。
そもそも漢方薬とは
そもそも漢方薬とは
漢方薬は、基本的に2種類以上の「生薬」の組み合わせからなる医薬品です。
生薬は、草木などの植物や鉱物、動物などを乾燥させたり加工したりして使いやすくしたものでこの生薬の組み合わせで漢方薬はできています。
どの生薬をどれくらいの量組み合わせるかは、漢方薬の古い歴史の中で脈々と受け継がれ、また文献として残されたものが、現在でも使われる漢方薬の元となっています。
日本で現在使われている漢方薬も、中国から伝わった処方を日本人の体質に合わせてアレンジしたり、独自に作ったりして現在に伝えられ、製剤化されました。
個々の生薬だけでは本来なら持たない効能が、方剤になると現れたり、毒性が減弱されたり、相乗的な効果(1+1が4にも5にもなる効果)が現れたりします。
漢方薬は、古からの経験と知恵によって受け継がれてきた「医療の知恵の結晶」とも言えるでしょう。
現在日本で使われている漢方薬の種類
漢方薬は、大きく分けて『煎じ薬』『エキス剤』『丸剤』『散剤』 があります。
煎じ薬
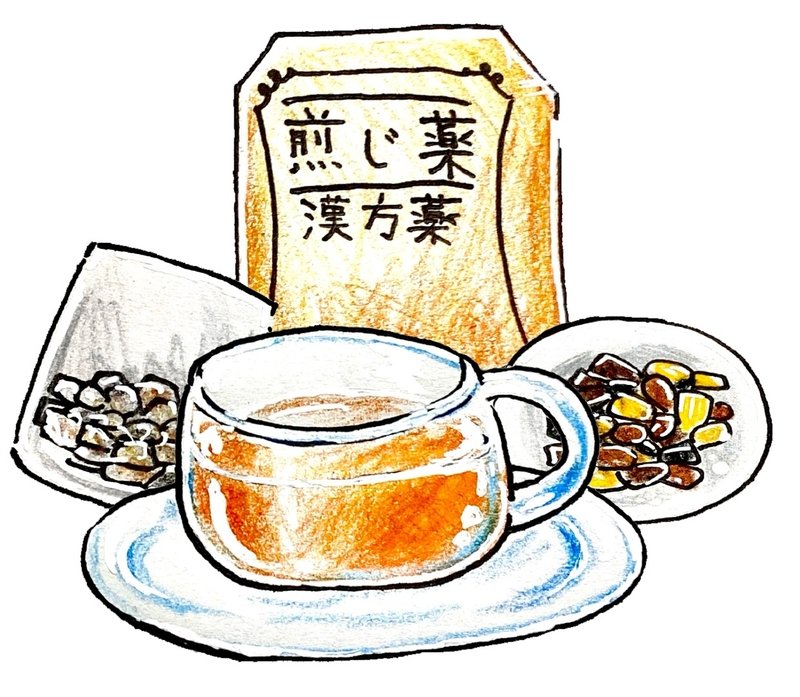
煎じ薬は、鍋に水と生薬を入れ、一定時間火熱をして生薬の有効成分を煮出したものです。
煮出したスープ状の汁を煎じ薬として服用します。
煎じ薬は、エキス剤に比べて効果が良いとされていますが、利便性や値段の面(煎じ薬は自費となる場合がほとんどで高価となります)からエキス剤が良い場合もあります。
生薬自体の価格が上がっている今、品質が良いものほど値段は高くなります。煎じ薬が値段が高いのは、生薬の品質にもこだわって作られているからとも言えるでしょう。
エキス剤
エキス剤は、煎じた生薬を濃縮し、水分を除いて粉末としたものです。
このエキス剤を元に、賦形剤などを加え錠剤や顆粒剤が作られています。
エキス剤とすることで、携帯することが可能となり、煎じ薬特有の味や香りをある程度軽減することができます。
病院でもらう漢方薬、ドラックストアで購入できる漢方薬はほどんどがエキス剤です。

丸剤

丸剤は、粉砕した生薬を蜂蜜などでまとめて丸くしたものです。
牛車腎気丸・六味地黄丸・八味地黄丸・桂枝茯苓丸など、●●丸と名前がつくものは、本来は生薬を細かく砕き、目の細かい古いにかけ、蜂蜜などの結合剤で「丸」として作られます。
散剤

散剤は粉砕した生薬を組み合わせたものです。
当帰芍薬散・加味逍遙散・五苓散などは、●●散と名前がつくものは、本来は煎じ薬やエキス剤ではなく生薬を粉砕して合わせて作られます。
散剤は香りが良いのが特徴で、煮出すと香りが飛んでしまうときにも散剤であればその香りもからだにはたらきかけます。

Q .1 メーカーによって同じ漢方薬でも成分に違いがあるの?
日本で販売されている漢方薬は、出典(古典)が同じであれば、基本的には漢方を構成する生薬は同じです。
ただし、メーカーによって使用する生薬の品質や抽出する方法、またエキス剤であれば添加物(賦形剤・矯味剤など)に違いがあり、それが効能に影響する場合もあります。
また、生薬の含有量が少し違う場合や、基原植物が異なる場合(日本薬局方で複数の植物が基原植物として認められている場合があるため)があります。
特に、白朮と蒼朮など、同系統の生薬は、メーカーによってどちらを使っているかが違うこともあり漢方専門医や漢方薬局では特にこだわってメーカーを選んでいる場合も多く見られます。
日本で販売されているメーカーに限って言えば、「構成される生薬は同じ」ですが生薬の量が違うこともあり、また「添加物の違いや製法の違い・製造技術の違い」が効能の差となって現れることもあると言えるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
