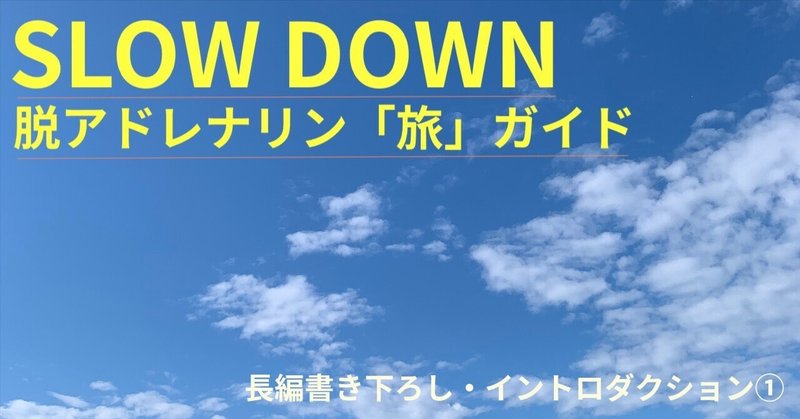
スローダウン〜脱アドレナリン「旅」ガイド〜プロローグ
このほんの数年の間、まるでパラレルワールドに迷い込んでしまったかのように、世界は大きく変わってしまった。
新型コロナウイルスという、目には見えない生き物……いや、生き物とも言えないミクロの存在がにわかに注目され、地球全土を席巻することで、この世界の歴史は大きく塗り替えられた。
2020年、2021年、2022年……。
誰もが想像してなかったところへと、いま、僕たち人類は向かっているのかもしれない。ただ、その方向をなんとはなしに予感し、不思議な思いに駆られて準備してきたような人たちもいる。
この本は旅ガイドをうたっているけれども、なぜ旅なのかということも含め、この予感についてしばしつづってみよう。
大事なのは、身体の働きに照らし合わせてみることだ。
かつて経済人類学者の栗本慎一郎さんは、「社会が変わる前にヒトの身体が変容する」と語っていた。社会がヒトによって構成されている以上、変化はまず構成因子たるヒトの身体に現れるということだろう。
この身体の変化は、細胞レベルでは、受容体(レセプター)と呼ばれるいくつものセンサーとつながっている。
たとえば、ウイルスが身体に侵入する際、最初に反応するのもレセプターだ。
感染するかどうかは、レセプターがウイルスの体(スパイクタンパク質)に反応するかどうかによって決まる。そのため、この結合を阻害する薬があれば感染が防げると考える人もいる。
ただ、感染を防ぐというのであれば、進入してきたウイルスを認識する免疫系のレセプターのほうが重要だろう。
その主だったものは、トール・ライク・レセプター(Toll Like Receptor)と呼ばれ、コロナによって耳にする機会が増えた自然免疫の要にあたっている。食べ物などと一緒に異物(ウイルスや細菌)が入ってくると、この自然免疫のセンサーがまず反応し、すみやかに対処していく。
こうした免疫の働きは、「異物に対する防御機能」として語られるのが一般的だけれども、フラットにとらえた場合、身体にとって必要なものかどうか、「区別する」ことにあるように思う。
そもそも、学者ですら当たり前のように使っている「ウイルスや菌と戦っている」という表現自体、妥当なんだろうか?
たしかにセンサーが反応するとサイトカインのような物質が細胞から分泌され、ウイルスや病原菌は排除される。
身体の反応としては、そこで炎症反応が起こるわけだけれど、こうした炎症は自分自身の細胞に対して向けられることも多い。
身体を守っているはずの免疫が、自らの細胞を攻撃する。かつてアレルギーや自己免疫疾患のような難病の原因としてクローズアップされてきたものが、近年では、細胞への攻撃=炎症作用はわりと頻繁に起こっていて、しかも慢性化していることが知られるようになってきた。
とりわけ問題になるのが、ストレスだ。たとえば、ストレスに対しても免疫は反応して、細胞を攻撃することがわかっている。そう、感染由来の炎症だけでなく、ストレス由来の炎症もあるわけだ。
こうしたストレスに対する身体の反応は、生きることそのものに深く関わっている。つまり、生き方の変化が身体の変化に現れる。
その先端にあるのがレセプターの反応であり、社会の利便性が増し、衛生環境、栄養状態が改善されてきたいま、その働きは細菌やウイルスよりもストレスに反応する割合が多いかもしれない。
ストレスへの反応、つまり、どう生きるかがより深く問われる時代、予感というのはおそらくその部分に接続している。
免疫はウイルスばかりに反応しているわけではなく、知らないうちに次代の意識の扉を開いているのかもしれない。
いや、もはやこじ開けてしまったと言ってもいいだろう。
★
扉が開かれてしまった時代のなかで、僕たちはその予感にゆらめきながら、新しい世界に向かおうとしている。
そこでは、わたしとは何か? という古くて新しい問いかけが、これまで以上に求められてくるかもしれない。
なぜか? ヒトの身体は「自己とを何か?」をたえず知りたがっているからだ。
免疫の話をここに重ねるならば、免疫とは「自己」を取り込み、「非自己」を排除する働き、と考えられている。
ちょっと難しく感じるかもしれないけれど、ここでいう自己はシンプルに「食事によって取り込まれる栄養」を指している。そう、食べたものが自分の身体につくりかえられる、つまり自己になる。
逆に言えば、自分の身体にならないものが非自己であり、細菌やウイルスは非自己にあたる。免疫が体内に入ってくるもののを自己か非自己か選別することで、僕たちの身体は一定に保たれている、
そうしたリモデリングの繰り返しのなかで、僕たちは生きているわけだけれど、自己を成り立たせている境界はかなり曖昧だ。
たとえば、腸内細菌のように排除されずに共生している非自己も存在している。
腸内細菌どころか、体内にはさまざまな細菌が常在しているし、かなりの数のウイルスが当たり前のように共生している。
この「共生」という視点に立つと、病原菌やウイルスをただ排除すればいいという話ではなくなってくるし、そもそも自己と非自己の定義自体、かなり大まかなものであることも見えてくる。
この大まかさのなかで、僕たちは心身のバランスをとりながら生きている。自己を自己として成り立たせている。
ストレスが過剰になるとこのバランスが崩れ、体内では炎症が発生する。放置しておくと体調が崩れ、病気にもなる。
悪者扱いされがちなウイルスにしても、体内に侵入したら即感染、発症とはならないことが広く知られるようになってきた。
ではなぜ発症するのか? それは、自分自身のバランスの崩れに体内のウイルスが呼応し、炎症反応が起こったということかもしれない。広い意味では、それもまた体内のバランス作用の一部なのだろう。
そうだとしたら、原因は自分自身にあるということだ。
自分の外部に悪いやつがいて、なにがしかの害悪をもたらす。だから、排除しなくてはならない……と思っても、じつはキリがない。
いやな人と無理につきあう必要はないけれども、排除しても排除しても、いやな人はまた次々と現れる。原因を相手に求めている限り、つねに振り回され、不安や猜疑心ばかりが増していくだろう。
それよりも、わたしをどう成り立たせたらいいのか? そこに目を向けてみる。
どこか哲学的な問いに聞こえるかもしれないけれども、それはだれにとっても切実な問いであり、生きるテーマそのものだろう。
この問いを解いていくには、事実を知っていくしかない。
自己と非自己の境界が曖昧で大まかである以上、自分の外部にあるものを敵か味方かでとらえる発想は、あまり生存には適していない。
目の前にいる相手は、敵か味方か、損か得か、善か悪か……、そんな分け方ではとらえきれない、複合的な存在だ。
物事を二つに分けてとらえる二元論は進化した脳の働きに他ならないけれど、それは比較を生み、競争を生み、ストレスの元凶にもなる。そして、炎症という形で身体に返ってくる。
身体の仕組みがここまで明瞭になってきた以上、僕たちはそろそろ自分を取り巻く世界の物語を書き換える必要があるかもしれない。過去にあるようでなかった、新しいまなざしで、新しい物語をつくる。
過去になかったと言えるのは、いまやオンラインによって地球のあらゆる空間が一つにつながろうとしているからだ。
地球のあちこちで生きてきた人たちが、まるで神経回路のように一つにつながろうとしている現実は地球生物の進化を思わせる。
テレパシーをことさら使わなくても、もはやテレパシックにさまざまな情報を受け取り、ところどころで発火が始まっている。
★
生物としての自己に目覚め、身体という共通のモバイルを通して、新しいまなざしでこの世界とふれあってみる。
そのためには少しギアを落とし、これまでの懸命に走る続けてきた生き方をシフトチェンジしたほうがいいかもしれない。スピードをゆるめても、生きていける。そのことを僕たちの身体は証明したがっている。
わたしという存在は単独で存在しているわけではなく、周囲との関係性のなかでストレス応答しながら自己を成り立たせている。
ストレスが悪いという単純な話ではなく、僕たちはストレスという外部刺激によってたえず世界を感じとり、自己の背後にある無限のリソース(森羅万象)と接触していると言っていい。
だとするならば、生きること自体が認識の旅、知の旅であるかのようだ。
どこで何をするか? 誰と過ごすか? そうした環境設定のなかでわたしはゆらめき、身体はたえず変容する。逆に、動きが失われ、固定化するほど変容は失われ、生きる喜びも失われる。
ゆらめき、バランスをとりながらより心地よいと感じる方向へ、そう、生物としての自己が求める方向へ。
どんな理論も、どんな思想も、身体が感じている事実には逆らえない。ヒトがそうした感覚にめざめた時、古い時代の価値観はゆっくりと崩れはじめ、幻想の向こう側にリアルな現実が現れるだろう。
生き物の世界へようこそ。ずっとそこにあった、古くて新しい無限の世界へ。これからの旅はそんな回帰のプロセスかもしれない。
迷うことがあったら、生き物であることの事実に立ち帰ろう。
食べること、動くこと、話すこと……ヒトはこれらの営みの総和のなかで、快と不快を感じながら生きている。
すべてはコミュニケーションであり、刺激応答だ。
ちゃんと食べられているか? 動けているか? 話せているか? 衣食住がある程度満たされていたとしても、こうした質の部分にアクセスできていないと幸福度は満たしにくいかもしれない。
旅の意味をここに重ね合わせた場合、動くことは動物としての特性であり、動物は植物や微生物に助けられて生きている。
日常と非日常を行き来しながら、植物や微生物にふれあうこと。たとえば、森に入り、土を感じ、その場の空気を吸い込んでみる。そうした体験もまた、心地よさに回帰する環境設定になるだろう。
歯を磨いて、ごはんを食べて、玄関を掃除をして、散歩して……日常で繰り返されるルーティンもリズムをつくり、身体性の目覚めにつながるけれども、ここに流動することを加えると心地よいアクセントが生まれる。日常と非日常、ヒトという生き物はそのどちらも求めている。
ならば、旅に出てみよう。歩いてみよう。異なる位相の世界に触れて、バーチャルの壁を軽やかに超えよう。
動き続けることで見えてくるもの、動きつつも心を鎮め、閉ざされし内なる感覚をよみがえらせていくこと。頑張ることだけに頼らず、むしろゆるめることで細胞の一つ一つを活性化させていく。
達成感のベクトルをずらすことで、意識のなかに革命が始まる。
★
この本では、コロナのパンデミックが世界を席巻する前から続いてきたいくつかの旅の記憶を、いくつかの物語としてまとめあげている。
キーワードは、信じてゆるめること。失うものを恐れずに予感のなかで生き、体験すること。そう、パウロ・コエーリョが著した「アルケミスト」のように、誰もが人生の創造者なのだから。
ーーー脱アドレナリン「旅」ガイド。
ここから始まる5つの旅の物語を、予言書ならぬ予感の書として受けとっていただけたら、とても嬉しく思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
