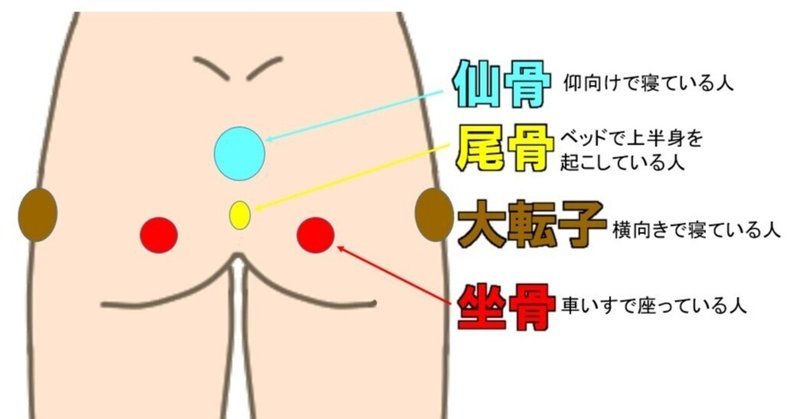
床ずれ対策は、クッション、マット、たんぱく質、亜鉛
◆床ずれとは? どうしてできるの?
「床ずれ」とは、主にお尻にできる病気です。
皮膚が赤くなり、進行すると皮膚が死んで穴が開きます。
同じ格好で長い時間寝ていたり、座っているとできます。
理論上、2時間動かなかったら、床ずれになると言われています。
私たちは2時間以上座ることがありますし、夜は約7時間寝ています。
なのに、どうして床ずれができないのでしょうか。
私たちは、座っているとき、無意識にお尻を浮かしています。
寝ている時は、こまめに寝返りをうっています。
それで床ずれができないのです。
◆床ずれは痛くない
体力の低下などで介護が必要な人は、車いすに座っているとき、
お尻を浮かすことができません。
寝ているときも寝返りが十分にできません。
それで床ずれができるのです。
体力の低下が床ずれの一番の理由ですが、感覚が鈍くなって、
痛みを感じないことも一因でしょう。
「床ずれ」は、外見は痛々しいですが、痛みはほどんどありません。
痛みがないから「床ずれ」ができるといっても間違いではありません。
痛ければお尻を浮かしたり、寝返ったりするのですが、痛みを感じないため、何時間も同じ姿勢で動こうとしないのです。
◆床ずれはどこにできるの?
床ずれは主にお尻にできますが、ライフスタイルによって、
できる場所が異なります。

座っている時間が長いとき、
坐骨(両方の尻たぶの奥に触れる骨)のところにできます。
ベッドで上半身を起こしている時間が長いとき、
尾骨(尾てい骨)の部分にできます。
仰向けで寝ている時間が長いとき、
仙骨部(尾てい骨の上)のところにできます。
横になっている時間が長いとき、
大転子部(太ももの骨が骨盤にくっつくところ)にできます。
◆予防法は?
床ずれができてしまうと、治すのに、予防の8倍の労力がかかると言われています。
床ずれは予防が大切です。
いきなり床ずれはできません。
まず、骨の出っ張っているところが赤くなります。
この時点で予防すれば防ぐことができます。
予防法は「除圧」と「栄養」です。
「除圧」とは、骨の出っ張りに圧がかからないようにすることです。
仙骨や尾てい骨、大転子の場合、耐圧分散マットレスやエアマットが有効です。
坐骨の場合、車いす用の耐圧分散クッションで予防できます。
介護保険でレンタルすることもできます。
「栄養」は、たんぱく質と亜鉛でしょう。
豆乳、豆腐、卵など、たんぱく質食品を1品追加しましょう。
亜鉛は、食事で補充するのは難しいので、サプリメントがいいでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
