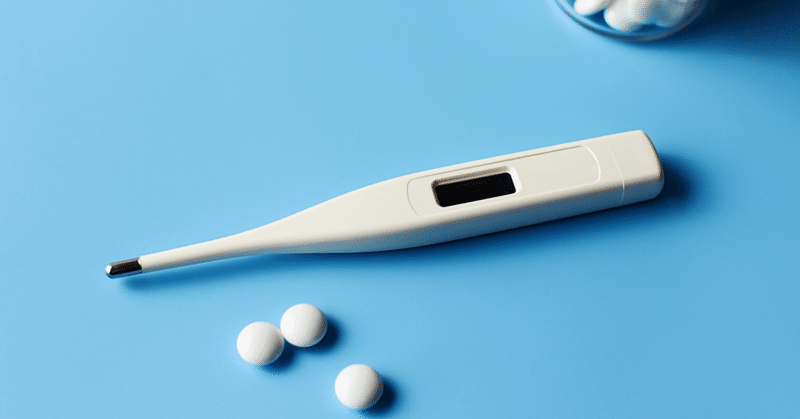
アルツハイマー神学
アルツハイマー病の新薬「レカネマブ」が正式に承認されるらしい。
私は医学を専門的に学んだことのある身ではないんですが、新聞やテレビの報道を見ていて言葉的に気になる表現が多かったので、すこしまとめておきたいと思います。
全体に、婉曲的で間接的な物言いが印象的なんですよね。多用されている言い回しを列挙すると、
アミロイドベータの蓄積が認知症の原因「と考えられている」
症状の進行を遅らせることが「期待される」
(平均で2、3年進行を遅らせることが「推定される」)
記憶力や判断力などの程度を「評価するスコア」の悪化が27%抑えられた
全部、状況証拠的な指標ばっかりなんですよ。アミロイドベータが原因だと断定できてもいないし、悪化が抑えられたのは記憶力そのものではなく記憶力を評価する指標の数値なんですね。基本的に推定ベースで、新薬が病気に効くとの根拠が積み重ねられている。
また、朝日新聞の記事では、さりげなく効果のイメージ図が差し添えられています。

「レカネマブに期待される効果の概念図」って、よく考えたらけっこうヤバいですよね。新薬の効果って、希望観測的な概念なんですか? そしてそんな状態で承認されそうなんですか?
こういうのを見ると、私なんかは神学を連想してしまいます。現実から遊離した、悪い意味での神学を。
見たこともない、実証もできない神をめぐって、状況証拠からその存在や能力をあれこれ詮索する知的態度と、アルツハイマー病に関する状況証拠を要領よく集めて筋を通して、一気に病気そのものを治せると罪深い期待を抱かせてしまう感じは、すごくよく似ていると。こういうのはもう「科学神学」とでも呼ぶべきかもですね。
ついでに、これは「延命治療」という表現にも感じることなんですが、アルツハイマーみたいな進行型の病気って、そもそも「治療」ってありえないんですよね。治すんじゃなくて、進行をちょっと遅らせることが期待できるだけにすぎない。
回復の見込みのある医療行為は治療と呼んでもいいと思いますが、それに携わっている関係者がそういう見込みをもたないまま仕事してるものについて、それは本当は治療と呼べないんじゃないかと。
待望の新薬!みたいな見出しなんか、回復や復活を連想させる前のめりなフレーズで、ミスリードなんじゃないかと常々思ってるんですよね。
今回のアルツハイマー病新薬にまつわる報道にとどまらず、一般に医学系のポジティブな報道というのは、一時が万事、こういう、諸概念を神学的に弄ぶモラルハザードな景色感が強いので、そのたびに私は「ああ、この薬は効かないんだな」と思うようにしています。
「〜な効果が期待される」みたいな言い回しは一発アウトっすね(笑)
実際、医者の大脇幸志郎さんも、レカネマブがそもそも効かないという話をわりと詳細にされてるんですが、大脇さんはさらに、レカネマブの課題を薬価だの地域格差だのといった話にすり替える危険性も指摘しています。
たいへん偏った報道。効かないという最も重要な点が抜けているので何もかも逆の意味に見える。
— 大脇幸志郎 (@0waki) August 21, 2023
アルツハイマー病新薬「レカネマブ」承認へ 原因物質を除去、国内初(朝日新聞デジタル)#Yahooニュースhttps://t.co/4DmGPU3MDv
財政負担とか検査体制の不備などを問題にする前に、そもそもこの薬は効かない。それが問題のすべてだと。さらに詳しい話は、今年1月の一連のツイートにもよくまとめられています。
もっとも、一歩引いて意地悪く製薬目線で語れば、
世間に出す手際が多少拙速であっても、背に腹は代えられない(と思っている)切実な認知症患者やその家族は、「ちょっとでも希望があるなら・・」と新薬に手を伸ばしたがるだろうと。
本当は十分な治験(人体実験)を済ませてから販売したいが、それよりも、とりあえず承認されてすぐに世の中に出回る方が、結果的に、より多くの人に行き渡り、事実上の人体実験データがたくさん集まる。
どうせ治る病気ではない、せいぜい進行を遅らせるだけの薬なんだから、それぐらいの横着は許されるだろうという甘えっすね。それどころか、それが医学の進歩につながると信じている。
人権と民主主義の時代に医学を進歩させるには、こういう力技が必要なんでしょう。そもそも医学は進歩すべきか、進歩すべきだとして、人類はその進歩に値するかは別件としても・・。
いずれにせよ、後世の人々は「エビデンス主義は神学になりがち」という知見を、21世紀の教訓として見出すかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
