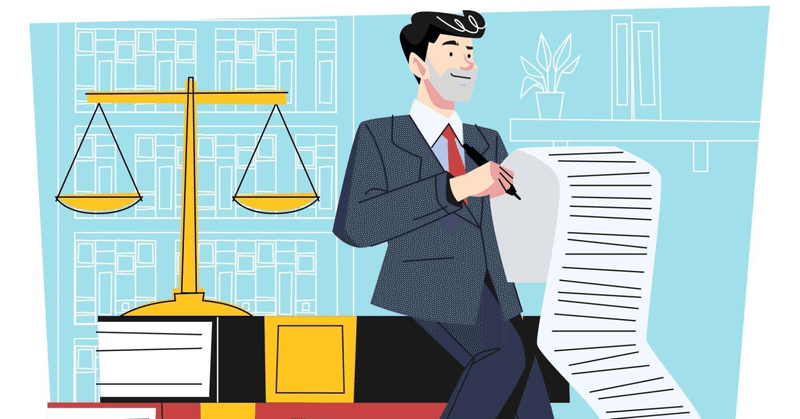
労働観 古代と現代
労働の歴史をふりかえるとき、よく古代(ギリシャ)では労働は軽蔑されてたっていわれるけど、それってよく考えたら貴族目線の話なんじゃないかとふと思った。
当時は貴族しか労働について語れなかったし、また、貴族が語ったものしか、現代には伝わっていない。
「働かざる者食うべからず」といって、現代の労働観はやけにセコいものに見えるけど、これは逆に、現代では労働者に労働のことを語る権利があり、また、労働者が語った労働観が、文献なり映像なり(ツイートなり)しっかり残っているわけですね。
現代の貴族(政治家や経営者、投資家など)は、相変わらず労働を軽蔑・嫌悪している。いわゆる「上級国民」に、労働愛好的エートスはイメージしづらい。
ただ、労働大衆の声がデカいから、たまたま現代は「労働に価値が付与された時代」ということになっているわけです。
古代だって、労働に従事していた奴隷は、心の中で主観的には、現代人と同様、労働に肯定的な意義を認めていたかもしれませんね。
ただ、その「声」は、古代を代表するものとしては今日認められていない、認めないことにしている。
まあ、資料もないでしょうし。
古代の理想を現代人が回顧的に語るとき、知らず知らずのうちにうっかり自分を「奴隷をこき使う貴族」と同一視するロマンを冒してしまっていると。
労働の歴史を振り返ってみたり、自身の労働観を問い直してみたりするのはよいことだけど、それは現代人がたまたま読み書きの能力に恵まれているからで、その言語能力を差し引けば、現代人の条件は古代の奴隷とあんまり変わらない、むしろそちらの部類であって、その事実からまずはスタートする。議論を混同させないためにも、このラインを自覚することが大事だと思うんですよね。
我々は古代を語るときうっかり貴族の観点を過大評価しがちであり、逆に現代を語るときには、労働大衆の観点を過大評価しがちである。
そして、本来、大衆と貴族は違うのに、「同じ人間」ということにして、貴族的に振る舞って他者を従属させたいという無意識の欲望から目を逸らしている。
この傾向や予断を自覚することが大事だと。
中山元さんとかは、最近の著書『労働の思想史』において、
かつては労働は人間の活動のごく一部を占めるにすぎなかったが、現代の社会においては、ほとんどすべての活動が労働とみなされるようになる。
と書いているけど、より精密には、
かつては労働は貴族目線で語られたので人間の活動のごく一部を占めるにすぎないように見えたが、現代の社会においては、奴隷が大衆として市民権を得たので、ほとんどすべての活動が労働として可視化されるようになった。
といった具合に言い直すべきではなかろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
