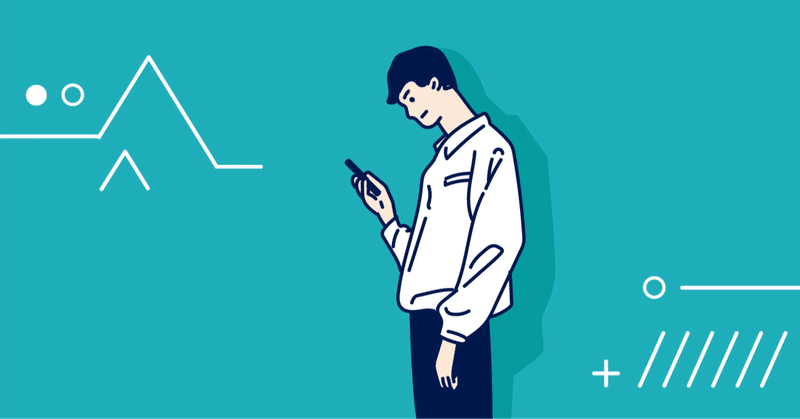
谷川嘉浩『スマホ時代の哲学』への違和感
先日、本屋で『スマホ時代の哲学』という面白そうな題名の本を見つけたので、購入して読んでみた。著者の谷川さんは、大学、そして学部の先輩にあたる。
ポップでカジュアルな語り口が印象的で、スマホやSNSといった新しい情報環境において、人間の在り方はどうなってしまうのか、その問題意識において、著者とは通ずるものがある。しかし今回は、この本について、その内容というよりは書き方、戦略、通底する気分に焦点を当てて、簡潔ながら批判的にまとめておきたいと思います。
まず、ざっくりとした所感なんですが、谷川さんは哲学者らしくなく読者フレンドリーです。「哲学者だってNetflixを観るし、ドクターマーチンを履く」という角度から自己紹介しますし、「エヴァ」や「燃えよドラゴン」など、大衆的な作品を材料に哲学の可能性を拡張していこうとする。
読者に寄り添って、哲学によってエンパワーしようという意識が感じられます。ただ、いきなり結論からいうと、哲学ってやっぱ「引き込む」もしくは「呼び込む」もんじゃないと思うんですよね。
冒頭でもニーチェの言葉を引きながら「ニーチェの指摘は他人事ではないはずです」と読者を煽りますが、
そこまで哲学って安売りするものなのかなと。
なんというか、必要じゃないものを「是非とも必要です!」と押し売りする時の気分を感じてしまうんですね。
ある箇所では哲学を医学に喩えたりしてますが、確かに本書の谷川さんにはどこかTwitterの医クラっぽい佇まいがあります。
病院で一対一で患者を見る医者ではなく、不特定多数に「是非とも医者にかかりましょう」「病気にならないよう健康的で衛生的な生活をするべきです」とポジショントークする医者と同列に見えてしまう。
僕なんかは、
哲学のある人生も良いが、哲学なしに済ませられる人生も良い。
とわりと真剣に思っていて、哲学者は、哲学を必要とする人を発掘する必要はなくて、必要だと信じ切ってやってきた「患者」に手を差し伸べる。それだけでいいと思うんですよ。
でもそれだけでいいと思えなくなった、いい意味で突き放すことができなくなった、というところに、現代の知的地平の限界が垣間見えもすると。
巨視的に見て、社会そして大衆が、そこまで哲学を必要としなくてよくなったということ自体は、祝福すべきことなんだと思うんですよね。
哲学も、露悪的に要約すれば、一つの精神論なわけです。
でも、モノやサービスがこれだけ充実した現代社会において、精神論に頼るまでもなく、その手前で、便利なモノやサービスで色々な問題が解消できてしまう。原理的に解決はされていないにせよ、主観的な生の手触りとしては、精神論に頼るまでもなく何事も比較的スムーズであると。
谷川さんは、現代ではいろんなことが便利になりすぎて、難解で消化しきれない「モヤモヤ」の人気がなくなってしまったみたいな感じで書いてますが、
「スッキリアイテム」と「モヤモヤアイテム」の選択肢があったとして、これまで後者は前者に打ち勝って常に選び取られてきたが、現代ではそうではなくなったみたいな話なんですかね。
たぶん違いますよね。
スッキリとモヤモヤって、もはや争ってすらいないと思うんですよ。どちらか選べるなら、スッキリ一択でしょう。
昔は情報環境や供給能力の制約から、たまたまスッキリを選べなかった(そんな選択肢はなかった)というだけであって、
昔の人は偉くて、スッキリに対してモヤモヤを選好していた時代もあった!だから私たちも考え方次第ではできるはず!
っていうのはミスリードでしょう。回顧的錯覚に自ら加担しに行っている。
オルテガの話とかもこれと似ていて、近代になって人間はバカになったのではなく、もともとバカなのが都市化によって可視化されただけだと解釈してはいけないのか。
モノやサービスの充実・向上は、「劣化した人間」を許容する。進化論を引いて「優れたものが生き残る」みたいな話もありますが、進歩した社会では、特別優れていなくても生き残れるようになるわけです。そしてそれは人類社会の「達成」だと。
単純で劣化した人間でも、豊かで安全な社会において、その劣等性が顕在化しないようなシステムに乗っかれているので、社会全体としても問題が大きくならない。それどころかわずかなリスクやハザードを真剣に騒げるくらい余裕が出てきているわけですね。
こうなるともう、哲学の出番はないわけです(笑)。
と言いつつ、僕も哲学者の端くれとして、あまりモノやサービスには頼らず「精神論」(とミニマリズム)で日々それなりに楽しくやっているわけですが、しかしそれも、やっぱ個人が自分で気づくしかなくて、気づかせようとか呼び込もうみたいな寄り添いは、余計だと思うんですよね。そんな出版社のブルシットジョブに乗っかる必要はないと。
もっとも、スマホ・SNSにどっぷりな読者大衆には、本書のようにカジュアルな表現で、手取り足取り説明しないと伝わらないのではという観測もあるんでしょうが、
そこまでしないと伝わらない相手にはそもそも伝える必要がないし、おそらく向こうもそれをそこまで必要としてないと諦めておくのも大事な「倫理」だと思うんですよ。
大学の教師としては、哲学で飯を食わないといけないので、ある程度哲学に興味を持つ層が社会に実在してないと困るという利害があるのかもですが、
そもそも哲学と大学は普遍必然的な関係にはないわけだと。そして、個人的な体感ですが、今の時代、出版物よりむしろまさにSNSの方が、哲学的にエッジの効いた言説に出くわすチャンスが高いようにも感じるんですよね。
このnoteもそうですが、良くも悪くも、SNSは書き手と読み手、発信者と受信者が直接つながることができるわけです。そこに編集者や出版社の入り込む余地はない。そのことによって、出版社の利害や編集者の忖度(とあえて冷淡に表現します)なしに、忌憚なく自由に表現することができる。出版のスケールは魅力的だが、スケールが大きいというまさにそのことによって、言いたいことの半分も言えなくなる。最悪「優等生」になって、出版的気分に適応した半端な知性と想像力で成長を止めてしまう恐れもあると。
その名に値する哲学をしたい場合、今日において、果たしてその場所は大学や出版の世界なのかと問う必要性はますます高まっているように思います。そして実際、本当の哲学に出会うチャンスを、スマホやSNSは阻害しているどころかむしろエンパワーしてくれている。そういう線で哲学の可能性を探る本格派の哲学書、誰か出してくれませんか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
