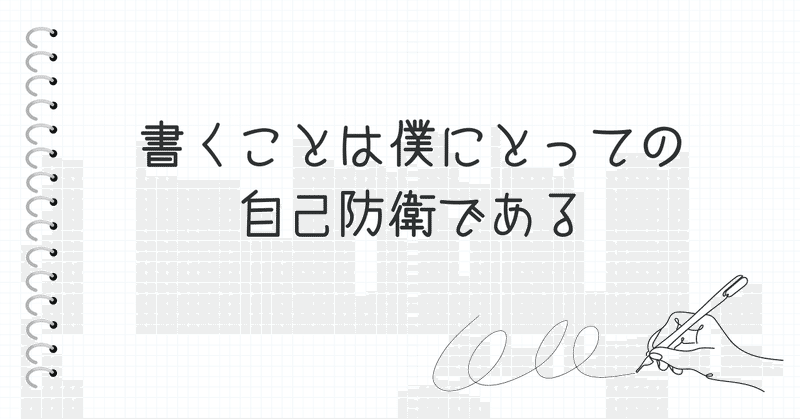
書くことは僕にとっての自己防衛である
先日、高倉大希さんというnoterの方の以下の記事を読んでいて、心に刺さることがあった。
記事の中では、田中泰延さんの「読みたいことを、書けばいい。」という書籍からこんな言葉が引用されている。
つまらない人間とはなにか。それは自分の内面を語る人である。少しでもおもしろく感じる人というのは、その人の外部にあることを語っているのである。(中略)自分の内面を相手が受け容れてくれると思っている時点で、幼児性が強いのである。
うーん、これは確かに僕のことだなあと思った。
幼稚性のかたまりである自分に対して、グサグサと容赦なく刺さる。
容赦なく刺さりすぎて、まんまと書籍まで買ってしまった。
どう反論してやろうかという、敵愾心を持って読み始めたのだが、あまりに文章が面白過ぎて反論を忘れたまま、一日で最後まで読み終えてしまった。
素晴らしい本を教えてくれてありがとうございました。
ということで、グサッと刺さったままおしまいでも良かったのだが、それでは何も進まないので、自分なりに僕はなぜ書いているのかという話を考えてみた。
結果として、僕の書くという行為が3つの動機に支えられていたことを、ここに記す。
なぜ僕は書くのか
情報を伝えるため
まず1つ目は、単純に情報を発信したいという動機である。
この情報とは、自分の中にあるものではなく外部にあるもの。
田中泰延さんは、この外部にあるものを「事象」という言葉で表現していた。
「事象」とはいっても、それを伝えたいと思うからには、そこには何らかの理由、つまり要求が含まれる。
例えば、読んでよかった本をお勧めする行為は、「あなたにこの本を読んで欲しい」という要求が暗に含まれる。
例えば、僕が書いた以下の記事。
これはもちろん自分が社会課題に関する講演を聞き、心動かされたから書いたものである。
だが、この文章を書いた目的は?と端的に問われれば、「社会課題を知って発信して欲しい」という他者への行動変容の要求である。
他者(の行動)を変えたいという要求のために発信をする。
それが1つ目の目的である。
承認欲求を満たすため
頭の中にある思考はどれだけ素晴らしくても、頭の中にある限り誰にも理解されなければ、認められることもない。
俗な話だが、承認欲求は間違いなく僕が書く動機の1つになっている。
承認されることがもちろん全てではないけど、
人に見られるからこそ、例え稚拙であったとしてもできる限り言葉を探し、表現を探し、ぼんやりとしたものから輪郭を作ろうとする。
そうしてできた文章がいいねと思ってもらえたのなら、それだけでとても嬉しいし報われた気分になる。
仮に自分の内面を否定されたとしても、文章だけでもよいと思ってもらいたいから、頑張って書く。
もっとも頭の中では、溢れんばかりに輝いていた思考が、文章として外に出した瞬間、一瞬で陳腐なものに感じて、書く意欲を失ってしまうことがほとんどだけど。
自己防衛
最後は、僕自身の幼稚性の象徴でありながら、書くことの一番の目的でもある自己防衛。
受け容れて欲しいという気持ちもあるが、自分がこんな存在であるということを、ただ残しておきたい。
僕は人に対して面と向かって、自分の口で自分を表現し、伝えるということが苦手だ。
それは、面と向かって表現した自分を拒絶されるのが怖いから。
でも文章ならいくぶんかは気楽に、素直に自分のことを表現できる。
僕は、陰鬱な考えをよくしてしまう人間で、だいたいのことを疑ってかかるミスター警戒心である。
でも、そんな自分であっても、文章としてなら表現しようと思える。
自分の内面を、文章として形にする。
そうしておけば、僕を知らない人であっても、文章を読んでもらえばなんとなくは自分のことを知ってもらえる。
それは僕にとって、とても楽なことで、生きていくために身を守る行為に近いのだ。
書く目的を考えてみて
書いてみたはいいが、なんとなくしっくりこない。
どことなく、自分の文章に嘘を感じる。
この文章を書いていて、文章の一番の欠点は、自分自身に対しても容易に嘘がつけてしまうことだなあと感じる。
自分の感情に嘘をつくことはできないけど、その感情が思考として言葉になった瞬間、いくらでも嘘がつけてしまう。それが無自覚であったとしても。
この文章も考え直した結果、ひっそりと更新されているような気がします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
