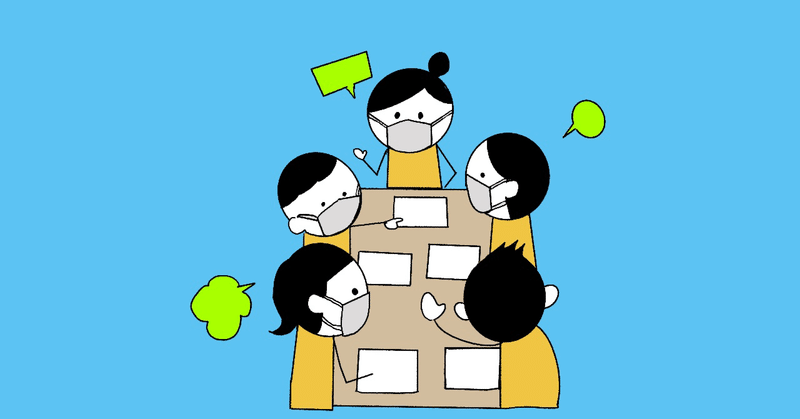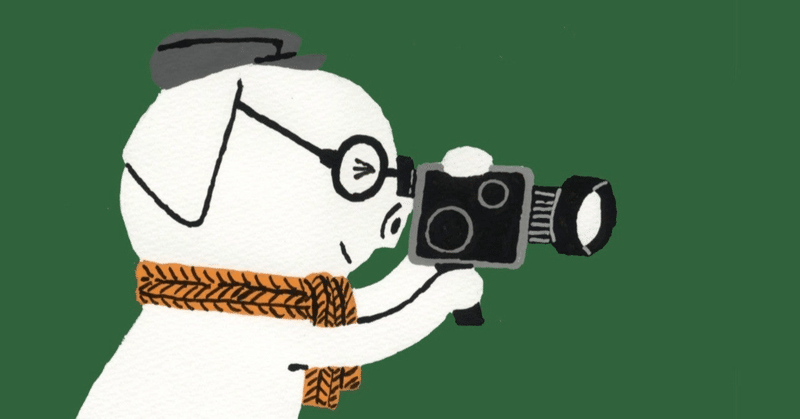最近の記事
マガジン
記事

【歴史総合】知識構成型ジグソー法の授業づくり② / エキスパート資料を作るときに気を付けていること①「史資料の読み解きを重視する」 / 科学的探求学習との違いと共通点
ここでは「知識構成型ジグソー法とはなんぞや?」という点は、他の方の解説に譲るとして、私が知識構成型ジグソー法(以下、KCJ)の授業を作るうえで、気を付けていることをまとめます。 1 エキスパート資料を作るときに気を付けていること①「史資料の読み解きを重視する」私は教員が講義をしているのを文字起こししたみたいな、出典のないオリジナルな文章をKCJのエキスパート資料の題材にするのは、しないようにしています。史資料の読み解きがミソだと思うからです。 実際のKCJの授業 以下は