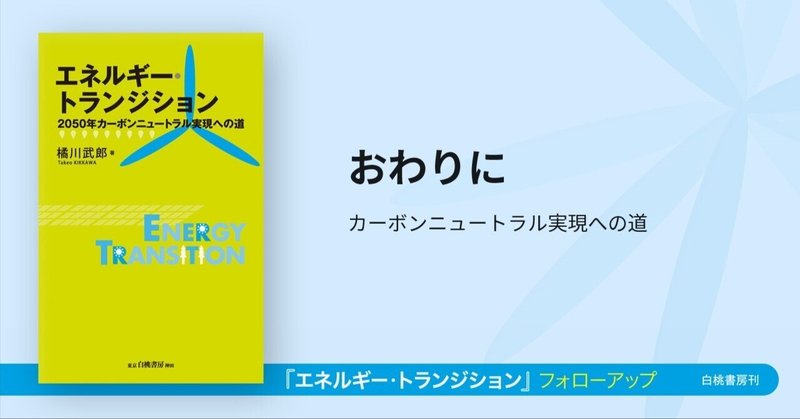
橘川武郎著『エネルギー・トランジション:2050年カーボンニュートラル実現への道』おわりに
国際大学学長/東京大学名誉教授/一橋大学名誉教授・橘川武郎著の『エネルギー・トランジション』(白桃書房刊)所収の「おわりに──カーボンニュートラル実現への道」を公開します。
カーボンニュートラルを実現するまでに残された時間は、限られている。目標年である2050年は、あと25年余りのちにやって来る。
限られた時間内でカーボンニュートラルにつながるエネルギー・トランジションを、どのように遂行するか。これが、本書で追求してきたテーマであるが、そこで強調した主要な論点を再掲すれば、以下のようになる。
・カーボンニュートラルを真に実現するためには、(1)需要側からのアプローチ、(2)熱電併給、(3)担い手としての地域、という三つの視点が欠かせない。日本のカーボンニュートラル化の担い手は、関連するイノベーションに取り組む大企業とそれを支援する政府、および(1)〜(3)の課題に深くかかわる地域、ということになる。
・2021年に閣議決定された第6次エネルギー基本計画が打ち出した日本の総発電電力量見通しには、2050年度までの数値(3〜5割の増加)と2030年度までの数値(1割強の減少)とが矛盾するという問題点が存在する。カーボンニュートラルにつながるエネルギー・トランジションを遂行するためには、そのための前提条件として、正確な中長期の電力需要見通しを確立する必要がある。
・求められるエネルギー・トランジションの柱となるのは、再生可能エネルギーの加速度的な普及である。そのためには、事業主体への住民・当事者の参加がきわめて重要であり、それが進めば、再生エネ事業発展の障害となっている地元とのトラブルの問題は、解決に向かって前進する。さらに、「セクターカップリング」の視点に立って、再生可能エネルギーを電源としても熱源としても活用することができれば、全体としてのコストを低減させることもできる。
・原子力発電については、「副次電源」であるとの認識に立って、古い炉を新しい炉に建て替える「リプレース」を進めながら、原発依存度を徐々に低下させべきである。また、使用済み核燃料の処理問題については、⑴「もんじゅ」に代わる有害度低減技術開発の具体的な方針を確立する、⑵原発敷地内に空冷式冷却装置を設置し「オンサイト中間貯蔵」を行う、⑶「リアルでポジティブな原発のたたみ方」という選択肢も準備する、という3点が重要である。
・カーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギー発電とそれをバックアップするカーボンフリー火力とががっちりタッグを組むことが不可欠であり、その意味で、「カーボンフリー火力なくしてカーボンニュートラルなし」と言いうる。カーボンフリー火力は、石炭火力のアンモニア火力への転換、およびガス火力の水素火力への転換という、二つの道筋を通じて出現する。このうち石炭火力に関して日本政府は、2040年をめどに石炭火力をたたむと、国際社会へ向けて宣言すべきである。
・水素の利活用を進めるうえでは、コスト低減とともに、大口の需要先の確保が主要な課題となる。燃料アンモニアの社会的実装のためには、「グリーンアンモニア」と「ブルーアンモニア」の大規模調達、コストのLNG(液化天然ガス)並みへの引下げ、ハーバーボッシュ法に代わる新しいアンモニア合成技術やNOXの排出を抑制する技術の確立などが、求められる。合成メタン(e-methane)、グリーンLPガス、合成液体燃料(e-fuel)などの合成燃料の開発にとっては、カーボンニュートラル燃料としての国際認証の獲得、二酸化炭素削減実績の帰属問題の解決、コストの低減が、重要である。
これらの諸課題を達成することは、けっして容易ではない。しかし、それらは、われわれにとって、もはや「なすべき事柄」の域を超えて、「しなければならない事柄」となっているのである。
(編集注:本ページは、「『エネルギー・トランジション』おわりに」をウェブページの特性を踏まえ、体裁を整えたものです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
