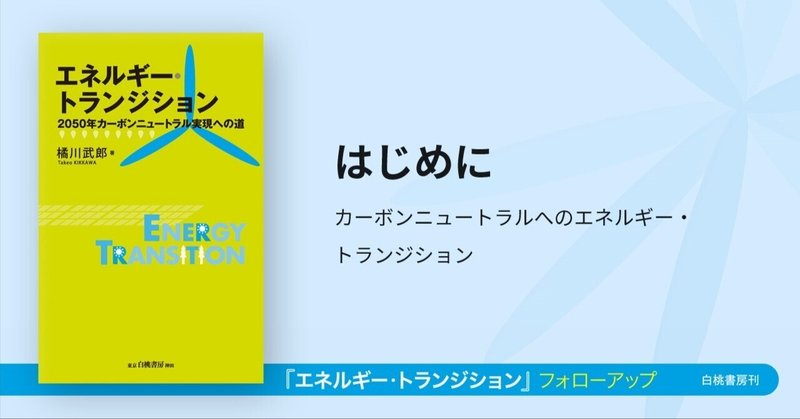
橘川武郎著『エネルギー・トランジション:2050年カーボンニュートラル実現への道』はじめに
国際大学学長/東京大学名誉教授/一橋大学名誉教授・橘川武郎著の『エネルギー・トランジション』(白桃書房刊)所収の「はじめに──カーボンニュートラルへのエネルギー・トランジション」を公開します。
本書の姉妹書である『エネルギー・シフト 再生可能エネルギー主力電源化への道』を白桃書房から出版したのは、2020年9月16日のことである。おかげさまで同書は多くの方々に読んでいただき、今日までに7刷を重ねることができた。
同書の第1刷を刊行した直後から、エネルギーをめぐる日本と世界の状況は、激しく変化し始めた。その変化に対応するため、同書を増刷するたびに、「おわりに」に補記を追加する措置を講じてきた。
─2021年4月16日の第2刷刊行時の「重版に際して」(執筆は2021年3月19日。以下同様)
─2021年6月16日の第3刷刊行時の「第3刷に際して」(2021年5月16日)
─2021年8月6日の第5刷刊行時の「第5刷に際して」(2021年7月24日)
─2022年4月16日の第6刷刊行時の「第6刷に際して」(2022年3月14日)
─2022年12月26日の第7刷刊行時の「第7刷に際して」(2022年12月5日)
が、それである。なお、これらの補記を付した「おわりに」については、次のリンクから(白桃書房『エネルギー・シフト』詳細ページ)無料で閲覧することができる。
しかし、状況の変化はあまりに激しく、もはや補記の追加だけでは対応できなくなった。また、変化が積み重なるなかで、エネルギー政策のめざすべき大きな目標も、「再生可能エネルギー主力電源化」から「カーボンニュートラル」へ深化するにいたった。地球温暖化への対応が喫緊の課題であるとの認識が、急速に世界中で広がったのである。このような事情をふまえて、筆者は、新たに本を書きおろす決断をした。その成果が、カーボンニュートラルへのリアルな道筋の解明をめざす本書である。
そもそも、カーボンニュートラルとは何であろうか。
日本だけでなく、世界中がカーボンニュートラルへ向けて雪崩を打っている。しかし、よくよく考えてみると、「カーボンニュートラル」とは変な言葉である。直訳すれば、「炭素中立」となる。何のことだか、よくわからない。今さらながらであるが、「カーボンニュートラル」っていったい何なのだろう。
カーボンニュートラルに近い言い回しに、「脱炭素社会」というのがある。これもまた、妙だ。文字どおり炭素がなくなってしまったら、人類は滅亡してしまう。炭素を含む炭水化物がなければ、人間は生きていけないからだ。
カーボンニュートラルの「カーボン」や脱炭素社会の「炭素」は、厳密に言えば「二酸化炭素」、つまりカーボンダイオキサイドのことだ。本来であれば「カーボンダイオキサイドニュートラル」とか、「脱二酸化炭素社会」
とか言わなければならないわけであるが、それは面倒くさいので「カーボンニュートラル」、「脱炭素社会」のように省略する。わかりにくさの一因は、この点にある。
二酸化炭素(CO2)が問題視されるのは、地球温暖化の原因である温室効果ガスの代表格だからである。CO2の排出を抑制し気温上昇をおさえこまないと地球は危機的状況に陥り、人類に未来はないとみなされている。
そうであるとすれば、なぜ、CO2の排出をなくすという意味を込めて、「カーボンゼロ」と言わないのか。それは、CO2の排出をゼロにすることが、事実上不可能だからである。
どんなに努力しても避けることのできない、ある程度のCO2の排出。その事実を直視するならば、排出と同規模のCO2の回収・吸収を実現して、差し引きゼロにするしかない。排出量と回収・吸収量とを等しくすることによっ
て、「実質ゼロ」を実現するわけである。
この「排出量=回収・吸収量」を意味する言葉が、「ニュートラル」だ。「カーボンゼロ」とは言わず「カーボンニュートラル」と表現するのは、このような事情が存在するからである。
ややくどいと感じながらも、ここでは、「カーボンニュートラル」という言葉の意味を詳しく吟味した。そうまでしたのは、「カーボンニュートラル」が、人類にとって、現時点で最も重要なキーワードの一つだからである。
とは言え、カーボンニュートラルを達成することは難しい。達成するには、バックキャストという手法を用いて、まず目標とする未来像を描き、続いてその未来像を実現するための道筋を未来から現在にさかのぼって記述するシ
ナリオを作成しなければならない。本書がめざすのは、このシナリオの作成である。目標とする未来像はカーボンニュートラルであり、すでに確定している。それを実現する道筋、シナリオの明確化こそが、問題なのである。
日本のエネルギー政策を、カーボンニュートラルを実現する道筋、シナリオに合致させなければならない。実現の期限は2050年であるから、移行(トランジション)のために残されている時間は、25年余に過ぎない。迅速かつ着実に、エネルギー・トランジションを遂行しなければならないのである。
『エネルギー・シフト 再生可能エネルギー主力電源化への道』の出版後、エネルギーをめぐって、大きな変化が次々と起こった。その主要なものだけを列記すると、
─2020年10月26日: 菅義偉首相(当時)が所信表明演説で「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」と宣言
─2021年4月22日 : 菅首相が、気候変動サミットで、2030年度に向けた温室効果ガス削減目標を、2013年度比で、従来の26%から46%へ引き上げることを表明
─2021年10月22日:岸田文雄政権が、第6次エネルギー基本計画を閣議決定
─2022年2月24日 :ロシアがウクライナ侵略を開始。世界的にエネルギー危機が広がる
─2022年12月22日: 岸田首相が、GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議で、既設原子炉の運転期間延長を含むエネルギー政策を発表
─2023年2月10日:岸田政権が、GX実現に向けた基本方針を閣議決定
─2023年5月12日: 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)が成立
─2023年5月31日: 「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)が成立
となる。
このような状況変化をふまえて本書では、まず序章で、カーボンニュートラルとエネルギー危機との関係について掘り下げる。続いて第1章で、「カーボンニュートラル2050宣言」とそれを受けて策定された第6次エネルギー
基本計画の内容を検討する。
カーボンニュートラルを達成するためには、電力分野での取組みだけでは、決定的に不十分である。熱利用等の非電力分野での取組みが、鍵を握るとさえ言える。そこで第2章では、電力分野・非電力分野・CO2除去を包含する日本のカーボンニュートラルをめざす施策の全体像に光を当てる。
その後第3章〜第5章では、第6次エネルギー基本計画と「GX実現に向けた基本方針」の記述を手がかりにして、各エネルギーの今後のあり方を展望する。具体的には、第3章では再生可能エネルギー、第4章では原子力、第5章では火力発電用化石燃料を、それぞれ取り上げる。そこで浮かび上がるキー・テクノロジーに焦点を合わせる形で、第6章では水素・アンモニア・合成燃料の社会実装への道筋を探る。
第7章では、視点を変えて、需要サイドからのカーボンニュートラルへのアプローチに目を向ける。そこで注目するのは、省エネルギーと地域の役割である。そして、本書のまとめに当たる終章では、2050年へ向けてのエネルギー・トランジションのリアルな道筋を展望する。
以上が、本書の構成である。なお、本書の記述は、基本的には、2023年9月末時点での事実にもとづいている。本書の出版に際しては、株式会社白桃書房の皆様、なかでも大矢栄一郎社長と平千枝子さん、金子歓子さんにたいへんお世話になりました。ここに特記して、心からの謝意を表します。
2023年10月6日
橘川 武郎
(編集注:本ページは、「『エネルギー・トランジション』はじめに」をウェブページの特性を踏まえ、体裁を整えたものです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
