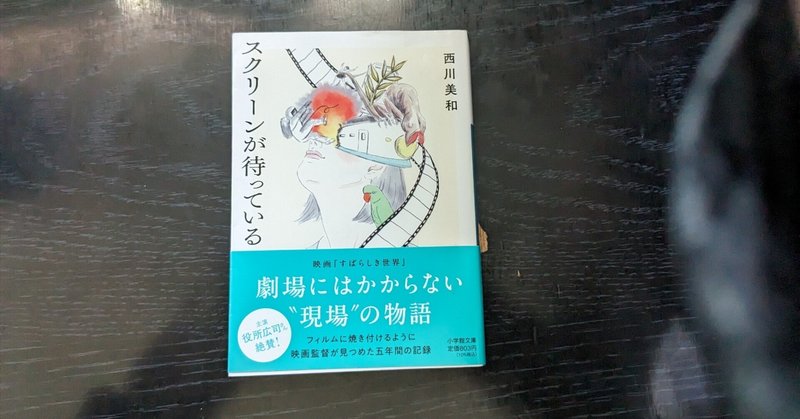
読書日記 西川美和・著『スクリーンが待っている』 役所広司の顔と映画作りに関する雑感
映画監督が書いた職業論のような製作日誌のようなエッセイ集
西川美和・著『スクリーンが待っている』小学館文庫という本を読んだ。2021年1月に出た本が、2024年の4月に文庫化されたのだ。
著者は映画監督だ。ウィキによると、是枝裕和の弟子筋に当たる人のようだ。
西川監督には、10本弱の映画作品がある。私は1本も見ていない。直近の作品が2021年2月に公開された『すばらしき世界』だ。
この映画は、役所広司が主人公を演じている。私は、少し前から役所広司の出ている映画を選んで見ている。誰もが役所広司はすごいと言うのだが、私はバカなのか、役所広司のすごさがわからない。
何を見ても、質の高い熱演だし、現代劇なら髪型も一緒だし、結果的に私には金太郎飴にしか見えないのだ。『すばらしき世界』の予告編を見たら、この映画の役所広司なら、私でもすごい、と感じることが出来るかもしれないと思ったのだ。我ながら屈折しているが、そんな理由で、『すばらしき世界』を見たいのだ。
原作は佐木隆三の「身分帳」という小説だ。この映画を探したのだが、私が加入しているネットフリックスにはなかった。検索しても映画館ではやっていない。レンタルビデオ(DVD)屋さんは、もうどこにいもない。
有料のネット配信で見るしかないようだ。でも、そこまでして見る気はしないのだ。ちなみに、ネットフリックスに西川作品は一つもなかった。
そういえば、『身分帳』は、最近、文庫で見かけたなあと思って、本屋さんに行ったら、西川監督のこの文庫があったのだのだ。
この本は、映画『すばらしき世界』を作っている時のことを書いた連載をまとめたものらしい。映画は見られないけど、本で我慢しようと思って、この文庫を買って来たのだ。
無数の職人が関わって一本の映画が出来上がる
この本は、バカみたいな言い方だけど、とてもいい本だった。映画関係者の書いた本は、大抵、クセの強さを感じさせるものが多いものだが、この本を読む限り、著者はクセもなく、さらりと誠実な人のようだった。
そして、一本の映画を完成させるためには、ほんとうにたくさんの人が関わっているんだなと教えてくれる本だった。
撮影前には、シナリオ執筆、スタッフの招集、配役、オーデション、ロケハンなどをやる必要がある。ロケハンというのは、ロケーション・ハンティングの略だ。要するに撮影場所を探して、決めるという作業だ。これは監督本人がやることが多いらしいが、場面によっては、助監督がやる。
たとえば、それがスーパーで買い物をするシーンだとしたら、たとえ30秒くらいのシーンでもシナリオの設定に近いスーパーを探して、撮影交渉をしなけばならない。相手方の了承を得たところで、監督に詳細を報告する。しかし、監督がイメージと合わないと判断したら、別のところを探さなくてはいけない。助監督の苦労は、水の泡だ。そんなことが日常的にあるのが映画作りらしい。
このスーパーのシーンは、ロケではなく、セットで再現することも可能だ。その場合は、美術さんが、監督のイメージやシナリオの設定に合わせて、スーパーのセットを作るのだ。
その際は、映画の時代設定に見合った品物を並べなければならない。撮影の日時に合わせて、品物を借りたり、スーパーだから生鮮食品を買って揃えたりする必要もある。もし、買い物をしているお客さんが必要なら、シナリオの設定時代に見合った服装をさせなくてはならない。
撮影当日には、役者が必要だし、客役のエキストラも必要だ。全員が衣装を着るし、メイクもするかもしれない。
撮影には、現場を仕切るスタッフが必要だし、カメラマンも必要だし、照明も必要だ。その他にも、衣装さんとかメイクさんとか、機材を運ぶ車両班も必要だし、出演者やスタッフの食事を用意する人も必要だ。
それらのスタッフは、どう考えてもそれぞれ数人は必要だ。助監督には、進行を管理する人と、カメラを管理する人と、美術を管理する人とかがいるらしい。映画作り全体のお金を管理する人も必要だし、日々の現場で財布を握っている人も必要だ。
撮影が終わったら、借りたものは返さなくてはならないし、買ったものは処理しなくてはならない。だから、それらは一々全部、記録されていなければならない。記録がないと、返品もしっかりできないし、場面が変わっても、役者の服装やメイクが同じでないと、画が繋がらなくなったりするからだ。だから、映画の現場には、専門の記録係がいる。
こういったことを考えただけで、私などは眩暈がしてくる。
映画作りには、素人の私が想像しただけでも、大量のスタッフが必要なことがわかる。しかも、その人たちは、おそろしいことに、基本的には、フルーランスなのだ。
この本を読むと、誰を雇う、雇わないは、監督の判断によるらしい。いつもの慣れた人と組むこともあるが、新陳代謝を考えて、別の人と新たに組んだりもする。
映画の場合、よく監督ごとに、なんとか組なんて言われることがあるが、そんな風に、大体は固定のメンバーで決まっているらしい。そこに新人が呼ばれて、新加入して、鍛えられ、成長していくものらしい。
しかし、新たに参加する者がいれば、卒業する者がいる。それが卒業だったらなんとなくもめない感じだが、切られたってことになると、切られた方が傷ついたりする。映画作りは、現場はハードだけど、人間関係はデリケートなのだ。役者のチョイスやオーディションも似たようなものらしい。
それまでの人を、別の人に変える時には、監督は身を切る思いをするのだ。本書では、そういう決断する監督の、葛藤も吐露されている。
その場その場画で判断するのが映画監督の大きな仕事
なんだかんだで、撮影が終わっても、編集作業が残っている。編集で丸ごとカットされるシーンなんかも出てくる。
音を加えたり強調したり、海外用に、セリフ以外の音を新たに録音しなおさないとならないらしい。へえ、そんなこともするのかと驚いたが、海外での場合、人のセリフはその国のコトバに吹き替えられることが多いのだ。
録音しやすいように、輸出する前に、人間のセリフとそれ以外の音を分けておく必要があるのだ。分けると言っても、実際には、スタジオの中で、音効さんが、音声を作りだして、再録音するのだ。
映画作りには、こんな風にそれぞれの段階に何人もの職人やプロのスタッフが関わっている。その人たちの手を経て、気が遠くなるような作業の積み重ねの末に、やっと作品が完成する。
そう思うと、どんな映画も襟を正してちゃんと見ないといけないような気持ちになってきた。
映画作りに関わるスタッフは、多分、プロ中のプロなんだろう。でも、彼らが関わるのは、どれだけ重要でも、部分でしかない。映画を作るなら、やっぱり監督じゃないとつまらないなど、私は無責任にも思ってしまった。
この映画『すばらしき世界』は作っている間に、世界中でコロナが流行してしまう。映画は完成したものの、映画館で上映できないという現実に直面する。そんなことが、この本では、西川監督の映画にかける熱い情熱とともに、ハラハラドキドキなんだけど、どこか淡々と語られている。
映画監督は、指揮官のようだ。刻々変化する状況に対して、的確な判断を下さなければならない。長い時間をかけて、地道に準備をしてきたものも、瞬時に切り捨てなければならないことも出てくる。どんなに迷っていても、時間までに決めるのだ。タイムリミットはすぐにやって来る。映画作りは、判断の積み重ねなのだ。
この本は、そういった映画監督業に対する、言い訳や、免罪、のために書かれたような気がしないでもないが、それ以上に著者である西川監督の誠実さが伝わってくる本だった。私はこの本を、映画のメイキングとしてよりも、職業論として読んでしまった。
西川監督には、エッセイや小説といった著作も数冊ある。本書を読む限り、語彙も豊富だし、文章表現も豊かで的確だ。文才もある人だと思った。そういう人の作った映画を見たくなった。ネットフリックスで配信してくれないかなあ……。
あ、そうだ、私は役所広司の顔が見たかったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
