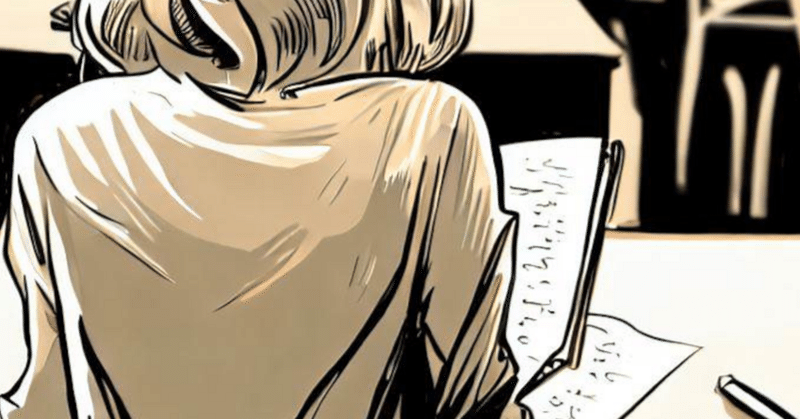
(短編ふう)タイムカプセル
実家の机の抽斗から、半世紀前の創作文が出てきた。
のび太の机はタイムマシーンの入口だが、実家の机は抽斗自体がタイムカプセルだ。
原稿はすっかり日に焼けてしまっている。
――――――――――
題:幼少の頃
幼稚園の頃、「おひるねのお時間」という一見とても悠長時間があった。
一見、である。
その実は眠かろうが眠くあるまいが無理矢理ひとを毛布の中に押し込めるのだから、眠くないこっちはたまったものじゃなかった。
実際、私は一度だって本当に眠ったことはない。眠らないと後で肝油ドロップがもらえないので無理にじっとして眠ったふりをしていただけだ。
そして、全くどういうわけか「おひるねのお時間」はえらく長かった。
私はこの長い時間を教室のロッカーの数を数えたりしてどうにかこうにかやり過ごしていた。気の弱い幼児であった私はこの退屈を、幼児には珍しい不屈の精神で黙ってよく耐えていた。しかし、内心、「毎日毎日そうそう昼寝ばっかりできるかい」と誰かが威勢のいい抗議をしてくれないものかと常に待ち望んでいた。その時には、及ばずながら即その傘下にはせ参じようと、いざ鎌倉の構えも怠りなかった。だが、とうとうそういう勇気ある幼児は現れなかった。
実際、どいつもこいつも、よくこれだけ悩みのない顔で眠れるものだ、と感心せずにはいられないくらい毎日毎日よく眠りこけていやがった。
しまいに私は、教室中のありとあらゆるものを数えてしまい、ついには暗記するまでになってしまっていた。
ロッカーの数。窓の数。窓の桟の数。
片隅に寄せられた机と椅子の脚の数。これは今思い出してみても難敵であった。目がちらちらして、私は何度も初めからやり直さなければならなかった。だが、私はいつしかこれも克服していった。この難敵を下した時、私は机の脚の一本一本、椅子の脚の一本一本、全ての脚のそれぞれの特徴をすっかり暗記していた。
しかし、今思えば、もうこの絶頂期から既に私は先生に目をつけられていたのだ。
ある日、私は級友のKという名の幼児に得意気に次のような質問をあびせた。
「おい、おまえはこの教室にロッカーが幾つあるか知っているかい?」
Kはハナで汚れた顔の真ん中に口をポカンと開けていた。
おら知んねえ、という顔だ。
世の中にこれ程無感動な顔もないものだと思った。
こんなやつに問うた自分が我ながら恥ずかしい。
「2行21列。全部で42個だよ。」
私は疲れた口調になった。
すると、その時だ。頭上で「そうか。そうだったのか。」という声がした。
驚いて見上げると、いつの間にかそこにはS先生が立っていた。
「そうか、そうだったのか。」
その大人はもう一度確かめるようにつぶやいた。
私は思わず後ろへたじろいだ。
Kは親指をしゃぶりながら私の様子を不思議そうに見ている。
「そうか、H君は(私のことである)いつもお昼寝のお時間、そんなことをしていたのね。」
先生は一歩足を踏み出した。
「ロッカーの数を数えていたのね!」
私は突然、背筋が凍るような恐怖に突き上げられて激しく首を振った。
「否定しても無駄よ!!」
先生は寸部の隙も見せずに立ちふさがっている。逃げ道はない…。
「君がいつも眠っていないのは知っていたわ!でも証拠がなかった…。だから、私はおよがすつもりで肝油ドロップをあげていたのよ。それに君は気がついていなかったようね。さあ、もう観念しなさい。君は眠ってなんかいない!ロッカーの数を知っているのが何よりの証拠よ!!!」
もうだめだ。
私はガックリと膝をついていた。
―――――――――
ほのかに甘い憧れを抱いていた文芸部の先輩に、得意気にこの原稿を見せたのを覚えている。
どう評してくれたか、は覚えていない。
ほんのちょっとクスリとしてくれたような気もするが、困ったようにただ返されたような気もする。
なにぶん先輩に見惚れていた。
きちんとアイロンのかかったブラウスの肩にセミロングの髪が優雅にかかっていた。
―了―
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
