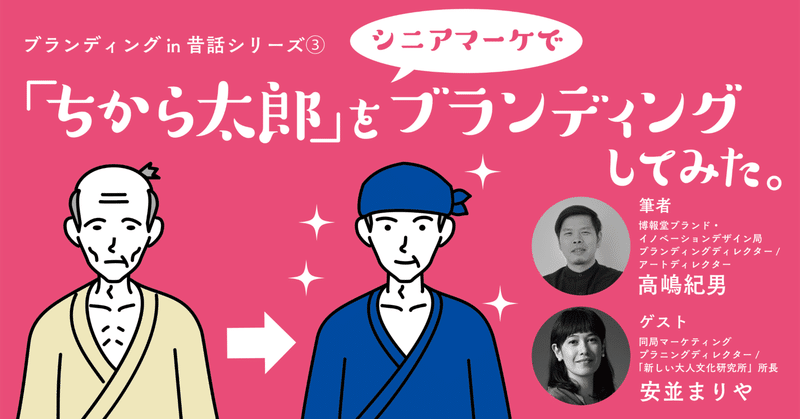
「ちから太郎」をシニアマーケでブランディングしてみた。
はじめまして。もしくはお久しぶりです。博報堂ブランド・イノベーションデザイン局(以下BID)のブランディングディレクター高嶋紀男です。
今回は第一弾『「かさじぞう」でブランディングしてみた。』、第二弾『「つるの恩返し」をSDGsでブランディングしてみた。』に続くシリーズ第三弾です。
このシリーズの趣旨は下記のとおりです。
私は、たまに学生さんとお話をする機会があるのですが、いつもブランディングについて伝えるのは難しいなあと感じます。
わかりやすく伝えるには例え話だろうと思い、昔話でブランディングを語るというアイデアを思いつきました。
昔話では、正直で働き者だが清貧な主人公が、超常現象によって報われるというストーリーがとても多いように思います。
しかし、現実はそうはいきません。正直で働き者であれば必ず超常現象が起こるわけではないのですから。
超常現象に頼らず、企業や事業主が世の中に認められるために行う活動が、いわゆるブランディングと呼ばれるものだと私は考えます。
この連載では、筆者が所属するブランディングの専門部署BIDの各分野のスペシャリストをゲストに迎え、ゲストと筆者が、「ブランディングを昔話に当てはめてみたらどうなるか」というテーマで話し合いながら、昔話をリライトします。
第三回のゲストはマーケティングプラニングディレクター で「新しい大人文化研究所」所長の安並まりやさん。
シニアマーケティングの視点で「ちから太郎」についてのブランディングのアイデアをいただきながら、「ブランディングちから太郎」を創作してみました。
原作の「ちから太郎」もしくは「垢太郎」は、ものぐさな老夫婦が久しぶりに風呂に入ったことで出てきた大量の垢で作った人形が動き出し、老夫婦が献身的に育てた後、悪者退治を果たして富を得て凱旋し、すっかり元気になった老夫婦が村人たちと共に盛大に祝うというあらすじが主流のお話です。
主人公はちから太郎ですが、老夫婦が生きがいを見つけて活気を取り戻す話でもあります。
さて、どんな「ちから太郎」になったでしょう?

ブランディングちから太郎
むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんとおばあさんは、まずしく、ものぐさなので、めったにお風呂に入りません。ある日、久しぶりに二人でお風呂に入ると、垢がわんさか出てきました。あまりにも出てくるので「ちょっと人形でも作ってみよう」と、垢をこねはじめました。
すると、ふたりとも楽しくなってきて、いつの間にか人形作りに夢中になっていました。やがて、みごとな力強い男の子の人形がひとつ出来上がりました。
おじいさんは言いました「これは、今にも動き出しそうじゃ」
するとおばあさんが、「あっ、いまちょっと動いたような・・」
・・・それは気のせいでした。
垢の人形が動くわけがありません。
しかし、それくらい上手に出来ていたのは確かです。
おじいさんは言いました。
「こんなに楽しくなったのは久しぶりじゃのう。しかも、なかなかうまくできたんじゃないか」
「そうさねえ、じいさんは才能があるのかもしれないねえ」
特におじいさんは、今まで力仕事しかしていなかったぶん、体力が落ちてからは他の何をやってもうまくいかず、無気力になっていたので、嬉しさもひとしおです。ちなみに、おばあさんに褒められたのも20年ぶりでした。
「もう垢はないが、ここら一帯は粘土が多いから、それで人形をつくってみよう。」
おじいさんは言いました。
創作意欲がとどまらないおじいさんは、力強い男の子の粘土人形を
次々とつくりました。
それらを乾かしがてら庭に飾っていると、村の年寄りたちの目に止まりました。
年寄りたちの数人がなぜか「作り方を教えて欲しい」と言ってきました。
話を聞いてみると
「最近は歳のせいか、力仕事はもちろん、他の仕事もする気力がなくなってしまってのう。せがれたちからのプレッシャーがすごいんじゃ。あんたらみたいにものぐさな年寄りが元気になってるのを見て、人形作りを習えばわしも働く気力がとりもどせるんじゃないかと思ってのう。」
このころは、老人は働けないと家族に冷遇される時代でした。
おじいさんは、面と向かって「ものぐさ」と言われたことにモヤッとしながらも、成る程と思い、人形作り教室を開くことにしました。
教室は大盛況。
人形作りで気力が蘇ることはもちろん、みんなが集まり会話をする場ができることで、家に居場所がない老人たちのコミュニケーションの場となったからです。
しかし、数ヶ月経ったころ、ある生徒が言いました。
「わし、ここが好きなんじゃが、そろそろやめないといけないと思っておってのう。ここに払う月謝を息子夫婦からもらうのが申し訳なくて。。」
おじいさんとおばあさんはどうすべきか話し合いました。
おじいさんがぽつりと言いました。「出来た人形は売るほどある。。」
するとおばあさんが言いました。
「そうじゃ!売ればいいんじゃ!
みんなうまくなってきてるから、クオリティは申し分ない。」
「『お年寄りがちからを取り戻し、見るものにちからを与える』という願いを込めて、商品ブランド名は『ちから太郎』はどうじゃ?

おじいさんが言いました。「よいのう!風のうわさで、子供のおもちゃとして内輪で作っていたものが土地の名産品として売れていると聞いたことがある。いける!」
おばあさんが言いました。
「そうすれば生徒たちに給料が払えるから、彼らの家での立場もあがるはずじゃ!」
こうして、人形作り教室は工房となり、お年寄りたちを研修込みで雇用するようになりました。
ちなみに売り物にするに当たって、人形は焼き物にすることにしました。
「お年寄りが、今にも動き出しそうなほどの生命力のあふれる人形をつくっている」というギャップのあるストーリーが縁起いいと、評判は上々で、村を支える産業にまで発展しました。
そして、力仕事が出来ているうちに工房で習い始め、お年寄りになると「ちから太郎」づくりに移行するというシームレスなキャリアロードマップが出来上がりました。

こうして、この村のお年寄りたちはみないつまでも元気に暮らしましたとさ。
めでたしめでたし。
おしまい。
振り返り
原作の「力太郎」もしくは「あか太郎」がいつ出来たかはわかりませんが、中世の日本は、労働力ではない老人を養う福祉の概念はなく、肩身が狭かったと言います。そして案外長生きだったとも。
現代も、もちろん福祉はありますが、頼り切ることが出来ないのが現状で、定年後に悠々自適な余生を過ごせることが難しい時代になっています。そしてやはり長生きです。
また、今の老人(とくに男性)は、人生の大半を仕事に費やし、それ以外での社会とのつながりを構築しないまま定年を迎え、「ちから太郎」の主人公のように無気力な状態に陥る方も多いそうです。
しかし、それを打開するため、「趣味を持つ」を通り越して「起業する」方も多く、なんと今の日本の起業家の4割近く(e-stat 「統計で見る日本」令和4年就業構造基本調査より)が65歳以上だといいます。
この「ブランディングちから太郎」におけるちから太郎工房は、ここでの老人たちにとって、今で言う「社会的処方*」なのかもしれません。
*「社会的処方」とは「薬を処方することで、患者さんの問題を解決するのではなく『地域とのつながり』を処方することで、問題を解決するというもの」。例えば、うつ病を抱えている患者さんを地域の趣味のサークル活動とつなぐなど、心身の不調を治療する際に薬で対処するのではなく、地域資源を通して生活環境を変えて困りごとを解決こと。
博報堂は、「100年生活者」発想でシニアビジネスを 開発・実施するワンストップ専門部隊「シニアビジネスフォース」で、新しい価値やビジネスチャンスを生み出す、創造的で実践的なビジネスソリューションを提供いたします。
https://hakuhodo-seniorbussiness.com/
また、生活者や社会とともに進めていく事業変革・事業成長のことを「ブランド・トランスフォーメーション(以下BX)」と定義しています。
https://www.hakuhodo.co.jp/bx/
ブランディングやBXに関して、もし少しでもご興味を持たれた方は下記リンクをのぞいていただければ幸いです。
BIDホームページ https://h-bid.jp/#top
BID Twitter https://twitter.com/hakuhodoBD
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
