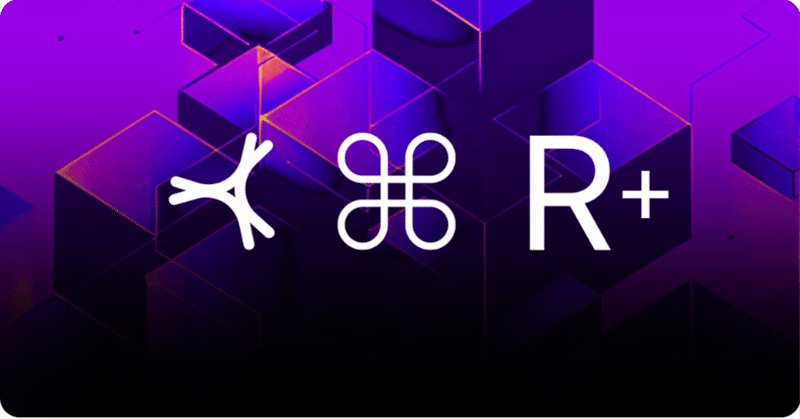
Command R+は面白い小説を書けるのか?
概要
先日Command R+というLLMが発表されたことをご存知でしょうか?
Command R+とは、Cohereという企業が発表した、RAGやToolの使用に最適になるように学習させたLLMです。
特徴として、学習に使用したパラメータが100Bと非常に少ないこと、そしてそんなに少ないにも関わらず、GPT-4やClaude-3に匹敵する性能を持っていること、非商用ではあるが生のモデルが公開されていること、などが挙げられます。
そして、自分が使用していてもう一つ、特徴的なことがありました。
それは、極端に高いモラルを持っていないこと。
GPT4などは非常に高いモラルを持っています。言い換えると、めちゃくちゃお上品なことしか言ってくれません。
しかし、Command R+は使用している限り、そのモラルによる制限がかなり少ないように感じられます。
使っていて、GPT4などでよくある、「そのようなことは言わないように~」みたいな表現で制止されることはありませんでした。
では、そんなCommand R+なら面白い小説も書けるのではないだろうか?
それがこの記事の主題です。
GPT4とかが書く小説って正直つまらないんです。お上品な道徳の教科書に載っているようなことしか言ってくれないから。
ではお上品なこと以外も言ってくれて、かつ性能も高いCommand R+なら面白い小説も書けるかもしれない。
そう考えて、今回の実験を行いました。
実験1
実験方法
まず、実験環境としては、以下のCohereが提供しているHuggingFaceのSpaceで行います。
https://huggingface.co/spaces/CohereForAI/c4ai-command-r-plus
LLMには小説の世界観とプロット、書く上での注意点を指示文として与えます。
世界観とプロットによって面白さが左右されるので、そこを人間が考えてはだめなのでは? という意見はあると思いますが、元々はこういう小説読みたいけど、自分で書いたらそんなに楽しめないんだよなー、と思っていたところからこの実験は始まったのでそこはご容赦ください。
世界観とプロットを与えた場合、AIはそれを面白く描写できるのか、という検証と考えていただければ。
与えた指示文
あなたは優れた小説を書くAIです。
以下の世界観とプロットから、面白い物語を記述してください。
世界観:
時は27世紀。
魂の存在を実証し、AIにほぼすべての労働を任せるユートピアにしてディストピアを生きる人類たちは、そのほとんどがニートになっていた。
そのなかの一人、堀川大樹は、今日も今日とて自分の作ったVR世界で一人、グレンという名前の魔術師として遊んでいる。
そんな彼の、ある日のファンタジー世界での冒険のお話
主人公の名前はグレン。魔術師である彼は4人で冒険者PTを組んで生活をしていた。PTのメンバーは優しい性格の少女である剣士クレハ、美しいお姉さんでミステリアスな雰囲気を持つ狩人レナ、PTのタンク役であり重厚な鎧に身を包む騎士のドロン。
彼らは中堅のPTで、若き新鋭と冒険者の酒場では思われている。
グレン以外の人物はみんなこのファンタジー世界で実際に生活をしているように認識していて、死ぬと実際に死ぬ。
グレン=堀川だけは、死んでもその世界からログアウトするだけだが、他の人たちはグレンが死ぬとそのまま死ぬと思っている。また再びグレンというキャラクターを使用して行動することはできないように堀川は設定している。堀川は世界観を崩したくないので、ログアウトとか、現実世界のことは一切言わずに、普通にファンタジー世界の住民としてファンタジー世界にいる間は生活している。
あとグリフィンは人間の言葉は話しません。
プロットは以下のものです。
プロット:
物語は冒険者の酒場で、昨日の冒険をPTメンバーで語り合う場面から始まる(冒険の内容は適当に考えてください)。
冒険を語り合っていたが、その途中で酒場の主人から大物である魔獣、グリフィンの討伐依頼を受ける。
途中まではうまくいっていたが、けがを負ったグリフィンが暴れて、クレハが大きなけがをする。
彼女を守るため、グレンは魔術でグリフィンを引き付けて囮となる。
クレハはそれを涙を流しながら拒否するが、ドロンに担がれてグリフィンから逃げることになった。
結局グレンはクレハたちを逃がせたことで満足して、そのままグリフィンに殺されてしまう。
それを遠目で見ながら絶叫するクレハを尻目に、グレンは殺されたことで、VR世界からログアウトして、自室でVRマシンの中にいる堀川大樹に戻る。
今日の冒険は失敗しちゃったなー、と言いながら、堀川はのんきにお茶を飲むのだった。(終了。クレハの悲痛さと堀川ののんきさを対比させる。)
指示:
文体は上質なファンタジー作品のように記述してください。
また、文章は小説のように、できるだけ詳細まで描写してください。人物の体の動きや心情描写、情景まで描写してください。
また描写はグレンの一人称で行い、一つ一つの描写に最低5行は記述してください。
優れた小説家のように、同じ描写を繰り返すことなく、読みやすくわかりやすい文にしてください。
物語はプロットに書かれたものが全体で2万文字になるぐらいの想定で、記述してください。
2万字も出力できない場合は、途中まででいいので、2万字になるように記述してください。
主人公がログアウトするまでは現実世界である27世紀の情報はモノローグにも決して出さないように。生成された小説1
冒険者たちの憩いの場、ロスト・ウルフ・イン。古びた木の看板が風に揺れるこの酒場は、私たち冒険者パーティーのもう一つの拠点だった。
「昨日の冒険は本当に凄かったわね、グレン。あなたの魔術が無事に成功して、本当に良かった」
剣士のクレハは、冒険の成功を喜びながら、食事を前に瞳を輝かせていた。クレハは、パーティーの中では一番年下で、まだ冒険者としては新人だ。細い体躯に、長い黒髪をなびかせた少女は、冒険者というよりは、可憐な乙女のようだった。
「ああ、あれは危なかったよ。一歩間違えれば、僕たちがあの世行きだった」
そう言って笑う私、魔術師のグレンは、このパーティーのリーダーだ。赤いローブを身に纏い、魔法の杖を携えている。
「でも、クレハの剣技が素晴らしかったから、僕の魔術も成功したんだ。君に感謝しないとね」
「えっ、とんでもないです! 私なんてまだまだですよ。グレンさんや、レナさん、ドロンのような先輩方に追いつけるように、もっと頑張らないと!」
クレハは、はにかみながら、食事に手を伸ばす。
「ははは、謙遜しなくてもいいさ。クレハは立派な剣士だ。僕たちが守ってあげないとね」
そう言って、鎧に身を包んだ騎士のドロンが、豪快に笑う。ドロンは、パーティーのタンク役として、常に前線で敵の攻撃を耐え忍んでくれる頼もしい存在だ。
「でも、あのゴブリンたちの群れは、本当に厄介だったわ。一匹や二匹なら、簡単に片付けられるけど、あれだけの数が一度に襲ってくるなんて、珍しいわね」
ミステリアスな雰囲気を纏った美しい狩人、レナが、しなやかな手でグラスを口元に運びながら言う。レナは、弓の使い手で、ドロンが敵の注意を引きつけている間に、的確にゴブリンたちを仕留めてくれた。
「ゴブリンの群れは、最近この辺りに多く出没しているらしい。何か理由があるのかもしれないな」
私は、一口ビールを口に含みながら、少し考え込むように言う。この世界では、様々な魔物や魔獣が棲息しており、冒険者たちは、人々から依頼を受けて、それらを討伐したり、護衛をしたりして生計を立てている。
「さて、今日はのんびりできるかなと思ったけど、どうやらそうもいかないみたいだね」
そう言って酒場のマスターが、一枚の紙切れを私たちのテーブルに置いた。
「また依頼ですか?」
クレハが、少し疲れたような声を上げる。
「ああ、この辺りの村々を脅かしている魔獣、グリフィンの討伐依頼だ。このままでは、村人たちに被害が出かねない。君たちならきっとやってくれると期待している」
マスターは、少し不安げな表情を浮かべた村人から依頼を受けたのだろう。
「グリフィンですか......」
私は、少し考え込んだ。グリフィンは、巨大な鷲のような姿をした魔獣で、非常に獰猛で知能も高い。グリフィンの討伐は、冒険者にとっては非常に危険な任務だ。
「私たちだけでグリフィンを倒すのは、厳しいのではないでしょうか?」
レナが、慎重な口調で言う。
「確かに、グリフィンは強敵だ。だが、君たちは中堅の冒険者だ。きっとやってくれると信じているよ」
マスターは、にっこりと笑った。
「......分かりました。やってみましょう」
私は、マスターの期待に応えるように、決意を込めて言った。
「よろしく頼むよ、君たちならきっとやってくれる!」
マスターは、ホッとしたような表情を浮かべた。
「さて、早速準備をしよう。グリフィンは、この近くの山岳地帯に棲み付いているらしい」
私は、パーティーに呼びかけながら、立ち上がった。
「山岳地帯ですか......。厳しい戦いになりそうですね」
ドロンが、少し険しい表情で言う。
「大丈夫、私たちがついていますから。クレハ、レナ、準備をお願いします」
私は、二人に優しく微笑みかけた。
「はい!」
二人は、力強く答えた。
こうして、私たちパーティーは、グリフィン討伐に向けて、冒険の旅路についたのだった。
山岳地帯へと続く道は、険しく、足場も悪かった。
「この先が、グリフィンの棲家か......」
私は、険しい表情で、眼前に広がる山岳地帯を見上げた。
「あの巨大な鷲が、グリフィンなのね......」
レナが、不安げな表情で、空を舞う巨大な影を見上げる。
「油断は大敵だ。慎重にいけば、きっと勝機はある」
ドロンが、決意に満ちた表情で言う。
「はい!」
クレハは、緊張した面持ちで、剣を握りしめた。
「では、行くぞ!」
私は、杖を構えながら、先頭を進む。クレハとレナがその後に続き、ドロンが後衛を務める。グリフィンは、すでに私たちに気づいているようで、鋭い鳴き声を上げながら、上空を旋回していた。
「まずは、あいつを地上におびき寄せよう。レナ、上空から攻撃できる位置を取ってくれ」
「了解!」
レナは、素早く反応し、的確な位置取りをする。
「クレハ、ドロンは、地面に降りたグリフィンを迎え撃つ準備を」
「任せてください!」
クレハは、力強く答え、ドロンは、重厚な鎧を身に纏った体を構える。
グリフィンは、私たちの作戦を理解しているかのように、一度上空高く舞い上がった。そして、鋭い爪を振り下ろしながら、私たちに向かって急降下してきた。
「今だ! レナ!」
「はい!」
レナは、弓を構え、矢を番える。
「放て!」
私の合図で、レナの矢が、グリフィンの翼を狙う。
「グァァァァ!」
グリフィンは、痛々しい鳴き声を上げながら、地上へと落下していった。
「今だ! 攻撃だ!」
私たちは、一斉にグリフィンめがけて攻撃を開始する。クレハの剣がグリフィンの身体を切り裂き、ドロンの斧が、グリフィンの翼を叩き割る。
「グレン、気をつけて!」
レナの警告が、耳に響いた瞬間だった。
「うわっ!」
グリフィンが、傷ついた体で、私めがけて突進してきた。
「クレハ、危ない!」
私は、クレハを突き飛ばし、自らグリフィンの攻撃を受けた。
「グレン!」
クレハが、涙ながらに叫ぶ。
「クレハ、逃げろ!」
私は、魔術でグリフィンを引き付けながら、クレハたちに逃げるよう指示した。
「嫌です! グレンと一緒に逃げます!」
クレハは、涙ながらに訴える。
「クレハ、君は生きろ。僕は、君を守りたいんだ」
「でも......!」
「クレハ、行け!」
ドロンが、クレハを抱え上げ、走り出した。
「グレン、気をつけて!」
レナが、弓を構えながら叫ぶ。
「ああ、任せてくれ!」
私は、グリフィンに魔術を浴びせながら、応えた。
「グァァァァ!」
グリフィンは、怒り狂ったように、私に襲いかかる。
「くっ!」
グリフィンの巨大な爪が、私の身体を引き裂いた。
「グレン!」
クレハが、遠くから叫ぶ声が聞こえた。
「ごめんね、クレハ。僕は、君を守れなかった......」
そう思いながら、私は、意識を手放していった。
「グレン! 起きて! グレン!」
クレハの声が、耳元で響いた。
「ここは......?」
私は、ゆっくりと目を開けた。そこは、見慣れた自室だった。
「ああ、また死んじゃったか......」
私は、のんきに伸びをしながら、VRマシンを外した。
「今日の冒険は失敗だったな。クレハ、ごめんよ」
私は、自室のテーブルに置いてあったお茶を飲みながら、のんきに一言つぶやいたのだった。
こうして、今日も堀川大樹の冒険は終わりを告げた。ユートピアにしてディストピア、ニートだらけの27世紀。この時代の冒険譚は、まだまだ続きそうだ。生成された小説2
「さて、今日はどうだったかな。やっぱり、あのゴブリンが予想以上に強くてね。危うくやられるところだったよ。」
冒険者の酒場に集まった私、魔術師グレンの言葉に、PTのメンバーはそれぞれの感想を口にする。優しい瞳をした剣士クレハは、少し恥ずかしそうにしながらも、
「ええ、あの時は本当に驚きました。でも、グレンさんが素早く魔法で援護してくださったおかげで、なんとか倒せましたね。」
と、にこやかに振り返る。美しい黒髪が印象的な狩人レナは、ミステリアスな微笑みを浮かべて、
「ふふ、あの時は私も弓を射るのに精一杯だったわ。クレハ、あなたが前衛で頑張ってくれていなければ、もっと危ない戦いになっていたかもね。」
と、クレハを讃えた。PTのタンク役、重厚な鎧に身を包んだ騎士ドロンは、豪快に笑いながら、
「ははは! だが、無事に帰ってこられたから良しとしよう! それに、今日はなかなか良い稼ぎになった! このまま行けば、近いうちにランクが上がるかもしれん!」
と、金貨の入った袋を揺らして見せた。私たちは中堅のPTとして、このファンタジー世界で日々冒険に挑んでいる。この世界では、魔法やモンスター、そして冒険者が本当に存在する。
私は、この世界を創り出した一人でもある。堀川大樹――それが、この世界では魔術師グレンとして存在している私の、現実世界での名前だ。27世紀、魂の存在が実証され、AIが労働を担うユートピアにしてディストピアと化した世界。そこで私は、このVR世界を創り、冒険者として生活を送っている。
だが、この世界の住人であるPTのメンバーたちは、私が創り出したキャラクターを演じているのではなく、彼ら自身としてこの世界を生きている。彼らにとっては、この世界が現実なのだ。そして、彼らがこの世界で死ねば、それは本当の死を意味する。
「さて、今日も依頼をこなして、さらに稼いでいくか。」
ドロンの言葉に、私たちは酒場のカウンターへと向かった。カウンター越しに、酒場の主人――ボルガロが、新たな依頼の書かれた紙片を差し出す。そこには、こう書かれていた。
『大物魔獣グリフィンの討伐』
グリフィン――それは、巨大な鷲のような身体に、獅子のような頭部を持つ魔獣だ。その翼を広げれば、ゆうに10メートルは超えるだろう。その強さは、冒険者ランクの中でも上位に位置する者でも、単独で討伐するのは難しいとされる。
「これは大物だな。だが、我々にだって十分な実力はある! 受けて立とう!」
ドロンの言葉に、私たちも同意した。こうして、私たちPTはグリフィン討伐へと旅立つのだった。
早朝、私たちはグリフィンが目撃されたという森へとやって来た。木々の間を抜ける風が、冒険の始まりを告げるように爽やかに吹いている。
「さて、グリフィンは空を飛ぶから、見つけるのは大変かもしれない。森の中をくまなく探そう。」
レナの提案に、私たちは森の中に分け入っていった。冒険者としての勘を頼りに、グリフィンの痕跡を探す。
「あ、ここに巨大な爪痕がある! グリフィンのものかもしれない!」
クレハが鋭い瞳で地面の痕跡を見つけた。確かに、巨大な鷲の爪で引っ掻いたような跡がある。
「よく見つけたな、クレハ。さすがは我らの剣士だ。」
ドロンがクレハの肩を叩いて讃える。クレハは少し頬を赤らめながら、
「えへへ、ありがとうございます!」
と、嬉しそうに笑った。
私たちは、その爪痕を辿るようにして森の中を進んでいった。森の奥深くへと進むにつれ、グリフィンの気配が濃くなっていくのを感じる。
「くっ、この先には間違いなくグリフィンがいる。気を抜くなよ。」
ドロンの警告に、私たちは身を引き締める。緊張感が高まる中、さらに森の中を進んでいった。
その時だった。
「グァアアアア!」
突然、巨大な影が空から降りてきたと思った瞬間、私たちは巨大なグリフィンの猛攻に晒された。その巨大な爪が、私たちを狙う。
「みんな、散開して! グリフィンは空を飛ぶから、まとまるとやられるぞ!」
ドロンの指示に、私たちは急いで散開する。グリフィンは、クレハを狙って急降下してきた。
「クレハ、危ない!」
私の警告が届くよりも早く、グリフィンの巨大な爪がクレハを襲う。
「きゃあああ!」
クレハの悲鳴が森に響く。彼女の身体からは、鮮血が流れ出ていた。
「クレハ!」
私たちは、一瞬凍りついたように動けなくなる。クレハは、傷つきながらも立ち上がり、剣を構えてグリフィンに立ち向かおうとする。
「クレハ、下がっていろ! ここは俺が引き付ける!」
ドロンが、クレハを庇うようにして前に出る。彼の鎧が、グリフィンの爪を受け止める。
「グレンさん、レナさん、クレハを! 俺はなんとか持ちこたえる!」
ドロンの言葉に、私たちは我に返った。
「クレハ、しっかり掴まっていろ!」
レナが、クレハに駆け寄り、彼女を背負うと、素早く木々の間を走り抜けていく。
「グレンさん、援護を!」
レナの声に、私は魔法を発動させた。
「火の玉よ、我が敵を焼き尽くせ! 『ファイアボール』!」
私の魔法が、グリフィンを狙い撃つ。だが、グリフィンは翼でそれを弾き飛ばした。
「くっ、なかなか手強い相手だな。」
私は、さらに強力な魔法を唱えるべく、呪文を紡ぎ始める。
「グレン、危ない!」
クレハの声に、私ははっと我に返った。グリフィンが、私に突進してきていたのだ。
「うわああ!」
私は、間一髪のところでその場から飛びのいた。グリフィンの巨大な爪が、私がいた場所を抉る。
「クレハ、レナ、早く逃げてくれ! ここは俺がなんとかする!」
私は、クレハとレナに声をかける。クレハは、涙を流しながらも、レナに促されて逃げていく。
「グレンさん、気をつけて!」
レナが、振り返りながら叫ぶ。私は、彼女たちを逃がすために、グリフィンに立ち向かった。
「さて、相手は空を飛ぶか。ならば、これだ!」
私は、グリフィンを狙って、魔法を唱える。
「風よ、我が敵の動きを封じよ! 『エアロ Bind』!」
私の魔法が、グリフィンの周囲に渦を巻き起こす。グリフィンの動きが封じられ、その巨体が宙に浮かんだ。
「今だ! みんな、逃げろ!」
私が叫ぶと同時に、ドロンが剣を振りかざしてグリフィンを斬りつける。
「くそ、離れろ小僧!」
グリフィンが、ドロンを振り払おうと暴れる。その巨大な翼が、私を襲う。
「ぐああ!」
私は、グリフィンの翼に叩きつけられ、森の奥深くへと吹き飛ばされた。
「グレンさん!」
クレハの声が、遠くに聞こえた気がした。私は、森の葉陰に倒れ込んでいた。身体中が痛み、動くこともできない。
「みんな、逃げてくれ。これが、俺の魔術師としての......最期だ。」
私は、静かに目を閉じた。
「グレンさん! 待ってください!」
クレハの声が、再び聞こえた。だが、その声は遠く、霞がかっているように感じた。
「......ログアウト」
私は、静かにVR世界からログアウトした。
「今日の冒険は、失敗だったな。」
堀川大樹――魔術師グレンとしての冒険を終えた私は、のんきにお茶を飲みながら、今日の冒険の反省をしていた。
VRマシンの中で、私は再びこのファンタジー世界に挑戦することを心に誓うのだった。考察
うん、あまり面白くないですね。
いや、プロット通りには書いてくれているんですが、でもやっぱり面白くない。
これはそもそものプロットがあまり面白くないという可能性はありますが(プロットが肝心の冒険部分をかなり端折って書いてしまってるので)、でもそれでもあまり面白くない。
表現の描写はある程度一貫性を保てています。
ただ指示文を守ってくれないことは結構あります。
二万字で表現してと何度も言っているのに、3000文字程度の文章になってしまっている。
ただこれはそもそもプロットの量が少なすぎるから膨らましようがないという可能性はあります。
プロットが小説の面白さのボトルネックになってしまっているようにも見えるので、次は世界観だけは与えて、プロットをまずAIに書いてもらって、そのうえで小説を生成するか、そもそもプロが書いた、できればそれを元に人間が描いた小説もあるプロットを使用して実験してみようと思います。
実験2
実験環境
今度は、あらかじめある程度形になっているプロットを使用します。
使用するプロットは以下のサイトに書かれているプロットを使用しています。
それ以外の環境は実験1と同じです。
https://monosai.com/faq/d-plot
与えた指示文
あなたは優れた小説を書くAIです。
以下の世界観とプロットから、面白い物語を記述してください。
設定
主人公は元プロボクサー。
23歳ぐらい。若い。
「勝たないと意味がない」と思ってる。
無敗で世界タイトル挑戦までいった。でも負けた。そこで潔く引退。
経験を活かしてボクシングの小説を書こうとする。
小説を書くのは生まれて初めて。
話のスジ
【起】
引退会見にのぞむ主人公。なぜ早々に引退するのか聞かれ「勝つ姿を見せられないボクサーに存在意義などないからだ」と言い放つ。
引退後、のんびりした暮らしをする主人公。でも退屈で何の張りもない生活に飽きてくる。どうすればいいのだろう。「そうだ。小説を書こう。経験を活かせばいいボクシング小説が書けるはず」
【承前半】
自分と同じように「勝たないと意味がない」と思っているボクサーの小説を書く。無敗で世界チャンピオンになる男のストーリー。自分の叶えられなかった夢を叶えるボクサーの話。
そうやって小説を書き上げた。でもなんだか面白くない。
なぜつまらない小説になってしまうのか、その原因の検討がつかない。仕方がないので取材に行くことにする。
【承後半】
お世話になっていたジムを訪問。取材する。
自分がデビュー戦でKOしたベテラン選手の引退試合も見に行く。弱い選手だったけど意外とたくさんのファンが駆けつけていた。
大怪我をして再起不能と言われた選手の復帰戦も見にいった。負けてしまったけど彼は今の自分にできることを必死にやろうとしていた。
新人王戦のとき1ラウンドで軽く倒した選手も取材させてもらった。もう子供がいて試合も何回か見に来ているらしい。でも毎回負けている。「今度こそ勝つところを見せたい」そう意気込んでいた。
【転結】
主人公はジムの会長に頼まれて天才高校生とエキシビジョンマッチで戦うことに。オリンピックを目指している期待の若手だ。
前座として他の選手の試合もいくつか組まれていた。「子供に勝つところを見せたい」と言っていたあの選手の試合もあった。主人公は会場の後ろの方からその試合を観戦する。彼の奥さんと子供も見に来ていた。でも彼は今回もやっぱり負けてしまった。泣き崩れながらリングを降りるその姿が主人公の胸に刺さる。
主人公はリング上で天才高校生とグラブを交える。彼の強烈なパンチを受けながら主人公はずっと自分の中にくすぶっていたものに気づく。
主人公は小説を書くことをやめて現役復帰のトレーニングをはじめる。もう一度世界タイトルに挑戦するのだ。
重要項目
オモテのストーリー
ボクシングの小説を書いて賞に応募。
裏ストーリー
引退したあと胸にくすぶっていたものを払拭。
秘めたる想い
勝たないと意味がない。
間違いが正される
勝つことだけにドラマが潜んでいるわけではない。
指示:
また、文章は小説のように、できるだけ詳細まで描写してください。人物の体の動きや心情描写、情景まで描写してください。
また描写は主人公の一人称で行ってください。
優れた小説家のように、同じ描写を繰り返すことなく、読みやすくわかりやすい文にしてください。
物語は全体で2万文字になるぐらいの想定で、記述してください。
2万字も出力できない場合は、途中まででいいので、最終的に2万字になるように物語を膨らませて記述してください。生成された小説1
勝利への渇望、そして新たな挑戦
私は元プロボクサー、桐島 拳(きりしま けん)。23歳。若くしてプロボクシングの世界に飛び込み、無敗のまま世界タイトルマッチのリングに立った。しかし、その大舞台で敗れ、私は一度リングを降りる決断をした。
「勝たないと意味がない」
それが、ボクサーとしての私の信念だった。勝利こそがすべて。負けるということは、存在意義を失うことに等しかった。
華やかな勝利の美学を追い求めた末、私は早々に引退を決意した。潔くリングを降りる。それが、私の美学だった。
引退、新たな挑戦への模索
引退会見の日、多くの記者たちが私の周りに集まった。
「なぜ、こんなに若くして引退を決意したのですか?」
「まだまだ戦えるのでは? 再起を目指すのではありませんか?」
矢継ぎ早に飛んでくる質問に、私は真っ直ぐな眼差しで答えた。
「勝つ姿を見せられないボクサーに存在意義などないからです。私は負けました。だから、リングを降りる。それだけです」
きっぱりとそう言い放ち、私は会見場を後にした。
その後の生活は、静かで穏やかなものだった。毎日激しいトレーニングに明け暮れていた頃とは打って変わって、ゆったりと時間が流れていく。
しかし、こののんびりとした生活は、私を満足させるものではなかった。何か物足りない。刺激が欲しい。そう思うようになった。
「リングの上で戦う緊張感。勝利を目指して突き進む日々。また、あの感覚を味わいたい」
そんな思いが日増しに強くなっていった。
ある日、ふとこんな考えが頭に浮かんだ。
「そうだ、小説を書いてみよう」
私は幼い頃から本を読むことが大好きだった。中でも、ボクシング小説に心奪われたことが、私がボクシングの世界に足を踏み入れるきっかけとなった。
「私の経験を活かしたボクシング小説なら、きっと面白いものが書けるはずだ」
早速、パソコンに向かい、小説を書き始めた。主人公は私自身を投影したボクサー。無敗のまま世界チャンピオンを目指す男の物語だ。
毎日少しずつ書き進め、ついに小説を書き上げた。満足のいく出来栄えだった。
だが、この小説を人に見せるつもりはなかった。これは私自身の叶えられなかった夢を叶えるための物語。私の心の中だけにしまっておくつもりだった。
取材を通しての気づき
しばらくして、ふと書いた小説を読み返してみた。しかし、どこか心に響かない。何かが足りない。
「なぜ、つまらないのか?」
その原因が分からず、私はモヤモヤした気持ちを抱えていた。
「もっとボクシングの世界を深く知る必要があるのかもしれない」
そう思い立った私は、かつてお世話になっていたジムを訪ねることにしいた。
ジムの会長は、私を温かく迎え入れてくれた。
「おぉ、桐島くんか。久しぶりだな。元気そうじゃないか。最近は何をして過ごしているんだい?」
「はい。引退してからは、のんびり過ごしています。小説を書いたりもしています」
「小説だって? へぇ、意外な才能だな。ボクシング小説を書いているのかい?」
「はい。自分の経験を活かして、ボクシング小説を書いてみたくなったんです」
「そうか。ぜひ読ませてもらいたいものだな」
会長はにこやかに言うと、ジムの中を案内してくれた。
スパーリングに励む選手たち。汗を流しながらサンドバッグを叩く音。シャドーボクシングをする選手の鋭い動き。皆、真剣な眼差しでトレーニングに打ち込んでいた。
「私も、あの中の一人だったんだ」
懐かしさがこみ上げてくる。私は彼らの練習を見学させてもらいながら、自分の現役時代を思い出していた。
このジムでのトレーニング、スパーリングパートナーたちとの練習、そして会長の叱咤激励。すべてが私の財産だった。
その後も、私はボクシングに関する取材を続けた。
デビュー戦でKO勝利を収めたベテラン選手の引退試合を訪ねた。彼は弱い選手だったが、たくさんのファンが応援に駆けつけていた。
「長い間、お疲れ様でした」
私はそう声をかけると、彼は笑顔で応えてくれた。
「ありがとう。ファンのみんなの声援が、私の力だったよ。負けても負けても応援してくれた。本当に感謝しているんだ」
彼の言葉が、私の心に引っかかった。
「負けても応援してくれるのか」
私は今まで、勝つことだけに執着していた。負けたボクサーは、誰からも見向きもされないと思っていた。だが、彼の笑顔を見ていると、そんな考えが揺らいでいくのを感じた。
続いて、私は怪我で一度は再起不能と宣告された選手の復帰戦を見学した。彼は必死にリハビリに励み、リングに戻ってきた。
「勝つことはできなかったけど、今の俺にできることを全部やった。後悔はない」
彼はそう言って、清々しい表情でリングを降りていった。
「負けても、やり切ったという達成感を得られるのか」
私は、今までの自分の考えが少しずつ変わっていくのを感じていた。
新人王戦で対戦した選手にも取材をした。彼はすでに引退し、家族を持っていた。今は時折試合をし、子供に勝つ姿を見せたいとリングに上がっていた。
「子供に勝つところを見せたいんです。今度こそは勝って、子供を喜ばせたい」
彼の言葉を聞きながら、私は複雑な思いを抱いた。
「負けても、家族は応援してくれるのか。勝つことだけが、家族を喜ばせる方法なのか?」
私の心の中で、様々な感情が渦巻いていた。
エキシビションマッチ、そして再起への道
そんな中、ジムの会長から依頼を受けた。
「桐島くん、頼みがあるんだが、エキシビションマッチをやってくれないか? 相手は天才高校生だ。オリンピックを目指す期待の星なんだ」
「エキシビションマッチですか? 私でいいのですか?」
「ああ。君なら素晴らしい試合をしてくれると信じているよ。観客も大喜びしてくれるはずだ」
「わかりました。やってみます」
こうして、私はエキシビションマッチに出場することになった。
試合当日、会場は多くの観客で埋め尽くされていた。前座として、他の選手たちの試合もいくつか組まれていた。
そこには、新人王戦で対戦した選手の姿もあった。私は会場の後方から、彼の試合を見守った。彼の奥さんと子供も応援に来ていた。
しかし、彼はまた負けてしまった。子供はがっかりした表情で、母親に抱きついた。彼は泣きそうな顔でリングを降りていく。
その姿を見て、私の胸に熱いものが込み上げてきた。
そして、私の出番がやってきた。リングに上がると、懐かしい感覚が体を包んだ。
天才高校生は、私よりも頭一つ分背が高く、鍛え上げられた肉体を持っていた。彼は鋭い眼差しで私を見据えると、グラブを合わせた。
ゴングが鳴り響き、試合が始まった。彼は若さ溢れるアグレッシブなファイトスタイルで攻めてくる。そのパンチは速く、重い。私は防戦一方になった。
再起への炎
彼の強烈なパンチを浴びながら、私は心の奥底でくすぶっていたものに気づき始めた。
「勝たないと意味がない」
そう、私はまだ勝利に執着していた。負けることが受け入れられなかった。
「なぜだ? 私はもう引退したはずだ。勝つ必要はない。なのに、なぜこの拳は震える?」
自分自身に問いかける。
「俺はまだ負けたくない。勝って、勝利という名の栄光を掴みたい」
その思いは、私の心の中で燃え盛る炎となっていた。
その時、私はある決断をした。
「小説なんか書いていないで、俺はもう一度リングに立つべきなんだ。世界タイトルに再挑戦するんだ」
エキシビションマッチを終えた後、私は会長に告げた。
「会長、私、現役復帰したいと思います」
「現役復帰だって? だが、君はもう引退した身だぞ。甘くはないよ」
「分かっています。でも、もう一度挑戦したいんです」
「わかった。それなら全力でサポートしよう。君のボクシングに対する情熱は本物だ。もう一度、世界を目指そう!」
こうして、私はボクシング小説を書くことをやめ、現役復帰に向けての過酷なトレーニングを開始した。
早朝ランニング、筋力トレーニング、スパーリング、食事管理。すべてを勝利のために捧げる。
「もう一度、世界タイトルマッチのリングに立つ。今度こそ、勝つ」
その思いを胸に、私は走り続けた。
勝利への疾走
現役復帰後、私は着実に勝利を重ねていった。一つ一つの勝利が、私の心を満たしていく。
「勝つことは、こんなにも気持ちがいい」
勝利の喜びを噛み締める。この感覚を、私は忘れかけていた。
かつてのライバルたちとの再戦。新たな強豪選手との対戦。激闘を繰り広げながら、私は着実に成長していた。
「もっと強くなりたい。もっと上を目指したい」
勝利への渇望が、私を突き動かした。
そして、私は再び世界タイトルマッチのリングに立つことになった。
会場は、熱気に包まれていた。大勢の観客が、熱い視線をリングに注ぐ。
ゴングが鳴り響く。私は、対戦相手と真っ向からぶつかり合う。パンチを繰り出し、パンチを被弾する。激闘の末、最終ラウンドを迎えた。
「勝つ。今度こそ勝つんだ」
その一心で、私は最後の力を振り絞った。
エピローグ ~勝利の先に見つけたもの~
最終ラウンドの激闘の末、判定の結果が告げられた。
「勝者、桐島 拳!」
勝利を告げるアナウンスが会場に響き渡る。私は感無量だった。
「勝った。ついに勝ったんだ」
涙が溢れ出た。勝利の美酒に酔いしれる。この瞬間を、どれほど待ち望んでいたことか。
私は、世界チャンピオンのベルトを腰に巻いた。夢が叶った瞬間だった。
しかし、勝利の先に見つけたものは、ベルトだけではなかった。
会場に駆けつけたジムの会長、スパーリングパートナーたち、そして、かつてのライバルたち。皆が笑顔で私を祝福してくれた。
「おめでとう、桐島!」
「よくやったぞ!」
「感動したよ、お前の試合を見て」
彼らの笑顔が、私の心に刺さった。
「勝つことだけがすべてじゃない。負けても、再起しても、みんなの心に何かを残せる。それが、ボクシングの魅力なんだ」
私は気づいた。勝利はもちろん素晴らしい。だが、それだけがボクシングの醍醐味ではない。
勝つこと、負けること。その過程で生まれるドラマ。そこにこそ、ボクシングの真の魅力があるのだと、私は気づいた。
私は、ボクシングを通して、人生の新たな一面を見た。
「勝つこと」に執着していたかつての私。そして、様々な出会いと経験を通して、成長していった私。
「勝つこと」だけがボクサーの存在意義ではない。私は、その答えを見つけた。
勝利の先に見つけたもの。それは、ボクシングを通して得たかけがえのない仲間たち。そして、ボクシングという競技の奥深さだった。
私は、ボクシングという競技に、深く感謝した。
こうして、私の第二のボクシング人生は、輝かしい勝利とともに幕を開けたのだった。生成された小説2
私は元プロボクサー、葉山拳太郎。23歳にして世界タイトル戦に挑み、敗れはしたが、無敗の記録を誇る。その強さから「無冠の帝王」の異名を取り、ファンからは「ハヤブサ」と呼ばれた。私は早々に引退し、今はのんびりとした生活を送っている。
[ 起 ]
「なぜ、この若さで引退を?」
引退会見の会場には、記者たちの疑問に満ちた視線が集まっていた。フラッシュがたかれ、無数のカメラがこちらを向く。私は落ち着いた口調で、こう言い放った。
「勝つ姿を見せられないボクサーに、存在意義などないからだ」
この言葉は、私自身を奮い立たせてきた信念だった。ボクシングは勝たなければ意味がない。勝利こそが、ファンを熱狂させ、自分の存在価値を証明するものだと思っていた。
しかし、世界タイトル戦で敗北を喫した瞬間、私は燃え尽きてしまったのかもしれない。もう一度挑戦する気力も、負けを認めて這い上がる根性も湧いてこなかった。
「これからは、第二の人生を歩むつもりだ。ボクシングを通じて学んだことを活かし、新しい道で頑張っていきたい」
そう締めくくり、私は会見場を後にした。
引退後の生活は、穏やかで平和だった。毎日、ゆっくりと朝を迎え、近所をジョギングする。時折、ジムを訪れては後輩たちの練習を見守ったりもした。
だが、どこか物足りない。張り合いがない。このまま静かな日々を過ごす自分の未来を想像すると、胸の中がむなしくなった。
そんなある日、私はふと思いつく。
「そうだ。小説を書こう」
私は小説など書いたことがなかった。だが、自分の経験を活かせるのではないか。ボクシングの世界を、自分の言葉で描いてみたい。そう思ったのだ。
[ 承・前半 ]
早速、パソコンに向かい、小説のプロットを練り始めた。主人公は、私と同じように「勝たないと意味がない」と考えているボクサーだ。無敗のまま、世界チャンピオンになるストーリー。私が叶えられなかった夢を、彼に託そうと思った。
キーを叩き、ストーリーを紡いでいく。主人公の幼少期から描き、彼の才能が開花していく様子を書く。次々と強敵を倒し、無敗のままタイトルマッチを迎える。そして、見事勝利を収め、歓喜に沸く――。
一心不乱に書き上げたが、出来上がった小説を読み返すと、どこか満足できなかった。
「なぜだ? 自分の経験をそのまま活かしているのに......」
主人公が勝利を重ねるストーリーは、確かに熱く、胸が躍るものだった。だが、どこかで読んだような展開。自分でも予想できる結末に、新鮮味がなかった。
「なぜ、つまらないのか......」
原因がわからず、私は頭を抱えた。
[ 承・後半 ]
小説がつまらない原因を探るため、私は取材を始めることにした。まずは、お世話になっていたジムを訪れた。
「お、葉山か。久しぶりだな」
ジムの会長は、私を温かく迎え入れてくれた。
「会長、お久しぶりです。今は小説を書いているんですが、どうも面白くなくて。もっとリアルなボクシングの世界を描きたいんです」
「ほう、小説か。葉山ならきっとすごいものが書けるだろう」
会長はにこりと笑うと、スパーリング中のボクサーたちを指さした。
「あいつらは、みんな葉山と同じように世界を目指している。だが、勝つやつもいれば、負けるやつもいる。負けても這い上がろうとするやつ、勝っても満足できないやつ。いろんなドラマがあるんだ」
私は、会長の言葉に耳を傾けながら、ジムの中を見回した。汗を流し、必死にサンドバッグを打つボクサーたち。彼らの瞳は、勝利への熱い思いで輝いている。
「葉山、試合を見に来るといい。葉山がデビュー戦で倒したベテラン選手が、今度引退するんだ。時間があるなら、見送ってやってくれ」
そう言われて、私は試合会場へと足を運んだ。そこには、私がプロデビュー戦でKOした相手、斉藤和馬がいた。
和馬は、私がプロとして初めて拳を交えた相手だった。当時、和馬はすでにベテランの域に達していたが、私は彼を軽々と倒し、華々しいデビューを飾った。
「葉山くん......。懐かしいな。まさか、君が試合を見に来てくれるなんて」
和馬は、控室で私を見つけると、優しい笑顔を見せた。
「お疲れ様です、和馬さん。今度引退されると聞いて、ぜひお会いしたいと思いまして」
「ありがとう。葉山くんは、デビュー戦で強烈な印象を残した。君の試合を見て、勇気をもらった若手は多いはずだよ」
和馬は、穏やかにそう言うと、リングへと向かっていった。
試合が始まり、和馬は若い相手に果敢に挑んでいた。だが、体力の衰えは隠せず、結局、TKO負けを喫してしまった。
「勝たせてやりたかったな......。でも、最後まで立っていてくれてよかった」
会長がつぶやく。
「和馬さん、たくさんのファンに支えられていましたね」
「ああ。和馬は強さだけじゃなく、人柄も愛されていたんだ。勝つだけがファンを惹きつけるんじゃない。和馬はそれを教えてくれた」
私は、和馬の試合を通して、勝ち負けだけではないボクシングの魅力を知った気がした。
[ 転・結 ]
その後も、私はいくつかの試合を取材した。大怪我をして再起不能と言われながら、必死にリングに戻ってきた選手。新人王戦で私にあっさり倒された相手も、今は父親になり、子供に勝利を見せるために戦っていた。
「今度こそ勝つところを見せたいんです!」
彼の言葉が、私の胸に響いた。
そして、ジムの会長に頼まれ、私はある天才高校生とエキシビジョンマッチをすることになる。その少年は、オリンピック出場を目指す期待の星だった。
試合当日、会場には多くの観客が詰めかけていた。前座として、先日取材した選手たちの試合も組まれていた。
「子供に勝つところを見せたい」
そう語っていた彼の姿を探すと、奥さんと子供の姿が見えた。彼は、今度こそ勝利を掴めるだろうか。私は、会場の後方から、その試合を見守った。
ゴングが鳴り、試合が始まる。彼は果敢に攻めていたが、相手の反撃を受け、ぐらりとよろける。そして、最後はカウンターを浴び、マットに沈んだ。
「パパ、負けた......」
子供の泣き声が、会場に響く。彼は、涙を流しながらリングを降りていった。
私は、胸に熱いものがこみ上げてくるのを感じた。
そして、私自身の試合が始まった。天才高校生を相手に、私は防戦一方となる。彼の鋭いパンチが、私のボディを捉える。
「ぐっ......!」
痛みに顔を歪めながらも、私は気づいた。自分の中にくすぶっていたものに。
「勝たないと意味がない」
そう、私はそう思っていた。だが、取材を通して、勝ち負けだけではないボクシングの魅力を知った。
「勝つことだけが、ファンを惹きつけるわけじゃない」
和馬や、再起を果たした選手、子供に勝利を誓う選手。彼らの姿が、私の頭に浮かぶ。
「葉山くん、どうした? らしくないぞ」
会長の声が、遠くで聞こえた。
私は、ふと我に返った。そして、天才高校生に向き直ると、今度は私から攻撃を仕掛けた。
パンチを繰り出し、相手のガードの上からでも打ち込む。ボディブローの連打で相手の動きを止めると、強烈なアッパーを浴びせる。
「ぐはっ!」
高校生が、苦しげな声を上げる。
「葉山! それでいい! もっとだ!」
会長の声が、会場に響く。
私は、さらに攻撃を続けた。相手がぐらついたのを見逃さず、とどめの右ストレートを叩き込む。
「ダウン!」
レフェリーのカウントが進む。
「7......8......」
会場が、どよめいた。
私は、ふと我に返った。
「勝った......?」
そう、私は勝ったのだ。エキシビジョンマッチとはいえ、私は勝利した。
だが、なぜか心は晴れない。むなしい気持ちがこみ上げてくる。
「勝ったのに......。なぜだろう......」
私は、その場に立ち尽くした。
[ 物語の結末へ ]
その夜、私はパソコンの前で、これまでの小説を削除した。そして、新たな物語を書き始める。
「勝つことだけが、ボクサーのドラマじゃない。負けても、立ち上がる姿だって、感動を呼ぶ」
私は、取材を通して出会ったボクサーたちの姿を思い浮かべた。
「勝つことだけが、ボクサーのすべてじゃない。負けても、再起を目指す。家族のために戦う。それぞれのドラマがあるんだ」
私は、キーボードを叩き、新たなストーリーを紡いでいく。
「勝たないと意味がない」
その信念は、間違っていたわけではない。だが、それだけがボクシングの魅力ではないと、私は気づいたのだ。
「ボクサーは、リングの上で生きている。勝っても、負けても、その生き様を見せることが、ファンを惹きつけるんだ」
私は、熱い思いを込めて、物語を書き進めた。
[ エピローグ ]
それから数年後、私は再びリングの上にいた。
「葉山拳太郎、見事、世界タイトルを奪取!」
リングアナウンサーが、そう叫ぶ。
私は、世界チャンピオンのベルトを腰に巻き、大歓声を浴びていた。
「勝った......。私は、再び勝った......!」
涙が溢れ出す。私は、感無量だった。
「葉山、よく戻ってきてくれた!」
会長が、涙ながらに私を抱きしめる。
「ありがとうございます! 会長、皆さんのおかげです!」
私は、ジムのみんなに支えられて、再び世界タイトルに挑んだ。そして、見事勝利を収めたのだ。
「勝つことだけが、ボクサーのすべてじゃない。負けても、再起する。家族のために戦う。それぞれのドラマを、私は見せたい」
私は、そう心に誓った。
そして、私は現役を続けながら、小説を書き続けた。ボクシングの魅力を、もっと多くの人に伝えたい。その一心で。
「勝つことだけが、人生じゃない。負けても、立ち上がる。そこにドラマがあるんだ」
私は、そう語りながら、小説を書き綴っていく。
葉山拳太郎。無冠の帝王と呼ばれた男は、再びチャンピオンベルトを巻き、第二の人生を歩み始めたのだった。
[ 終 ]考察
さっきよりは面白いです。
特に生成の二個目はけっこうおもしろかったです。
ただどうにもやっぱり短いと言うか、プロットをもう少し膨らませて書いてほしいのだけど、いまいち書いてはくれません。
もう少しプロンプトを変えたら膨らませてくれるのか、それともなんらかの性能的な限界があるのか。
このプロットからこの小説を書いて、みたいなインストラクションが学習時にほとんど存在しないからかもしれません。
感想は、二歩ほど惜しい感じ。
次はプロットもLLMに書かせてみましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
