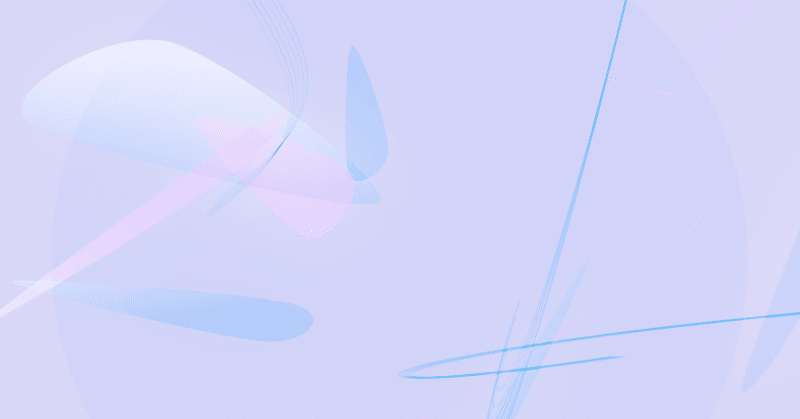
写真を受けてわたしが生きさせられる
先日、京都国際写真祭2022の一環として行われている、KG+ SELECTを見に行きました。既に活躍している写真家というより、これから活躍が期待される若手写真家たちの展示でした。
わたしは普段、趣味で写真を撮っているのですが、自分の行為をただ趣味としかとらえていませんでした。写真は自分にとってただの趣味。表現の方法としては考えたことがありませんでした。だから今までも、写真展があっても惹かれたりせず、写真の前を素通りしてきました。だって、写真は、ただ目の前で起こった出来事を撮るだけで、そこにわたしの意思は介入しえないと思っていたのです。もちろん、どこをどう切り取るか、という撮影者の目が必須であることはわかっています。けれど、それを表現とはどうしても考えられない、というのが今までのわたしでした。
KG+の展示で、わたしの考えは砕かれることになります。
西村楓 わたしが生まれなおす日
この作品が一番印象的でした。
ギャラリーの一画に、ずらっと並ぶ顔。顔写真はどれも同じ大きさ、同じ感覚で均等に横並びされていました。胸の上あたりから上の、上半身を撮った写真で、どの写真の人も服を着ていませんでした。

均等、というのはわかります。等価、というのも。どれも同じ価値がある。それは値段とか意味があるということではなく、どれも同じだということを表すものだと思います。写真にうつる人はみな均等で同じで、みな違いました。わたしはその、みんなが違う、というところに惹かれました。 西村さんは、個々のセクシュアリティーが等価だと示したいと言っているので、ここでは生物学的な性別は論じられないでしょう。その点においてみんなどこかの区分に区別されることはありません。髪をブリーチしていて個性的な髪形であったり、スタイリングをしてきれいに整えていたり、染めずにおろしていたり、短く切ったり。髪はどれも、その人のこだわりの主張だと感じました。服を着ていないのでみんな同じような肌の色で、その中で髪の個性が際立つのです。もちろん自分がやりたいように髪を整える、というこだわりがある人ももちろんこだわりがあるのですが、あまり整えずにそのままにしておく、というのも髪に対するその人のこだわりであると思うのです。ここに、わたしはその人個人が見えるような気がして。みんな、何かしらの意思があり、強く生きる人間なのだと感じました。ひとりひとりの主張を感じずにはいられなかったのです。
普段はマイノリティーの立場でも、別のマイノリティーに対してマジョリティーの目線をもって接してしまうことは、よくあることだと思います。わたしも精神障害者、というある種のマイノリティーに属するでしょう。わたしがマイノリティーだからといって、わたしとは別のセクシュアリティーの人に対して、マジョリティー特有の淘汰をしてないかといったら、そうではないと思います。わたしはセクシュアリティーにおいては、異性愛者でありマジョリティーに属されるものだからです。どの人にも、マジョリティー的な視線はある。そして、マジョリティー的な立場を取っている自分に気づくことは、とても難しいと思います。
この作品によって思い知らされたのは、わたしたちは何かに属するより先に、一人の人間なのだということです。目のかたちや耳のかたち、眉毛の色、髪形、唇の色、首から肩にかけてのライン、そういったものが全部違うように、みんな違う人間だということです。自分がマイノリティーだ、マジョリティーだ、と思うより先にしなければならないことは、その人と人として向き合うということかなと思います。何かに区分するのはわたしの役目でなく、社会が勝手に決めているものです。勝手に決められたものに、わたしが従う必要なんかない。人の属性ではなく、その人そのものを見ることです。
わたしは普段社会で当たり前とされていることができなくて、苦しんだりすることが多いです。そのせいあって、自分はこの社会ではマイノリティーの立場なのだとよく考えていました。しかし、そのせいで自分はマジョリティーとマイノリティーという属性を意識しすぎた。人間は多種多様で二項対立ではないはず。もちろん、わたし自身も。マイノリティーにならなくていいし、マジョリティーにもならなくていい、普通にならなくていいから、わたしはわたしという人であろうと思いました。まず初めにわたしがそうすることで、他の人と接するときに、属性を考えずに対等に付き合うことができるだろうと思うからです。
松村和彦 心の糸
認知症の人に焦点を当てた展示。写真の中に、ところどころ冊子が置いてありました。紙を重ね合わせ、それらを糸で結っただけの、シンプルな冊子。冊子の中には、写真の認知症の方の生きた軌跡である物語が刻まれていました。認知症の方とそのパートナーとの夫婦の物語など。
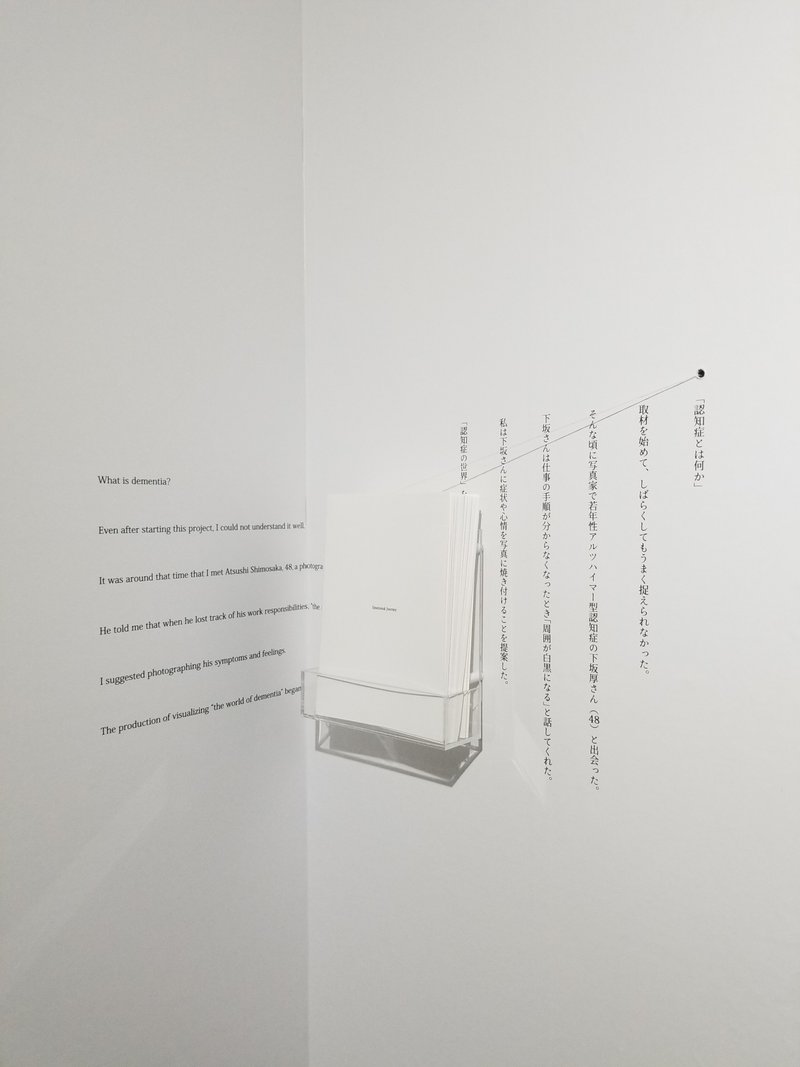
その冊子をぱらぱらとめくり、日本のどこかにあった家族の物語にわたしも入り込むことで、わたしも実際にその人たちと出会い、一緒に過ごしたかのような感覚が得られました。でも物語の中の人は、もうこの世界には存在していなかったり。実際に発せられたことば、実際に行った場所、実際にあった出来事。そういったこまかな事が、淡々と、やさしく綴られていました。泣かずにはいられませんでした。
わたしの祖母も、二年ほど前に認知症と診断され、今は介護なしには生きることができない状態です。母は定期的に祖母のところへ訪ねて行って、介護をしています。わたしは、母からも祖母からも離れた土地で暮らしているので、簡単には関わることはできません。それでも、自分に何かできることはないのかな、とずっと考えていました。
この展示を通して、記録することの大切さを学んだ気がします。大きな社会現象ではなく、日本の中の小さなひとつの家族で起こっている出来事。それは、日本のあらゆる場所、あらゆる場面で乱立し、いつかは消えていくものと思います。出来事を記憶に留めておくことはできます。しかし、記憶は不確かでいつしか自分が築いてきた行いに自信を感じられなくなるかもしれません。写真という、目の前の現実をそのままに記録する行為は、写真に写っている人や、写真を撮ったわたし自身をも確実にする方法です。母は介護のためにたくさんの作業を行っているはずです。祖母は認知症になりながらも、毎日を確実に生きているはずです(それも忘れていってしまうけれど)。それを記録することができれば、わたしたちは今も過去も、生きて成してきたことを、永遠にあたたかく受け入れられるのではないでしょうか。展示を見ながら、そのようなことをふと思ったのです。
わたしは帰省するたびに、写真で記録することを決めました。このゴールデンウィークでもすでに、祖母の写真をたくさん撮りました。その中であった出来事含め、いつかアルバムのようなZINEを作れたら、と思います。
高杉記子 むすひ
福島にある馬追村に焦点を当てた展示。馬追村には古くから今でも続く、土地の安寧を願う祭事が残っているそうです。東日本大震災で大きな被害を受けながらも、その祭りは行われ、コロナ禍でさえも執り行ったといいます。今福島は復興によって大きく変化しようとしています。しかし、変わらないものもあり、それが馬追村の祭というアイデンティティです。この展示では、継続するアイデンティティについて、出来事や歴史と絡めながら明らかにしようとしていました。

この写真に写る女性はどちらも、同じ人であるにも関わらず、わたしは全然違うものを感じてしまいました。違う雰囲気が発せられていると思ったのです。右側の女性は、普段わたしが外を普通に歩いていても、どこにでもいそうな女性。しかし左側の女性は、とても強く、他にはない輝きを持っているように見えました。馬追の衣装を着ることによって、普段は外になかなか現れない”馬追村”というアイデンティティを纏う。そしてそれによって、わたしはこの女性の真の姿を見た気がしました。隠しているわけではないけれど、普段は発露しない、けれど強く根を張るアイデンティティがあるということ。わたしは写真によってむすびつけられただけで、福島ともこの女性ともあまり関係がないように思います。それでも、わたしはこの写真を見たことによって関係していたい、この女性と馬追村とを記憶に刻んで、留めつづけたい、と思いました。
しかし、わたしは右側の女性の方がとても気になってしまいます。なぜ、こんなに惹きつけられてしまうのだろう、と思います。それはきっと、この写真は、語っていない物事をわたしに語りかけているような気がするから。写真のそばに刻まれている言葉以上に、膨大な言葉の宇宙に触れているような気がしたから。そのすべてを語りつくすことはできないと思います。それは、言葉にならないものだからです。わたしは写真が持つ能力の片鱗に触れた気がしました。それはつまり、言葉で語られないものを含ませ、目には見えない物事までをも映す力です。
写真に何ができるのか、というよりきっと、写真を見たわたしやわたしたちに何ができるのか、そこが大切だと感じました。
まとめ
今までお前は何を見ていたんだ、と怒鳴りたくなりますが、わたしは写真を見ることをしてきませんでした。こんなにも、写真にはわたしを動かす何かが込められていたのに。
少しだけでしたが、京都国際写真祭を観ることができて本当によかったです。写真を手にするものとして、写真を手段の一つとして考えていくことも、これから行っていきたいです。
