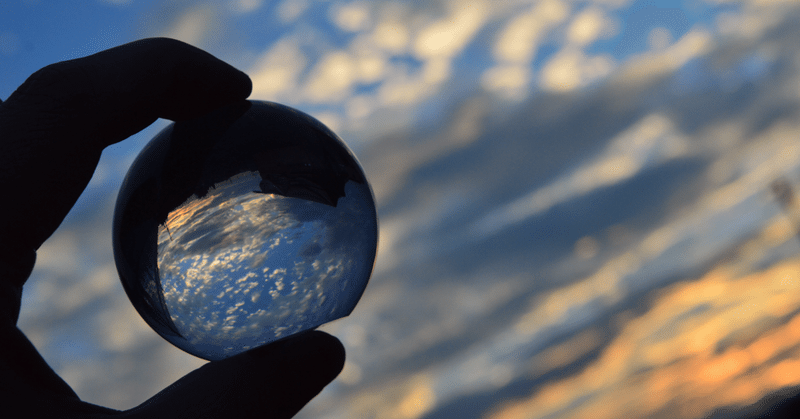
地球環境の変化と子どもたちの健康リスク
こんにちは!ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。不安定なお天気が続きますね。どうか体調管理に気をつけてお過ごしください。
今日の東京は肌寒いですが、ゴールデンウィーク期間中は30度を超える暑い日もありました。そして、すでにアレの発生が…!そうです、蚊です。公園で遊んでいる時に刺された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今日は、「今年も変な気候ね・・・」ではすまされない、紫外線の増加や有害な虫の増加といった、子どもたちの健康に直結する環境変化についてお伝えします。
紫外線の増加:皮膚がんリスク
オゾン層の破壊により、地表に到達する紫外線の量は年々増加しています。紫外線は、将来的な皮膚がんや白内障などの原因となることが分かっています。特に、子どもの皮膚は大人よりも薄く、紫外線ダメージを受けやすいので注意が必要です。

皮膚がんは、日本でも近年増加傾向にあり、特に若い世代で増加しています。20歳までに蓄積された紫外線量が多いほど、将来的に皮膚がんを発症するリスクが高くなることが分かっています。
温暖化による有害な虫の巨大化・増加:デング熱や日本脳炎の脅威
温暖化の影響もあり、世界中に生息する昆虫の40%が劇的に減っているそうです。ハチやカブトムシ、蝶など、人間にとって有用といわれる益虫たちです。その一方で、最近はトコジラミ(南京虫)やカメムシの大量発生がニュースになることもあるように、害虫は増えているのです。
そして、蚊やダニなども増加しています。蚊やダニは、デング熱や日本脳炎などの病気を媒介しており、子どもたちの健康を脅かします。
デング熱は、近年日本でも流行しており、2014年には国内で約150人の患者が発生しました。デング熱のウイルスを媒介する蚊の一種ヒトスジシマカは1940年代後半は本州の北関東から南で見られたのが、2015年には本州全域で確認されています。また、熱帯地域にいるネッタイシマカが日本に入り込んで越冬できてしまえば、よりリスクは増すのです。
現在、デング熱にはワクチンや治療薬はなく、主な治療法は発熱などの個別の症状を抑える対処療法になります。そのため、虫に刺されないことが最も有効な予防になります。
(参考)国立感染症研究所「ヒトスジシマカの分布域拡大について」(2020)
環境変化の中で、今できる対策を
私たちは、子どもたちやその次の世代を取り巻く地球環境を守るために、環境対策に取り組んでいきたいものです。そして、目下の環境変化から子供たちを守る対策もしていかなければなりません。
1. 紫外線対策
紫外線対策には、日焼け止めを使用することが重要です。単にSPF・PA値の高い日焼け止めを選べば良いわけではありません。
子どもの肌は大人の肌よりも薄く、刺激から肌を守る表皮の厚みは大人の約半分。バリア機能も低いです。乾燥しやすく、かゆみや湿疹も生じやすいので、肌に負担をかけない配慮が必要です。
SPF・PA値が高くなると肌への負担も大きくなり、しっかり洗い流しにくくもなります。シーンに合わせた、良いバランスの対策を心がけましょう。
2. 虫対策
虫よけには、虫よけスプレーや蚊帳などの伝統的な方法が有効です。
現在は多くの虫よけスプレーにDEET(ディート)が使用されています。長時間効果が続き、日本では50年近く使われている成分です。正しく使えばリスクが低いとされていますが、過度に使うと悪影響が出るとされ、日本では 12 歳未満の子どもへの使用は濃度が規定されています。
厚生労働省の報告では安全性が高いという評価がありますが、実験・調査をおこなっている協議会がDEET含有商品を販売している企業で構成されているため、海外でも懸念されている皮膚の炎症、吐き気、頭痛、めまい、集中力の低下、脳細胞や神経系への影響など、慎重にリスクを判断したいものです。
お子さまの商品選びには、DEET に代わる化学物質や天然由来の成分を配合したものも選択肢に入れて考えてみてください。
(参考)
厚生労働省 ディート(忌避剤)の安全性について
Toxicological Profile for DEET (N,N-DIETHYL-META-TOLUAMIDE)
3. 環境問題への積極的な取り組み
環境問題は、子どもたちの未来を守るために私たちが取り組むべき重要な課題です。子どもと共に環境問題について学び、地球を守る行動も心がけたいものです。
GROWNIQUEではこのようなことを考えながら、商品開発をおこなっています。商品の一部にはRSPO認証原料を使用しています。RSPO認証は持続可能なパーム油の生産・利用を目指す国際的な認証制度で、ESGとして、アブララヤシ農園開発による熱帯林破壊の問題解決に取り組み、持続可能な世界を目指します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
