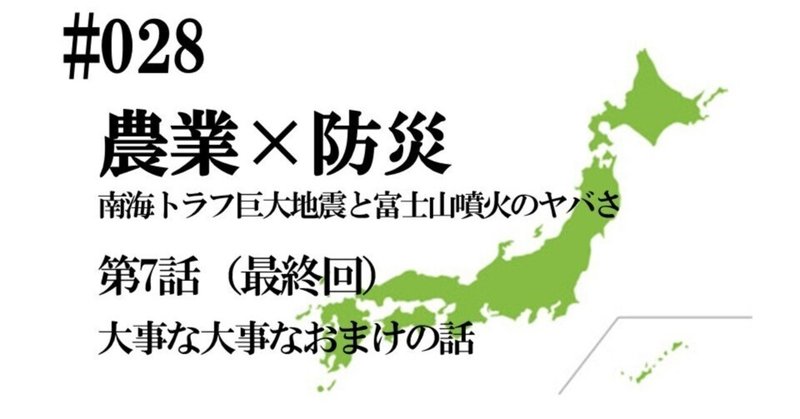
#028 農業×防災(最終回) 第7話:大事な大事なおまけの話
皆さん、こんにちは。
いつもお読みくださり本当にありがとうございます。
このシリーズでは第1回~第6回に渡って「農業×防災」をテーマに書いてきました。
前回の第5回目では、災害時における農業の具体的な役割に加えて「共同体意識」や「相互扶助」などの”精神的な側面”も農業の価値として防災に繋がるのではという話をしました。
最終回の今回は「農業×防災 大事な大事なおまけの話」と題して、ある書籍を紹介しながら話をしてみたいと思います。
近い将来に我々が経験するだろう未曾有の大災害。その時、生き残った者の心のあり方について参考になれば幸いと思い、この話を書こうと思いました。
それでは引き続き最後までご覧ください。
3月11日 東日本大震災から13年
明日は3月11日。東日本大震災から13年になります。
今日はこの東日本大震災に関連して、ある書籍を紹介します。
死者の力 津波被災地「霊的体験」の死生学、という本です。

この本は、東日本大震災後の被災地で語られた、いわゆる「霊的な体験談」を題材にした書籍です。
ただし、一般的によく語られるオカルト的な心霊体験そのものについて語ったり紹介する本ではありません。
この本は、あくまで「霊的な体験談」を題材にしつつも、実際にそれらを体験した被災者達の宗教的な観点や地域性等の特徴を切り口に”霊的な体験に対してどのような意識の差があるか”を調査、研究した書籍です。
この、「被災者達の宗教的な観点や地域性等の特徴によって霊的な体験に対してどのような意識の差があるか」という点が非常に興味深いと思いました。
内容に触れる前に、そもそも被災地で語られる「霊的な体験談」とはどういった事かを説明します。
被災地で発生する心霊体験?!
東日本大震災後、当時のネットや雑誌記事の一部では被災地で見受けられたいわゆる霊的な現象にまつわる体験談が話題になりました。
・被災地の現場付近を車で通ると頭が痛くなる
・大勢の人影が海の方へ向かっていく姿を見た
・横断歩道を横切る人を待っていたら後ろからクラクションを鳴らされて実は誰もいないことに気がついた
・コンビニの自動ドアが誰もいないのに開閉する
などなど、様々な人が様々な体験をしたり、聞いたと言ったケースが当時多くあったそうです。
それも一件や二件の話ではなかったようで、産経新聞をはじめとし全国紙でも多く特集されたようです。更にNHKでも特集が組まれ「NHKスペシャル 『”亡き人”との再会』(2013年8月23日放送)」が放送されています。
あれだけ大勢の方々が被災され命を落としたのですから、何かしらの事象が身近に起きる、あるいは人伝手に耳にするといったことはまったく不思議ではないと思います。
私自身、当時建築関係の仕事で被災地で泊まり込みをしていた友人からもそういった話を聞きました。
一方で、こういった体験談の多くは、世間一般ではいわゆるオカルトちっくな事象に矮小化されてしまいがちな部分も少なからずあり、震災後の不安定な状態もあって体験者自身も誰に相談して良いのか分からない場合が多かったようです。
そういった背景から精神的なケアの意味からお寺の住職など、宗教的な環境に身を置く宗教家達が相談の取り組みを始めたとされているようです。
この本が面白いと思った点は、そういった霊的な体験に対する各個人の捉え方について、その人自身の宗教に対する心の位置づけ方や地域性等によって全く捉え方が異なるという点を、膨大な聞き取り調査を元に分析したという点です。
具体的に例を挙げながら話を進めていきます。
霊的体験に対する意識の違い?
調査の中で、霊的な体験をした人の中では宗教的な立場や地域性によって様々な特徴がみられたそうです。
一つ例をご紹介しますと、霊的な体験をした人の中において、精神的な感情は大きく二つに分けられたということが紹介されています。
端的に言うと、霊的な体験に対して「①心温まる思い」か「②冷たく、得体のしれない思い」の二つだそうです。
そして、この両極端な感情の違いは自身の宗教観や地域性、その人を取り巻く社会性が関係していると、調査の結果を著者は説明しています。
①の感情を抱く背景として、最も身近と言える肉親、兄弟、子、親戚、隣近所、親しい友人との「不条理な死別」があげられます。それに対して②の感情を抱く背景としては、どこの誰だか分からない「ただただ無気質な冷たい死」という点です。
①は「別れ」「遠くに行ってしまった感覚」「今でも心の中に生き続けている」といった感覚を死者と共有している訳です。「たとえ肉体がなくてもいいからそばにいてほしい」「幽霊でもいいから会いたい」といった感覚に近いと言えます。
そして、このような意識、心の在り方を持つ方というのは、どちらかというと都市部よりも郊外(中山間地帯、農村部)の方が多いということです。あるいは、お葬式、お盆、お彼岸、初詣など、普段から何らかの形で宗教的な環境と何らかの形で接している人だということです。両者の共通点として言えることは、地域行事や慣習行事等を通じ、宗教的価値観、伝統的価値観、共同体的価値観に馴染みが多い人とも言えます。
つまり、物理的にも精神的にも多くの人と繋がりを持っている人、という事です。
私は、この事は今後我々が立ち向かうであろう未曽有の大災害が発生したとの時、大切な人との死別を迎える時、「心のあり方」として十分に理解しておくべき重要な点であると考えています。
精神的な心の繋がりの重要性
このシリーズで最も伝えたかったメッセージは「農業を通じた精神的な繋がり」の重要性についてでした。
今回ご紹介した「死者の力」でも語られたように、繋がりを持つために重要となるのが、宗教的価値観や伝統的価値観、慣習、地域行事等です。
これまで繰り返し述べて来たように農業という営みは単に食べ物を作り出すことに限らず、それらの精神的な繋がりを強化する為の土台の役割も担っていると私は考えます。
そのことを踏まえて、いざという時の心のあり方や死生観についてこの本で語られている例を参考にしつつ、この先の激動の時代を乗り越えていきたいと思います。
そういった観点で皆さんの参考になればと思い今回紹介してみました。
最後に
全7回に渡って「農業×防災」というテーマで話をしてきました。
近い将来我々が体験するであろう未曽有の大災害。
京大 鎌田教授によると、東日本大震災をきっかけに日本列島が大地激震の時代に突入したと話します。
南海トラフ巨大地震、直下型地震、活断層地震、富士山噴火、豪雨災害、様々な災害と常に隣り合わせの我々日本人。
元日の石川能登地震から早くも2ヵ月以上経過した中で、依然過酷な生活を強いられておられる現地の方々。また災害援助やボランティア活動をされている方々。本当に心からお見舞い申し上げます。
最近では妙に千葉県周辺で小規模な地震が相次いでいます。
このブログでも書いたように、日本列島は基本的にはいつでもどこでも地震が来る場所です。
明日、3月11日の東日本大震災の発生日をきっかけに今一度災害対策について考えてみては如何でしょうか。
その為に少しでも多くの方にこのブログをお読みいただけると幸いです。
最後までお読み下さり、ありがとうございました。
終わり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
