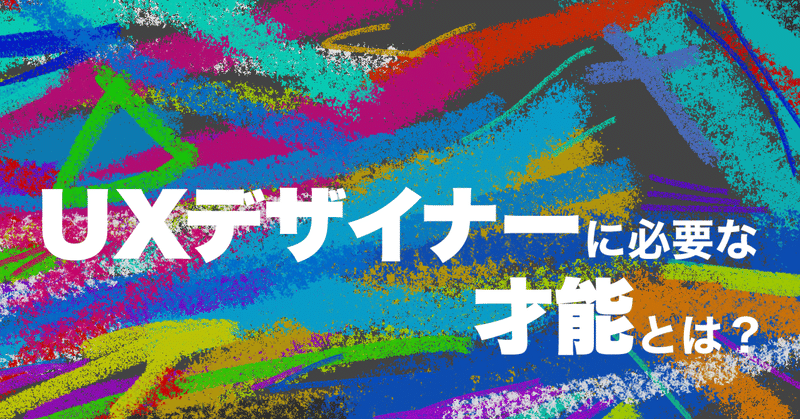
UXデザイナーに必要な才能とは?
GoodpatchのDesignOpsに所属する角野です。
もともとはUXデザインやサービスデザインを専門として、クライアントワークに従事していましたが、今はDesignOpsでクライアントワーク事業自体の運営、組織開発、人材育成に向き合っています。
このnoteでは、自分自身が仕事で行っていた「UXデザインにも才能って必要なのか?」とぼんやり考えてみたことをまとめたいと思っています。
才能の科学
冒頭でも少し触れたように今の仕事はDesignOpsという立場で、多くのデザイナーと関わっています。仕事の中でもデザイナーを育成することや、さまざまなデザイナーの個性に触れることの多い立場になります。
そんな中で最近読んだ本に「才能の科学」という本があります。
本の中では「傑出性」つまり才能があることについて紐解かれています。多くのプロスポーツ選手、特に天才と言われる選手ももともと才能があるかもしれないが、幼いときから誰よりも練習を重ねることで技術を身に着けてきたことに触れられています。
タイガーウッズは、3歳のころからクラブを握り毎日父親と練習をし、ベッカムは、チームの練習が終わったあと、何百回とフリーキックを自主練し、
その結果、今の成績や活躍を収められたと書かれています。
本の中で事例として触れられているのはプロスポーツ選手でしたが、デザイナーもまたセンスや才能という言葉が紐づく職種だと思っています。
UXデザイナーの才能とは?
UXデザイナーという職種でみると、ビジュアルデザイナーやUIデザイナーのような目に見える表現でアウトプットをするわけではないので、デザイナーといってもセンスや才能の見え方は少し違うようにも感じます。
UXデザイナーの仕事を一言でまとめると、サービスや製品を使うユーザーの属性、行動、価値観を調査によって読み解き、サービス、製品を通したユーザーの体験を構築することだと思います。
さらに簡単に分解してみると、調査工程と仮説構築工程に分解することができます。
調査工程
調査設計
ユーザーインタビューやユーザーテストの実施
インタビュー、テストからの分析
ペルソナやユーザーの個票まとめ
カスタマージャーニーマップのような行動・課題分析
KA法や価値マップ、価値サークルを使ったユーザーの価値観の構造化
などなど、サービスや製品によってプロセスは変わってきますが、ユーザーのことを深く理解、知るためにかなり泥臭い作業も行う必要があると思っています。
それ自体に向き合える力もそうですが、多くの情報から鍵となる行動や価値観、考え方を抜き出すことがこの工程で必要な力といえます。
仮説構築工程
インタビューの分析から紐解いていったサービス・製品を使う中で
コアになる課題やユーザーの持っている価値感の抽出・フォーカス
サービス・製品をより良くするための改善案の検討や新規事業であればコンセプトなどの
アイデアを出すこと
筋の良いアイデアを選択すること
などなど、調査結果をもとにした新しいサービスや製品を考え出す企画力、既存サービスや製品のより良い改善を複合的に考える改善力が必要な力といえます。
周りのUXデザイナーを見てみても、調査工程での各プロセスの知識や実行ができるというだけでなく、調査を行うに当たっての適切な調査設計ができるかやプロセスから導き出したユーザー情報に深く潜り、深層にある課題や価値を拾ってこれるかは、人によってかなり差があるように思います。
また、仮説構築工程でも得た情報からコアとなる課題や価値にフォーカスできるかや、そこから導き出すアイデアが論理的であり、かつ創造的なものを出せるかでも人によって差が生まれると感じます。
なぜ、このような違いが生まれるのか?
この部分、つまり「適切な調査設計を行った上で深層にある課題や価値を拾い、論理的かつ創造的なアイデアを導き出せる」これこそが、プロセスや知識を持っているだけではないUXデザイナーの才能だと思っています。
UXデザイナーの才能が際立っている人の共通点
才能の科学の本の中でも傑出性について触れられており、それがどこから生まれてくるかも触れられていたのですが、UXデザイナーも同じことが言えると個人的には思っています。
本の中では、才能が開花するには、1万時間のトレーニングが必要という分析をしています。1万時間というのは、1日に3時間毎日したとしても約10年かかる時間です。
人生の中で長時間一つの枠組みに投資することで、生まれるのが傑出性であり才能と呼ばれるものとされています。生まれ持った才能があったとしても結局時間をかけないと開花しないとも言えます。
UXデザインのプロセスの中でも泥臭い作業はかなり多く、インタビューの書き起こしやそこから価値を抽出するKA法などは本当に時間がかかる作業で、かつとても細かいと思っています。
仕事としてやるには時には辛い作業といってもいい気がしています。
Goodpatch内で定期的に個人の振り返り・内省会を実施するのですが、その中で上記のような作業が「辛い」ではなく、「楽しい」と振り返っているUXデザイナーが時々います。
長時間一つの枠組みに時間を投資する際、「言われたからやらないと・・・」「期限が・・・」という外発的動機では長続きするモチベーションは得られず、「楽しくてやりたくてしょうがない」「気がついたら考えている」などの内発的動機がそこにあるかは大きな差になります。
UXデザイナーの才能を開く道
UXデザイナーの場合、自分とは違う人の考えや行動、価値観などに深く触れることに対しての面白みやUXデザインのプロセスの中での楽しさを持っているかどうかは、才能の科学でいう1万時間のトレーニングを超えるに必要な要素になり、そのトレーニングの中で培ってきた知識やプロセスの実行を重ねた経験値が先に述べたような違いを生み出し、UXデザイナーの才能につながると考えています。
これからのUXデザイナーの才能
ただ、今現在進行中であるAIの劇的な進化により、UXデザイナーのプロセスも大きく変わってくることが予想されます。だからといって今UXデザイナーがやっている仕事をやらなくて良いのか?というとそうではないとも考えています。この大きな変革は、UXデザイナー自身が才能を改めて見つめ直す機会になっているとも思います。そのあたりに関しては、またの機会があれば別のnoteでまとめられればと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
