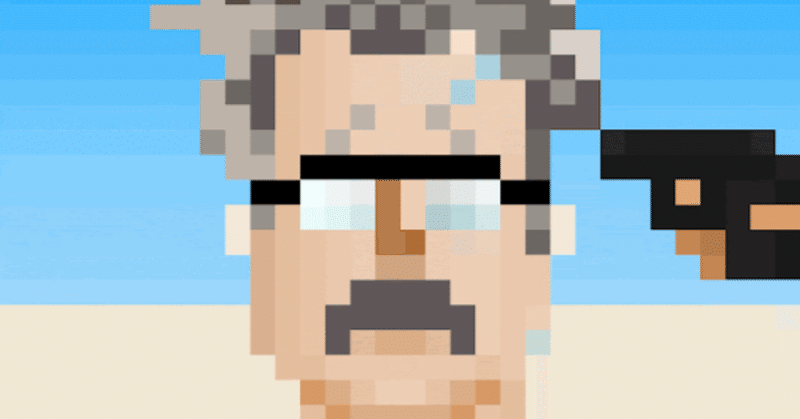
【1】アートを見てみYO!!
YOYO‼
最強最悪のアーチスト、GOROだPOW(^_-)-☆
前回、俺の芸術思想を公にする事を高らかに宣言した訳だが、正直言うと何を語るべきか結構悩んでいて、海に向かってバカヤローと叫んだりして過ごしていた。
そしてとりあえず、読者にアート分野以外の方が多いだろう事を想定し美術史の話を途中まで書いてみたりしたものの、そいつはボツとした。アートとはなんぞや、という事を理解する上で美術史はめちゃめちゃ重要で、サッカーをする時に「ゴールはどこにあるのか」とか、万引きをする時に「今日の監視員は何色の服を着てる人か」とか教えてもらうのと同じくらい不可欠なものだ。しかし、書いていてなんか気分が乗らなかったのだ。どっかのアート系サイトに書いてありそうな事を俺がわざわざ再度説明するという行為がなんとなく陳腐に感じてしまったというのもあるし(と言っても美術史を理解してもらった後でないと話せない内容もある為、近々する予定)、「GOROってアートの事知ってんだナ」って事が読者の皆さんに伝わるだけで、肝心のGOROってなんなの?という話をするのが次の回までお預けになってしまうのも気になった。かといって前回のチュートリアルの続きのような話をするのも退屈だ。
そして、いろいろ考えた結果、今回は「見ること/視ること」にテーマを絞ってGOROの個人的な美術体験を語る事で、GOROについて、美術についてどちらもなんとなく伝わるような内容を狙ってみたいと思う。
チェケラッチョ☆(/・ω・)/
【GORO青年の話】
GOROおじじにも、美術を知る前の時代があった。絵を描くのは好きだったが、ゲージツとは何なのか、どんなゲージツが世間で素晴らしいと言われているのか、皆目見当がつかなかった時代が。詳細はハショるが当時高校生だったGORO青年はいろいろあって「ゲージツの事はよく分かんねえけど、海賊王世界一の画家に俺はなる!」という気概だけは猛烈に持っていた。そしてまあ下らないデッサンの練習なんかを始める訳だが、当時ゲージツ(というかデッサン)について真剣に考えたGORO青年は下記の方法論に辿り着いた。
デッサンはまず、モノを「見る」こと
そして、絵を描いて、いい感じかどうか画面を「見る」こと
↓
という事は「見る」という能力を極限まで極めれば、凡人どもの及びつかないカモメのジョナサン的な何かになれるんじゃねえの!?

後年、この考え方は撤回されるものの、絵画というものは視覚芸術であるから、確かに一理あるような気はせんでもない。ちなみに、今はどうか知らないが当時の日本のデッサン教育はGORO青年の方法論と同じくらい感覚的な所があって、予備校なんかに行くと「石膏像の表面を歩いているアリになったつもりで観察するんだあ!」とか「石膏像を取り巻く空気の塊を描くんだ~!」とか「石膏像自体ではなく、石膏像を画学生が取り囲んでいるという事実を、人工衛星から俯瞰的に見てるつもりで描くんだーー!」とか、なんかもう好き放題言われてた。最後のやつとか完全に意味不明であるが、当時は言う方も聞く方も結構マジだった事を考えるとちょっと怖い。(この辺りの雰囲気を詳しく知りたい方は、-千住博の美術の授業 絵を描く悦び 光文社新書-を参照されたし。)
まあともかく、己の信念に従って「死に物狂いで見て描く」という事を始めるのだが、まず最初に「モノが見えているつもりでも全然見えていない」という事実に打ちのめされた。
想像してみていただきたい。
今、あなたはGORO美術研究所の2階におり、あなたの目の前に石膏像が置いてある。とてもクリアに、くっきりと、世界堂のセールでGORO先生が買ってきたマルス像が見える。口元には僅かにそれと分かるほどの笑みがたたえられ、優雅にゆったりと傾けられた上体に、年季の入った窓を通して柔らかな太陽光が降り注いでいる。白の諧調は息を吞むほど豊かで、石膏のボリューム感はあくまでも上品だ。心なしか、マルス像の周りの空気までもが浄化され、教室にマイナスイオンが満ち溢れてきたように感じる・・・

しかし、あなたが今描いているデッサンはどうだろうか。
手汗とパンくずでドロドロになった木炭が画面に醜く付着している、単なる汚れた紙にしか見えない。家畜小屋の中に一日豚の足ふきとして紙を置いていたらこういう風になるかもしれない。といった類の汚さだ。
百歩譲ってもジョジョに受けた波紋攻撃で四肢が溶かされ悶え苦しむ吸血鬼の図、といった所だろうか。とてもあの美しい古代ローマの名品、マルス像には見えない。もし、ナチス時代のドイツでこれを「マルスのデッサンです」と言ったならば、古典芸術の冒涜した罪で処刑されちゃうに違いない。それぐらいの惨状だ。
だが、あなたはなんとかこの死にかけの吸血鬼を本物の石膏像と見違えるくらい超絶リアルにしたい!という気迫だけは持っている。
そう思いながら朝から8時間くらいずっと石膏像を眺めているのだ。
だけど、悲しい事にどこがどう違うのか分からない。どうすれば実物に近づくのかが分からない。明らかに性質の違う2つの映像が眼前にあるのに、だ。つまり、その時あなたは完璧な答えが既に目の前にあって、しっかり見えている筈なのに、その答えが分からないという謎の事態に直面していると言えよう。デッサンを始めたばかりの多くの若者はここで
「普段ものが見えているつもりでも全然見えてなかった~\(^o^)/オワタ」
という事に気づくのだ!!
そしてGORO青年も例外なくそうであった。
GOROがこのような体験を通じて学んだ事は、人間の認識能力がいかにいい加減かという事。そして、ものの見方を変えると世界は様々な見え方をするという事だった。
【ものを見るという事】
昨今の美術界では、実践的な部分ではデッサンを勉強する意味はほぼなくなってしまってはいるが、この「ものの見方」自体は美術を鑑賞したり作ったりする時にも応用する事が出来るのではないかと思う。なぜなら多くの美術作品は「こんなものの見方もあるのかあ」という新しい「見方」を教えてくれるものである事が多いし、一度自分の認識能力を疑った上で再構築する、という経験をしていると自分の理解を越えるような作品や、難解な作品に出会ったときに、前向きに作品と向き合える体力のようなものがつく気がするからだ。
例えば、GOROが初めて興味を持った画家はピカソだった。ピカソの若い頃のデッサンはめちゃ上手かったので、絶対こいつに勝つ!!と思っていたし、えげつない程の金持ちで、女にモて、レストランに行くと紙ナプキンに落書きするだけで支払いが完了する(!)という神エピソードにもシビレた。
しかし、そんなピカソが描いた抽象画はどこが凄いのかさっぱり分からなかった。ただ、デッサンを通じて「俺は実はなんにも見えちゃいねえんだ!!」という事を学んだ後だったので、俺っちが未熟なだけかもしんねえ!と思ったGORO青年は本屋でお年玉を使い切って分厚い画集を買い、清らかな赤子の様な心でピカソの絵を毎日見まくった。死に物狂いで、隅々まで、見て、見て、見倒していると、次第に絵が持っている「におい」のようなものを感じるようになった。この「におい」とは何なのか?
GOROは、初めてデッサンをした時に「自分の見えてなさ」を痛感したように、その後も絵を描くという行為を通じて人間という生き物がもつ能力の限界、弱さや拙さを常々実感してきた。
そして、ピカソも同じ人間である。巨匠であっても、そしてどんなに絵のスタイルをコロコロ変えたとしても、人間である以上「ピカソのにおい」のようなものがどうしても残ってしまうのだ。よく、個性的っていうと奇抜で人と変わった事をする奴っていうイメージがあるが、それは多分違う。奇抜かどうか、人と違うかどうかは周りの人次第で変わるからだ。しかし、「におい」はどんなに隠そうとしても滲み出てきてしまう。逃れる事ができない。個性とは、もしかしたらそういったものなのかもしれない。そして、GORO青年はピカソの「におい」に非常に画家らしい何かを感じた。

最終的に、GOROがピカソを理解できたのかは分からないが「ピカソを見まくる」という行為を通じて絵画が人間にどれほど豊かな悦びを与えてくれるものなのか、そしてそのひとつひとつの経験は到底語りうるものではない事を学んだ。このnoteを読んでいる人の中にもしかしたら、アートってよくワカンナーイっていう感想を持っている人もいるかもしれないが、GOROの経験から言うとまず「自分の目で」アートを見てみて欲しいと思う。ピカソは存命中、アートについて多くを語らなかったが、ぶっちゃけ大して何も考えずにラクガキ感覚で絵を描いていたのではないかと思う。それでもピカソの絵がGOROに悦びを与えてくれたのは事実だし、まず自分の目で全力で見てみて、その時に己の肉体で感じた事だけが紛れもない真実であって、それを批判する事は誰にもできない。
ちなみに、絵を見て「におい」みたいなものを感じるようになる頃には、世の中にある有象無象から様々なものを感じられるようになる。例えば木の枝。同じ木でもエロいやつがいれば、大人しそうなのもいれば、悪そうなのもいる。GOROは絶対にあいつら一本一本には性格があると思っている。それは人間がもっている「性格」とはちょっと違うタイプのものかもしれないが、世界には、人間の持っている言語で語る事のできない、ある種の豊かさが確かにある事を感じる。魂と言うとまた違うかもしれない、科学的に捉える事のできない、そして大して意味のない、だけどそこに確かに存在している異国のことばのようなもの。その辺に生えている草、落ちている手袋、遠くに見える山、海、なんだっていい。全力でものを見るという訓練を積んだ後なら、きっとこれを読んでいる皆だって何かを感じる事ができるはずだ。
【補足】
「上手いデッサン」を描こうとした時に、このようなものの見方をすべきかはまた別の問題であるし、またこういった類のものの見方がGOROの嫌いな一部のリアリズム絵画の崇拝者を生み出している事についてGOROは問題意識を持っているが、これを論じだすと終わらなくなってしまうため今回は割愛する。※野田弘志という人が書いた「リアリズム絵画入門」という本を図書館や書店で見かけたら決してページを開かず即刻焚書処分する事をお勧めする。
しかしながらGOROの人生の非常に初期にデッサンを通じて得たこれらの認識は、GOROの人格形成に大きく影響を与えた事自体は間違いない。
時間的な問題もあるのでとりあえず今回はここまでとして、小出しに話していく事とする。
最後の行まで読んでくれた君だけに、この言葉を贈りたい。
Chill
GORO
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
