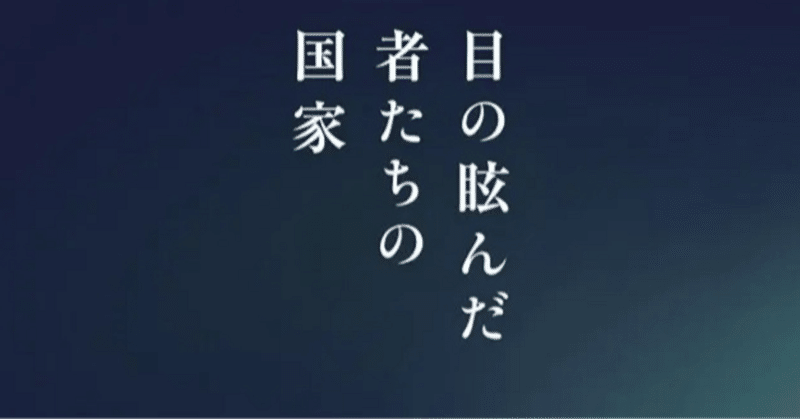
読書メモ・第11回・キム・エランほか著、矢島暁子訳『目の眩んだ者たちの国家』(新泉社、2018年)、斎藤真理子『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス、2022年)
出張から戻り、一日休みだったので、「時間のかかる終活」を続ける。本棚に入らずにダンボール箱に入れておいた本を、1冊1冊取り出しては、これはいる、これは売る、という選択をくり返す。
箱の中からキム・エランほか著『目の眩んだ者たちの国家』が出てきた。私はこの本を買ったとき、何度となく開いてはその言葉にふれることをくり返した。
2014年4月16日に、旅客船セウォル号が全羅南道珍島沖で沈没した事故と、それに対する政府の対応の酷さについては、その後の韓国社会に暗い影を落としている。韓国文学に関心がある人であれば、このセウォル号事件が大きく時代を区分し、「セウォル号以後文学」といった文学史上の転換点になるほどの衝撃を与えたことはよく知られている。
『目の眩んだ者たちの国家』は、セウォル号事件に衝撃を受けた作家や詩人、思想家、学者などによる魂の叫びである。
「船が沈没したその瞬間からいままで、本当に多くの嘘をついた。何のためらいもなくついた。遺族たちが嗚咽している前でも、嘘をつくなと罵る声を聞きながらも、全国民が見守る前で国民を相手に嘘をついた。すべてを変えると嘘をつき、聖域なき調査をすると嘘をついた。救助に全力を挙げると嘘をつき、(中略)史上最大規模の捜索を展開するという史上最大規模の嘘をついた。三百四人の無辜の死の前で、あなたたちは数え切れないほどたくさん嘘をついた。なぜかとは聞かない。これ以上嘘を聞きたくないから。嘘は意図からきている。いや、嘘は、それ自体が意図であり、事件なのだ。人類の歴史を通じて、これほど多くの嘘を必要とした事故の収拾はなかった」(パク・ミンギュ〈作家〉「目が眩んだ者たちの国家」)
「私たちは十分に救えたはずの人たちを見殺しにした。多くの人たちが長い間苦しんでいる理由もそこにある。死んだ人たちがただかわいそうだからではなく、彼らが死んでしまうまでの長い時間、何もできないような、めちゃくちゃなシステムを放置していた私たち自身に対する羞恥心のために、身の毛がよだつのだ。そしてこれが、同情心に溢れ善良な顔をした政治家たちを見て多くの人があきれる理由でもある。この惨事を交通事故にたとえて言うことが許されるとすれば、みんな自分が飲酒運転で他人を殺してしまったドライバーにでもなったかのように自分を責めているのに、政治家たちだけは、まるで交通事故を目撃した通行人のようにふるまっている」(チン・ウニョン〈詩人〉「私たちの哀れみは正午の影のように短く、私たちの羞恥心は真夜中の影のように長い」)
斎藤真理子さんは、『韓国文学の中心にあるもの』の中で、こんなふうに書いている。
「この事故はたんなる海難事故ではなかったし、ただ人災といってすませることもできないほど重大な意味を持っていた。(中略)東日本大震災の直後に津波の映像を呆然と見つめ、続いて福島第一原子力発添書の爆発のニュースに接したときのことが思い出される。原発の危険性は分かっていながら手を打てなかった私たちが、故郷を後にする福島の人々を目撃したときの自責の念と無力感を」
2011年の東日本大震災にともなう福島の原発事故の直後に、ミュージシャンの斉藤和義さんが、自身の楽曲「ずっと好きだった」の替え歌として、「ずっとウソだった」という反原発ソングを歌ったことが思い出される。しかしそれが表現者たちの大きなうねりにならなかったことが、返す返すも悔やまれる。
斎藤真理子さんはこんなことも書いている。
「作家のキム・エランは、事故直後、政府など「上の方」から下りてきたもっともらしい話の数々には、副詞や形容詞、述語や抽象名詞はたくさん使われていたが、その時制は不明で、動詞や主語、固有名詞はほとんどなかったと書いている。「積弊」「責任」といった言葉が盛んに使われたが、話を全部聞いても、誰が何に対してどう責任をとるというのか、わからなくなったという。そして、「言葉の一つひとつではなく、文法じたいが破壊されてしまった」「ある単語が指す対象とその意味が一致していられず揺らいでいる」という危機を、作家は感じる。これもまた、日本に住む人々が近年たびたび、政治家の信頼性をめぐって味わってきた失意に似ているだろう」
標記の本を読めば読むほど、韓国のセウォル号事件は、この国のいま置かれている状況の「鏡」に思えてくる。しかしこの国の表現者たちがこの状況に対してどれほどの言葉を紡いでいるかについては、よくわからない。だから私は、セウォル号事件をきっかけに紡ぎ出された言葉にそのことを求めているのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
