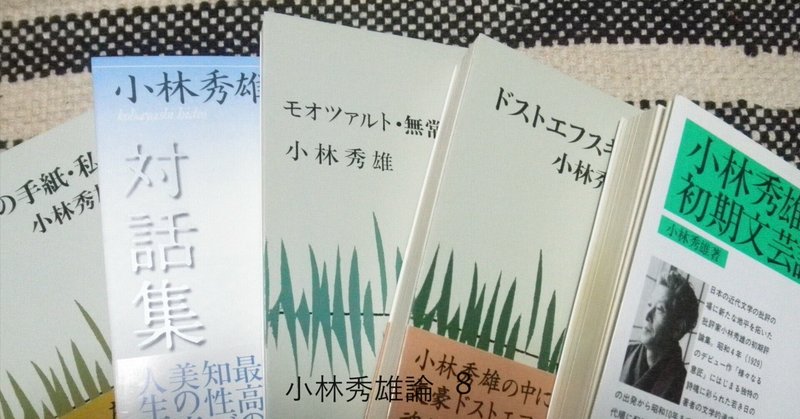
小林秀雄論ー志賀直哉について、対話集からー
小林秀雄論ー志賀直哉について、対話集からー
㈠
今回も、『小林秀雄 対話集』から、対話の台詞を抜粋する。正宗白鳥との対話「大作家論」から、志賀直哉についての対話である。小林秀雄は、青年期に志賀直哉文学に救われた過去があるから、評論でも、志賀直哉への批判は一切していない。尊敬する小説家に対しては、批評家であっても、批判はしないものの様だ。
㈡
小林 作文とおっしゃる意味はよくわからぬが、志賀直哉という人を偉いと思うのは、あの人の一種の原始性なんですよ。観念的なものに惑わされないで、物をじかに見る眼です。すぐれた画家が持っているような眼なんです。
これは、物を見る眼においても、広域があるということを、真に語っているが、小林秀雄がそこまで言う、志賀直哉の眼は、「すぐれた画家が持っているような眼」だという。このことから、小説家においても、そういった、物を見る眼があるという事が分かるが、志賀直哉が、自身の眼にそのようなものが宿っていたかを自覚していたかは、正直分からない。ただ、小林秀雄が言うのだから、確かにそうなのだろう。志賀直哉の小説は、非常に簡潔明瞭であり、また、心が思ったこと、心が感じたことを、正直に述べて居る。この正直に、というのが、「物をじかに見る眼」だと考えれば、小説の神様と言われるだけの、素晴らしい志賀直哉像が、小林秀雄の台詞から浮かび上がる。
㈢
続いて、引用。
小林 (略)当時の若い作家たちは、志賀さんの仕事とくらべると、実に観念的な仕事をしていた。眼前のものが端的に、まるで見えていないような仕事をしていた。
ここでいう、「眼前のものが端的に、まるで見えていないような仕事をしていた。」という若い作家に比べて、志賀直哉は、眼前のものが見えて居たということになる。それは、そこに現実というものが有る、という事を言って居る。リアリズムを避けずに、リアリズムに傾倒することもせず、リアリズムを見る、ということをした、志賀直哉はその点で現実主義者であり、だからこそ、そのリアリズムに即した小説が書けたということだろう。
㈣
小林秀雄は、眼前のリアリズムを批評するが、志賀直哉は、眼前のリアリズムを小説にする。志賀直哉の書いた小説が、何故こんなにも人の心を打つのかは、そこに、何度も繰り返すが、リアリズムがあるからだ。作り物ではない、本来の現実があるからである。小林秀雄は、そこに、尊敬の念を抱いているのだと言えよう。小林秀雄論ー志賀直哉について、対話集からー、として述べて来たが、物を見る眼にも、様々な種類がある事が明示されている、この対話集は、小林秀雄、その人を知るには、とても分かり易い本である。ここで、小林秀雄論ー志賀直哉について、対話集からー、を終えようと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
