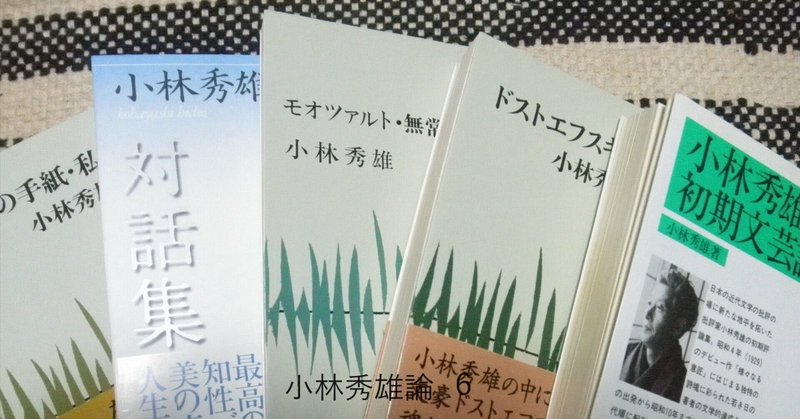
小林秀雄論ー徒然草についてー
小林秀雄論ー徒然草についてー
㈠
小林秀雄程、徒然草の兼好に、魅せられた人はいない。というより、小林秀雄程、兼好の本質を吐露したものもいなかった。実に難しいことを、簡単に言って居る、徒然草は、すごいことをした、小林秀雄はそういうのである。兼好を批評家と見た小林秀雄の眼に、恐らく狂いは無かったであろう。引用して、論を進めてみる。
㈡
兼好の家集は、徒然草について何事も教えない。逆である。彼は批評家であって、詩人ではない、徒然草が書かれたという事は、新しい形式の随筆文学が書かれたという様な事ではない。純粋で鋭敏な点で、空前の批評家の魂が出現した文学史上の大きな事件なのである。
以前、物を見る眼を発見したのは小林秀雄が初めてだと書いたが、兼好の場合は、自身がものを見る眼があったかどうかを自覚していたかは無いにしても、その「批評家の魂が出現した文学史上の大きな事件」だと、小林秀雄は言う。自己投影ではあるが、少し距離を置いて誉めている点で、投影以上の尊敬の観が見て取れる。小林秀雄にすれば、兼好の徒然草は、よほど達観した位置に居た者にしか書けないものだと写ったのだろう。そして、日本文学史においても、世界を見渡しても、文学というものの歴史の上で、大きな事件だと述べている。
㈢
彼は、モンテエニュがやった事をやったのである。モンテエニュが生れる二百年も前に。
この言葉が、兼好への最大の褒め言葉であろう。そして、小林秀雄は、古典において、日本文学史上の誇りとして、兼好を位置付ける。
どんな思想も意見も彼をうごかすに足りぬ。
小林秀雄が自分の事を言う様に、兼好に対する表現が誇張気味に見えるが、そんなことはないだろう。「どんな思想も意見も彼をうごかすに足りぬ。」とは、小林秀雄の投影でもあるが、それ以上に、兼好の本質を言って居るのであろう。うごかすに足りぬ、とは、どんなものも、悉知した上で、それを見通す、ということだ。理解しているということだ。
㈣
小林秀雄論ー徒然草についてー、として述べて来たが、小林秀雄が、古典を振り返る時、批評家としての、兼好と宣長を述べて居る文章が、一番読み手に分かり易く伝わってくる。それは、同じ批評家としての、生き方の先祖にあたるからだ。小林秀雄の思いにおいては、それ程如実に、批評というものの存在が大きかったのである。同族意識と捉えても良い。かなりの尊敬の念が看取出来るが、それを精緻な文章にしてしまえる小林秀雄の存在もまた、我々現代の文学を考えるものとして、偉大なものだ。小林秀雄の書いた、『徒然草』がある限り、^日本文学史において、兼好の位置は、偉大なものとして、規定され、後世に残存していくだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
