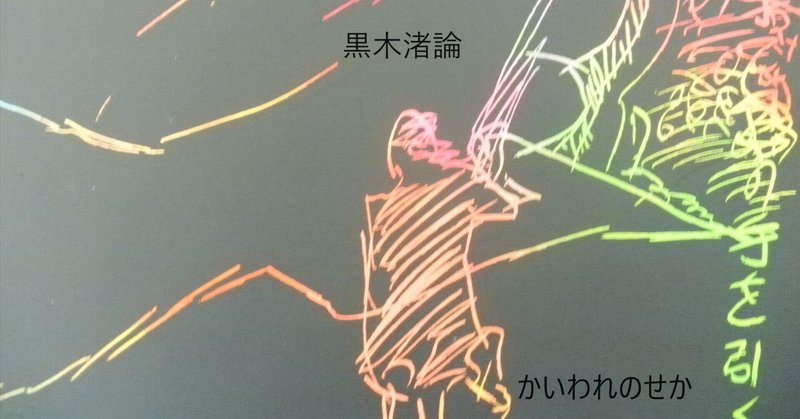
『黒木渚論』―黒木渚、そのイニシアチブに沿って―
『黒木渚論』―黒木渚、そのイニシアチブに沿って―
かいわれのせか
まず初めに、どこにも発表していない、『黒木渚論ー序説ー』を書いた。その後の構成としては、【第一章】は、小説家になろうで、書き溜めた評論的文章のまとめになっている。一部省いているが、大体の、黒木渚論を載せた。【第二章】は、note、から、適切だと思われる文章を載せた。こちらは、評論というより、エッセイに近い文体である。【第三章】は、自分が、2023年の一年で書いた、【黒木渚格言集】(2023年)でまとめてある。
『黒木渚論ー序説ー』、「おわりに」の書下ろしを含むと、全42論の、長編である。小説家になろうや、noteで、黒木渚論を書いていても、それを時にいいねで、励まして頂いた、黒木渚さんに、改めて、感謝します。また、執筆を励まして下さった黒木渚のファンの方々を始め、出版に関わって下さった、全ての方々に、感謝の意を表します。
※本論の編集に於いて、文章に多少の加筆、修正を、加えましたことを、明記して置きます。
目次
【第零章】
『はじめに』
『黒木渚論ー序説ー』
【第一章】
『黒木渚論・・・小説と歌詞における言葉の考察』
『黒木渚論・・・呼吸する町について』
『小説の言葉の結び方』・・・黒木渚の『本性』に於ける考察
『黒木渚論・・・心がイエスと言ったなら、について』
『黒木渚論・・・死に損ないのパレード、について』
『黒木渚論・・・ライブの本質』
『黒木渚論・・・配信ライブ、死に損ないのパレード』
『黒木渚論・・・ベストアルバム発売』
『黒木渚論・・・新曲『ロマン』について』
『黒木渚論・・・芸術の天才の分岐点』
『黒木渚の、ベストアルバムについて』
『黒木渚論・・・10周年の間の歌詞の変遷』
『黒木渚論・・・10周年の間の歌詞の変遷』(補足)
『黒木渚の棘ー或るラジオー』
『黒木渚論・・・その歌詞と方法論』
『黒木渚論・・・「さかさまの雨」と戦後』
『黒木渚ー100周年記念ワンマンー【東京】』
『黒木渚論・・・自由なライト』
『黒木渚論 黒木渚の棘に見る棘の意味』
『黒木渚論・・・最高傑作「Light house」について』
【第二章】
『黒木渚「落雷」における歌詞』
『黒木渚さんと哲学』
『黒木渚「落雷」の可能性』
『黒木渚「落雷」が落雷して、日本の神になる話』
『黒木渚ステッカーで、落雷しかけた話』
『小旅行記ー東京(頭狂)日記ー』
『黒木渚、歌詞に見る高揚の原則』
『黒木渚さん、ビルボード迫る』
『黒木渚×ジャズ×ビルボード、について』
『黒木渚さんの、イベント配布、カレンダー』
『黒木渚さんの、器器回回ツアーが、楽しみな理由』
『黒木渚さんの、「さかさまの雨」と「落雷」』
『黒木渚さんの、武道館への階段』
『黒木渚さんの、曲タイトルで、書いた小説』
『黒木渚さん、「落雷」、140,000 回視聴』
『黒木渚格言集の編集について』
『黒木渚さん、最新アルバム「器器回回」配信開始』
『黒木渚「器器回回」ライブ、大阪』
【第三章】
【黒木渚格言集】(2023年)
『おわりに』
※文章の中で、黒木渚という本名で活動されているので、黒木渚と表記していますが、決して渚さんを呼び捨てにしている訳ではないことを、ご了承願います。
※本論の編集に於いて、文章に多少の加筆、修正を、加えましたことを、明記して置きます。
【第零章】
『はじめに』
まず初めに、どこにも発表していない、『黒木渚論ー序説ー』を書いた。その後の構成としては、【第一章】は、小説家になろうで、書き溜めた評論的文章のまとめになっている。一部省いているが、大体の、黒木渚論を載せた。【第二章】は、note、から、適切だと思われる文章を載せた。こちらは、評論というより、エッセイに近い文体である。【第三章】は、自分が、2023年の一年で書いた、【黒木渚格言集】(2023年)でまとめてある。
『黒木渚論ー序説ー』
㈠
自分が黒木渚さんを知ったのは、ヤフーニュースでの、黒木渚解散、という記事である。そこから、黒木渚というバンドが解散するのだ、ということを知り、その後、黒木渚さんは、ソロデビューを飾る。しかし、ソロとは言っても、バンドスタイルの、制作、ライブであることは、確かだった。
㈡
イニシアチブ(主権)という言葉を、黒木渚さんは使われていて、それは、「大本命」という曲の歌詞で歌われるように、「戦って行くの本当の名前で」という、云わば自我と世界との闘いでもあった。ソロになってから、曲は聴いてはいたものの、始めて参加したライブは、「ふざけんな世界、ふざけろよ」の時である。
㈢
その後のライブは、大阪で開催されるものは全て参加している。一度、東京にも行った。そして現在、黒木渚さんは、独立されて、大作をどんどん、発表している。直近の「器器回回」は、素晴らしい作品だと思って居る。さて、この文を、『黒木渚論ー序説ー』、とするが、以降、自分が今まで書いて来た黒木渚論を、ピックアップして、まとめることとする。
【第一章】
『黒木渚論・・・小説と歌詞における言葉の考察』
㈠
4冊の小説を出している黒木渚※であるが、言葉の使用方法が、どちらかと言うと、主体が隠れているのである。小説に本質はあるのに、主体が隠れるとはどういうことだろう。これは、多分に、本人も述べていたが、内容の裏を取っていることが影響していると思われる。また、本人と小説の内容が、これもまた同化しないのである。
しかしこれは、文章力があるということに尽きるだろうし、そもそもが、小説で自分のことを述べなければならない必要性はないし、小説の言葉を、独り歩きさせ、その独り歩きを、俯瞰で見て執筆を続けている、といった感じだろうか。
㈡
また、忘れてはならないのは、黒木渚は、もともと音楽家であって、その歌詞は、高く評価されている。その歌詞が、非常に今まで読んだことの無い様な、つまり、音楽の歌詞の歴史に突然現れたかのような、過去性のない歌詞なのである。
「あしかせを付けた私は逃げ出すこともできず この小さな空間で死んでくのかな」
「あしかせ」から
といった、民俗学にまで発展しそうな、この概念的歌詞は、死んでいくのかな、という絶望とともに、そのもがき苦しむ心象衝動を的確に表していて、聞き手に響いてくることは確かだ。また、足枷という漢字を使わず、ひらがなでタイトルを付けているところにも、何か独房の様な家に囲まれて、家の外に出れないような、檻の中の感覚を、まさにその叫びとして、漢字よりも印象付けている。
また、例えば、
「ユーモアの蕾ほころんで 世界が溶けていく 世界に溶けていく」
「ふざけんな世界、ふざけろよ」から
などは、世界が溶けていくという外界の現象から、世界に溶けていくという内界の自己現象にまで引き戻すことで、一種の溶ける感覚を、ユーモアを起因として、蕾に例えていることで、歌の終着をこれ以上ないほどに美的に結んでいる。こう言った、言葉の前後関係の倒置使用方法は、類い稀なものだと言えるだろう。
㈢
この様に、小説と歌詞における言葉の使用法は、上記した以外に、数え切れないほど使用されているので、まずは音楽と小説を味わってほしいし、自分としては、此処に感動を感じている。また、当の本人は、あまりこういった創作に対する努力態度を垣間見せない。
これは、黒木渚の一つの美学観からくるものだと推測しているが、とにかく、そのセンスに酔えることで、多くのファンを獲得しているのだから、生きる姿勢にまで、ファンは共感を抱いているのかもしれないと感じている。
上記してきたものは、あくまで自分の感想であって、黒木渚本人の意向とは異なっているかもしれないが、少なくとも、自分はこの様に小説と歌詞、音楽、に触れる時に、このように酔えることで、エネルギーを貰っていることだけは疑いないと言える。
『黒木渚論・・・呼吸する町について』
㈠
黒木渚※の小説を読んだ時、前回書いたが、主体が見えないと書いた。これは、しかし逆説的に言うと、客体として小説を執筆していると言えるのではないかと思った。それが小説の本質なら、確かに小説は客観的である。
『呼吸する町』は文芸誌に記載され、最終章以外は、本が刊行される前に読んでいたのだが、方法論として、ドストエフスキー的だな、と思ったり、村上春樹を超えているな、と思ったりしたものだ。それでも、それらの方法論に撒かれることなく、しっかりとした文体である。面白い、とか、悲しいとか、辛い、と言った感情観を考えさせられる個所もあるが、一貫して、それは、楽観的な町で起こっている出来事なのだ。
㈡
ラクトル、という架空の飲み物を中心として、この呼吸する町は描かれているが、本質は、日常の人間劇である。それがまた、人々が呼吸する様に、当たり前に描かれている点で、架空と現実が相まって、架空を現実感のあるものに創り上げている。人々の会話も非常に現実的だし、かと言って、唯現実的なだけではなく、小説的でもあるのだ。この不思議を何と例えれば良いだろうか。
しかし読者は、その様な方法論を考えるまでもなく、小説の世界にしっかりと入れるし、実感を持ってその世界観を味わうことが出来る。結句、この小説は、あくまでも読者主体に描かれているから、我々はその世界に、入りやすいのである。これは、少なくとも自分が思うには、黒木渚独特の、小説執筆の方法論である。それが故、小説を読んでいて、面白いし、飽きないのだ。
㈢
ところで、小説の限定版には、サイン入りであることと、ラクトルのボールペンが特典で付いて来た。これが非常に嬉しかった。楽しい、の上に、嬉しい、という感覚が重なり合った本になったし、家宝にしようとも考えている。いくつか案があった中で、ボールペンになったことは、自分としては嬉しかった。
そしてまた、小説の根底にあるある種の楽観的思考というべきものが、読者の日常を楽しくしてくれるので、また、ありがたいことなのだ。まさに、自分にとっては、エネルギーを貰うと言った感覚になる。
夏に刊行されたこの小説に続いて、秋には音楽家としての黒木渚が戻ってくる。まさに、新たに再生し、呼吸をし始めた黒木渚が、今度は音楽で何を以ってエネルギーを与えてくれるのか、この夏の暑さにも増して、楽しみで仕方がない。
『小説の言葉の結び方』・・・黒木渚の『本性』に於ける考察
㈠
四つ目の小説としても、定義することが可能だとされている、あとがき、では、この様に結ばれている。
「人間の本性なんて、幻想のようなものなのですから。」
黒木渚※の文庫本の話なのであるが、敢えて、あとがきを、小説形式にしたことは、より、小説『本性』を不可思議なものへと育てあげたと言えるであろう。奇怪、不可思議、こう言った言葉が適切かどうかは分からないが、『本性』に漂う、或る種の、一般の小説からはかけ離れた異質さが、見て取れる訳である。
㈡
『本性』が、三つの小説と、あとがきの、四つで構成されていることは、周知の事実だ。どれもが、独特の、純文学として、社会の構図を芯から捉えた形の小説になっている。其処には、いわゆる、人間味が表現されていて、とても観念だけで書き上げたとは言えないであろう、社会の本質を言い当てている。
㈢
熟読して読み込むと、其処には、生身の人間生活に於ける、虚像と実像が浮かび上がってくる。黒木渚は、小説の執筆にあたって、随分と取材を重ねたと発言しているが、だからこそ、空想を跳ね除けた小説=幻想が現実の如く、読者に伝わってくるのであろう。
もう一度読み返したい、と思わせる内容になっているのは、絶えず、言葉の結び方が、復読を喚起するからである。我々は其処に、いわゆる、現実を幻想の様に見ているのである。
もう一度、述べておきたい。あとがき、では、この様に、結ばれている。
「人間の本性なんて、幻想のようなものなのですから。」
『黒木渚論・・・心がイエスと言ったなら、について』
㈠
黒木渚※の新しいアルバムが、7/7に発売される。待ちに待った、というべきか。このコロナ禍の中で、新たな一歩を踏み出した、その姿を、音楽から聴き取りたい。というのも、リード曲、心がイエスと言ったなら、からは、これまでとは違う、日本の音楽性が感じ取れるのである。
㈡
文字通り、心がイエスと言ったなら、は、自分の心に正直に生きることの、応援歌だが、戦後日本は、ノーが言えない日本人ということを、良く揶揄されてきたことを思い出した。心がイエスと言ったなら、は、イエスと言う、ということではない、心がイエスと言ったなら、ノーと、言うことも、必要だと読み取れるということだ。
㈢
言葉の音楽性が、どれほど、新しいアルバムから聴き取れるかは、既に配信済みの、ダ・カーポ、と、竹、から、既に高尚なものとして、認知されている。全曲を、通して聴いた時、アルバムの全貌が見えてくるだろう。特典のグッズも、楽しみで仕方がない。
『黒木渚論・・・死に損ないのパレード、について』
㈠
黒木渚※の新しいアルバムが発売された。死に損ないのパレード、という名の、名盤である。自分は、黒木渚史上、最高傑作ではないかと思っている。オリコンでも、5位に位置した、ということは、ファンの、狭い所にも、広い所にも、両方に響いたということだろう。新たなファンも、増えたに違いない。
㈡
一言で言えば、深刻もユーモアも、適切に配置されている、と言う感じである。これは大変難しいことで、殆どのアーティストが、極に寄るのであって、両極を持ち合わせるのは、非常に困難であると思う。それを成し遂げたのは、一つには、声得の先天性的一定性によるものだろうか。想像よりも、音楽は証明しているだろう。
㈢
自分は、タワレコ、HMV、ラストラムで、購入したので、グッズも集まったし、3盤全てが揃ったので、満足している。そして、死に損ないのパレード、というアルバムを、届いてから、何度も聴いた。もう、本当に、何回も聴いた。それでも飽きないのは、黒木渚という歌い手の成せる業か。明日も明後日も、来年も、恐らく、聴いているだろう。間違いない。
『黒木渚論・・・ライブの本質』
㈠
黒木渚※の、配信ライブ、『死に損ないのパレード』が、来たる11/6(土)21:00に、公開される。チケットは、イープラスで、¥2,500、となっている。自分は、このライブを、直接、生では見に行かなかった。様々な理由があるが、コロナ禍だったということもある、行かなかったら、行かなかったので、配信ライブは、当然見るのである。
㈡
どの様なライブなのかは、11/6まで分からないが、既に発売された、アルバム『死に損ないのパレード』は、毎日、聴き込んでいるので、これらの曲が、どの様に演奏されるのか、楽しみでしかたがない。恐らく、とんでもない世界を、表現されるであろうことは、アルバムタイトルからも、想像出来よう。
㈢
言葉や音楽は、日常に根差してはいるが、非日常である。まるで、日常では体感することのない、上質な世界を、味わうことが出来る。即ち、自己の人生が、悉く、変容してしまう様な、実体感というものが、ライブの本質である、配信ライブであっても、その本質は、伝わってくるだろう。コロナ禍という、異常事態に、まるで事態を制圧した世界を、見れるだろうと思う。興味のある方は、是非、パレードに参加してみてはどうだろうか。
『黒木渚論・・・配信ライブ、死に損ないのパレード』
㈠
配信ライブ、死に損ないのパレードを、見終わってから、もう、何度も見返したが、やはり、素晴らしい内容だった。舞台装置の設定や、演奏の形式が、まるで前衛芸術の舞台の様に思え、また、黒木渚※が、音楽家ではあるが、女優の様な姿勢で居て、センスが有り、とにかく最高だった。
㈡
始まりの、演奏からの、何ら本質の消失した、メタファとしての球体が、まるで、心臓の様に、呼吸をしている。何かが始まった様で、もう終わってしまったかの如く、そのメタファが、崩れた時に、黒木渚が現れた、圧巻のひと言である。どの曲も最高だったが、心がイエスと言ったなら、は、本当に、素晴らしかった。
㈢
繰り返される音像は、女優の様な姿勢の黒木渚を、より引き立てる。間違いなく、見て置いた方が良い、と断定出来る内容だった。恐らく、いつ死んでも後悔のない様に、全力で生きているのだろう。自分も、死を意識し出した頃から、全力で生きることを、目標にしている。「狂ったように走ってゆけ」は、心に響く、言葉だった。
『黒木渚論・・・ベストアルバム発売』
㈠
来たる、4月20日に、黒木渚※のベストアルバム、『予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる』が、発売される。全23曲入りで、予約特典の、『さかさまの雨』も含むと、24曲となり、かなりの収録数だが、値段は手頃になっており、黒木渚を初めて知るファンにも、打って付けの販売方式である。
㈡
個人的には、新緑が3曲、『さかさまの雨』も含むと、4曲となり、とても楽しみなのである。また、今月22日の黒棘では、新曲が流れるとのことで、今から来週火曜日が、楽しみである。アートシーンを塗り替えて来た、黒木渚の真骨頂が詰まった、最高のベストアルバムなので、是非、購入して聴いて貰いたい。
㈢
また、様々に、特典も付いてくるので、こちらもお勧めである。思えば、各アルバムごとに、入れ替える必要がなく、2枚組なので、通して黒木渚の曲が聴けるということで、リピート再生は、マストになるだろうと思っている。春ごろから、本格的に、黒木渚が動き出す様で、新たな情報を待ちたいところだ。
『黒木渚論・・・新曲『ロマン』について』
㈠
昨日の黒棘で、春に発売されるベストアルバムから、『ロマン』が流れ、本日の0時から、ダウンロードが開始された。ゆったりとしたバラードで、聴きごたえのある一曲である。自分は、初めて聴いた時に、この壮大なバラードに感動した。
㈡
「ロマンを抱えて生きている」、まさに、普遍的な、感覚ではないだろうか。手に入るもの、手に入らないもの、すぐに手にするから虚しい、すぐには手に出来ないから必要とする、そう言った、パラドックスを超越した、歌詞の語群が、脳髄を打つ。
㈢
ベストアルバムがディスクユニオンから発売され、特典にキーホルダーが付くことも、発表された。是非、チェックしてみて貰いたい。ベストアルバムの発売日が迫るに寄せて、新曲の解禁が少しずつ始まっている。今週末には、『ロマン』のMVも、プレミア公開の様だ。アルバム発売までの、この焦燥も、一つのロマンの様である。発売日が待ち遠しい。
『黒木渚論・・・芸術の天才の分岐点』
㈠
黒木渚※の活動が、活発になって来た。7月には、ライブの開催も決定している。ベストアルバムが出るということは、恐らく、ライブも、音楽家としての、一つの集大成となるだろうことは、予想できるが、それにしても、この素晴らしい芸術家にとっては、大きな分岐点になるだろう。
㈡
何かが始まることは、何かが終わることで、何かが終わることは、何かが始まることである、こんな風に考えると、今回のツアーとベストアルバムは、黒木渚の偉大なる位置、を感じさせる。自分には、この芸術家が、音楽家であり、小説家であるという、二つの場所に、意味があると思っている。
㈢
例えば、『死に損ないのパレード』にある、「静寂にも飽きたころだろう?」という台詞には、時代の先を見通した、芸術家としての位置が見出せる。世界が静寂であることの、場所の発見は、奇妙にも、世界を前進させる意思の力が読み取れる。
㈣
静寂は良いことだ、しかし、静寂の位置だけには、留まっていられまい、という言葉の響きが、音楽と相まって、天才の明証となる訳である。また、本質的には、本物の芸術家は、芸術にどれだけ金と労力が掛かっても、芸術に手を抜くことはしないのだ。
㈤
だから、我々は、黒木渚の芸術に、期待するし、期待させられるのである。そして、ライブという空間の体現という、もう一つの武器によって、芸術は開花する。今回のライブにおいて、黒木渚は、大きな分岐点を迎えるだろう。停滞からの、必然的前進、ということである。世界が前進する様に、黒木渚も前進する。
㈥
日本の芸術史において、突如現れた、黒木渚は、黒木渚以前、黒木渚以後、として、位置を確保したのではないだろうか。類稀なる、芸術のセンス、言葉のセンス、そして、黒木渚の人間的魅力、芸術界に、突如として現れた逸脱的新しさが、今度は、黒木渚以前の芸術が、逸脱していたかのように映る世界が、日本の芸術界の先を行くだろうことは、自明の理だと、思われるのである。
まさに、天才の分岐点となるだろう。
『黒木渚の、ベストアルバムについて』
㈠
本日、黒木渚※のベストアルバムが、手に入った。つまり、新曲4曲が聴けた、ということである。まずは、新曲を聴き、その後、通して聴いてみた。充分過ぎるくらいの、最高感である。そしてまた、リミックスされているのか、詳細は分からないが、既発曲も、音質が違って聴こえた様に思う。とても嬉しかった。
㈡
端的に言って、『予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる』という、タイトルのベストアルバムだからだろうか、タイトル曲には、痛烈な迫力がある。また、打って変わって、ダウンロード曲の『さかさまの雨』は、静寂の悲しさの様である。何と言っても、雨、と言う言葉が、なじんだ曲調である。
㈢
『ロマン』は既に聴いていたし、『V.I.P.』も、セルフカバーとなっている。どちらも、初めて聴くファンには、荘厳に映る音像だと言っていい。もう一度言って置きたいのは、自分だけかもしれないが、既発曲も、今までとは異なって聴こえるということ。もう既に、様々にアルバムを持っているファンでも、購入して、充分過ぎるくらいに、最高感が味わえる、ということ。
7月の黒木渚のライブは、最高の音楽祭になるだろう。
『黒木渚論・・・10周年の間の歌詞の変遷』
㈠
黒木渚※1の、10周年の間の歌詞の変遷、ということで、内容をまとめて置きたい。ベストアルバムに集約して述べることにする。DISC 1、DISC 2、に分けられた流れを看取すると、解放前から、解放後、ということになるだろうか。原理的には、『解放区への旅』が、内界から外界へ、と言うことになる。
㈡
DISC 1、から歌詞を拾えば※2、「それに飽きたら」「ほんの出来心」「墓石に」「はさみを」「罪を知る」「ひとごみの中」「崩れあってゆく」「いいかげんな誰かの」「孤独の種」「腐敗する心」「ふざけんな」「切なさに溺れて」、と在る。内界へと向かう歌詞は、一つの孤独世界を表してはいまいか。
㈢
内界は、芸術を創造するには、打って付けの財産だ。傷が有るほど、その傷は、残酷にも、負の遺産として、芸術に変貌する。内界に生じた歌詞の数々は、音楽に乗せて、ファンへと届けられて来た。黒木渚は、云わば、そう言った内界に生きる者たちへの、孤独救済のメッセージとして、躍動して来た、という原理になる。
㈣
ところが、DISC 2から歌詞を拾えば※3、「今を生きる」「息をしてる」「憂鬱も手放して」「どこへだってゆける」「毒、吐く」「世界を吸い上げて」「泣いてないで」「走ってゆけ」、と在る。外界へと向かう歌詞は、聴く者の心を、外界へと向かわせはしまいか。
㈤
外界とは、内界から外へと出た世界のことである。云わば、前向きになった歌詞で、黒木渚は、聴く者の心に、外へ外へと、意識を向かわせるのである。生きていれば、死にさえしなければ、人生は続いて行くものだ、という死と決別したメッセージを、表現しているという、原理となる。
㈥
黒木渚の、10周年の間の歌詞の変遷とは、こういった、或る種の解放原理を標榜してはいまいか。それは、実際には、内界で躓いた者にしか与えられない、外界の存在理解と言うものだろう。外界と言う世界がある、ということへの気付きが、歌詞の変遷として、表現されて来たのではないかと、思わされるのである。これから先、また、黒木渚は、ファンに、新しい世界を見せてくれるだろう。改めて、その意志の姿を待ちたい。これで、変遷の集約としておく。
※新曲の歌詞は、省きました。新曲については、自己前書に、一部分有り。
『黒木渚論・・・10周年の間の歌詞の変遷』(補足)
㈠
DISC 1、から拾った歌詞の内在する曲目。
「それに飽きたら」・・・あたしの心臓あげる
「ほんの出来心」・・・カルデラ
「墓石に」・・・骨
「はさみを」・・・はさみ
「罪を知る」・・・革命
「ひとごみの中」・・・虎視眈々と淡々と
「崩れあってゆく」・・・君が私をダメにする
「いいかげんな誰かの」・・・大予言
「孤独の種」・・・アーモンド
「腐敗する心」・・・原点怪奇
「ふざけんな」・・・ふざけんな世界、ふざけろよ
「切なさに溺れて」・・・灯台
㈡
DISC 2、から拾った歌詞の内在する曲目。
「今を生きる」・・・解放区への旅
「息をしてる」・・・火の鳥
「憂鬱も手放して」・・・美しい滅びかた
「どこへだってゆける」・・・檸檬の棘
「毒、吐く」・・・ダ・カーポ
「世界を吸い上げて」・・・竹
「泣いてないで」・・・死に損ないのパレード
「走ってゆけ」・・・心がイエスと言ったなら
㈢
取り上げた歌詞が内在する曲目を、補足として明記しておきます。
『黒木渚の棘ー或るラジオー』
㈠
youtubeで、毎週火曜日の夜9時から1時間、黒木渚の棘、というラジオが放送されている。もうずっと、毎回視聴しているが、とにかく面白い。退屈のない、もう1時間経ったのか、と、時計を見て唖然とするほどに、とにかく面白い。
㈡
我々には、時間を自由に使える自由というものがある。確かに、火曜の夜9時は、眠たい時もある。しかし、それをおしてでも、今回も視聴しようという気になる、面白さである。端的に言って、ユーモアの塊の様なラジオなのだ。
㈢
様々なコーナーが設けられており、我々はその題目に対して、メッセージを送る。読まれる時も、読まれない時もあるだろうが、ファンのかたの、メッセージを聴いてるだけで、面白い。つまり、このー或るラジオー、は、明白に言って、-最高のラジオ-、なのである。
『黒木渚論・・・その歌詞と方法論』
㈠
今年で10周年を迎える、黒木渚※だが、ベストアルバムに入っている歌詞を読んで、やはり秀逸だな、と思うのである。何と言うか、無駄が無いのに、隙も無いというか、やはり完成度が非常に高い、と言えば、最適だと考えている。
㈡
勿論、歌詞には、音楽が付いていて、曲として存在しているのだから、歌詞だけを見ても、意味はあるまい。歌詞の価値というものは、音楽の演奏、音律、そして声によって、多方向に様々に、意味を含蓄して、成立するのである。
㈢
既出論、『黒木渚論・・・10周年の間の歌詞の変遷』、でも歌詞を取り上げたが、黒木渚の曲は、音の押し引きによって、形成されている様に思う。例えば、「ダ・カーポ」の、
ここに出口はない
(「ダ・カーポ」黒木渚)
とあるように、その音の押し引きに入り込んだなら、聴き手も、出口はなくなるだろう。これは、一種の黒木渚の方法論ではないだろうか。6/15に、単行本、文庫本の発売、7月にライブ、と、目まぐるしく、黒木渚は動いている。是非、アルバムと書籍を手に取って、ライブに臨んで貰いたい。
『黒木渚論・・・「さかさまの雨」と戦後』
㈠
本日、黒木渚※の、「さかさまの雨」が、デジタル配信された。自分は、特別に、この曲が、日本の歴史と関連して聴こえる様に覚えた。というのも、アレンジが、どこか軍歌調で、そこに、黒木渚の歌詞が相まって、何か、第二次世界大戦後の、戦後日本を想起させられたからである。
「君は私のものだったよ」
(「さかさまの雨」黒木渚)
という歌詞、勿論、それだけに集約されない、歌詞全体が、原爆投下後の日本における、天皇をイメージさせられた。
㈡
単純に言って、「さかさまの雨」から、戦後日本を想起した、として、論じることは、極端なことを言っているのは、自分でも自認している。ただ、「予告通りに堕落して終わる」、なども、見逃せない、歌詞としての、重要な位置を占めている様に、強く感じさせられる。
㈢
日本が今後、どうなるかは不透明だが、雨の描写も、井伏鱒二の『黒い雨』を思わせるし、何か、日本が本当に復興するための、何かを含蓄した歌詞に思われる。何度も述べるが、アレンジの軍歌調が、想起するに至った起因にはなっている。
「君は私のものだったよ」
日本人は、今後、日本の君、を捉えられるだろうか。課題は沢山ある、迷妄の世界に入らない様に、世界でその確かな位置を、示していて貰いたい、国家そのものが。国家そのものが。
『黒木渚ー100周年記念ワンマンー【東京】』
㈠
皆さんが、ライブレポをされているので、書くことがないのだが、ライブはやはり良いな、と思った日だった。7/8に、朝から新大阪へ行き、新幹線に乗って、東京に着いた。実は、一人東京旅は、初めてだったので、不安もあったけど、ライブが最高だったので、全てが、終わり良ければ総て良しだった。
㈡
100周年記念ワンマン、どの曲も良かったけれど、「灯台」のアレンジは良過ぎた。是非音源化を、と、聴いている時に、すぐ思った。黒木渚※は、途轍もなく、かっこよかった。もう、形而上も形而下もない、ど真ん中の、音像だった様に思う。良席だったので、なお、良かった。
㈢
会場では、予約していたグッズの受け取りと、自分は追加で、書籍を2冊。既に持っていたのだが、記念にと思い買ったら、昨日見たら、両方ともサイン入り。買っといてよかった、ありがとうございます。東京に一泊して、7/9に、帰ってきたが、これを書いて居る現在でも、ライブの余韻は残っている。この最高の余韻は、いつまで続くだろうか。
『黒木渚論・・・自由なライト』
㈠
7/8に、東京国際フォーラムCでの、黒木渚のライブに参加したことは、以前述べた。その時の自己の状態を振り返ってみる。席は前から5列目の真ん中だったからか、とにかく暗闇で照らされるライトが目に入って、半ば、光の中で過ごしていた。勿論、音楽は、しっかりと、耳に届いていた。
㈡
自由なライトだった様に思う。その自由の根幹は、芸術である。光とともに生きてきた、黒木渚※が、光を失い、やがて、
「『檸檬の棘』のツアー(2020年開催)で、さらに巨大になった光が戻ってきたんです。その現象に名前もないし、意味もわかっていないけど、きっとあの光は、みんなが取り戻してくれたということに私の中ではしています。本当に、光を取り返してくれてありがとう」(ライブレポから抜粋)
と言う状態まで戻ったことの、ファンへの感謝の光だったのではないだろうか。あの自由なライトは。
㈢
つまり、あの自由なライトは、ファンを照らすという、黒木渚からのファンへの、感謝のメッセージだったのだろう。あのライブの夜、その自由なライトの中、舞台は光に満ちていた。今でも、その光に照らされて得たエネルギーで、自分は、生活をしている。もう一つ踏み込んで換言すれば、黒木渚は、「灯台」そのものだった。
客席を自由なライトで照らした、東京でのライブでの場の記憶を、自分は恐らく、一生、忘却しないだろう。
『黒木渚論 黒木渚の棘に見る棘の意味』
㈠
黒木渚※が、毎週火曜日の21時から、youtubeでラジオをやっている。黒木渚の棘、通称黒棘、というラジオである。以前にも書いたが、とにかく、ユーモアに溢れていて、面白い。アルコールを飲みながらの配信の時もあるが、とにかく、ユーモアに溢れている。
㈡
さて、どう論を運ぼうかと思うが、このタイトル、黒木渚の棘、というのは、小説であり楽曲である、『檸檬の棘』の、棘という言葉を使用しているのだが、ラジオの最後はいつも、尖って行こうぜ、という台詞が、決まり文句となっている。
㈢
楽曲『檸檬の棘』の歌詞には、
君はやがて知るだろう あの素晴らしい棘を 「檸檬の棘」/黒木渚
と記されている。
㈣
また、尖るという言葉には、
1,物の先端が細く鋭くなっている。2.敏感になる。3.声などが興奮などのために高く鋭い調子になる。とげとげしくなる。4.(比喩的に)他よりも突出している。過激である。または、相手の弱点を容赦なく突いている。 「デジタル大辞泉」から
と記されている。
㈤
棘が尖るという意味で、尖って行こうぜ、となると、全ての意味を包括していそうだ。それはまさに、鋭く尖って行こうぜ、となる。そしてその棘は、素晴らしいと歌われている。何れにせよ、こういった精神に基づいて、創られているラジオが、黒木渚の棘、なのである。
㈥
メッセージを募集して、読まれたり、読まれなかったり、それは様々にある。チャットの言葉も拾われ、循環しながらラジオは進む。本当に、面白いし、飽きないので、ずっと見ているが、自分にとっては、人生史上、一番面白いラジオとして、位置付いているので、今回、取り上げてみた。
『黒木渚論・・・最高傑作「Light house」について』
㈠
敢えて、最高傑作、と言って置きたい。ファンなら分かる、「灯台」のアレンジバージョンだが、空気感は全くの別物だ。黒木渚※が言うように、ファンのために作られた楽曲、それが「Light house」である。灯台のことを、英語では、Light houseというらしい。タイトルも変わって、更に、別物だ。
鼓膜にそっと触れるかのような、絶妙な歌いでもって、「Light house」は成立している。ただ、自分が思うに、敢えて最高傑作、というのは、このアレンジを含めて、である。始まりの電子音が、電話する時の、初めの通話音に、酷似しているのである。
㈡
海を照らすLight house、何か、海に飲まれて死んでしまった人々へ、そっとその回帰を促すような、死者への言葉の寄与の様にも聴こえてくる。死者の携帯に電話するかのような。つまり、津波に飲まれて、死んでしまった人への、レクイエムの様に聴こえてくるのである。
だから、津波を取り扱った、最高傑作、と言って置きたい。云わば、神の位置から、そんな人々の魂を、救済するかのような曲なのである。単なる恋愛歌ではなく、まさに、レクイエムとして、「Light house」は、灯台から海へと拝跪しているかのようだ。
㈢
だから、その点で置いて、「灯台」とは全く意味の異なる曲として、リリースされたのである。まだ、曲の聴きこみが少ないせいか、ー何度も何度も聴いていて、それでも足りないと思うくらいにー、その本質を掴むことで精一杯だが、これからも何度も聴くだろう。
曲を評論するのは、とても難しい。自分にとっては。だからこそ、何度も聴くのである、その実体を知るために。些か、難しい理論的めいた評論になったが、純粋に、「Light house」は、最高に良い曲である。考察などしなければ、この何度でも聴く、が、「Light house」という曲の最高傑作としての聴き心地の良さを、証明しているだろう。
【第二章】
『黒木渚「落雷」における歌詞』
これまで、MVとの関係性について述べてきたが、今回は、歌詞に絞って、述べてみたいと思う。
歌詞について述べるにあたり、詞音や意味、言葉の配置についてなど、様々に述べてみる。
例えば、初から見ていくと、
壊れつつあるのか 回復してるのか
「落雷」/黒木渚
闇のような光のような
「落雷」/黒木渚
産まれつつあるのか 滅びつつあるのか
「落雷」/黒木渚
この、3つの歌詞を見ても分かるように、両極性が看取できるのである。「壊れ」「回復」、「闇」「光」、「産まれ」「滅び」。この両極性というものは、芸術家特有のものなのだろうか。例えば芥川龍之介は、『歯車』の中で、
「さうでもない。僕にははつきりと言へないけれど、……電気の両極に似てゐるの かな。何しろ反対なものを一しよに持つてゐる。」
『歯車』/芥川龍之介
と述べている。両極というものは、物事の両極端、つまり端と端であるが、これは芸術にはたいそう使いやすいものでもある。読解する者の、精神を、端から端へと移動させ揺さぶるのである。それは、読解者を懐疑させるのである。どちらなのか、という混迷が、芸術的に作用している。また、引用したすべての歌詞の語尾が、「a」の音で終わっている。これは、聴き手の内部にリズムを生じさせるものであって、ただ、ひたすらに、聴き心地の良さを、どんどん上昇させていくのだ。
黒木渚「落雷」における歌詞は、見事に、的確に配置されており、曲としても音としても、秀逸である。
何故、繰り返し、聴かれるのか、その要素の一端は、紛れもなく、述べた様な詞音や意味や配置によって、聴き手を惹きつけるからであろう。何、難しいことはない、思うが侭に、「落雷」に、自由に身を委ねるのだ。身体の内部で「落雷」という芸術が、飽和するだろう。
『黒木渚さんと哲学』
黒木渚さんと哲学、を関連付けるに、一番てっとりばやいのは、哲学うさぎ、だろう。その存在は、ファンには知られているが、哲学うさぎが最近姿を現さない。
思うに、哲学とは、観念上のものだから、そうそう現実に役立つ訳ではない。しかし、以前自分がどこかで書いたことがあるのだが、要は、現実で使用し成功した哲学文、というものが、本当の哲学だろうと思うのだ。その点で、例えば黒木渚さんの、予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる、という言葉などは、哲学を超えた、現実上の行為、である。「予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してるということは、つまり観念上の~」という文体になって行くと、それは哲学の文章である。しかし、黒木渚さんは、そんな哲学は関係ないのだろう。或いは、超越しているのだろう。まさに、文字通りの行為として、人を、予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してるのである。
黒木渚と哲学、というタイトルで、ニーチェやカントを、持ち出すべきかと思ったが、そこは、元来の黒木渚さんが、現に実行している、隣人愛、の様な現実を視座に据えたほうが、適切だと思ったので、敷衍しなかった。
もしも、黒木渚が、哲学と結び付く曲を作ったとしたら、それは、観念上のくだらない偽語ではなく、現実で通用し響く、壮大な曲になるだろうと、思われる。
それは、そこでしか行われない、ではなく、世界中で行われる、喝采を浴びるだろう。
『黒木渚「落雷」の可能性』
黒木渚の今作、「落雷」には、大きな可能性が詰まっていると思われる。
まず、MVの再生回数がどこまで行くか、というもの。次に、ライブでどの様な感じで演奏され、集客が見込めるか、というもの。また、ヒット曲となり、周囲を巻き込んで、武道館まで一直線の、代表曲になるかどうか、というもの。
可能性は尽きない。次のアルバムに、恐らく入るであろうから、その位置として、どういった位置づけになるか、ということだ。「独立上昇曲 第一番」、「Lighthouse」そして、「落雷」、名曲は整った。後は、どういう雰囲気のアルバムにするかで、何かグランジの代表格、NIRVANAの「Nevermind」が登場した時の様な、新しい世界が開けそうなのである。
勿論、セールスよりも、自分のファンのために、という意識が強い、黒木渚さんだから、セールスに尽くすということにはならないだろうが、そんな心配をもよそに、「落雷」がこの侭、どんどんと進めば、道は開けるだろう。
また、MVをNYで撮っているから、海外の関心をも巻き込むことが出来そうだ。あの場所知ってる、と、youtubeで、MVを観た人が居れば、ファン層も、世界的なものになるかもしれない。最早、今現在、黒木渚は、日本の黒木渚ではなく、世界の黒木渚なのだ。
それは落雷のように
「落雷」/黒木渚
引用しておいた歌詞、「それは落雷のように」、世界中の人々に、音が響き渡って衝撃を受ければ良い。
『黒木渚「落雷」が落雷して、日本の神になる話』
※この文章は、特定の誰かを誹謗中傷するものではありません。
日本の神は、自然万物に宿っていると、聞いたことがあります。それを敷衍してですが、黒木渚さんは、現在、「落雷」という曲を配信しています。聴き心地が良く、MVの再生回数も高いため、注目度は相当高いと思うのですが、先日、日本で落雷があり、電車が止まりましたよね。
別にこれを、黒木渚さんのせいだとか、そんな大それたことを言うつもりは、全くありません。偶然中の、偶然です。ですが、初めに戻りますが、日本の神は、自然万物に宿っていると、聞いたことがあります。つまり、落雷があったあの瞬間、黒木渚さんは、一瞬、日本の神になったのではないでしょうか。
黒木渚さんが、悪いことをした、と言っているのではありません。これは、本音ですし、そう解釈しないで貰いたいのです。それは、例えば自分が「地震」と言う小説を書いて、それが売れた或る日、地震が起こった、みたいなことです。この場合も、云わば、言葉上の問題として、自分が日本の神に一瞬なった、という訳です。
勿論、他の誰かが、自然について述べ、それが自然災害の内容だった時に、その誰かが、一瞬、日本の神になった、みたいなことです。
そういう意味合いにおぃて、黒木渚「落雷」が落雷して、日本の神になる話、と題して、云わば誇張気味に書いた、ということです。しかしこういう発想は、非常に芸術というものの立場から、くるものかもしれませんね。科学的に何の根拠もない、と言われてしまいそうです。そうです、根拠というものは、神にはないんです。
根拠がないから、神様がいる、という発想が懐疑されるのです。しかし実際
、日本の神は、自然万物に宿っている、とされるんです。恐らく、宇宙論を解明しないと、こういうことの論拠は掴めないとは思いますが。
しかしそれにしても、毎日、毎日、黒木渚さんの「落雷」を繰り返し聴いている自分にとっては、実際に日本で最近落雷があった、と知ると、黒木渚「落雷」が落雷して、日本の神になる話、というものを、書いてみようという気になるのは、自然な流れでした。
根拠はありませんが、日本のみなさん、黒木渚さんに、一目置きましょう。必ず、日本を、破壊から再生へと、導いてくれるはずです。
そのために、黒木渚さんの、「落雷」を聴くのを、おすすめします。今後の日本人の生き方の、先駆者としての体感が得られるかもしれません。
断定は、致しませんが、先駆者としての体感が得られるかもしれません。
『黒木渚ステッカーで、落雷しかけた話』
黒木渚の独立後、初のグッズが発売されている。売り切れの商品もあり、現在入荷待ち、と言う状況である。自分はTシャツと、ステッカーを購入できた。この、ステッカーは、値段も手ごろで、何枚あってもいいという状況なので、これからも買い続けるだろう、ステッカーを、という訳なのである。
トートバックと、ロングTシャツは、買えなかったので、今後、金銭に余裕がある時に購入する予定だが、問題は、落雷のことなのである。
黒木渚の「落雷」の視聴回数が、12万に達した。これからも、どんどん、伸び続ける予感しかない。自然との融和が、「落雷」には見える。
ところが、驚いたことがあった。実は、グッズのステッカーの一部が、防水加工ではなかったため、後日、防水加工のステッカーが送られて来たのだが。これは本当の話である、袋を開けて、ステッカーを手に取ったところで、何と雷が鳴ったのである。タイトルの、落雷しかけた、は誇張気味だが、実際にあのタイミングで、と思うと、最早、世界は、黒木渚の落雷に、支配されているのではないか、という疑問すら沸き立つ。
つまり、神になった黒木渚が、我々を支配し、崇高な場所へと導いてくれる、くらいの、余裕があるのだろう、今、黒木渚ステッカーで、落雷しかけた話が、書けているのも、あの時、落雷しなかったためなのであるから。
マジで、「落雷」は聴いたほうがいい、グッズも勝ったほうがいい。そして、ライブに行ったほうがいい、時代の先端を行く、黒木渚、というかもう、黒木渚様状態である。
云わば、落雷を落とされたくなければ、言うことを聞けよ、という、黒木渚教が、つまり、この宗教が、世界の先端を行く、宗教になっているのであるから。だから、落雷を落とされたくなければ、もう一度言う、
「落雷」を聴いたほうがいい。
と言って置く。
『小旅行記ー東京(頭狂)日記ー』
去年、一泊二日で、初めて一人で、東京に行った。
黒木渚さんの、ライブを観るというのが、最大の目的ではあったが、何かと様々に、得るものがあった。云わば、小旅行である。
ノートに順番に行く当てを書き残す様に、脳内に順路を残して、歩いて行く。ライブ会場の周囲に着いて、石の芸術品みたいなところに、腰かけて、ライブまでの時間を費やした。
現在でもまだ続いている、声がはっきりと出ない、と言う状況下においても、何、難しいことはない、メモ帳に言葉を書き込んで、警備員さんなどに尋ねると、東京の難しい回路の様な街が、縮図に見えてくる。
実はその日、故安倍晋三元首相が、撃たれた日だった。
何か、自分が関西から離れたことで、故安倍晋三元首相を守れなかったのではないか、という大それた空想の責務が、肩に圧し掛かった。無論、そんなことは、偶然である。東京へ向かう新幹線の中で、その一報を聞き、時代と言うものの流れを感じたものだ。
楽しいライブだった。このライブのことは、もう小説家になろう、のほうで、様々に刻銘に書いているので、楽しいライブだった、とだけ記しておく。
ライブ後、タクシーを探して、予約していた、ビジネスホテルの様な宿まで移動し、受付を済ませて、部屋へと入った。実家に居ることが多い自分は、こういう感じで、一人で宿の部屋に入るということは、初めてだった。学生時代、友人たちとの旅行で、旅行したことは何度もあるが、今回は一人だ。まさに、小旅行なのである。東京一人旅なのである。クーラーをつけて、リュックに入れていた飲み物を出して、一服する。明日の起きる時間を確認して、少しゆったりとしながら、ライブの余韻に浸っていた。
もうすぐ寝ようと思い、部屋の電気を消す。あとは、明日起きて帰るだけだ、責務は果たした。東京(頭狂)日記、と言う感じで、眠りに入る。頭を使い過ぎて、狂う程に疲れたが、東京一人旅は、見事に成功した。
翌朝起きて、タクシーで東京駅まで向かい、新幹線に乗って、帰路につく。
小旅行記ー東京(頭狂)日記ー、と題した、東京一人旅の、一幕であった。
『黒木渚、歌詞に見る高揚の原則』
久しぶりに、黒木渚さんの、ベストアルバムの歌詞カードを、取り出して見ている。23曲の、代表曲が集まった、大盤である。
何から書き始めようか、と言う時点に至って、やはり、歌詞について書くことにしたので、題目を、黒木渚、歌詞に見る高揚の原則、としてみた。
歌詞カードだけを見ていると、途方もなく練られた、詩集の様に見えてくる。そこには一つの、高揚の原則があるように思う。
何か、この歌詞カードの様な詩集に、中原中也賞を寄与されるべきなんじゃないか、と思わんばかりの、言葉の規律があり、メロディなしても、読み手の気分を高揚させる、原則が見いだせそうだ。
自分は昔、小説家になろうで、『黒木渚論・・・10周年の間の歌詞の変遷』(補足)と言うものを書いて、記している。そこから、重要箇所を抜粋。
〇DISC 1、から拾った歌詞の内在する曲目。
「それに飽きたら」/あたしの心臓あげる
「ほんの出来心」/カルデラ
「墓石に」/骨
「はさみを」/はさみ
「罪を知る」/革命
「ひとごみの中」/虎視眈々と淡々と
「崩れあってゆく」/君が私をダメにする
「いいかげんな誰かの」/大予言
「孤独の種」/アーモンド
「腐敗する心」/原点怪奇
「ふざけんな」/ふざけんな世界、ふざけろよ
「切なさに溺れて」/灯台
〇DISC 2、から拾った歌詞の内在する曲目。
「今を生きる」/解放区への旅
「息をしてる」/火の鳥
「憂鬱も手放して」/美しい滅びかた
「どこへだってゆける」/檸檬の棘
「毒、吐く」/ダ・カーポ
「世界を吸い上げて」/竹
「泣いてないで」/死に損ないのパレード
「走ってゆけ」/心がイエスと言ったなら
※当時の新曲の歌詞は、省いています。
「予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる」/黒木渚
この様に、曲の流れから、言葉を拾って行くと、歌詞の一部抜粋箇所に、タイトルがメタファとして作用していると見えてくる。歌詞とタイトルが呼応し、それぞれが補完し合って、黒木渚音楽史の歌詞部門の、重要な言葉の配置の役割を見るかの様だ。そして、その呼応が、気分の高揚を生じさせ、一つの規律的原則を、アルバムの歌詞内で内包しているのである。
例えば、DISC 1の初めの曲、「あたしの心臓あげる」
「それに飽きたら」
「あたしの心臓あげる」/黒木渚
場所の転化を思わせる台詞は、次の行の、あたしの心臓あげる、に、距離を持たせて、位置づけられている。こういう技法は、歌詞内のストーリーを想起させるし、また、同時に、渇望の本質を前方から後方へと移動させ、後方にリアリティを発露させるのである。飽きることのないもの=心臓の鼓動、と言う流れを、停止させ決壊させ、言葉として現出させる、精緻な方法論が見られるだろう。
また、DISC 2の初めの曲、「解放区への旅」
「今を生きる」
「解放区への旅」/黒木渚
今度は、歌詞の最終部で、まさに解放されていく自己を、俯瞰し、今を生きるという言葉で、自己を解放している、詞的原理である。歌詞の始まりから続く、或る種の鬱屈が、最後で解き放たれた時にこそ、タイトルの「解放区への旅」の終わり=今を生きる、と言うことの始まりが、表記されている。この様に、ベストアルバムの歌詞カードを見て居れば、これを単なる歌詞カードで終わらせて良いものか、と思わされるのも当然である。
歌詞に見る高揚の原則は、まさに、非原則と非原則を、=、にした原則と、捉えられはしまいか。
非原則=非原則という原則
『黒木渚、歌詞に見る高揚の原則』
心臓や生きる、と言う言葉で、この様な原則を内包し、また、読み手にその原則を提示した、意味、と言うものは大きい。そして、黒木渚さんは、その後、独立の道を歩むことになる。
現在、「落雷」と言う曲で、新しい新境地を提示しているが、これが抜群に良く、MVの再生回数も伸びている。一つの区切りを終えた黒木渚さんが、次にどんなステージ(ライブやアルバム)を、見せてくれるだろうか、楽しみである。最後に、意味深な、信号機の爆発を載せて置く。落雷によるものだが、それが信号機だったという事実は、何かへのメッセージを意味するであろう。
6月には、ビルボードでの、ライブが決定している。是非、参加して貰いたい。
『黒木渚さん、ビルボード迫る』
黒木渚さん、ビルボード迫る、と題したのだが、詰まるところ、6月に2本、ビルボードでライブがある。昼夜を入れると、4公演になる。
6/11(日)ビルボードライブ横浜 昼夜 2公演
6/18(日)ビルボードライブ大阪 昼夜 2公演
何とも、楽しみな訳である。横浜、大阪、公演ともに、1ヵ月を切っていて、一体どんなライブになるのか。「落雷」は歌われるのか、など。
話は変わるが、「落雷」の、一疑問とされている「それ」と言う言葉、調べたところ、6箇所使われている。いわゆる、「それ」問題も、突き詰めることなく、音の一部として、自然に楽しんで聴くのが、適切だろう。
ビルボードにも、「それ」があると良いなと思いながら、日々を過ごしているが、「落雷」のジャズバージョンって、なんか難しそうだな、と思う。勿論、ライブまでに標準を合わせて来るだろうが。
現在発売されている、Tシャツなどの、公式グッズも販売されるようで、当日が実に楽しみだ。それにしても、何故こんなに、グッズって、買うのが楽しいんだろうな、と今更、不思議感が増している、昨今です。
『黒木渚×ジャズ×ビルボード、について』
6/18に、ビルボード大阪で行われた、黒木渚×ジャズ、のライブに行ってきた。他のアーティストで、2回来ていたので、今回のビルボード大阪でのライブは、3回目の参加となった。
まずは席の確認、それから、ドリンクを貰う場所、食事を頼む場所、それぞれ、把握していたので、それぞれ注文を済ませて、グッズを購入した。
ライブ前にお会いしたり、拝見したりした方々が、カジュアル席の自分から、様々に見える。しかしやはり、この会場の全員が、同じ目的を持って集っているということが、何より嬉しいことだった。
黒木渚さんのライブ、昔中止になった、そのリベンジのためと言うべきか、演奏が始まったら、最高の声で、バックにジャズを添えて、黒木渚さんは歌い始める。
一部のみの参加だったので、二部で何が歌われたかは分からないのだが、一部だけで言えば、「ダ・カーポ」は、最高に良かった。完成度の高さ、その次元がまるで普段どこでもなっている、いわゆる流行りに乗じた曲とは、決別したかのような、強烈な個性が、其処にはあった。
ここに出口はない
「ダ・カーポ」/黒木渚
紛れもなく、我々はその時、ビルボード大阪という、ひとっの箱に、出口のない箱に閉じ込められ、芸術祭を見ていた、と記憶している。
ジャズ特有の、なのかは、ジャズ通ではないので、分からないが、あの不協和音と、黒木渚さんの真っ直ぐな声が、あれほど混ざり合って、我々の必要な音楽になるということは、奇跡に近い様なものだと思った。是非、毎年恒例で、開催して貰いたいと、思いながら、一部を聴き終えた後、帰路についた。
あの日聴いた、いわゆる、音像を超えるものが、この先、聴けるのだろうか、と思うとともに、完璧に感動した身体を動かして、ビルボード大阪を後にした一日だった。
『黒木渚さんの、イベント配布、カレンダー』
去年、黒木渚さんと、ファンとの交流会の様なイベントがあった。そこで、参加者に云わば、特典として配布されたのが、自分がツイッターやインスタで上げている、カレンダーなのである。
このカレンダー、月曜始まりなのだが、(自分は普段日曜始まりを使っている)、見ているだけで、とても気分が上がるカレンダーなのである。
3月の部分には、黒木渚さんの、サインが直筆で入っている。オシャレであるしまた、使いやすいというのも利点だ。
このような、特典と言う意味において、自分は他のアーティストでもそうだが、直筆サインと初版、にたいそう拘っている。
例えば、芥川賞作家の西村賢太が死去したあと、必死に初版を探し、原価が上がったところで売却するという手法を取った。無論、売るためだけではなく、きちんと読むか、2冊買っているか、の状態である。
黒木渚さんの、グッズを、だから売ろう、と言う訳ではない。勿論、丁寧に保管し、死ぬまでおいて置くだろうが、それでも、この直筆サインというものに、非常に拘っている自分が居て、そういった意味においても、この、イベントカレンダーは、非常に気に入っているのだ。
2023年を、この、黒木渚さんの、イベントカレンダーと共に、乗り切りたいものだ、と、真摯に思って居るのである。
『黒木渚さんの、器器回回ツアーが、楽しみな理由』
黒木渚さんの直近の新曲、「落雷」のyoutubeでの視聴回数が、随分伸びている。何か、大きな何かが動いている。こんな状況で、ビルボードライブを見事に成功させ、次のツアーが組まれた。
「器器回回ツアー」と呼ばれる、全国4箇所でのツアーである。チケット代も低額に抑えられ、参加しやすい状況になっているが、どうやら内容は、そうとうすごいものらしい。
すごいものになるはずである。現在まで、デジタルリリースされた曲は、4曲(「落雷」を含む)。恐らく、それらが聴けるだろうし、グッズなども楽しみだ。
楽しみな理由は、他にもあるだろうが、まだ言えない状況だろう。しかし、完成形が見えたなら、我々はただ、ソウルドアウト、のために、ライブハウスに足を運ぶのみだ。
自分は、大阪の梅田クラブクアトロに参加予定だが、何かとてつもないものが待っている気がしてならない。そのため、楽しむために、お金を貯めているのである。
そう、黒木渚さんの、器器回回ツアーが、楽しみな理由は、今から他のことに散財せずに、貯金が出来るという理由なのである。分かって貰えただろうか。最高の芸術にお金を使うのは人間の最上の幸福である、からだ。
「最高の芸術にお金を使うのは人間の最上の幸福である。」
上記したのは、自分の最近の信念である。
9/14、が、楽しみで、待ち遠しくてならない。そんな状況である。
『黒木渚さんの、「さかさまの雨」と「落雷」』
ふと、思ったのだが、黒木渚さんの、「さかさまの雨」と「落雷」、ともに、天候についての曲だな、ということだ。これは、黒木渚さんが、自然と呼応する形で、云わば、自然芸術に、傾倒しているふしが見える。
勿論、単なる偶然かもしれない。しかし、雨、雷、こういうものに、着目しているのは、何か意味があるのだろうか、と思うのだ。雨、であれば、悲しみの涙。雷、であれば怒りの雷。
どうも、感情との、曲との往復の様な動きが見え、またそれが、非常に曲として優位的に鳴っているのが、或る意味、不思議な感覚を、聴く度に覚えるのである。
「落雷」に至っては、驚異的なペースで、視聴され、もはや、黒木渚さんの代表曲の一つにも成り得そうな勢いである。まさしく、音楽業界に、落雷が響いている。
黒木渚さんの、「さかさまの雨」と「落雷」、について述べてみたが、どうだろう。関連させることは、考え過ぎだろうか。器器回回ツアーが、益々楽しみである。あと、2ヵ月後に、迫っている。
『黒木渚さんの、武道館への階段』
何れ、黒木渚さんは、武道館に立つだろう、という「大予言」は、黒木渚さんな「大本命」になるファンの数を増やすことに、一つの帰着が見られると言えるだろう。
音楽家が、武道館でライブするのは、活動中であったり、解散ライブであったり、時期はそれぞれだ。黒木渚さんに、武道館に立って貰いたいけれど、それはどの時期であっても、自分は良いと思うのである。
ヒットシングルを持つことが、武道館への階段の足掛かりになるだろう。未来を、「はさみ」で切り割いて行くような、代表曲は、と言われば、「あたしの心臓あげる」だろうか。
youtubeでの、視聴回数を見れば、
「あたしの心臓あげる」1,419,390 回視聴
「はさみ」 644,251 回視聴
「落雷」 139,031 回視聴
(2023/07/17 現在)
3曲上げてみた。「落雷」においては、独立後の自主成果だから、そうとぅ回っていると言えると思う。「落雷」は、150,000 回視聴は行くと思っている。独立後の代表曲が、今のところの「落雷」なら、武道館も近づいてくるだろう。「落雷」を落とすことが、音楽業界への切り込みならば、能力の本質は、実存していると言えそうである。
その、黒木渚さんの、武道館への階段のことを、考えれば考える程に、今回の器器回回ツアーによって、その階段の道筋は、成果として現出するだろう。
やはり、その時のにわかファン、よりも、「大本命」のファンの数を増やすほうが、着実な階段になるだろうと思うと、黒木渚さんが、どんな人物か、詰まるところ、ユーモアを持った、アーティストであることは、黒棘を見ても分かるように、要は、人徳があるのである。
この様に、面白さ全開の黒木渚さんを、器器回回ツアーで見に行こう、というのが、自分にとっての、黒木渚さんへの「窓」である。そこには「像に踏まれても」消え去らない「砂金」がある。まだ誰も知らない、「ロマン」がある。
器器回回ライブでは、実際には起こり得ない、グラスの中でのメタファのしての、「さかさまの雨」の様な、異常現象=前衛芸術、が見られることだけは、約束しておく。
『黒木渚さんの、曲タイトルで、書いた小説』
黒木渚さんの、曲タイトルで、小説を書くことに、挑戦します。ベストアルバムから、曲順に。
㈠
「あたしの心臓あげる」と言う言葉は、果たしてメタファなのか、と言う疑問もそぞろに、地上に出来た、大きな「カルデラ」を夢想してみる。そもそもが、考え得る限り、そこに「骨」を投げ入れれば成仏するだろう。
それにしても、世界の真ん中を、「はさみ」で切り割いて行く様な行為が、一種の、「革命」だとしたら、真面目に思い付いたその発想の起点に恐れ慄くが、実際、人は、そんな状況でも、妙に、「虎視眈々と淡々と」しているものだ。
「君が私をダメにする」と言われたらしい友人は、その「大予言」の通り、私と言う一人称が、毎日毎日、「アーモンド」ばかり食べる生活に陥ったことを、後に知ったそうである。
「原点怪奇」を聴きながら、そんな日々の中で、耐え難いことは仕事でもなんでもあるもんだよ、と友人は言い、毎日、「ふざけんな世界、ふざけろよ」が口癖になっていたが、或る夜、「灯台」の神秘的な夢を見て、価値感が変容したと言っていた。
㈡
この侭だと自滅しそうだ、「解放区への旅」へ出かけようと思ったのも束の間、お金が底をついていることに気付く。仕方なく、手塚治虫の漫画、「火の鳥」を古本屋で売り、「美しい滅びかた」。
そう言えば、黒木渚さんの自伝小説に、「檸檬の棘」と言うのがあったことを思い出し、人生を変えるべく何度も「ダ・カーポ」しながら、小説世界に入り込み、教訓を得る。
そうだ、度に出るなら、防御道具くらい必要だと思い、遥か遠い、「竹」が生えている山へ登り、良質のものを持ち帰り、ナイフで綺麗に削って、防御道具にする。
そうするともう、無敵の感覚を得て、旅に出る前は、「死に損ないのパレード」に加わって、無敵の行進で、夢を見続けた。「心がイエスと言ったなら」、明日にでも旅にでよう、そう固く、決心をして、小説のページを閉じる午後三時。
『黒木渚さん、「落雷」、140,000 回視聴』
「黒木渚さん、「落雷」、140,000 回視聴、おめでとうございます!」
よくぞ、ここまで登り詰められたと、心底すごいと思っている。デジタルシングルとしては、十二分な域に達した作品だと思う。黒棘で、音楽とMVの親和性の高さについて、黒木渚さんは述べていたが、まさにその結実が、数字になって現れていることが、すごいと思う。この「落雷」と言う曲、何がすごいかと問われれば、全部すごいと、答えるしかないのですが、歌詞、メロディ、MV、演奏、全てが一致したという他ないと思います。
数字だけに拘っているのも虚しいですが、寧ろ、作品に数字が付いて来たという、逆転の発想で良いと思って居る。武道館へ行くための、足掛かりになると思いますし、実績として、youtubeに残ることが、独立を上昇させる要因になることを願います。
9月から始まる、器器回回ツアーが、楽しみでなりません、恐らくは、予想を遥かに超えてくると思っていますが、ライブでその音像を体感した時に、初めて本質が現れ、問われるのだと思います。
グッズも楽しみです。今年は、楽しい一年になっています。最後まで、今年を楽しみきりたいと思います。
「黒木渚さん、「落雷」、140,000 回視聴、おめでとうございます!」
『黒木渚格言集の編集について』
黒木渚格言集の編集について、です。
ツイッターにこの様に載せています。
黒木渚さんの、小説や歌詞から、言葉を格言としてピックアップし、解釈を載せる、【黒木渚格言集】は、週2日、木曜日と土曜日に更新。 ※黒木渚の棘(youtubeで、毎週火曜日21時から配信のラジオ)で、ご本人にも、存在を、お伝えしてあります。
ツイッター/かいわれのせか
今年一年、続けると思います。というか、今年一年は、達成します。ですから、来年になると同時に、更新は停止する予定です。今までの記録を、どこかでまとめて載せるか、とか様々に考えていますが、読んで下さっている方々がいらっしゃるので、大変嬉しく思っています。
黒木渚さんの格言を、解釈するなどという偉そうなことをしてしまっているかもしれない、と思いつつ、少しでも、黒木渚さんに貢献出来れば、と思い、記載しています。
本来、芸術の言葉とは、それ自体が独立し、美を放つのであって、それ以上にこちらが、感想を述べるべきではない、という考え方もある様です。しかし、どの様にも解釈できるその独立した芸術を、様々に楽しんでこそ、芸術が大衆化され、面白いものになるのだ、という考えがあります。
黒木渚格言集の編集について、ですが、とにかく、この2023年の一年間は続けますので、もし宜しければ、御一読下さい。毎週、木曜日と土曜日、更新です。
『黒木渚さん、最新アルバム「器器回回」配信開始』
2023/09/06から、黒木渚さんの、最新アルバム「器器回回」が、配信開始されている。
1曲1曲が、高度に独立した、素晴らしいシングルだが、これらをまとめて、1つのアルバムに仕立て上げた時に、これ程の驚愕的芸術になるとは、思いもしなかった。
「落雷」に始まり、「独立上昇曲 第一番」に終わるが、これがまた、繰り返し聴けるのである。つまり、「独立上昇曲 第一番」が、「落雷」につながっているのである、音楽性として。
「独立上昇曲 第一番」には、空が写っているが、そこに「落雷」が落ちるという流れにおいて、中核の「器器回回」は、上質に居座って、アルバムの位置のバランスを取っているのである。
黒木渚さんの曲には、少し前の音楽シーンで使われた言葉、所謂、捨て曲、というものがない。一つもない、ということは、音楽を聴いて来た自分にとっては、驚きの事実なのである。
今回の、「器器回回」は、上記したように、素晴らしいアルバムである。是非、ライブで、その神髄を体感したいと思って居る。ライブはもうすぐであるし、グッズも楽しみだ。音楽業界の中で、今確かに、大きな現象が、起ころうとしていることを、知って置いて貰いたい。
アルバム「器器回回」/黒木渚
https://open.spotify.com/intl-ja/album/1yrsuxaSlA0QvvF7hfNRzN?si=aC7DVmccS_KJaHWK7o9d-A&nd=1
『黒木渚「器器回回」ライブ、大阪』
自分にとっての器器回回ライブは、参加は大阪のみです。
そのため、もう終わってしまった、器器回回になるだろうと、予想はしてました。ところが、グッズを沢山買って置いたおかげで、充分に、器器回回に、まだ、浸っています。
とくに、アルバムと小説。アルバムは、スマホで聴くより、全然良いし、小説は、云わば、今の黒木渚さんのいる、立ち位置とでも言おうか、その背景が知れる内容で、何か、漠然と伝わってくるものがありました。
福岡、横浜、参加される方々は、是非、小説、お勧めです。そして、大阪では、黒木渚さんのファンの方々に、お声を掛けて頂いて、楽しくライブに臨めました。ありがとうございました。
少しずつ、年内の、今ツアー以外のライブも、発表されてますね。自分は、関西以外は、余り行けない経済状態なので、貯金で、既発のグッズを買うことで、応援しようと思っています。
黒木渚「器器回回」ライブ、大阪、ということで、黒木渚さんの、最高のライブが観れて、本当に、心底、嬉しかったです。エネルギーを頂きました。ポスターを部屋の扉に貼りました。とても、気に入っています。
【第三章】
【黒木渚格言集】(2023年)
黒木渚さんの、小説や歌詞から、言葉を格言としてピックアップし、解釈を載せる、【黒木渚格言集】は、週2日、木曜日と土曜日に更新。
※黒木渚の棘(youtubeで、毎週火曜日21時から配信のラジオ)で、ご本人にも、存在を、お伝えしてあります。
〇ツイッターに載せていたものを、ここに記して置きます。
【黒木渚格言集】(1)
「人間の本性なんて、幻想のようなものなのですから。」『本性(文庫本、あとがき)』/黒木渚
文庫本の『本性』のみに、記された、あとがき、から。人間の本質を突いていて、興味深い。恐らくは、事実上、その通りだと、思われる。
【黒木渚格言集】(2)
残された1%の そのアイデアが その直感が「エジソン」/黒木渚
エジソンの発明はすごいと思う、その観点を視座に据えて、歌われた歌詞だろう。まさしく、科学者の様に、曲は動態している。
【黒木渚格言集】(3)
言葉を使う動物はみんな詐欺師だよ「独立上昇曲 第一番」/黒木渚
本音を言っても、嘘を言っても、受け取る側は、本質を常に逸することがある。その点で、詐欺師、というのは、実に的確なメタファなのである。
【黒木渚格言集】(4)
追い風よ もっと強く吹け!「革命」/黒木渚
応援歌としての、追い風の表現。何かで後押しするなら、人生を走る時、追い風が、直悦的に後押しになるのは、表現を超えた事実なのだろう。
【黒木渚格言集】(5)
「うん、人生で一度も病んだことない」(中略)やっぱりあれは弟の優しい嘘だったのだと思う。『檸檬の棘(文庫本、あとがき)』/黒木渚
弟さんとの会話の中で、弟さんの言葉に、優しさを見た台詞。弟さんの言葉を優しい嘘だとした、黒木渚さんの優しさが見て取れると思う。
【黒木渚格言集】(6)
こうばしい明日が香る「アーモンド」/黒木渚
孤独の種としての、アーモンド。実際に、明日、前向きに生きるという、こうばしい明日。それに、アーモンド自体のこうばしい香りとしての意味が付加されている。
【黒木渚格言集】(7)
何かを待ってただ歌うだけ「あしかせ」/黒木渚
歌い手としての、黒木渚さんが、云わば、その歌いがあしかせに、なるとでも言う様な、逆説。人間に常に起こり得るあしかせの、普遍性。
【黒木渚格言集】(8)
悲しく積もるユウウツを どうしてブルーと呼ぶのかな「ブルー」/黒木渚
晴れた日に、働かされるから、憂鬱になる。晴れた日の青が、ブルーになる。つまり、憂鬱をブルーというということ。この曲で、その意味を知った。
【黒木渚格言集】(9)
命短し我々が 最後は勝つのさ 大予言「大予言」/黒木渚
予言というものに、託された、最後は勝つのさ、という台詞。また、それが、命が短い我々が故に、というのが、大きな起点になっている。
【黒木渚格言集】(10)
親族からの怒号が響いていた。背中に投げ付けられる口汚い言葉の数々。だけど平気だ。私はとても強いから。『壁の鹿』/黒木渚
壁の鹿の、最後の風景。家族の問題、死の問題。けれど、それと決別した時に、自己の本当の人生が始まるかのような、風景描写。強さの明証。
【黒木渚格言集】(11)
駆け上がって転げ落ちて人生はコメディ「ふざけんな世界、ふざけろよ」/黒木渚
面白おかしく歌われた曲だが、歌詞の随所に、ポストモダンが見て取れる。ふざけんな世界、ふざけろよ、は、意味を成していない様でいて、意味を成している。
【黒木渚格言集】(12)
美しく滅びてく私をみていてよ「美しい滅びかた」/黒木渚
美しい滅びかたは、人生の一つのテーマである。どうせ死ぬなら、美しく滅びたい、という美学が、歌詞に攪拌されている。
【黒木渚格言集】(13)
シャンパングラスの中 さかさまの雨が降る「さかさまの雨」/黒木渚
さかさまの雨、と題された曲だが、さかさまの雨は、シャンパングラスの中で起こるメタファである。秀逸な、発想の起点を知ろうと思わされる。
【黒木渚格言集】(14)
ひとりで夜更かし 世界の寝息を聞いていたい「Sick」/黒木渚
呼吸が題材になっているようで、世界の寝息を聞いていたいは、頂上から、人々の呼吸を聞いているという描写言語。病を逆手にとって、歌詞に変容させているかのようだ。
【黒木渚格言集】(15)
鹿の剥製が最初に話した言葉は、「まったく、理解不能です」というものだった。『壁の鹿』/黒木渚
着目点が、異常であるとでも言いたげな、鹿の剥製の言葉。序章のこの言葉から、小説は奇怪に始まっている。
【黒木渚格言集】(16)
孤独は宇宙だ 真空で息もまともに吸えない「解放区への旅」/黒木渚
解放区へと、自己を解放しに行く、旅が、ストレートに描写されている。孤独は、宇宙だ、まさに、最高の格言に成り得ている。
【黒木渚格言集】(17)
水平線はねじ曲がり 真っすぐに歌うのは難しい「大本命」/黒木渚
自己が人生を歩めば歩む程に、水平線は、ねじ曲がるだろう。そんな破壊された自己を、大本命にしてほしいと、歌えない真っすぐが、歌われている。
【黒木渚格言集】(18)
絶望にも飽きたころだろう?「死に損ないのパレード」/黒木渚
死に損ないであることは、即ち、絶望を知り、その絶望にも飽きたことに、依拠している。これ以上ない、絶望を知れば、死ぬ気すら起こらないという、人々のパレード。
【黒木渚格言集】(19)
鈍く光った表面に 本当の私が写っている「はさみ」/黒木渚
はさみを、メタファとして、書かれているが、鈍く光った表面は、実際のはさみだ。そして、本当の私が、交差するのは、はさみか、人か。
【黒木渚格言集】(20)
この世界の何処かでのうのうと生きている父親を軽蔑することによってのみ、今日まで生きながらえてきたのに。『檸檬の棘』/黒木渚
親という存在への、拒否衝動。どんな親でも、それは親である限り、子にとっては何かの標的者に成り得る。この場合の、軽蔑や憎悪など。
【黒木渚格言集】(21)
「最低だ」と思う日も 会いに来てよ「カルデラ」/黒木渚
この、「最低だ」と思う日も 会いに来てよ、という歌詞は、全ての人類を救済する。受け入れられることへの、感謝が、この曲を聴いていて、萌芽するのだ。
【黒木渚格言集】(22)
あなたもわたしも脆いから いっそこの手で崩しましょう「砂の城」/黒木渚
砂場の城を崩すような、原風景が想起されるが、脆さを崩すことは、何かの再建になるだろう。砂の城は、再生を予期させてくれる、繰り返される、こわい、という言葉から。
【黒木渚格言集】(23)
夜に浮かんで目もくらむような 一筋を眺めていたい「灯台」/黒木渚
灯台を、人に例えた、メタファとしての歌詞。光の一筋を、浴びたいではなく、眺めていたい、という位置の転化が、美しい風景を、想起させる。
【黒木渚格言集】(24)
入っていたのはマトリョーシカ「マトリョーシカ」/黒木渚
結果論から言うと、入っていたのはマトリョーシカ、だが、そこまでの落ちの歌詞に、社会風刺が述べられている。願いや救いが、マトリョーシカに託される。
【黒木渚格言集】(25)
私は光に向かって宣言する。これからは全てを音楽に捧げて生きていくと。『予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる』/黒木渚
過去の、黒木渚さんの、決意表明のようにも取れる。生きる意味、大きな代償を払ってでも。
【黒木渚格言集】(26)
恨み 裏切り 裏返し 奪われていく「原点怪奇」/黒木渚
人間の本質を言った、怪奇な現象の歌詞。繰り返される、人生上の輪廻のごとく、歌詞はメロディと一致し、歌われている。
【黒木渚格言集】(27)
最高過ぎて苦しいね「テーマ」/黒木渚
脳内の一つの頂点で、テーマは歌われているかのようだ。ポストモダン的解釈をすれば、これ以上ない、最上の幸福を、その頂点が苦しいと、いうことだろうか。
【黒木渚格言集】(28)
打ちのめされて墜落して どん底蹴ってまた飛び立つよ「火の鳥」/黒木渚
喉の不調から、不死鳥の様に、飛び立つことを明示している。まさに、運命に復讐するために、火の鳥は飛び立ち、聴き手にその衝動を投げかけている。
【黒木渚格言集】(29)
君の中には小さなピカソが住んでいるんだろ?「ピカソ」/黒木渚
ピカソ主体ではなく、聴き手の中にピカソの存在を意識させる内容。一見、簡易な内容の歌詞だが、劇薬のような、という言葉で、ゲルニカが脳裏を過る。
【黒木渚格言集】(30)
何かに触れるたびにとめどなく溢れてくるアイデアや繊細な気付きを自分の中に封じ込めるようになったのはいつからだろう。『本性(東京回遊)』/黒木渚
芸術家の方法論が看守出来る台詞。東京回遊の、様々な格言の内の一つ。
【黒木渚格言集】(31)
何がロックだ何がパンクだ「アンチスーパースター」/黒木渚
スーパースターではなく、アンチスーパースターの位置での思考。ポストモダン的であるし、逆説的に曲調は、ロックなのであるから、強烈な衝動的音楽である。
【黒木渚格言集】(32)
何を欲しくて集うのか ホントは私こそ知りたくて「クマリ」/黒木渚
クマリという異文化を、日本に輸入して歌われた、興味深い歌詞の言葉の数々。自己を必要とする理由を自己が知りたいという、純粋無垢が、聴こえてくる。
【黒木渚格言集】(33)
ごめんなさいごめんなさい 躍らせてたんだよ「懺悔録」/黒木渚
懺悔する位置は、まるで神の座に居る黒木渚の様に、聴こえてくる歌詞。物事の拡大縮小という、俯瞰的位置から、言葉は懺悔している。
【黒木渚格言集】(34)
現実を忘れてループする ここに出口はない「ダ・カーポ」/黒木渚
迷宮という言葉が、相応しいだろうか。出口のない現実を、音楽的にダ・カーポとした、その設定にこそ、また、発想にこそ、意味が見出されるだろう。
【黒木渚格言集】(35)
私はどこへ帰ればいいのだろう。『檸檬の棘』/黒木渚
自己が自己の人生を思考するとき、誰もが対峙する、どこへ帰ればいいのだろう、という台詞。場所は、ノスタルジアか、母体か。
【黒木渚格言集】(36)
今日と明日が繋がって 続いてく合わせ鏡「合わせ鏡」/黒木渚
人生を共に生きる時、続いていくものが、合わせ鏡としてメタファになる。信じあう、許しあう、その先に、心中をすれば、永遠にまで、合わせ鏡だろうか。
【黒木渚格言集】(37)
世界を巻き上げて上へ「竹」/黒木渚
竹の動態に、自己の存在を重ね合わせたのだ。竹が上へ上へ、と動態するように、まさにその様に、自己の人生をも、上方へと進むことを、願えば、適切だろう。
【黒木渚格言集】(38)
心がイエスと言ったなら 一秒で世界は裏返る「心がイエスと言ったなら」/黒木渚
すべては、心の問題なのか、と考えされる格言。世界を裏返すのは、身体ではなく、心の問題だろう。時として、心がイエスというなら、ノーということもまた、現象する。
【黒木渚格言集】(39)
ロマンを抱えて生きている「ロマン」/黒木渚
日常で気に留めないことかもれないが、人間はロマンを抱えて生きていると、気付かされた歌詞。もともと、歌詞が先にあった、という曲。
【黒木渚格言集】(40)
父が私を捨てたように、私も父を捨てたのだ。『檸檬の棘』/黒木渚
親と子の問題。渚さんが、捨てるのが得意というのは、恐らく、ここで規定された。愛情を感じなかった子は、父親に、同様の意識を持つだろう、その普遍性。
【黒木渚格言集】(41)
血の通った人間に会わなけりゃ「フラフープ」/黒木渚
人間関係の機微を、ダイナミックに書いたのだ。「好き」「嫌い」「生きる」「死ぬ」、と叫ばれる中で、回るフラフープが其の侭、人生を振り回す比喩。
【黒木渚格言集】(42)
こざかしいんだよ くたばれ「ロックミュージシャンのためのエチュード第0楽章」/黒木渚
ロックについての、渚さんの表現は、しかし、声質が優しいためか、過激な歌詞も、心地よく聴こえてくる。第0楽章という言葉が、興味深い。
【黒木渚格言集】(43)
分裂してしまう あなたの目の前で「プラナリア」/黒木渚
プラナリアは、日本の川に生息しているようだが、まさに、その分裂を、自己の精神の決河した分裂に準えている。あなたの目の前で、と、現実に引き戻される。
【黒木渚格言集】(44)
閉じたカーテン 夕日に伸びる私の影「窓」/黒木渚
閉じたカーテンの先に、自己の思う人がいること。夕日に伸びる私の影、で時刻が表明される。片思いとしては、絶妙の描写。
【黒木渚格言集】(45)
幻聴だと思った。こんなにはっきりと聞こえるものを気のせいで済ますことはできない。『予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる』/黒木渚
音楽家としての、原点が見い出される。幻聴が芸術へと、変容する過程の表現。
【黒木渚格言集】(46)
瞳よ鼓膜よ渚へおいで 強くたくましいこの場所では 誰もが自由だ「砂金」/黒木渚
砂金に、自己の状態の救済を祈っているかのようだ。渚さんが、まるで風景の渚として、我々を呼んでいる場所は、救いの場所からである。
【黒木渚格言集】(47)
何を合図か 一斉に 土手を燃やして彼岸花「彼岸花」/黒木渚
毒を有する彼岸花に、歌詞を情景に透写した歌詞が、綴られている。土手を燃やして彼岸花は、強烈な直喩であるが故、聴き手にストレートに入ってくる曲。
【黒木渚格言集】(48)
自由になった心はどこへだってゆける「檸檬の棘」/黒木渚
小説『檸檬の棘』と、重複して聞けば、尚、自由になった心はどこへだってゆける、の意味が、異質に現出する。素晴らしい棘は、渚さん自身の、体感的言語となる。
【黒木渚格言集】(49)
望みひとつ自分ひとり 虎視眈々と坦々と「虎視眈々と淡々と」/黒木渚
言葉通り、自己が自己として、自己でのみ、戦っていく意思表明のような曲。歌詞は、音に乗って、ストレートに心に響く、或る種の、最高傑作。
【黒木渚格言集】(50)
「どうか、お元気で」(中略)「あなたが人間だったら、私、恋をしていたかもしれないよ」『壁の鹿』/黒木渚
対物性愛としての、表現の極致。おそらく、全ての芸術は、ここから始まる。例えば、目の前の人に話さず、思いをノートに殴り書きするかのような。
【黒木渚格言集】(51)
死んだ後でも楽しめるように 墓石に点数を彫ろう「骨」/黒木渚
墓石に点数を彫ろう、という実に斬新で新しい発想が記されているが、実際、どのように満足して人生を送れたか、ということは、一つの点数に成り得る。
【黒木渚格言集】(52)
直線12個集めたら ひとつ出来たよ角砂糖「あたしの心臓あげる」/黒木渚
理系的発想の、文学的な歌詞。角砂糖の甘さが、一つのこの格言から、曲全体に広がっていることを、理解しておくと、尚、楽しめる。
【黒木渚格言集】(53)
例えあなたが持ち得たとしても きっとすぐに捨てる すぐに捨てる「うすはりの少女」/黒木渚
自己に先天的に与えられたものが、想像以上だった場合、自己に人は集まるが、厄介になることもある。捨てる、とは、客観的な、自己の良点のことだ。
【黒木渚格言集】(54)
この想い叫べば 「非国民」 後ろ指刺され「赤紙」/黒木渚
戦時中のことを、また、その内容を、鑑みて歌われる歌詞が、メロディと相まって、非常に高度な内容を示唆している。
【黒木渚格言集】(55)
女の頬には銀河の形をした大きなほくろがある。『呼吸する町』/黒木渚
生まれ持ったものの、精緻な描写である。銀河という表現が、殊の外、イメージを掻き立てる、小説の導入としては完璧である。
【黒木渚格言集】(56)
貴方のため 砂金集め作った砂時計「砂金」/黒木渚
自分のためではなく、貴方のため、というのが、一つの起点となる。砂金を与えてもらう渇望よりも、砂金を与える愛情が勝っている。
【黒木渚格言集】(57)
あしかせをつけた私は逃げ出す事もできず この小さな空間で死んでいくのかな「あしかせ」/黒木渚
あしかせ、によって、人生が規定されてしまう、一種の寂しさが歌われている。非常に文学的な歌詞は、絶望の中にある。
【黒木渚格言集】(58)
指先に 指先に 指先に 曲がるスプーン「エスパー」/黒木渚
エスパー、という曲だから、という訳だろう。曲がるスプーンは、実際、「あたしの心臓あげる」のMVでも、披露されている。
【黒木渚格言集】(59)
スイーツ・サブカル・草食系 人間図鑑の大都会「マトリョーシカ」/黒木渚
人間図鑑として、まとめられたカテゴライズとしての言葉。大都会の危険的現状や範疇を提示した、歌詞に着目したい。
【黒木渚格言集】(60)
馬鹿にされればされるほど、腹の底から声が出た。『予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる』/黒木渚
黒木渚の、原点の明証ではないだろうか。正夢のような懐かしい感覚とした、この場において、小説の目的は果たされている。
【黒木渚格言集】(61)
一人で行くには遠すぎた でも裸の足は歩いた「革命」/黒木渚
裸の足は歩いた、という言葉は、非常に痛々しいまでに、孤独と到達を思わせる。まさに、革命者だけの、悲観的特権である。
【黒木渚格言集】(62)
約束なんてしてもしなくてもどっちだっていいよ「像に踏まれても」/黒木渚
そもそもが、約束は守るためにある、という既成概念を壊した歌詞。ユーモラスな歌詞の中に、気楽に生きれる優しさを孕んでいる。
【黒木渚格言集】(63)
味気ないし 華もないし 添えものの人生「カイワレ」/黒木渚
食用としてのカイワレに、まさに、カイワレ的に生きる人を重ね合わせた曲。歌詞は最後まで、面白ろ可笑しく、表現されている。
【黒木渚格言集】(64)
ああー ああー 崩れあってゆく「君が私をダメにする」/黒木渚
黒木渚の、一つの恋愛観だとされる本作。互いに支えあっていたものが、崩れあっていくことが、一つの恋愛に、終止符を打つかのような、独自の終末。
【黒木渚格言集】(65)
「分からんことはここに全部書いてあるけん」 私の脳裏に父の声が蘇る。『檸檬の棘』/黒木渚
小説の、親らしさを穿つなら、この場面は重要である。大きな転機としての、父の声の復元が、言葉に作用する。
【黒木渚格言集】(66)
扉をロックしてください「テンプレート」/黒木渚
テンプレートとしての、扉をロックしてください、という言葉。閉めるロックと、音楽のロックの、ダブルミーニングが、看取出来る。
【黒木渚格言集】(67)
数百の世界線 もつれあって文学「器器回回」/黒木渚
言葉と言葉を結ぶ、数百の世界線が、文章であり、もつれあう結果、文學となる。文學を、数百の世界線と、表現し得た、新しい世界的メタファ。
【黒木渚格言集】(68)
表現を自重する芸術家 能無しが出世する「ふざけんな世界、ふざけろよ」/黒木渚
社会風刺としての、意味を持つ歌詞である。能無しが出世することだけでなく、そういう社会体制を風刺し、ふざけんな、と繰り返し歌われる。
【黒木渚格言集】(69)
泣き笑い 回している フラフープ「フラフープ」/黒木渚
フラフープを回すことを、人生を生きることに準えて、また、人生に即して、例えられている、メタファとしての、痛快な歌詞の曲。
【黒木渚格言集】(70)
真面目に働いた一日は、なんと気持ちが良いのだろう。『本性(ぱんぱかぱーんとぴーひゃらら)』/黒木渚
ビールで肉を流し込んだ後の、台詞。現在の黒木渚さんの、原体験の様だ。興味深い。
【黒木渚格言集】(71)
君はやがて知るだろう あの狂おしい棘を「檸檬の棘」/黒木渚
心に芽生える、狂おしい棘とは、内部で生成されたロックの精神の様なものだ。狂おしい棘がある限り、人生はロックである。
【黒木渚格言集】(72)
凪のような嵐のような直感 神様の降りたような瞬間「落雷」/黒木渚
落雷を様々なるメタファとして、封印された歌詞が、劇的に鳴り響いているような曲。歌詞が韻を踏んでいる個所も多々ある。黒木渚さんの、新境地だと思われる。
【黒木渚格言集】(73)
鈍く光った表面に 本当の私が写っている「はさみ」/黒木渚
本当の私、という歌詞が興味深い。鏡に自己を見ることはあるが、はさみに自己を見るとは、何とも言えない、着眼点の発想の豊かさを底に見る。
【黒木渚格言集】(74)
イタリアという国には素敵な靴があるという「あしかせ」/黒木渚
ここ、から離れられないあしかせに、掴まっている自己が、イタリアに思いを馳せるのである。素敵な靴を履くことが、羨望になって、現状の悲痛さを、更に助長させる。
【黒木渚格言集】(75)
私には死人の恨みかたが分からない。『檸檬の棘』/黒木渚
すでに喪失してしまっているが故、声をぶつける対象のないことの、或る種の悲哀。
【黒木渚格言集】(76)
あなたは返事をくれるでしょうか 身勝手な私の申し出に「はさみ」/黒木渚
身勝手な私の申し出、とあるが、この身勝手であるかの状況に、私の本当の思いが託されている。受け取った側は、必然的に、返事を迫られるが、私の本音だと、受け取って良いだろう。
【黒木渚格言集】(77)
曖昧な何かじゃなければいい「さかさまの雨」/黒木渚
人と繋がって居たい、という思いが、述べられた歌詞。曖昧な何かじゃなければ、自分は安心するという、何か精神が破綻しそうな歌詞が、軍歌調に聴こえる。
【黒木渚格言集】(78)
よろしくさみしい本物たち「Sick」/黒木渚
本物は常に、さみしいものだ。本物であるなら、様々な現実を、受け入れなければならないからである、まさに、本物も、病気=Sick、と言えば、それが事実だろうか。
【黒木渚格言集】(79)
危ういバランスでたっている砂の城「砂の城」/黒木渚
砂の城は、危ういバランスであることで、怖い、という後の歌詞が、そのバランスを回顧される歌詞の順番になっている。まるで、砂の城に見立てられた、人間の本質の如く。
【黒木渚格言集】(80)
「女はブラックホールなのよ」『本性(超不自然主義)』/黒木渚
何もかもを吸い込むことの、メタファとしてのブラックホールの表現。この頃すでに、黒木渚さんは宇宙観に、着手している。
【黒木渚格言集】(81)
遠くから見るあなたって 凛とそびえる灯台「灯台」/黒木渚
あなた、という対象を、灯台に見立てているのだ。この壮大な歌詞の始まりは、このメタファから始まる点で、キーワードである。
【黒木渚格言集】(82)
宇宙の心理まで透視してしまえ「エスパー」/黒木渚
宇宙の心理まで、という箇所が、エスパーの能力の高さを物語っている。透視してしまえ、で、聴き手に、衝動が投げ掛けられる。
【黒木渚格言集】(83)
メンヘラ・トラウマ・依存症 人間嫌いの大都会「マトリョーシカ」/黒木渚
カテゴライズされた、病理としての、人間嫌いの大都会である。人間が大都会を嫌うのか、大都会が人間を嫌うのか。
【黒木渚格言集】(84)
冷たくなった彼の身体 もう一度ナイフを突き立てた「ウェット」/黒木渚
深刻な歌詞であるが、曲調は至って明るい。実際、「ふざけんな世界、ふざけろよ」でもそうだが、深刻な歌詞の時に、曲調が明るくなると、過去に述べられている。
【黒木渚格言集】(85)
「東大寺さん、この世はでっかいラクトルかもしれない」『呼吸する町』/黒木渚
ラクトルについての、大きな発言。この世が何かで出来ていることは明白だが、この小説のテーマを内包した台詞だと思う。
【黒木渚格言集】(86)
右目には冒険が宿り 左目は未来を見る「革命」/黒木渚
革命者としての、視覚状態の歌詞。黒木渚独特の表現だと思うが、こういう状態の時に、人は革命を遂げるのだろう。
【黒木渚格言集】(87)
クマリを見る自分の目 神殿を奪ったあの子は誰?「クマリ」/黒木渚
神の座を降りた自分が、神の座に就いた誰か、について、羨望の思いを馳せる歌詞。クマリ、という他文化に、その思いを一致させている。
【黒木渚格言集】(88)
開き直って愉快だな「死に損ないのパレード」/黒木渚
開き直ることで、死への憂鬱を吹き飛ばすのだ。そんなパレードに加わることで、自殺は乗り越えられる。先導者としての、黒木渚。
【黒木渚格言集】(89)
夜空を突き抜けて惑星のスケールで「解放区への旅」/黒木渚
黒木渚さんの、解放区への思いが、ストレートに歌われた歌詞。壮大な、宇宙への思いが、惑星のスケールで、と誇張され、大らかに強く歌われている。
【黒木渚格言集】(90)
ふと目を覚ますと、ベッドルームの床に父の頭が転がっていた。『檸檬の棘』/黒木渚
小説の書き出しとしては、文句なしの導入である。檸檬の棘の構造は、ここに収斂されていると思われる。
【黒木渚格言集】(91)
君の欠落が愛しい カンペキなものは虚しい「火の鳥」/黒木渚
カンペキなものは虚しい、とは、かなり卓越した思考なのである。人はカンペキを目指すが、そこに垣間見える欠落が、補完の対象となる。
【黒木渚格言集】(92)
ほんの一瞬の命さ 痛いほど「心がイエスと言ったなら」/黒木渚
ほんの一瞬の命、が故、自分に正直に生きることで、人生の価値が決定するという、まさに、心がイエスと言ったならの、神髄である。
【黒木渚格言集】(93)
身軽になって そこから始まる「独立上昇曲 第一番」/黒木渚
独立後の最初の曲。身軽になって そこから始まる、は、独立の精神の意識だが、何かを新しく始める人への、或る種の応援歌でもある。
【黒木渚格言集】(94)
キュビズムのように難しく ラクガキのようにあどけないもの「白夜」/黒木渚
キュビズムと、ラクガキの、対比。偉大なものと、素朴なもの。そのような対比が、おおらかに歌われる、白夜の歌詞の、本質が見て取れる。
【黒木渚格言集】(95)
眩しくて失明してしまいそうなほど、強く、白い。『予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる』/黒木渚
小説の最終部、スポットライトを浴びての、思いの叙述。強く、という言葉に着目すれば、黒木渚は、やはり強い。
【黒木渚格言集】(96)
100万円のレスポールどぶ川に投げ捨てた「レスポール」/黒木渚
捨てることが得意だ、と本人も言う通り、ここでは、100万円のレスポールが、どぶ川に投げ捨てられる。物としての愛情ではない、本当の愛情を、自覚させるため。
【黒木渚格言集】(97)
それはまるで 骨の様に 私を通る 強い直線「骨」/黒木渚
それはまるで、という風に、常にそれの本質は語られない。骨の様に、というヒントからしても、やはり骨は、異性のことを歌っていると思う。
【黒木渚格言集】(98)
丸いあぶくは恋の数 消えないあぶくはどこにある「金魚姫」/黒木渚
消えないあぶく、を探す動態において、それはまさに、金魚姫としての生き方に即している。あぶく、としてのメタファが、曲や歌詞を、成立させている。
【黒木渚格言集】(99)
あなたの武器は言葉なんでしょ「モンロー」/黒木渚
武器としての言葉。人間関係で、人生を生きる上で、どうしようもなく戦わねばならないとき、渚さんにとっての武器は、言葉、ということに、帰着するのだろう。
【黒木渚格言集】(100)
世界で一番暗い場所は、人間の黒目の中にある。『壁の鹿』/黒木渚
楽曲、「虎視眈々と淡々と」でも歌詞になっている、この文章。黒目というのが、キーワードになっている。黒目から見る世界も、暗いだろうか。
【黒木渚格言集】(101)
生身のあなたが怖い「窓」/黒木渚
想像と現実の問題。片思いで思っている内は、想像が勝つが、現実になった時、想像が壊れることが、怖い、となる。
【黒木渚格言集】(102)
導き給うはイエス様 熱を帯びてゆく眼球「あたしの心臓あげる」/黒木渚
心臓をあげるのは、暗喩としての、イエス様になぞらえた、君、であることは確かだろうが、眼球という言葉で、それが視覚的なものであることが、明示されている。
ー追加で書いて置いたものー(+α)
【黒木渚格言集】(103)
命短し我々が 歯向かってゆくは 大予言「大予言」/黒木渚
大予言と題された、ライブでの人気曲。命短し我々が 歯向かってゆくは 大予言、とは、それこそ、大予言だと、歌詞は結んでいる。
【黒木渚格言集】(104)
「大人の遊びさ」 口髭が笑う「あしながおじさん」/黒木渚
大人の男の一つの原型として、「大人の遊びさ」は、大人らしいが、大人のような子供にも聴こえる、歌詞の羅列。
【黒木渚格言集】(105)
こころはもう逃げない しあわせよかかってこい「ブルー」/黒木渚
こころはもう逃げない、とは、ブルーな憂鬱にも対峙し、受け止めたうえで、乗り越える意識の萌芽のことだ。この歌詞で、憂鬱のブルーが、もう一度、晴れた気持ちに転移する。
【黒木渚格言集】(106)
バカになる覚悟を決めて走れ「解放区への旅」/黒木渚
黒木渚さんの、解放区への思いが、ストレートに歌われた歌詞。バカになる覚悟とは、過去の自分を捨てて、新しい自分になることだと言えるだろう。
【後記】
一年間、読んで下さり、ありがとうございました。いいねも、励みになりました。此処、note、にて、全て、(+α)、を載せて置きます。
『おわりに』
ここで、本書、『黒木渚論』―黒木渚、そのイニシアチブに沿って―、を終わることとするが、これからも、自分は、黒木渚さんの、黒木渚論を、書き続けるだろう。そして、本にするだろう。黒木渚さんの、芸術に対する姿勢への尊敬からである。また、本書を読み終えて下さった方々には、是非、毎週火曜日にyoutubeで放送されている、黒木渚の棘、も観て貰いたい。とても面白く、尖っているからである。此処まで書けたのも、黒木渚さん、そして、黒木渚さんのファンの方々が、応援して下さったからこそである。感謝の念を持って、一先ず、ここに筆を置くこととする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
