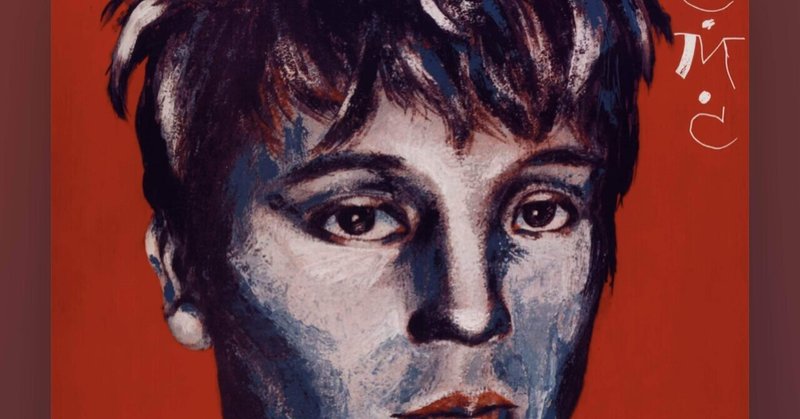
ロックンロールは頭で考えるもんじゃねぇけど、たまには頭で考えてレッツロックしようぜ
俺が中高生の頃。
既にルースターズは解散して20年以上が経過していたが、当時活動していた日本のロックンロールバンドの多数がルースターズの影響化にあった事、同じ頃に海外で起きていたロックンロール・リバイバル(当時「いや、リバイバルもクソもロックンロールは別に一回も終わってねーだろ」と思ってた)の影響でルースターズ・リバイバル的な空気があった。
かくいう俺もルースターズはめちゃ好きだった。
ただ、そのカッコ良さの理由が説明できなかった。
ルースターズは「日本のパンクの名盤」的な認識で1stを聞いたのが最初だった。
文学的な歌詞とグルーヴが云々…みたいな語られ方をしていたので、もっと小難しいかと思ってたら軽快で、さも80年代日本的なバランスの録音だったのも意外だったし「俺はただおまえとやりたいだけ」「お前の体思い出して一人であれを」とかの文学的どころか相当に直情的な歌詞にびっくりした。
一人称が「おいら」なのもびっくりした。
一人称が「おいら」なのに慣れてきた頃、妙に垢抜けていてホンモノな感じするし、とにかく聞いていて楽しかったので他のアルバムを聞いてみると、音楽性がどんどん広がっていくのにおどろいた。
しかし、自分が一番ハマった曲は日本語版の「LET’S ROCK」だった。
これ以上にシンプルにしようがないくらいシンプルなロックンロールで、なんというか研ぎすまされていると思った。
特にドラムのブレイクが入ってギターソロに向かう所など何回聴いてもテンションがあがる。
2回目のフィルとギターが合う所もわけもわからずかっこいいと思ってしまうのだ。
初期の頃は直情的だった歌詞も
「ヘイベイビーどうしたんだい/髪の色は抜け落ちて新しいスーツはボロボロだ/楽しもうぜSpecial Life/今素敵な方を選ぼうぜ」
と、激情と斜陽が交錯したような深く胸を打つ歌詞に変化している。
自分は特に、このモラトニアムの終焉の様な心の揺れを描いたものが好きなので、完全に諦め切った様なこの後の歌詞もまた好きなのだが、この時期のギリギリで正気を保っている様な歌詞は特に感動してしまう。
それからしばらくして、何とルースターズが(当時は一夜限りとして)大江さんのボーカルでフジロックにて再結成した。
大江さん自身のバンド「UN」も結成され、俺もライブを見に行った。
この時期にルースターズやモッズ、さらにはボウイの影響をハードコアパンクのアグレッションでアップデートした日本脳炎も1stをリリースし、俺の様な「ルースターズ00年世代」が多数うまれたことだろう。
ルースターズの再結成ライブを当時始まったばかりのYouTubeの配信で観た記憶がある。
「ガキの頃の決着をつけてやる」みたいな、マフィアみたいな雰囲気がとてもカッコよく思えた。
俺がバンドを再結成したらこうしようと思った。
それから自分もバンドを始めた事で、それまであまり触れてこなかったハードコアパンク寄りのオルタナティヴ・ロック(あるいは逆)を対バンした先輩などを経由して知った。
自分はこの時点でいろんな音楽を聞いていたけど、そうやって教えてもらうオルタナティヴなロック、ハードコアはルースターズなど自分が元々好きだったロックンロールとは全然真逆に思えた。もっと体感的だったからだ。
目まぐるしく変わるドラムのリズム、型にハマる事なくアイディアを型にしていくようなギターやベース、芸能的である事をかなぐり捨てるかの様な聞きとれないほどのシャウト、その凄さ、聞いた事のなさに夢中になった。
そんな中でもルースターズのプレゼンスは高く、DJで突然「どうしようもない恋の唄」が流れると、皆が歓声を上げ合唱した。
地元だからというのもあるが、そんなロックンロールバンドはルースターズだけだった。
とりわけ今年もある時、ふと久々にルースターズを聞き、やっぱりカッコいいなあ、と思っていたら突然ルースターズのサブスク配信が発表された。
ちょいと運命的なものを感じた。
大江さんはオフィシャルにこうコメントをしている。
やっと。ようやく。いよいよ!
とうとう、ザ・ルースターズの配信が始まる。
ルースターズ?デビュー1980年?知らねえよ、そんな化石みたいな音楽。
今のハヤリの音楽に満足してる人たちに是非、聞いて欲しい。
どうかこの世からロックンロールが消えてしまう前に。
自分で「化石みたいな音楽」と言っているのに次の行で「今のハヤリの音楽に満足してる人たちに是非、聞いて欲しい」と言っているのが実に大江さんっぽい感じがしていいなあと思ってしまう。
リリースから43年経っているわけだが、ハヤリの音楽はどう変わったんだろう。
まず、43年前は一部を除き、音楽は人が楽器を演奏して奏でていたが、現在はコンピュータでの演奏、作曲が中心となり、楽器はそれを補足する役割になっている。
なんでコンピュータになったかといえば効率がいいからなのが最大の理由だと思う。
もちろんそれによって新たな作曲の形や音色が産まれているけど、人間が本質的に好きなメロディとかリズムは変わらないと思うので、効率と見せ方(音色も含む)が変わってきているのだと思う。
それに付随して音楽がほぼ無料でいつでも手に入ることになった事で曲がすっ飛ばされない様な工夫が作曲の時点で組み込まれることにより曲調そのものも変わっている。
もちろん、それはマスな音楽が中心の話だが、そのマス音楽が流れる社会でアンダーグラウンドな音楽も影響しあうのもまた間違いない。
ただ根底には「どうやったら楽しくなれるか」があるのは間違いない。
そしてコンピュータ音楽の根底には「どうやったら楽しくなれるか」の効率化もあると思う。
そうやって考えた時に、音楽が楽しくなるいくつかの理由が思いつく。今回は
・劇場型
・体感型
・情報型
で考えてみる。
劇場型はストーリーを楽しむ様な形である。
歌詞のストーリーだけでなく、曲調そのものの起承転結を劇を見る様に楽しんでいるのである。
次に体感型はリズムやメロディそのものを楽しんでいるのである。
良いリズムはずっと聞いていたし、良いメロディはそれだけで何度だって聞きたい。
基本的にはこの二つのバランスで音楽が成り立っている気がする。
ストーリーだけだと気持ちよくないし、リズムだけだと飽きてしまう。
しかし一方でリズムかストーリーを他の何か(空間、形式、酒やドラッグ、情報)で保管できるのであればどちらかに偏った表現も受け入れやすくなる。
個人の感覚はそれぞれなので、みんな好きなバランスを探している。
ちょっと違うのが最後の「情報」の部分である。
これは音そのものに加えて情報を楽しんでいる、いわゆるマニアの楽しみ方である。
例えば小川マッドキネシスというバンドがいて、そのファンがこういう会話をしていたとしよう。
「小川マッドキネシスの3rdの旧ミックス盤がやっと再発されたね。」
「うん。俺聞いたけど二曲目「キャットの風来坊」の後半のノイズが消えてたね。オリジナルだと「マルチタスク」の前まで鳴ってて、リミックス盤では消えたから、修正されてるんじゃないかって気はしてたけど。けど、「キャットの風来坊」はLIVE盤のがギターがこうじの頃で好きかな。ギターソロが全然違ってて。」
「こうじでいうとあのライブ盤よりもクアトロのが動画で上がってるけど、ちょっと不安定な感じがいいんだよね。確か加入して3日とかで、「GURRRRN!」のインタビューでは小川からの無茶振りだったって答えてたよ。そのせいで4thの前半ってギターよく聞いたら入ってないじゃん。」
「らしいね。俺も4th何回か聞いたんだけど、あれやっぱギター入ってないよね。ブートで出てる流出テープには入ってるみたいだよ。所々聞こえるらしい。」
この二人は熱く小川マッドキネシスについて語り合っているし、詳しいのは分かるが音楽そのものの良さを語り合っているのではなく、小川マッドキネシスの情報を交換し合っているのが分かる。
これにより、ストーリーと体感性に+して「だからこうなっているのか」という理解が深まり、より音楽体験が強くなるのだ。
(問題は実際にこういうマニアの人がいたら恐ろしくて話に入れないことであるが)
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
