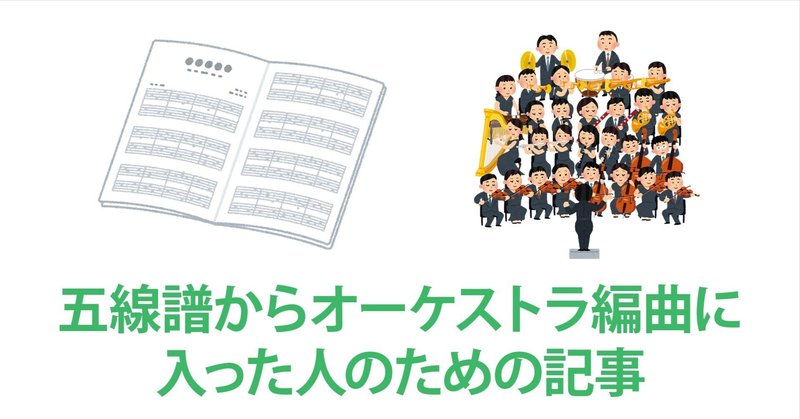
五線譜からオーケストラ編曲に入った人のための記事
DTMの普及によって打ち込みからオーケストラに入る人口が増えた一方で、クラシックピアノなどで音楽に触れて五線譜とともに育って来た人は当然五線譜からオーケストラのアレンジメントに触れる可能性が高くなります。
私もDTMを初めて間もない頃はSinger Song Writer(正確にはU-8 Composer)を使っていたので、初めてSONARに触れた時にはピアノロールの存在に困惑したのを覚えています。
本記事では音楽制作を突き詰めていくうえで果たしてDAWやMIDI、ピアノロールは避けて通れない道なのか、覚えることにどんなメリットがあるのかを考察していきます。
また、ここで言う「五線譜から入った」というのはその適切な書き方や楽器の仕組みについて独学ではなく専門的な教育を受け実践しているものとします。
大前提: 譜面は重要
当たり前ですが、音楽を作るうえで譜面の読み書きができることは極めて重要ですし大きなアドバンテージです。ハイクオリティなオーケストラの楽曲を作ろうと思ったら人間による生録音は必須であり、レコーディングは譜面無くして実現できません。そして譜面の質は演奏の質、録音の質に直結します。
なので、五線譜からオーケストラに入った人はそのまま譜面の読み書きを突き詰めていくことが音楽家として大きな武器になります。また、後述しますが譜面を書ける人間の方が打ち込みも上手にできます。
譜面とMIDIの目的の違い
では何故DAWやMIDIを使う人がいるのか。MIDIの打ち込みと譜面はそもそも目的が異なります。
譜面: 人間に弾き方を伝えるためのプロトコル
MIDI: コンピュータに弾き方を伝えるためのプロトコル
譜面は人間に対して演奏表現を伝えるのに適していますが、コンピュータに演奏を指示するには情報の解像度が不足しています。譜面は情報が十分に曖昧なので奏者が演奏表現を考える余白があり、それが音楽を解釈することの面白さにつながっています。
一方で、コンピュータはMIDIの打ち込みで与えられた通りの演奏しかできませんが、MIDIで送ることができる情報の量は膨大です。ピアノロール等を使ってシンセサイザーやサンプルライブラリに対して与える命令と同じだけの情報量を五線譜の中に書き記すことはできません。(というかそんなにごちゃごちゃ書かれたら見づらくてやってられません)
五線譜で音楽を作ることに慣れた人がMIDIにつまずく理由はシーケンサー(DAW)の操作の煩雑さもあるでしょうが、譜面であれば考えなくても良かったディテールまで打ち込みでは細かく詰めなければならないことの面倒くささがあると思います。あとミックスという全く別の世界のタスクが否応なく降り掛かってくることも。
打ち込みに慣れることのメリット
五線譜で音楽を作り始めそれで不自由していない人にとって、打ち込みに手を出すことのメリットは分かりづらいですし、人によってはあまりないかもしれません。
打ち込みに慣れると何ができるかを列挙すると
録音/実演前のデモの表現力が向上する
人間が演奏しない楽器も音楽の中に盛り込める
音楽制作をより俯瞰的に捉えることができる
録音/実演を伴わない音楽の仕事も請けることができる
あたりになるでしょうか。
ノーテーションソフトから書き出したオーディオよりもDAWで緻密に打ち込んだものの方が表現力が豊かになることは想像に難くありません。NotePerformerのように五線譜からの直接の書き出しで表現力を高める方法もありますが、DAWで打ち込んだ方が1音1音に対して厳密に表現を管理することができます。
また、MIDIを使って制御することを前提とした楽器(シンセサイザー等)や積極的なエフェクト処理によって作られたエフェクティブな音色を楽曲の中で表現するには五線譜よりもMIDIによる制御の方が圧倒的に適しています。MIDI CCやボリュームの複雑なオートメーションを行うには五線譜というインターフェースは抽象度が高すぎます。
また、五線譜から距離を置いてDAWの中で作業することで音色や音質といった録音音楽の持つ特性にフォーカスする考え方、聴き方が身についてきます。
どの国のどのスタジオで、どのエンジニアに依頼してどんなマイクをどこに立てて録音してどのマイクポジションの音をどんなバランスで使ったらモニタースピーカーからどんな音が出てくるのか、その時にバンドの楽器やシンセサイザー、エスニックな楽器を混ぜたらどんな音響的な効果が生まれるのか、ミックスの仕方で表現がどのように変わるのかといったことを考えることで、作編曲家ではなくプロデューサー、エンジニアとしても音楽を聴いて判断できるようになります。
こうした力が身につくと、打ち込みを始める段階で適切なサンプルを選択しオーケストラ以外の音色と組み合わせながら、打ち込みだけである程度作品を作り上げることができるようになります。
つまり録音しなくても最低限説得力のある音源が作れるし、録音すればもっと説得力のある音源が作れるという無敵の状態に至れます。打ち込みからオーケストラに入ってしまった人はここにたどり着くことができません。
最低限説得力のある音源を手元で作れるので、編曲は依頼したいけど録音の予算まではとれない人たちを手助けできるようになります。「編曲はできるけど打ち込みだと形にできなくて…」といって逃してしまう機会が無くなります。
打ち込みが上手いとはどういう状態か
打ち込みが上手いというと大規模なDAWテンプレートを適切に管理し、人間が演奏しているかのような自然な演奏表現をデータ入力の妙によって実現できることのように思われるかもしれません。
打ち込みが上手い人は当然そういった技能を持っていますが、それらを活かすためには上手に編曲する能力を有していることが大前提です。ベロシティやCC1、エクスプレッションの入力は上手いけど編曲のことは何も分からない、というケースはあり得ません。
打ち込みの中で技術的に覚えなければならないことはそう多くはありません。少なくとも、オーケストラに関しては
音源選び
奏法選び
ベロシティ
CC1 (ModWheel)
CC11 (Expression)
だけ理解していればあとは打ち込む人の好みや感性だけの問題になります。
音源選びはサンプルが収録された国、スタジオ、奏者の人数といった要素を楽曲に合わせて適切に選ぶということです。
奏法選びは、Legato、Long、Staccato、Marcato等、どの奏法を選べば自分が出したい音を出せるか把握するということです。
ベロシティは特にShort系(Staccato、Spiccato、Pizzicato等)の音の強さを決めることに使います。
CC1はLong系(Legato、Long、Marcato、Tremolo、Trill等)の音の強さの時間変化を曲線で描くためのものです。
CC11は主にLong系の音量の時間変化を曲線で描くためのものです。
細かいことを言えばここにどこでボウを返すだとかビブラートはどの程度かけるだとか弓を駒からどれくらいの距離に当てるといったことまで考える必要がありますが、出音へのインパクトが大きいベーシックな部分は上記の5つくらいだと思います。
ではなぜ打ち込みに上手い下手が出てくるかというと、楽器に対する理解が深い人と浅い人がいるからです。楽器を理解することは、打ち込みで扱われるMIDIメッセージを理解するよりもよっぽど時間のかかることです。
打ち込みの操作を覚えること事態はおそらく数ヶ月もあれば十分で、そこから楽器のことを知るにつれて徐々に「打ち込みが上手い」状態に近づいていくわけです。
よく、ノートを並べただけでベロシティやMIDI CCを何も入力していない打ち込みのことを「ベタ打ち」と揶揄することがありますが、仮にMIDI情報をきめ細やかに入力したとしても根本的に楽器のこと、編曲のことが理解できていなければその方がベタ打ちよりも傷が深いというか先は長いと思います。
ここまで書くと既にご理解いただけているかと思いますが、五線譜からオーケストラに入り楽器や編曲のことを理解した状態で打ち込みに手を出した人は、極めて短期間で急激に打ち込みのクオリティが向上する可能性が高いです。
打ち込みの習得を阻む要素
では何故打ち込みに苦手意識を持つ人が出てくるのか。色々理由はあると思いますが、次の2つは大きいと個人的に考えています。
DAWの操作方法を覚えるのが大変
とてもお金がかかる
ミックスが分からない
1: 操作方法を覚えるのが大変
ノーテーションソフトの使い方に加えてDAWの操作方法を覚えるのは最初は非常に苦労するでしょう。なぜなら、音楽の捉え方、考え方が大きく異なるからです。五線譜にただ音符を置いていけばOKなノーテーションソフトとは違い
トラックを作って
インストゥルメントを読み込んで
チャンネルのoutからインストゥルメントを指定して
インストゥルメントのオーディオアウトを指定して
リージョンを作って
ノートを入力して
必要に応じてCCやベロシティを書き加えて
というのを楽器の数だけやらないといけません。ノーテーションであれば五線譜だけを見ていればOKですがDAWだと
MIDIトラック
オーディオトラック
インストゥルメントトラック
AUXトラック(バス)
のように役割の異なるトラックがいくつかあるのでその意味合いも覚える必要があります。
しかも、DAWによって仕組みも仕様も違えば、同じ機能を指していても用語が異なることがほとんどです。仮にLogicを導入したとして、CubaseユーザーやStudio Oneユーザーに質問しても答えは返ってこないかもしれません。
が、見方を変えてみるとこのあたりは気合と時間さえあればなんとかなります。おそらく最も時間がかかりストレスが溜まるのはやりたいことは定まっているのにどこを操作したらいいか分からない瞬間だと思うので、そういったタスクに出会う度にその操作のキーボードショートカットを探すのが良いと思います。キーボードショートカットをそのまま覚えるのは大変ですが、Stream Deck等の左手デバイスにボタンとして登録してしまえばキーの形を覚えなくて済むので便利です。
2: 非常にお金がかかる
これは本当に難しい問題です。生業として打ち込みを続けてきた人であれば打ち込みはお金がかかるという事実に慣れきって麻痺してしまっていますが、音源を1つ買うのに何万円も、下手したら何十万円もかかるのは打ち込みに手を出しづらくしている大きな要因だと思われます。
出したい音、やりたいことが定まっていて情報の探し方がわかっていれば余計な出費をしなくて済みますが、そうでなければ無数にあるプラグインインストゥルメントの中でどれを買えばいいのか途方に暮れてしまうでしょう。
これは誰に相談すればいいんでしょうね…正直ここは未解決問題だと思います。ただ、いわゆる打ち込みに強い作曲家はただ欲しいからという理由で音源を数百万円分買ってしまうことができる狂人ばかりです。打ち込みに仕事として取り組むとなれば多少なりともそういった側面があることは覚悟しておいた方がいいかもしれません。
3: ミックスが分からない
個人的にはこれが最も大きな障壁だと思います。譜面で音楽を作っている限り、それがどのように録音されてどのようにミックスされるか、その具体的な中身や手順を自分自身で把握して実践する必要はありません。
しかし、オーケストラの打ち込みとはすなわち「録音されたものを並べて録音音楽を作る」行為なので、ミックスというプロセスを経なければ完成にたどり着くことはできません。
扱うものがオーケストラだけであればマイクのバランスとEQ、リバーブ程度でかなりのことができますが、そこにシンセやバンド楽器、民族楽器、サンプル特有のエピックな打楽器類を加え始めるとどうしてもある程度ミキシングの技術が要求されるようになります。
ミキシングはエンジニアリングと呼ばれる通り理系のタスクで、感性で突破することは難しいですし、体系的に学ぶことができる機関というのもあまりないと思います。また、作編曲と使う脳が別物過ぎて興味を持って前向きに取り組むことが難しいこともハードルを上げている点だと思います。好きになったら突き詰めてしまいますが、好きにならなければただ難しくて面倒なだけかもしれません。
ただ、これが安心材料になるかは分かりませんが世の中に発表されている音源の全てがプロのエンジニアによってミックスされたものというわけでは勿論ありません。つまり、作曲家自身がミックスについて分からないなりに頑張ったものが世の中には大量にリリースされています。それでいいのです。
ミックスについて良くないのは、分からないからと過度に恐れること、避けてしまうことです。分からないなりにやったという事実は積み重ねればいずれ自信につながってきますし、そうした精神論的な部分を抜きにするのであれば、信頼しているエンジニアに事情を伝えて自分の曲をミックスしてもらった上でどのように考えどのようにアプローチしたかの指導を受けるのは非常に有効なことだと思います。細かいことは教えてもらえなかったとしても、ミックスしてもらうことによって自分の曲がどのように仕上がりうるのかという指標を得ることができます。
まとめ
色々と打ち込みに取り組むメリットや難しさを並べてはみましたが、五線譜で音楽を作れることは本当に強い武器ですし積極的に磨き続けるべきものです。その強みを活かすためのサブウェポンとして打ち込みにもある程度真面目に取り組むことは音楽家としてのキャリアを考える上で思いの外大きなプラスになるだろうというのが私の個人的な考えです。
とはいえ好きになれないことに時間と労力とお金を捧げることは難しいとも思いますので、なにか簡単なことからでも興味を持って取り組めるといいんじゃないかなと思います。
例えばクラシックの譜面でも自分が過去に書いた譜面でもいいので、少し打ち込みの中で再現してみるとDAWの操作方法も分かりますしミックスでのバランスの取り方も分かりますし、自分に必要な機材、音源も見えてくるのではないでしょうか。
そうは言っても打ち込みに対する苦手意識は中々消えないかもしれません。気休めにしかならないかもしれませんが、打ち込みの何が苦手なのか、何が好きになれないのか、何が上手くいかないのかを立ち止まって考えて、可能な限り言葉にしてみるといいかもしれません。
そうすれば、何か問題が解決するかもしれませんし、逆に打ち込みをやらずに譜面等他のことに集中することで自分の強みだけで戦うというスタンスが明確になるかもしれません。
打ち込みは便利ですし有益なものですが、音楽家全員がやらないといけないものでもありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
