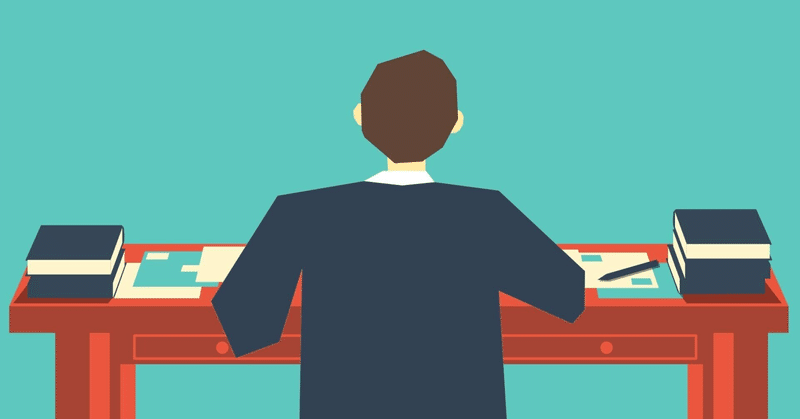
意思は強く、苦難にへこたれず、飾らず、余計なことを言わず。
剛毅木訥(ごうきぼくとつ)
「物事に恐れず立ち向かう意志の強さ(剛)、
苦難にへこたれない強さ(毅)を持ち、
誠実で飾らず(木)、
文句や余計なことは言わない(訥)ことで、
徳の高い、真心を持った人格へと近づき、将来大物にもなることができる だろう」
論語から広まった四字熟語の一つであり、私の好きな言葉の一つです。
「剛毅木訥(ごうきぼくとつ)、仁に近し」
“剛毅”とは意志がしっかりしていて物事に屈しないこと。
困難で大変な状況でも、文句も言わずに頑張る人を示します。
“木訥”とは飾り気がなく、余計なおしゃべりやお世辞を言わず、
何事も黙々とやり通す人を示します。
そういったちょっと無骨で、でもまっすぐな人の方が人間味があり、将来成果を出すと語られています。
「剛毅木訥」という四字熟語をとりあげましたが、
四字熟語とは学んでみるとなかなか奥深いものです。
四字熟語と聞くと、漢字や熟語を組み合わせた、なんだか難しい言葉を国語で習うやつだなぁ、テストや受験で絶対出るやつだなぁ、という印象の方が多いのではないでしょうか。
四字熟語は慣用句で成り立っているものが多いです。
慣用句とは、独立した単語の複合により異なった意味を持つもので、
日常の行動や物事の状態などを表現したものとされています。
単に熟語の意味や事柄を示すだけではなく、一種の比喩表現でもありました。
大昔の人たちは人としての本質を語る際や、世の中の現状に対する風刺、何かしら揶揄する際に、漢字四文字のシンプルな言葉にして表現したのです。
また、それを通して感情表現をし、相手との意思疎通もはかっていたのです。
自分の心情を表現する時、人を正す時、世の中の状態や問題など、
四字熟語を通して伝えられ、それが現代にも残っているのです。
四字熟語とは、人の心や本質、倫理観などを凝縮したものとも言えます。
四字熟語は、例えば目標を決める時や、スローガン、座右の銘としてよく使われますね。
私たち人間には、信念・決意・協調性・教訓などの精神や文化が、大昔から引き継がれているため、ふと学んだ言葉を思い出して使ってみたくなるのです。
四字熟語のことが詳しくは分からなくても、学ぶべきものとして心の奥底に、無意識の中にあるのです。
論語から生まれた四字熟語は多くあります。
また追々、記事にできたら良いなと思っております。
皆さんの好きな四字熟語は何でしょうか。
私は公認心理師・臨床心理士の仕事の傍ら、
発達障がいや、最近よく言われるグレーゾーンと呼ばれるような、
ちょっと学習や社会生活・対人関係に困っている子達への塾を経営しています。
通っている子ども達も、心理の仕事で関わる子ども達も、
皆「やりたいことなんてない」「目標とか別にない」とよく言います。
彼らには自分で ”できる!” と実感できることが乏しいから
このように言ってしまうのです。
傍から見ている大人からすれば、友達に優しかったり、
ケガしている人を見て心配したり、
運動がよくできたり、
機械に詳しかったり、
いろんな良さがある子達なのですが、
本人達にその自覚はあまりありません。
言葉にして伝えてみても、「いや、他の子だってできることだし」と。
自己評価が低く、他者と比べて自分は全然だ、と思っている子が多いです。
他者がどうあれ、自分も得意なんだ、○○については詳しいんだ、と
胸を張って言えると、もっとやりたいこと・頑張りたいことが思い浮かんでくるもの。
ですが、そこに到達するには高いハードルが彼らにはあるようです。
中には、できる・頑張れることを前面に出すと、
大人に過剰に期待される、もっとやれと言われる……
それが嫌で自分の価値を下げてしまう子もいます。
頑張ろうと思えば頑張れるけど、それを持続させる自信も、体力・気力もない。
頑張っても自分よりすごい奴がいたら挫けてしまう。
それが嫌で、最初から頑張ろうとしない、
目標なんていらないという子も実は多くいます。
せっかくできていること、頑張れること、
人より優れたところがそれぞれあるのに、もったいない……
彼らの良さと、その自覚を引き出すのが大人の務めなのでしょう。
良いところ、できること、魅力的なところ
それらをもっと言葉にしてやりつつ、強要し過ぎず見守ること。
なかなかこの匙加減は難しいですが、
・プレッシャーがあっても頑張れる子とそうでない子
・褒めて伸びる子か、そうでない子か
・叱られて「なにくそ!見返してやる!」と思える子なのか
子どもがどういう性格と考え方かを見極めることがまずは大事でしょう。
見極めができていれば、その子に合った言葉と
背中の押し方も本来分かるはず。
分からなければ、それは大人の方が未熟ということでもあります。
自分の子ども時代に立ち返って考えてみれば良いのです。
自分の時はどうだったか。
周りに居た友達はどんな子だったか。
大人に言われたことをどう受け止めていたか。
我が身のこととして考え直せばそこにヒントがあります。
分からないのは自分を理解できていない、これまでの人生を整理できていないということ。
自己を見つめ、知る良い機会になるかもしれません。
子どもと親は鏡のような存在。
子どもでなくとも、目の前にいる”何か課題があるなと思う人”も、自分の鏡として現れた存在です。
子どもにできないこと、トラブル、
うまくいかない状況が生じている時、
それは関わる親や大人も何かしら問題となる要素を持っており、
それを大人に気付かせ、改善させるために、子どもが代わりとなって問題を生じさせていることが多いです。
大人が改善してこなかった部分を子どもが背負い、
大人に訴えかけてきているのです。
「物事に恐れず立ち向かう意志の強さ(剛)、
苦難にへこたれない強さ(毅)を持ち、
誠実で飾らず(木)、
文句や余計なことは言わない(訥)」
これらが難しい子はもしかすると、
親や見本となる人が
「物事を何かと恐れて立ち向かわず、意思も弱い。
苦難にもへこたれやすく、
不誠実で、自分を飾りまくり
文句や余計なことをよく言う」人なのかもしれません。
親がそうであるかもしれないし、
普段関わっている人の中にそういう人がいるのかもしれません。
残念ながら剛毅木訥とは真逆の大人をよく見かけます。
これから親となるであろう、若い世代にも。
年上の世代にも。
子どもだけでなく、仕事における姿勢においても
剛毅木訥とは反する生き方の人は
若かろうが、中年や老年であろうが、どこの現場にもいます。
同業で、「資格を取って世の悩みある人の支えとなって頑張りたい」と夢を持ったにも関わらず、仕事の責任、人の人生に関わる責任の重さに耐えられず、夢破れた仲間や後輩も多くいます。
苦難や責任に耐えられず、
自己の在り方と問題点・改善点に向き合えず、
自分がうまくいかないのは職場のせいだ、
環境のせいだ、周りの人のせいだ、と自己保身に走り、
お世話になった人達と、関わっていた相談者を裏切るような形で現場から去っていった弟子も私にはいます。
そのような大人が子ども達や、
社会に出て間もない人達の見本となれるでしょうか。
見本となってはいけません。
誰しも大なり小なり、失敗した経験、
若さゆえに、知らないことがあったゆえに
不義理なこと・失礼なことをしてしまった経験はあるでしょう。
迷惑をかけたことも、人を怒らせたことも
思い出したくない経験も多いにあるでしょう。
それでも良いのです。
それらの失敗と苦い思いを、子ども達や若い世代に正直に伝え、
そこから学んだことと、こんなことをするとえらい目にあるぞ、という危機感も伝えていく。
『あなたの今できないと諦めていることは、自分達ももちろんそうだった』
『できないなりに頑張ってみたらうまくいったこともあるし、
代わりに別のことを頑張ってみたらなんとかなった』
『不得意を克服したくて努力した』
『自分も人の目や評価を気にしてしんどかった時期はある』
そういう話をたくさんしてあげてください。
経験を語ること。それを聞き、人から学ぶことが
お互いに何よりも深い学びになります。
理屈や理論がどうだとか、そんなものはあまり印象に残りません。
それらは研究の世界や論文など、かしこまったところで語ればよろしい。
人間の心を豊かにするのは、実感溢れる経験と言葉です。
子ども達と、これから社会で頑張っていく人達が、
剛毅木訥の精神溢れる人の姿を多く見ることができますように。
自分自身も、子ども達にその姿を見せられるようにしていきたい……
日々精進です。
こんな辛辣なことばかり文章にしてしまうので、現在執筆している心理エッセイ本の編集の方々には「厳しい」とよく評されている今日この頃です。
本の執筆もまた、剛毅木訥の精神で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
