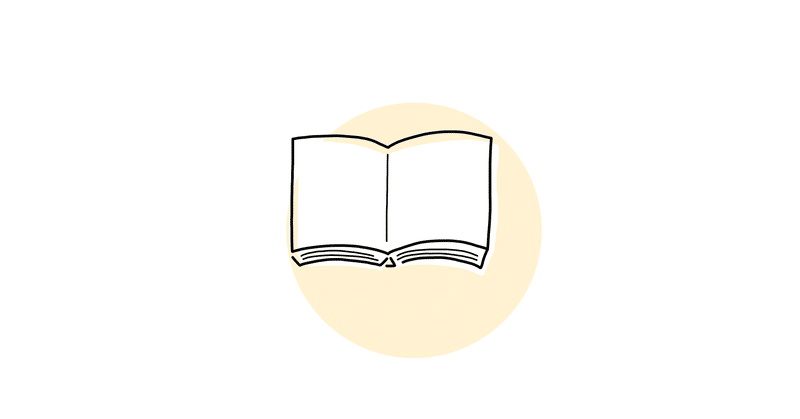
2021年2月に読んでよかった本、買ってよかったもの
■読んでよかった本
あなたの知らないあなたの強み
チームマネジメントをするときに、個々のメンバーの特性を理解し、それぞれのメンバーが持つ強みや弱みを客観的に把握する手法のFFS (Five Factors and Stress) 理論の紹介本。
悪い人はいない。強みがちがい、価値観がちがい、ストレス状態がちがうだけ。
漫画『宇宙兄弟』をとおしてFFS理論が紹介されているので、『宇宙兄弟』を読んだことがある人なら、説明がするする入ってくることまちがいなし。
自分の個性を知るだけでなく、身の周りの人の個性も理解することで、感情的にならずに冷静に相手を見つめることができるようになり、対人関係の改善や向上につなげられる。
人は人との関係性で成長する。
自分の特性を理解し、強みを活かし、弱みは仲間に補ってもらう。
そんな関係性を意識したチームづくりが大切、とのこと。本当にそう思う。
そのための自己理解・他者理解の大切さを意識させてくれる一冊でした。
世界のニュースを日本人は何も知らない2
目次を見ると、興味をひく見出しばかり。
「イギリスの学校には健康診断がなく保健室もない」
「『海外の学校はIT化が当たり前』という誤解」
「『子ども部屋おじさん』は世界の最先端 !?」
「『アナ雪』は『アンパンマン』に負けていた!」
日本のニュースだけを見て、なんでも知ったつもりになっているのは本当にこわい。
『トム・ソーヤーの冒険』の著者、マーク・トウェインもこのように言っている。
WHAT GETS US INTO TROUBLE IS NOT WHAT WE DON’T KNOW. IT’S WHAT WE KNOW FOR SURE THAT JUST AIN’T SO.
(問題なのは何も知らないことではない。本当は知らないのに、知っていると思い込んでいることなのだ)
海外のニュースも積極的にインプットしなくちゃと気持ちを新たにした。
※本書は『世界のニュースを日本人は何も知らない』に次ぐ2冊目。
こちらも合わせておすすめ。
(Kindle Unlimitedの会員なら無料で読めます)
絶対に挫折しない日本史
固有名詞がほとんど出てこないし、超俯瞰的視点でどんどん時代が進んでいくので本当に読みやすかったです。なにより古市さんの言い回しが、パンチが効いていておもしろい。
自分の思っている「当たり前」が、いかに小さくて狭い価値観に基づくものなのか。改めて身にしみた。
歴史を学ぶ意義はビスマルクのこの一言に凝縮されていると思う。
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
歴史本はこれからも読み続けたいな〜。
Business Agility――これからの企業に求められる「変化に適応する力」
最近よく耳にする「アジリティ」という単語。「変化に適応する力」と訳されることが多い。でも実際のところ、この言葉の解像度は低く、あまり理解し切れてはいない……。そんな背景から思わず手にとった。
企業のビジネスプロセスマネジメントのアドバイザを担ってきた著者が
ビジネスアジリティとは?
ビジネスアジリティの獲得のためには?
をやさしく解説してくれる。
「アジリティ=変化の早い時代に”生き残る”ための力」と解釈されがちだが、著者はビジネスアジリティの本質を
変化の速い環境でも、いち早くビジョンを達成し、社会に価値を提供していくための力
と説く。ハッとさせられた。「アジリティの向上」や「企業の生き残り」はあくまでも結果でしかない。
「ビジネスアジリティ実現の鍵は、人の自律と組織文化」
「これからは変革を企画する側だけでなく、変化に反対する側にも説明責任が生じる」
など、組織としてアジリティといかに向き合うかを考える上で(自分を含め、アジリティの知識が浅い人にとって)参考になる部分が多い。
これからの企業のあり方に悩む経営層の人におすすめ。
即答するバカ
本書内の「おわりに」から一節を引く。
好悪の印象を分けるもの。そこには次々思い浮かんだ人物のちょっとした物言いの「すごい力」が関係している。
「すごい力」ではあるが「ちょっとした物言い」だから「問題な印象」を与えている側は、自分のしゃべりのどこがどう問題なのか気付きにくい。とはいえ「ちょっとした物言い」で人生が左右されることもあるのだから放置できない。
なんとなくギクっとしてしまった自分がいた。
たとえばこんな指摘がある。
・すぐに「だから」を使う人は、スマートで賢く見えるかもしれない。でも実は、単に短絡的で安直な人かもしれない。
・ひらがなを使えない人がいる。
即答こそ正義だと決めつけて、即答するクセはないか?を見つめ直したくなる一冊でした。
世界一わかりやすいDX入門 GAFAな働き方を普通の日本の会社でやってみた。
DXを推進するうえで必要な組織構造や人材、コミュニケーション方法が、IT分野の会社を渡り歩いてきた筆者の経験をもとに簡潔にまとまっているので、(「世界一わかりやすい」かどうかは別にして)「DXとは何か」「DXをすすめるためには」を知る手がかりの1つとなる。
GAFA的な働き方を安直に模倣するのではなく、「日本型の企業のよさを活かしながら働き方を改革するためにはどのような方法がいいのだろうか?」という視点から考察・説明がすすんでいくのがとても参考になりました。
■買ってよかったもの
特にナシ。
今月は以上〜!
サポートしていただいたお金はすべて、安眠のために使用します。
