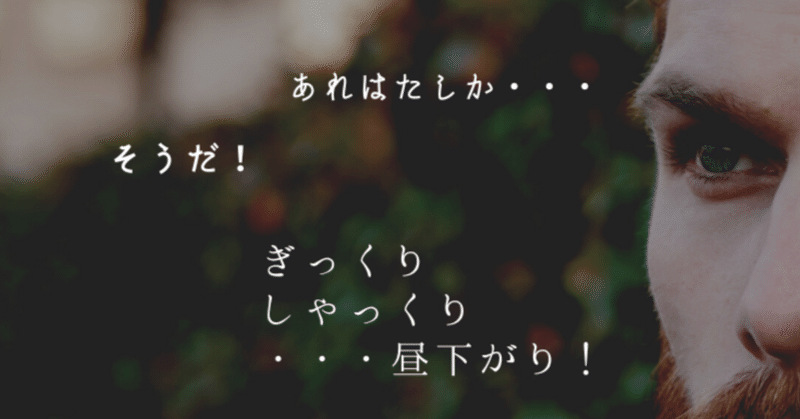
ギク川霊のぎっくりしゃっくり昼下がり 23年冬 - 3
そういうことである。
その3である。
はいっ!
ということで、わたくしですね、そろそろ肝心のお話の内容についてお聞きしたいわけですがっ! わけですがっ!
どこまで話しましたっけ
えーっとですね、まだお話に入ってませんね、というところまででっす!
……そうでしたか。たしか、書き始めたものをいちどボツにしたところくらいでしたかね。
そうですっ! そのあと、待望のウミネコ応募作が!
……そ、そうですね。いちどストーリーをボツにしてから、ちょっと引っ掛かってたところがあってですね
と言いますと?
お爺さんと孫娘って、どうして「はやてこぞう」の話をしていたんだろうって。別の話をしたっていいんですけどね。
お爺さんにとっては気になる存在だったんでしょう。最初に書きかけた話では、孫娘が「しゃべらないで暮らすって、どんな感じかな」と言ったのに対して、お爺さんは「さぁ、わからんよ」と答えるんですが、そのふたりが言葉のない世界をどう捉えてるんだろうと思ったんですね。
じゃあ、もうちょっと待ってみたってことですか
そうですね。何か出てくるだろう、という予感みたいなものがあったんでしょう。ふたりの捉え方は、言葉のない世界、喋らない人を、特にかわいそうだとか、不便だろうとか、単純な捉え方をしてなかったように思ったんですね。不便なことには違いないと思いつつ、哀れみとは違う感情があったんだと思うんですね。
自分とは別の世界を生きている人への興味というか、不便さを受け容れたうえで切り拓く世界を想像するようなところがあったのかな、と思いました。
そしたら、喋らない人のことが気になってきますね
そうなんですね。そこで改めて喋らない人に目を向けることになりました。童話は、大人になるまえの人が感情移入できる形でないといけないと思いましたので、喋らない人は、やっぱり少年なんだな、と思いました。
「はやてこぞう」ですね!
そうなんですよね。喋る分のエネルギーを他のことで発散してたんでしょう。きっと走り回ってたに違いないと思ったんですよ。そうしたら少しずつ彼の輪郭が見えてくるように思いました。
ほかの登場人物とか、やっぱり出てきました?
いえ、まだです。頭の中で形がクリアになってきた人物に向かって、君は誰なんだ、どういう人なんだ、と問いかけるような時間がしばらくありました。
どんな答えが返ってきたんですか?
彼は喋らないですからね。これだって答えはなかったです。それに、喋らない人のことを描写しようと思ったらまわりの人間を通してやるしかないので、彼は周りの人とどう接するんだろうと考えてみたんですよ。
なるほど〜
「はやてこぞう」だったので、仮に「はやて」と名づけて、顔立ちや体格も具体的にイメージして、頭の中で動かしてみようと思ったんですね。
どんな顔だったんですか?
ナイショです
くわっ!
ふふ。あとでお知らせするかもしれませんけどね
はいっ! ぜひっ!
そうですね。仮に名前を与えて、顔立ちや体格をイメージしたら、また世界が広がった感じがしました。で、お爺さんと孫娘との会話のなかで「はやて」がいなくなったって言ってましたが、彼はどうしていなくなったんだろうというのがわたしのなかで引っ掛かってて、そこに至る経緯を知りたいな、と思って眺めてました。
その理由、わかりました?
しばらくしたら、わかりました。ああ、そういうことだったんだ、と思って。周りに人がいるからこそ理由がある。でもその理由を理解するには彼は少年であってはならない気がしたんですね。
……と言いますと
悪いことをして追い出されたわけじゃないんですよ。そんなだったらお爺さんが孫娘に語るような話にならないですからね。誰も悪くはない、でも答えがない、そういう状況になっちゃったんです。お爺さんは答えが出ないことがずっと引っ掛かってたのかもしれません。話としてそういう事情を自分なりに呑み込むには「はやて」って少年じゃなくて青年のほうがふさわしいな、と思いました。自分でもこれは童話かな、と思ったんですが、人の心理面を描くものになるのでいいだろうと
うーん、ギク川ですね〜、よくわかんないですが
そうですよね、独り言言ってるみたいで。ものがたりとしては、具体的に「去っていく場面」が頭に浮かんだので、今度はいけそうだぞ、と思いました。主人公に名前と輪郭を与えることで、場面を見せてくれたわけですから。
はっ! やっと! おはなしがっ!
そうですね。やっとおはなしが見えてきました。長いですよね。
長いです!
ははっ、そうですよね。すいません。でもそういう道のりだったんだからしょうがないです。そうしたら、いくつかの場面がアニメーションみたいにふわっと浮かんできたんですね。
geekさん! 書き始めましょうっ!!
ええ、そう思いました。とはいえ
とはいえ?
浮かんできたいくつかの場面がどう関連しているのか、していないのか、もう少し見てみようと思ったんです
geekさん、……じっくり型ですね
それがね、頭の中に「書けるぞ!」という感触がわいてきて、書き始めちゃいました
じゃあ一気に!
いえ、一度に1000字くらいずつです。ひとつの場面を描こうとしたら、彼の周りの景色が明確に浮かんできて、ああ、彼はこういう世界を生きているんだな、と思いました。彼はちょっとした村に住んでたんですよ。そこにある音やにおいまでこちらに伝わってくるような感じで、自分がその世界に入り込んで様子をみているような気になりました。
なんだかすごいですね
ね、ふしぎですよね。彼がしゃべれないものだから、彼のことを知ろうとすると周りにどんな人がいたのかをみていかないといけないんですけどね、いろんな人がいるんだな、と思いましたよ。
たとえばどんな人ですか?
実際のお話に書いた人だと、同年代の少年とか、農作業をする村の人とか、それぞれの場面がリアリティを持って浮かんできました
じゃあそういう人たちとのやりとりもあったんですね
そうですね。それをどう書いたらいいかな、とは思いましたが。字数制限があったので、書かなかった日常の場面もあります。
最初はそのなかでも村でのできごとをいくつか書けば、ものがたりとして組み上がっていくだろうと思ったんですけどね、エピソードをひとつ書いたときに、歌がきこえてきたんですよ
歌ですか? うた?
そうです、うた。といってもメロディがあるわけじゃなくて、節もついてないんですが、なんて言うんですかね、暗いところからフレーズだけ転がってきました
えっと、どんな感じなんですか?
「山越えて いのち抱いて」って。なんのこっちゃと思ったんですよね。歌をたぐっていくとどうやら「かいなにいのち抱いて」ってことらしいんですよ。かいなっていうのは、腕のことです。赤ちゃんでも抱いて走ったんですかね?、と思ったんですがどうにもリアリティがなくて、……何いってるんでしょうね? ははっ
えーっとですね、その歌はどうなったんですか?
作品のなかに入ってます。
最初このフレーズに気づいた時、誰かがそういうフレーズを残したんだから、それにまつわるエピソードがあるに違いないと思ったんですね。彼はしゃべれないんだから、彼の行動を見たり聞いたりした人が歌を作ったんです。
その歌ってどうやって出来たんだろうと思ったんですね。どうやら彼はいろんな人に接して生きているらしいぞ、と実感しましたし、歌になるなんてよっぽどのことじゃないか、と思いました。
彼は、喋れないからってひとところに留まってるんじゃなくて、なんだか一生懸命なやつなんだな、と思えてきて。じゃあその一生懸命なお前はいったい何をやって歌を作ってもらったんだ?と問いかけてみたら、答えを出してくれました。
じゃあ、おはなしができたわけですね!
そうですね。なんというか、こんなにエネルギーのあるやつだったのか、と思いました。仮に「はやて」って呼んでたんですが、ほんとに「はやて」って名前にしちゃったんです。
あとは、全体にメリハリをつけるようにしたらそこそこのものがたりとして組み上がるな、と思いました。
でも、1000字くらい書いてたんですよね?
あ、そうです。書き始めたときは「うまくいきそうだ」と思いつつ、全体としてどうまとまるか、実はみえていなかったんですよね。歌がヒントになって、構成が決まった感じです。
ギク川、読んでみようと思いまっす!
はい、ありがとうございます。じゃあご感想を次回伺いましょう。
よござんすか?
よござんすっ!
