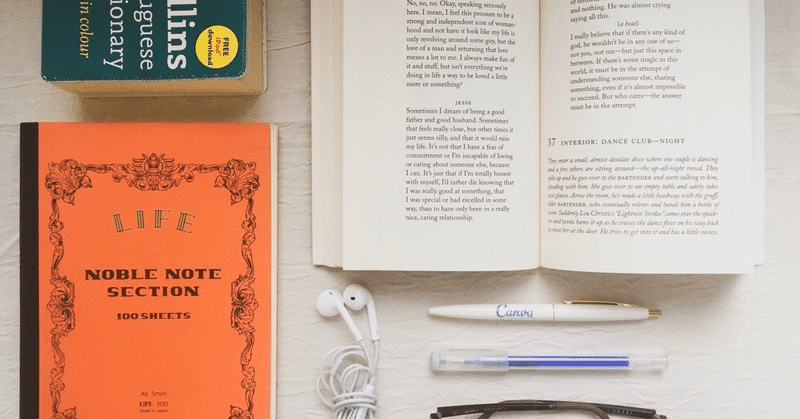
【1回で覚えられる人】への嫉妬と憧れと承認欲求
「1回説明したんですけどね。」
語学の先生のセリフだ。10年ほど前に言われた。そして、今もこうして覚えている。
アラフォーの私はこれまで親先生上司先輩からたくさんたくさん説教を受けてきた。
読書もしてきた。
アニメも映画もみてきた。
愛読書はワンピースである。
人は生きている間に数え切れないほどのセリフを耳に入れる。
そのうちどれほどのセリフが頭の中に残っているだろうか。
この冒頭のセリフは、多くの忘れ去られたセリフと違い、10年経った今でも記憶に残っている。むしろ、私に積極的に思い出させてくる。
「1回説明したんですけどね。」
なぜ冒頭のセリフは私の心に残り続けているのだろうか。
10年前、私は、上司の命令で語学研修に送られ毎日毎日語学勉強をさせられていた。将来、外国語を使って外国人の応対する人材を作ることが目的であった。
私は高学歴者でもなければ帰国子女でもない。
研修では文字通りゼロから外国語を勉強する日々であった。
当時の語学の先生が、冒頭のセリフの発言者である。
ここでは彼をA先生と呼ぼう。
研修は中盤に差し掛かり、中間テストの振り返りをしていた日だった。A先生は、我々研修生にテストを返却し、間違っていた箇所の解説をしていた。この解説中にその瞬間は訪れた。
「みなさん、この問題を答えられた人は誰もいませんでしたね。おかしいですね。授業で1回説明したんですけどね。」
あまりにも自然なセリフだった。濁りがなかった。
その口調は実に穏やかで、嫌味や怒りなどの雑味の感情は感じられなかった。まるで、おばあちゃんが縁側の下で孫に優しく語りかけるような温かい優しい雰囲気だった。
A先生は、日頃から私たちに丁寧に寄り添ってくれる「良い先生」を絵に描いたような人だった。時に情熱的に、時にユーモアをもって講義をしてくれた。
彼の経歴や実績については、研修が始まったばかりの時、研修施設側から教えられていた。日本最高峰の大学、大学院を卒業後も国内外で活躍されている人。
このような研修でもなければA先生は、私と時間も空間も交差することはない人である。
「1回説明したんですけどね。」
その発言の隣には「1回説明したら覚える」という前提がうっすらと、でも確実にあった。
私は思わず授業のノートをめくった。授業の記録を振り返った。確かにノートに書かれていた。テストで全員が間違えた箇所は、授業で説明されていたのだ。
先生を疑ったつもりはなかった。先生が説明したと言えばしたのだ。そこに疑いはなかった。でも私はノートを見返したくなった。ノートをめくった本当の理由は、心のざわつきを抑えるためだったかもしれない。
「1回説明したら覚える」
A先生のセリフから透けて見えたそれは、彼の能力の本音だと感じた。
単純に我々研修生が授業の要点を理解していなかったという問題点も大きい。例え、1回しか説明されていないとしても(もしかしたらその後も何回も説明されていたのかもしれない)、テストの問題として出されたということはその説明箇所が重要だからだ。
その問題を研修生全員が間違えたからこそ、A先生は驚いたのだろう。だからこそ発せられたセリフだった。
授業の要点を抑えていなかったというのは、我々は大いに反省すべき点であるが、私の心が揺れた理由はそれではない。
1回説明を受けたら覚えるのが当たり前。その前提に私の心は惹きつけられた。
A先生はそうやってこれまで生きてきたし、これからもその前提は変わらないだろう。彼の実績からそれは想像できる。1回知ったら覚える、その単純なことに私は圧倒されたのだった。
私は超絶の凡人である。むしろ、周りより劣る。英単語は何回も復唱して書いて覚えるのが当たり前の世界で生きている。というか、それでも覚えられない。
1回聞いただけで覚えるなんて言葉のあやでしょ、と思いたい感情も湧いた。しかし、多分それは凡人の枠の発想であって、私の願望だと思う。
私は”そっち側“でないから私の想像でしかないが、たぶん、彼らは覚える。
1回で覚えて爆速でもっと先まで行っている。もはやその表現も彼に追いついているのかはわからない。
A先生に会うまで”そっち側”の人に出会ってこなかった。
いや、違う。
会ってきたんだろうけど、私の能力ではそれに気づけなかった。
幸運にも、A先生は我々の語学の講師であり、共有する時間が長く、意見を言い合う機会が多かった。さらに、語学学習という枠に限定された環境だったからこそ、私でも”そっち側“の能力に気づけたのだと思う。
能力差とはこれなのだ。
知れて良かった。こういう世界で生きている人がいる、というのに気づけたこと。これは研修で身につけた語学とは比べられないほど、貴重な経験だった。
矛盾するようであるが、才ある人間の存在を知れた経験を誇張するがあまり、この研修で身につけた語学に価値がないような表現をしてしまったが、この表現は大きな間違いであろう。
「高い領域で生きる人」と自分を繋ぐ道具が「この研修で学んだ語学」であり「教え子となった関係」なのである。いま身についている言語力には、単に外国人とコミュニケーションがとれる以上に、別の付加価値が付いている。
そう言いたくなるくらい、私はA先生に憧れ、認められたいと焦がれているのだ。
私は今もA先生に習った言語の学習を続けている。自分自身でも驚いているが、10年経った今でも止めずにコツコツと続けている。
続けられている理由は、単に語学学習が好きになっただけでない。正直なところ、A先生をがっかりさせたくないという気持ちがある。
A先生に依存した語学学習の継続。それは事実だ。A先生に認めてもらいたいという承認欲求を受け入れるのは気が引けるが、受け入れるのだ。
結果として語学学習を続けられていることもまた事実だ。承認欲求は行動で管理するのがするのが良さそうである。
まとめ
問:なぜ冒頭のセリフは私の心に残り続けているのだろうか
回答:理由は承認欲求としての嫉妬と憧れ。副産物は語学勉強を継続できるようになったこと。
**************
いかだだったでしょうか。
印象の残っているセリフについてその理由を文字化して承認欲求と向き合ってみたという記事でした。
最後まで読んでいただき本当にありがとうございます。少しでも面白かったと思っていただけたらハートマークへのタップ、そしてシェアをしていただけると嬉しいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
