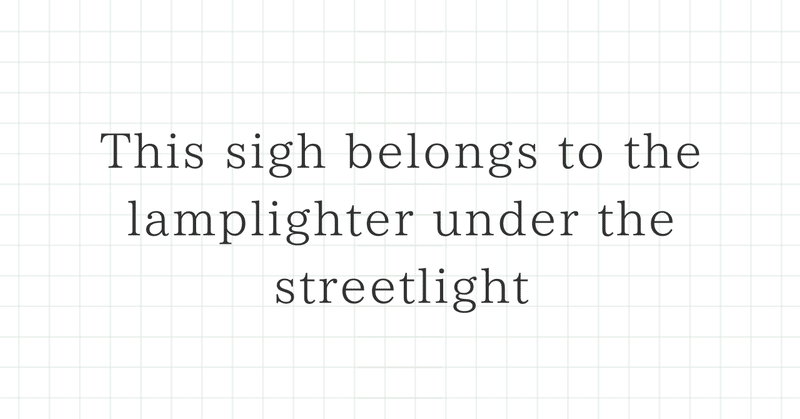
このため息は、街灯の下の点灯夫の
好き好んで点灯夫になったわけではない。
最初から決まっていた、生まれた時から点灯夫だった。
誰に言われたわけでもない、気づいたら松明を持っていた。
その松明をどう使うのか、本能でわかっていた。
歩き出した。
生まれてまだ三日目だった。
街灯の下まで来て、火を灯した。
ぼわっと燃えた。
街灯が灯ると、人々は家に帰った。
その合図として街灯があった。
点灯夫は、街頭に火を灯したあと、その街灯に照らされる自分の足を見た。
磨かれた茶色の靴を履いていた。
誰が磨いたのだろう。
最初から履いていたのだろうか。
点灯夫にはわからなかった。
街灯の上に星が見えた。
やけに大きな星だった。
星に誰かが立っていた。
それが見えるほど、その星は近くにあった。
やあ、と声をかけてみた。
やあ、と声が返ってきた。
向こうも同じように街灯に火を灯した後のようだった。
街灯の下に立っていた。
君は、どこに帰るんだい?
帰るところなんかないさ。
じゃあこれからどうするつもりだい?
どうもしないよ、朝が来たら火を消すだけさ。
朝までそこにいるつもりかい?
そうさ。
点灯夫は自分も、この場所にいるべきか、考えた。
それが正しいような気がした。
けれど、それではいつか自分が自分でなくなってしまいそうな気がした。
だから点灯夫は一歩踏み出した。
街灯から離れることにした。
一歩、また一歩、点灯夫は街灯から離れていく。
そのうち、街灯が見えなくなった。
どこまでも歩いていけそうな気分だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
