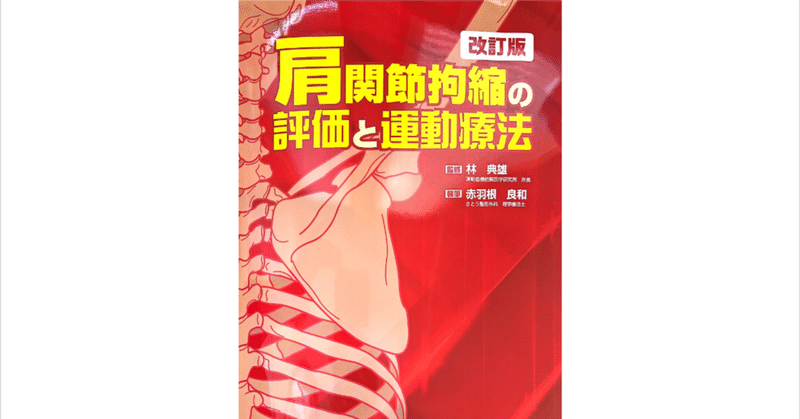
肩関節拘縮の評価と運動療法【第1弾〜問診編〜】
みなさん、こんにちは!
運動器理学療法の革命児です。
今回のテーマは肩関節拘縮の評価と運動療法です。
私は臨床で林先生、赤羽根先生の評価・治療を参考にしています。
その一部を紹介します。
肩関節拘縮の基本評価では、問診・視診・触診を上手く組み合わせることが重要である。
問診では、運動療法に必要な様々な情報を過不足なく得ることが重要であり、治療すべき組織の抽出のための第一歩となる。
特に、疼痛に関する問診は重要な情報源であり、発症時期、発症要因、発痛部位の示し方、落痛の発現部位などを聞き出し、おおよその病態を想像する。
視診では、まず局所をじっくりと観察することが重要である。
健側との比較は極めて大切であり、明らかな左右差は病態を把握する上で大きなヒントとなる。
局所を十分に観察した上で、続いて全身を観察する。
局所観察より得られた所見は、目の前の全身所見とリンクするのか、また、その逆はあるのか否かを考えながら観察する。
触診では、肩を構成する組織について三次元的な構造をイメ ージしながら触れる ことが大切である。
関節肢位が異なることで、対象となる軟部組織の緊張はどう変 化するかを、機能解剖学的に考えることが重要である。
また、体表から深部に位置する組織の触診情報を出来るだけ多く収集することも必要であり、治療者としての確実な触診技術が要求される。

問診
問診には、患者の訴えを聴取する方法と、こちらから質問を投げかけて必要な情報を返答してもらう方法がある。
臨床ではそれぞれを使い分け、過不足なく情報を得ることが、スムースな評価や治療へとつながる。
疼痛の発生時期
疼痛の発症時期とは・・・
疼痛出現から現在までの時間的経過や、きっかけとなった外傷要因を可能な限り聴取することで、疼痛の主因が炎症によるものか、拘縮をはじめとした機能障害によるものかについて、おおよその判断をつける。

a ) 疼痛が2 ~3 日前から急に発生した場合
その症状は急性期の可能性が高い。
急性期の疼痛要因は、基本的に炎症由来である。
この時期の症例は、肩峰下滑液包等へのブロック注射の効果が高く、また、消炎鎮痛剤の服用による薬理効果により疼痛が寛解することが多い。
患部に機械的刺激が加わる運動療法の実施は、炎症や疼痛を増悪させる危険性が
あることを常に念頭に置き、局所安静の必要性と具体的な日常生活指導を確実に行 いたい。
b)窓痛が2 ~4週間前から発生した場合
その症状は亜急性期の可能性が高い。
亜急性期では、急性症状を脱した時期であり、部分的に組織修復反応が進行してくる頃である。
この時期の癒着は、まだ不分なものであり、拘縮の程度としては比較的軽いのが通常である。
多くの場合は、 運動療法により筋業縮を除去することで 、可動域は大きく変化することが多い。
しかし、炎症反応が選延している症例や合併症に糖尿病を有している症例では、炎症の再燃や疼痛を悪化させない適切な対応が求められる。
c)窓痛が2~ 3ヶ月以上前から除々に発生した場合
その症状は慢性期の可能性が高い。
慢性期では、拘縮を主体とする機能障害の存在が疼痛の要因となっている症例が多い。
炎症は基本的には落ち着いていると考えられるため、拘縮除去を中心とした運動療法の実施が重要となる。
また、1年以上前にもわたり疼痛が存在し、いくつか施設で加療しても疼痛が軽減しない症例が来院してくることも時折経験する。
このような症例では拘縮の残存とともに、二次的な腕神経叢由来の疼痛が絡んでいることも多く、神経叢自体の緊張緩解を目的とし た運動療法が必要となる。
疼痛の発症要因
サポートお願いします🙇 活動費として使わせていただきます。
