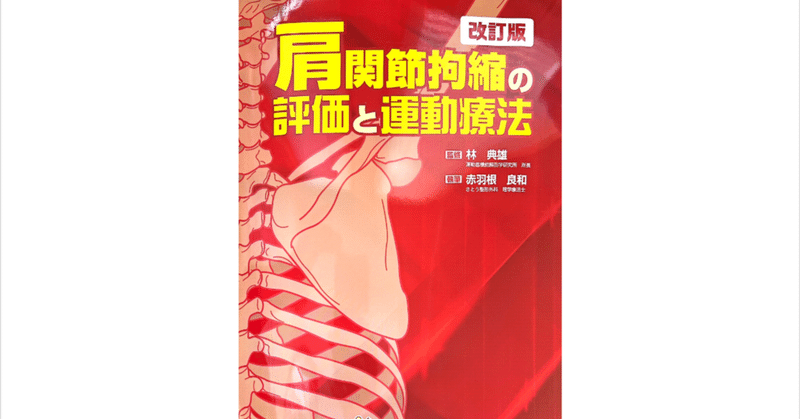
肩関節拘縮の評価と運動療法【第3弾〜触診編〜】
みなさん、こんにちは!
運動器理学療法の革命児です。
今日も1日仕事、学校お疲れ様でした。
みなさんの貴重な時間をいただいて読んでくださる方にはいつも恩返しをしたいと思っております。
図々しいのは承知なのですが、♡をクリックしていただけると嬉しく思います。
ぜひ、押してください。
フォローも宜しくお願いします。
今回のテーマは肩関節拘縮の評価と運動療法です。
私は臨床で林先生、赤羽根先生の評価・治療を参考にしています。
その一部を紹介して、私なりに所見の解釈、そして検証作業を行い、病態を明確にしてから治療に専念しています。
症状・理学所見→臨床推論→検証→結果(理学所見の再評価)→考察→評価or治療の流れを意識して臨床を行うようにしています。
理学所見から臨床推論をしてどんな検証を行うのか?を整理していきます。
今回の内容は目次にもありますが盛りだくさんです。
症例も含めた触診技術になります。
肩甲下滑液包について、腱板疎部損傷についてはこれを見ると理解できるはずです。
病院に行くと診断名がつけられると思いますが、診断名と病態は違います。同じこともありますが。。。。。8割違います。
診断名に惑わされないためにも、自分で知識を身につけてください。
肩関節拘縮の基本評価では、問診・視診・触診を上手く組み合わせることが重要である。
問診では、運動療法に必要な様々な情報を過不足なく得ることが重要であり、治療すべき組織の抽出のための第一歩となる。
特に、疼痛に関する問診は重要な情報源であり、発症時期、発症要因、落痛部位の示し方、落痛の発現部位などを聞き出し、おおよその病態を想像する。
視診では、まず局所をじっくりと観察することが重要である。
健側との比較は極めて大切であり、明らかな左右差は病態を把握する上で大きなヒントとなる。
局所を十分に観察した上で、続いて全身を観察する。
局所観察より得られた所見は、目の前の全身所見とリンクするのか、また、その逆はあるのか否かを考えながら観察する。
触診では、肩を構成する組織について三次元的な構造をイメ ージしながら触れる ことが大切である。
関節肢位が異なることで、対象となる軟部組織の緊張はどう変 化するかを、機能解剖学的に考えることが重要である。
また、体表から深部に位置する組織の触診情報を出来るだけ多く収集することも必要であり、治療者としての確実な触診技術が要求される。
問診
肩関節拘縮の評価と運動療法【第1弾〜問診編】にありますのでそちらをご覧ください。
視診
肩関節拘縮の評価と運動療法【第2弾〜視診編】にありますのでそちらをご覧ください。
触診
サポートお願いします🙇 活動費として使わせていただきます。
