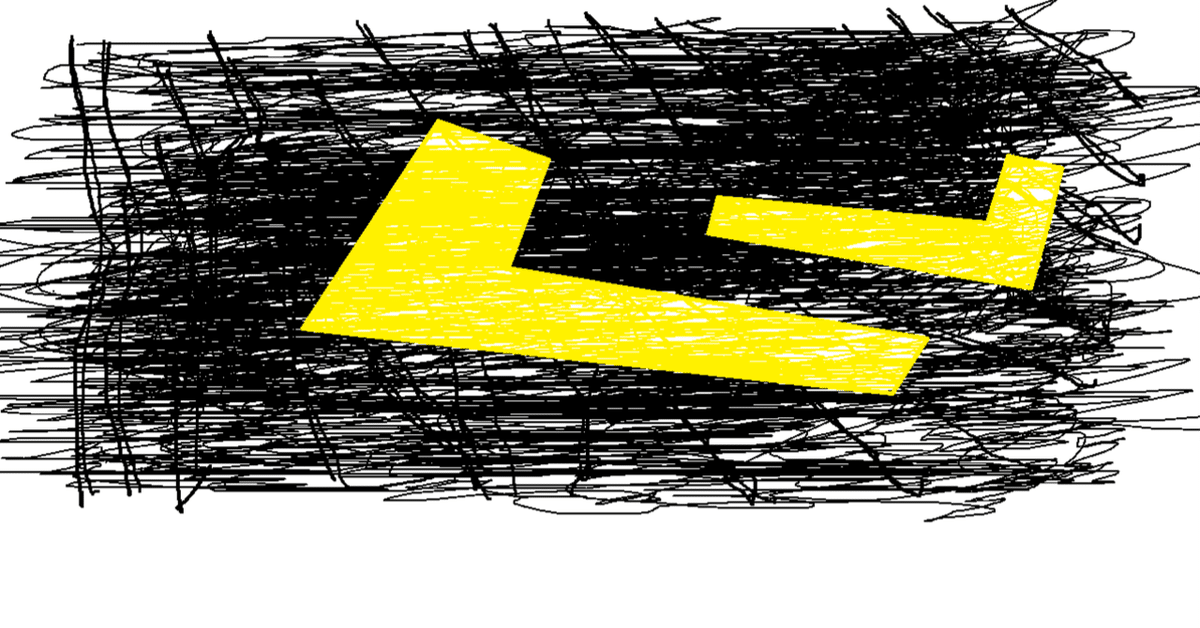
ぼくのエポックメイキングを回想するー3
今日は、2つのことを書きます。
ぼくが小学6年生だったかなあ、戦争が終わって7,8年たっていたころの話です。
取るに足らないことのようだが、なぜか、ぼくの心から離れないのです。
共通するのは、父親が経営していた小さな鉄工所に関連することです。ですから、まず、その工場(こうじょう、ではなく、こうば)のことから書きます。
当時、私の父は漁船の鉄鋼部品を製作する小さな鉄工所を経営していました。経営といっても、従業員10数人の、零細な町工場です。戦前に、四国から九州にやって来て、起業しました。終戦直前から戦後にかけて休業したものの再開、品質に絶対の自信を持っていた父の仕事は、造船所や船主の信用を得て、業績も順調でした。
で、1つ目の、お話です。
季節は忘れました。時刻は覚えています。午後4時過ぎでした。ぼくは父親と、県道に沿ったわが家の前に立っていました。なぜ、父と一緒だったのかは覚えていません。
そこへ、乗用車が通りかかりました。車、特に乗用車は珍しかった時代です。父の工場にも棒ハンドルの三輪トラックが1台あるきりでした。
乗用車はぼくたちに近づくと、人が早足で歩くほどに、スピードを緩めました。
乗客は2人。運転手と後部座席の男性。後部座席の男性は、スーツにネクタイ姿、のようです。と、その男性が、こちらに向かって、深々と頭を下げたのです。気がつくと、隣に立つ父もていねいに返礼していました。その間、5秒ほどだったか。車は何事もなかったように、遠ざかって行きました。
「誰や、あれ」
「○○鉄工所の、○○社長や」
「あん人を、よう、知っとんのか」
「昔は、な」
○○鉄工所は、わが町を代表する会社です。当然、○○社長も、わが町の知名の人です。いや、県下の実業家としても著名人です。
父が、日ごろ、○○社長のことを口にしたことはありません。経営規模はまるで違いますが、かつての船舶関係の同業者同士、と言えなくもありません。
父は、それ以上は語らず、ぼくから離れました。
このことをすっかり忘れてしまった、その数か月後のことです。
ぼくが友人を待って家の前に立っていると、見覚えのある乗用車がこちらに向かって来ました。車は、至極当たり前のように、ぼくの前で速度を落とし、後部座席の○○社長がぼくに向かって頭を下げたのです。
「えっ、社長が、おれに? 何で?」と思いつつ、ぼくは去って行く車に、礼を返しました。
同じようなことが、年に数回、ぼくが進学して町を離れるまで続きました。スーと車を寄せ、頭を下げて去って行く。ただそれだけのことです。このことは、父には話しませんでした。
「あんたのオヤジさんも、うまくやれば、もっと工場を大きくできたのに。職人一筋の人だったからなあ」
この話を聞いたのは、父の仏事の席でした。父の知人や元従業員さんの
話で分かったことはー。
「あんた(ぼくのことです)のオヤジさんが開業したのは、○○鉄工所の○○さんと、ほぼ同時期」「○○さんは金物屋の丁稚奉公から。オヤジさんは他国で裸一貫から。たたき上げの2人が、同じ町で小さな鉄工所をスタートさせた。似た者同士だ」「でも、オヤジさんは勝ち組にはなれなかった。商売で儲けるには妥協が必要だが、その妥協の一番の強敵は職人気質だ」などなど。
そういえば、父は、顧客を満足させることとは、自分の腕に満足することであるという信念を、頑固に持ち続けていました。「そこまでせんで、ええじゃろ」と言われるほどに仕事を完璧に仕上げました。
後で知ったのですが、その点、○○鉄工所の○○社長は、用地の買収、政財界、特にその当時絶対的な力を持っていた軍とのパイプを作り、経営拡大の途を探り、成功したのです。
しかし、とぼくは思いました。○○社長は、そういう父のことを分かっていた。父も自分の足らざるところを知ったうえで、○○社長の手腕に敬意を払っていた。
それにしても、過去の同業者の息子を見かけるたびに会釈する○○社長は、ただ者ではない。自分の利害をこえて、人と接することは、誰にでもできることではない。これは経営に携わる人の価値の基準ではなく、人が生きる度量の基準である。
ぼくは、その後、人と接することで色々な問題が生じたとき、○○社長の姿を思い浮かべることにしています。
2つ目の、お話です。
父の工場は、小規模とはいえ、常時10数人の職人さんが働いていました。その中には、通いの職人さんに混じって、住み込みの職人さんもいました。小さいながら、その人たちが生活する建物(寮と呼んでいました)も工場内に別棟でありました。
住み込みの職人さんは、ほとんどが中学を卒業し、職に就いたばかりの人です。ぼくは小さいときは、住み込みの職人さんに遊んでもらっていましたが、だんだんに年齢が上がると、距離をおくようになります。
と言うのも、職人さんがどんどん大人になっていくからです。仕事の上で、手子(てご:下働き)から、簡単な作業ならまかせられるほどになります。先輩の職人から、社会生活の手ほどきも教わります。2年もすると一丁前の職人に変わっていくのです。
一方で、ぼくはと言えば、学校への行き帰りばかりで、その場で社会に放り出されたとしたら、ひとりで生きていけない役立たず人間、なのです。
住み込みの職人さんは(通いの職人で独身の人も)、ぼくの家族と一緒に食事をします。
わが家は、道に面して事務所があり、その奥にぼくたち家族の部屋があります。家の裏に(工場側に)回ると、台所と土間があり、板敷きの部屋へ続いています。板の間はすぐ上がれるように低くしつらえています。さらにその奥が畳部屋へと続いています。畳部屋は、板の間からは高く見えます。
この板の間で職人さんたちは食事をします。家族は、職人さんと同じ時間に畳部屋で食事をします。家族の行動にはあまり注文をつけない父でしたが、職人さんと共に食事をすことだけにはこだわっていました。
当たり前のことですが、職人さんも家族も同じ料理を食べます。
父の、食事をすることの、もう1つのこだわりは、ご飯は腹一杯食べる、ということでした。腹が減っていては、職人はいい仕事ができない、ということでしょう。
この父のこだわりは、おそらく自分の修業時代の経験からきているのでしょうが、実は、ぼくは父から若いときの話をじっくり聞いたことがないのです。子が、親の生きた道を聞き置くことが、親孝行になるのかどうかの判断は分かれるところでしょうが、ぼくの父に関して言えば、生前にもう少し水を向けてみたかった、と今思い返しています、
で、ここからが、ぼくのエポックメイキングな出来事です。
中学3年でした。新しく住み込みの職人さんが来たときですから、春のことです。
ある夜、夕食を終えて、寮に遊びに行きました。寮にはおとな向けの雑誌などがあって、それを見せてもらうためです。
新しい職人さんが1人でいました。何やら食べています。職人さんは布の袋に手を突っ込んで取り出すと、右手をぼくの方に差し出しました。
「食うか?」
それは煎った大豆でした。多分、郷里のお母さんが持たせてくれたものでしょう。ぼくは両手で受け、こぼれたものも拾って食べました。
その翌日のことです。ぼくは、いきなり宣言したのです。
「今日から、板の間で食べる」
職人さんにも、家族にも、ぼくがどちらの食卓に座るかなんて、どうでもいいことです。でも、その時のぼくには重大事でした。
父親の食事への考え方を突き詰めれば、ぼくは板の間で食事をとるべきである、と判断したのです。
なぜ、このような、他人からすれば些細なことが、ぼくのエポックメイキングなのか。
それは、よく分からない。分からないが、ぼくが立ち位置に迷ったとき、この2つのエポックメイキングが、まちがいなく感応するのです。
例えば、ぼくが社会や政治を見る目は、迷うことなく、板の間から見る目です。
人を見る目は、車から礼をし、それに礼を返す目です。
これらの目は、対立することがしばしばあります。が、ぼくは複眼的に物を見ることは健全なことだ、と思っています。
視点が定まれば、人が見える、社会が見える、世界が見える、とぼくには思えるからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
