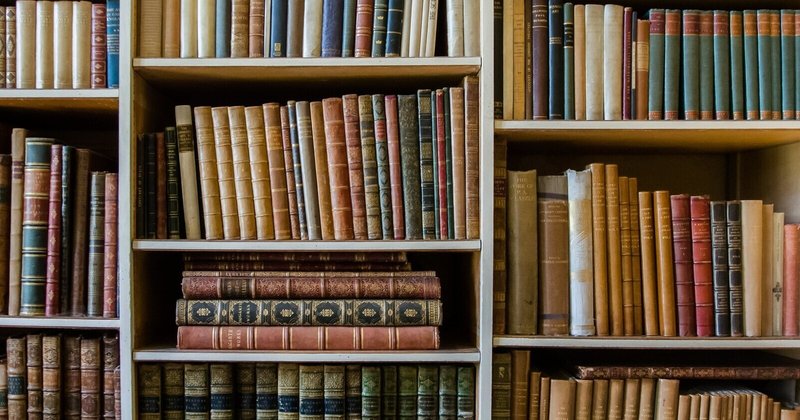
古本屋アンソロジー
私の祖母は、幼い頃から私に読書を勧めることが日課のような人だった。
顔を合わせては「本を読んでいるか」。
食卓で膝を突き合わせては「本も食べ物に劣らぬ栄養になる」。
買い物に出た先では「欲しい本はないか」。
スーパーで買う牛肉1つの価格でさえ1円単位で気にする祖母が、本屋においてだけ財布の紐が緩かった。
おかげで私は生半可に本を読み、結果子供らしからぬ悪知恵をつけた。祖母からもらった1000円を握りしめ、駄菓子屋やゲームセンターで遊蕩し、帰りに古本屋で50円の本を新品の本と言い張り買って帰る。最初に悪知恵を実行に移した日に、古本屋の前で見知らぬサラリーマンと遭遇した。私は伏し目がちにその見知らぬサラリーマンを脇を抜けた。小脇に分厚い本と薄っぺらい罪悪感を抱え、風よりも早く走り抜けた。
そのまま私は自宅に着くも、視覚も疎くなった祖母はあえて本の内容を確認することはせず、身に不釣り合いな分厚い長編小説を抱えた小学生の私を満足気に眺めるだけで、私の犯す小さな偽証について、それ以上のアリバイ確認も追及もしなかった。
晴れてそんな小さな犯罪者になった私のそれからの生活はというと、本を抱えた私に向けられる満足気な祖母の笑顔から生まれ出でる罪悪感、古本屋から引きずってきた罪悪感の2つを消化するために、その50円の本を読み終えることを日々の贖罪としていた。
そんな祖母が、私が高校に入学して間もないある日、病院から危篤である連絡を受けた。
自宅で湯上り時に脱衣所で倒れた祖母は、頭に小さな切り傷を昏倒時に負った程度で、病室に血相を変えて慌てて駆けつけた家族を「大袈裟だ」と笑った。
自分の周囲の人間が初めて入院するという大事件に人生で初めて遭遇した私は、笑う祖母とは対照的に半泣きで祖母の手を握ると、二度と今後は小遣いをせびるまい、不正も不義もするまいと心に誓った。祖母となんの関連もないが、当時の自分にとって経済的に重すぎる誓約をすることで、八百万の神に祖母の安全と健康を約束する取引を持ち掛けたつもりだった。
しかし、八百万の神はその取引を認めず、後日簡単に祖母をどこか遠くへ連れ去ってしまった。
退院して3日後、脱衣所で再度祖母は昏倒し、全裸で頭から血を流し気絶、そしてそのまま絶命。真冬の脱衣所での心筋梗塞だった。
祖母の初めての昏倒事件以来、ずっと過去の小さな偽証を謝るタイミングを見計らっていた私は、棺桶の中で眠る祖母に心の中で謝った。
懺悔にも、八百万の神に対する子供の地団駄にも似たその告解を、今となってはもう祖母がどう思っているのか確かめようがない。
一回目の昏倒時、病室で自らの手を握った私に祖母は
「最近は本を読んでいる?本を読むことはね、人の人生を体験できるの。それは巡り巡って、貴方をきっと守る。」と優しく諭すように話しかけ、自分そっくりのくせ毛で覆われた私の頭を愛おしそうに撫でた。
私はその日、人生初の身銭を切って、古本屋で本を購入した。
その本とは、文庫版 結城昌治の「不良少年」だった。時代遅れの1980年代レトロな不良が、小さな盗みや暴行程度の犯罪から始まり最終的に殺人と銀行強盗まで犯すその物語は、偶然目についたから買っただけの私の幼き頃の罪の意識を一層深め、その後の私の軽率な行動に些かの制約を与えてくれた。
読むほどに哀しいその本の温度に耐えきれず、私は終盤その本を読み進めることを諦めた。しかしその時点で学んだこともある。
人が堕ちていく姿は、教科書にはもってこいなのだ。
*
世の中にスマートフォンが行き渡り始めた頃、私は大学に入学した。
なぜか学生時代とは、学校で学ぶことよりも学校以外で学ぶことのほうが思い出に残り、その後の人生に大きな教訓を与えてくれる。私もその極意に漏れず、様々な教訓を痛かったり苦かったりと様々な思いをしながら学んでいた時期だった。
しかも校外で起きる奇想天外な事件の彩りは実に見事で、全く世の中の出来事はいい意味でも悪い意味でも私を退屈させたりはしてくれなかった。アルバイトを始めた私に襲い来る社会の理不尽な波。時に怒号や悲痛な叫びに姿を変えて私の心に巣食う不服や不安は、私に中々処理しがたいストレスを与え続けた。
ある日のことだった。その日アルバイトの飲食店で、教えられてもない調理仕事を押し付けられ、見よう見まねでまな板の魚を捌いた。
刺身になるはずだった目の前のカンパチは、まるでサバイバル料理のようなダイナミックなブロックに切り分けられ、頭、身体、尾という男らしすぎる見た目になってしまった。気のせいか切り分けられる前よりも虚ろになったカンパチの目が、私を恨み深そうに見つめていたのを覚えている。
当然、飲食店の管理者は私を叱責し、今まで聞いたことのない汚い言葉に私を例え、詰(なじ)った。
私は初めて言われたその汚い言葉「魯鈍(ろどん)」を、理解できないままその叱責を聞いていた。何かわからないが悲しい。コレはどういったことだろう。意味すらわかっていないのに可笑しいな。何に例えられているかすらわかっていないのに悲しいとは。
その後10分間押し付けられた処理も消化も不能な理解不能な言葉たちは、私の心の未成熟で柔らかい部分を的確に追い詰め、時間を空けて私の目から涙を押し出した。
怒られて以降の自分は、まあ見るも無残な態度で、決してアルバイトとはいえお客からお金をもらえる態度の人間ではなかったと思う。その不貞腐れ具合といったら、ここまでくれば何か大会にでも出たいぐらいだった。
その結果、戦力外とみなされた私はアルバイトのシフトを減らされ、自宅で時間を過ごすことが多くなった。その不貞腐れた私は、不意に自宅の本棚から「不良少年」を手に取り、暇をつぶす目的でさらりと、5年は挟まったままの栞を引き抜いた。
作中で主人公の少年は徹頭徹尾、誰にも言えない考えを、誰にも言うほどではないと考え、誰にも言わなかった。
自分では真面目に、そして可能な限り尽くしているのに、社会に評価されない。それどころか見放され、嫌われ、怒られと散々な主人公の少年。
主人公の少年は、その10代の年齢に似つかわしくなく、感情を外に出すタイプではなかった。しかし作中で主人公の少年の心情はずっと霞がかかったように得たいの知れない形をしていた。周囲の描写、登場人物の所作、数少ない会話、その節々から主人公の少年が抱く消化しきれない感情の負債が伺い知れた。
最終的に、そのモヤモヤは間違ったエネルギーに変わり、主人公は罪を犯す。誰にも言えなかった葛藤と、誰も知らなかった哀しみが、行き場をなくしてその本の章末まで遺っていた。
私は、その主人公の少年の考えが痛いほどわかった。同時に恐怖もした。
誰にも言えなかった葛藤と、誰も知らなかった哀しみは、言えなかったのではない。知られたくなかったのではない。どうすればいいのかわからなかったのだ。なぜなら、今の私の如く、その感情や思いが何なのか自分自身でも説明ができなかったから。
自身にしか感じられない無色の煙のような感情を、どうして他人に説明できようか?
そして、今の私もこのまま主人公の少年のようにこの感情を飼殺せなくば、人をも殺めるのか?
私は誰もいない自室で身震いし、すがる気持ちで救いを求め、ページをめくった。
巻末に近づくにつれて、その少年は大罪を重ね、最後に人を殺めた拳銃をその身に向けた。最後まで救いなんてなかった。
その少年が自らに銃を向けてから引き金をひくまでに、わずか数行もなかった。
引き金を引いた理由は、銀行強盗に入った彼が警察に取り囲まれ逃げ場を失くしたことも大きな理由だが、人質にとった銀行員の女性に処理できていない自らの感情の隙を突かれたこと。その許しがたい怒りと焦りが彼を殺した真の弾丸であった。
「不良少年」を読み終えた私は、その彼の動揺が手に取るように理解できた。自分が表現できなかった感情を他人に見透かされた自分、とても惨めに感じただろう。これほどまでに自らの人生や自らの価値に悩みぬいた自分が、自分自身を理解していなかった、その事実がこれまでの彼の自尊心を激しく揺らしたのだ。
主人公の少年に対する私の共感は留まるところを知らず、自分がフィクションである主人公の少年の生まれ変わりではないかとすら思った。
そしてその時、私は悟った。
本を読む価値はここにあったのか。
フィクションであれど他人の思考、境遇を本の中で体感し、自らに重ね、その結末を体験する。
それはまるで、人の人生を食い、自らの栄養とするかのようだ。
だから祖母は、私に本を勧めたのだ。
沢山の人生を体験させ、その教訓によって私を守るために。
*
それから10年が経った。
季節外れの小春日和のような日差しの年始、私は仕事で神保町を通りかかった。取引先へと急ぐ私の目に、全てが老舗であり相応の歴史を有しているであろう古書店や古本屋の暖簾が飛び込んでくる。
退屈そうに半目を開けた古本屋のシャッターの隙間から、店構えに似つかわしくない年齢の子供が小脇に古書を抱えて私の脇を伏し目がちに小走りで通り過ぎた。
思わず口元がほころぶ。
古本屋からインクの匂いがする。
春が待ち遠しい。
オバケへのお賽銭
