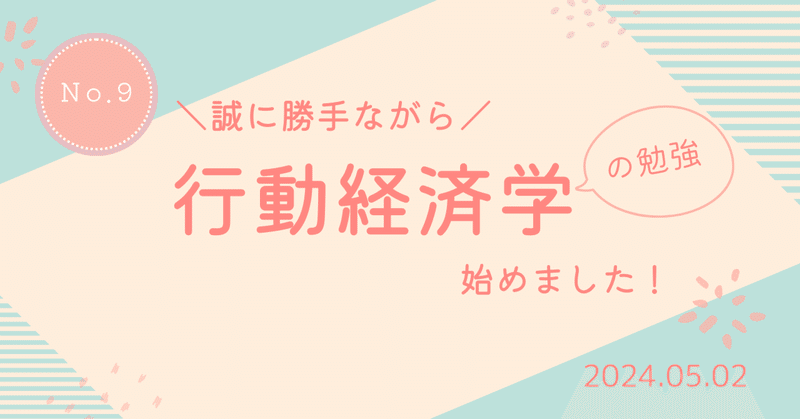
思考には2つのモードがある

速い思考、遅い思考
行動経済学で考えられている人間の非合理的な行動には法則があるのではないか?この法則に着目したのは特徴なのだが、そもそも行動経済学の”行動”とは心理学の”行動主義”からきている。
2002年ノーベル経済学賞を受賞したのは、心理学者のダニエル・カーネマン。(あれ、この方、ほんの先日2024年3月27日に亡くなったんだ💦)
著書『Fast&Slow』の中で、わたしたちには「速い思考」=システム1と「遅い思考」システム2があると述べたのだと。
速い思考=システム1
無意識的であり、コントロール不能、一度発動したら止められない
その代わりに考える努力が要らないので”楽”
印象で感じたり、連想が得意
バイアスがある
遅い思考=システム2
意識的であり、コントロールが可能
システム1で答えが出せないときに発動する
考えるには注意力がいるので、エネルギーを使う”疲労”
論理的で統計的、思考が得意
最終決定権はシステム2が持つ
二重システム理論
人は判断をするとき、いずれの2つのシステムの内のどちらかを使っている。それぞれ特徴があるので、どちらが良いとか悪いとかではないが、だいたいのことをシステム1で処理しているのはわたしだけ?
Q : バットとボールの合計金額は1ドル10セント、バットはボールよりも1ドル高い。ボールの値段はいくら?
10セント! と即答してしまったあなた、残念。正解は5セントです。
少し考えれば分かることなのに…と落ち込む必要はありません。実はハーバード大やプリンストン大といったアイビーリーグの名門校の学生ですら、50%以上が「10セント」と答えたんですから。
あまり深く考えないで、ちゃちゃ~っと片づけたい場合システム1を使っているが、しっかり考えるとできない問題じゃないんだよね。
直感で答えているのだが、認知バイアスによる思い込みで間違ってしまっている。理性でしっかり考えると間違えないんだろうけどね。時間がかかる。もし、これが人生を大きく変える資格試験とかだったらしっかりと取り組むんだろうけど、「だって忙しいから…」なんだよな(笑)
参考資料
・Udemy はじめての行動経済学 丹羽亮介講師
・「速い思考」と「遅い思考」 ノーベル賞学者ダニエル・カーネマンが解き明かす 「ファスト&スロー」という我々の脳の習性 | データで越境者に寄り添うメディア データのじかん (wingarc.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
