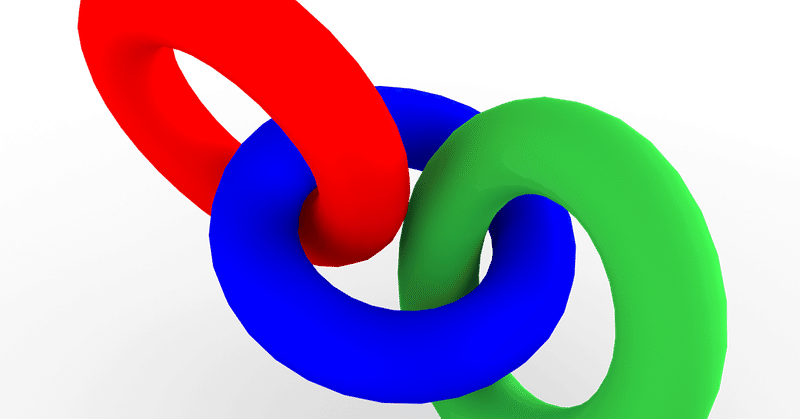
発達障害の併発について
発達障害併発はわりと普通にあること?
私は以前から複数の発達障害を併発している人は、とても多いのではないかと思ってきました。数年間、ツイッターを利用してきた経験から見ても、発達障害アカウントの半数近くは、併発タイプ(ASD+ADHDのタイプが多い)という印象です。
ASDやADHDの症状が弱~強のスペクトラムであるのと同様に、ASD・ADHD間も、ASD単発タイプとADHD単発タイプを両極とするスペクトラムに分布しているのだと思います。むしろ、純粋なASD・ADHD・SLDの方は少ないのかもしれません。
また、発達障害に20年以上関わっている精神科医師・医学博士の本田秀夫氏の著作「発達障害 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち」においても、発達障害を併発している人たちは多くいるにもかかわらず、その理解や対応は間に合っていない旨が書かれています。
併発特性の出方は実に様々
発達障害の併発は、大きく分けて以下の3つのタイプがあると思います(ここでは、ASDとADHDの併発について考えます)。
①どちらの障害も強く出るタイプ
②一方の障害が他方の障害より強く出るタイプ
③どちらの障害も弱く出るタイプ
①はどちらの障害も症状がはっきり出るのでやっかいです。ですが、対処法もそれだけに明確です。
②は私の印象では、一番多いタイプだと思っています。私の場合は、ASDがメインで、ADHDがサブの障害です。数字で表せば、ASD:ADHD=7:3といった感じでしょうか。このタイプでやっかいなのは、自分のメインの障害についての自覚はあるけれど、サブの障害については自覚がないことです。また診断がついていない場合も問題です。こういった場合、生きづらさは①以上になりえます。
③は特性の出方が弱いので、他の2つのタイプに比べて、生きづらさはましなケースが多いでしょう。しかし、場合によっては、①・②以上の生きづらさを抱える人もいると思われます。例えば、個々の障害特性が弱いがゆえに、ASD・ADHDの診断が下らず、必要なサポートを受けられないというケースです。また、そもそも本人が発達障害の自覚がない場合、困難な事態となりえます。
併発は単発より生きづらい
敢えて併発タイプを3つに大別してみましたが、併発の発現の仕方は無数のパターンが考えられます。発達障害の本は、きっちり、ASD・ADHD・SLDに分けて解説していますが、そんな教科書通りの説明にしっくりこない人も多いのではないでしょうか?
実際は「対人関係で困っているが空気が全く読めないわけではない、こだわりの数は少ないが強め、不注意が目立ち、聴覚過敏がひどい・・など、障害間の枠を超えて特性が強弱バラバラに現れるのが発達障害の実状なのだと思われます。
発達障害の併発は単発より生きづらい・・・これはまぎれもない事実だと思います。いわゆる発達障害の3層、バリ層・ギリ層・ムリ層で言えば、バリ層(特性を活かしてバリバリ働けるタイプ)は発達障害の単発タイプの人達(純粋なASDや純粋なADHD)で占められており、多くの併発タイプはギリ層(ギリギリ社会適応しているタイプ)、ムリ層(社会適応が無理に近いタイプ)なのでは?、と個人的には考えています。
併発(ASD+ADHD)に長所はあるのか?
ASD・ADHD併発だと、ASDの集中力がADHDの不注意特性で弱まったり、逆にADHDの行動力がASDのこだわりの強さで制限されたり、と一見マイナス面しかないように思われます。
しかし、着眼点や発想力についてなら、単発タイプより優れているかもしれません。併発であっても、ASDのシングルフォーカス特性のおかげで、細部の違いによく気づきます(着眼点)。ADHDの注意散漫も、色々な方向にアンテナが張られているぶん、発想力につながっているとみなせます。個人的には、この2点の組み合わせが併発の長所ではないかと考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
