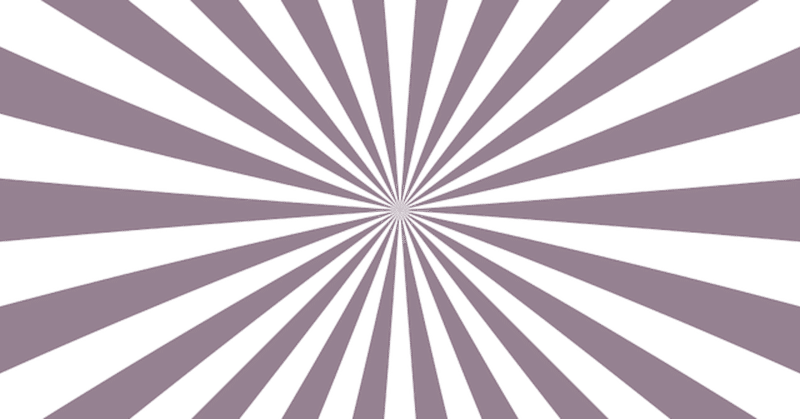
ASDのシングルフォーカス特性について
さて、今回はASDの本質的な特性であるにも関わらず、なぜか話題になることの少ない(・・と個人的には思っている)「シングルフォーカス特性」を取り上げようと思います。
シングルフォーカス特性とは?
シングルフォーカス(以下SF)とは、注意が細部に集中して、物事の全体像が把握しづらくなるASD特性です。ASDの興味の狭さの元になる「木を見て森を見ず」の認知傾向でもあります。SFがあると、ある部分に注意を向けると、別の部分や全体との関係が掴みづらくなります。
この用語の由来は、精神科医の米田衆介さんの「アスペルガーの人はなぜ生きづらいのか」という本にありますが、SFという言葉はツイッター界隈でもよく使われています。ちなみに、SFは「弱い中枢性(全体性)統合」という自閉症の理論が背景にあります。よろしければ、各自で調べてみてください。
SFの問題点①:視野が狭くなる
SF1つ目の問題点は、視野が狭くなることです。SFがあると、注意を向ける範囲が狭くなり、広い範囲を見渡すことができなくなります。
例えば、アマゾンでショッピングしている時に、これだと思う商品を見つけたら、もっといいものがあるかもしれないのに、その商品に注意が囚われます。その結果、他のものを探したり調べたりすることなく、注文のボタンを押してしまうことになります。
また、SFがあると、一つの考え方・立場しか見えないのも特徴です。東京オリンピックに賛成なら、反対意見には見向きもしません。カジノに反対なら、賛成意見を検討することはまずありません。
つまり、SFがあると、一度ある考え方を持ったり、ある立場を取ると、
そこだけにこだわり、柔軟な思考ができない傾向があります。
SFの問題点②:関連付けができない
SF2つ目の問題点は、物事の関連付けがうまく行かないことです。物事には、当然の順序や、明白な因果関係などがありますが、SFがあると、それが把握しづらくなります。
例えば、僕は以前アルバイトでピッキング作業をしていたのですが、そこでは、ピッキングした商品は梱包して、出荷する流れでした。なので、ピッキングしたものは、パレットに積んで、エレベーターで下の階へ下げなければなりません。ですが、僕はピッキング作業と出荷作業の2つが頭の中で関連付けられていなかったので、集めた商品をエレベーターで上の階へ上げるというアホな間違いを犯してしまいました。
つまり、SFがあると、物事を単発、単発で認識してしまう傾向が出るので、「Aをした後は、当然Bをするよね」という、普通の人にとっては自明の流れが分かりづらくなります。
SFの問題点③:人の話が分かりづらい
SF3つ目の問題点は、人の話が分かりづらいことです。前のトピックで、関連付けが難しいと述べましたが、これは一人で考えるときだけでなく、人の話を聞くときも同じです。
SFがあると、注意が一点に向きがちになるので、話の要点同士の関係を理解するのが難しくなります。話に分からないところがあると、その一か所に注意が集中して、他の箇所を聞き逃してしまうこともよくあります。
実際、アルバイトや仕事の指示で、長めの説明受けた後、他の人はすぐテキパキ動き出すのに、ASDの人は自分だけ何をしていいのか分からないというのは、よくある光景だと思います。
追加説明:シングルレイヤー特性とその問題点
ちなみに、ASDにはSF特性と似ているシングルレイヤー特性(以下、SL)というものもあります。SFは今まで言ってきたように、1つの対象に注意が集中することですが、SLの方は1つの対象にも色んな性質や側面があるにも関わらず、それを把握しきれない特性のことです。
言い換えれば、シングルレイヤーとは、対象(もの)は通常、様々な層(マルチレイヤー)から成り立っているにも関わらず、それを1つ(シングル)または少数のレイヤーでしか認識できない特性と言えます。
例えば、新しい洗濯機を購入することに決めたとします。その場合、実際に買う前に、普通は「値段・機能・デザイン・色・耐久性・保証期間」など、色々な項目を比較検討するはずです。しかし、SL特性があると、そこに検討漏れが生じやすくなるということです。以上をまとめると、
シングルフォーカス特性がある → 広い範囲で考えるのが苦手
シングルレイヤー特性がある → 複数の側面・条件を考えるのが苦手
この2つは似ていますし、区別が曖昧な部分もありますが、一応、SLの方も紹介しておきました。では、SFの方に話を戻します。
SFの長所について
次に、SFの長所について話します。これは何が得意なのかによって違いが出てきますが、基本的には、細かいところに気づく能力と言えます。僕自身を例に出すなら、言語優位のASDですので、文章には割と敏感です。
例えば、複雑な文でも、文法的に分析するのは得意です。言語優位の人なら、文章の推敲・校正が上手い人は多いと思われます。視覚優位であっても、やはり、細部への注意力がポイントになるでしょう。
SF/SLへの対処
最後に、SF/SLへの対処法について、原則的なことを述べておきたいと思います。まず、物事に取り掛かる前に、とりあえず立ち止まる癖や、できるだけ広い範囲・複数の条件で考える習慣をつける。目の前のことだけでなく、先の見通しや全体像を意識するのが重要です。
あとは、視覚化・言語化を取り入れます。ASDだけでなく、発達障害の人にとって、「紙に書いて考える」は有力な問題解決方法です。紙の代わりになるアプリでもいいでしょう。
最後に言えるのは、そもそも、全体的な状況を把握して、すぐ判断する事態は、できるだけ避けるのも大切かなと思います。
この記事を読んでいただき、ありがとうございます。
もしよろしければ、「スキ」を押してもらえると、幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
