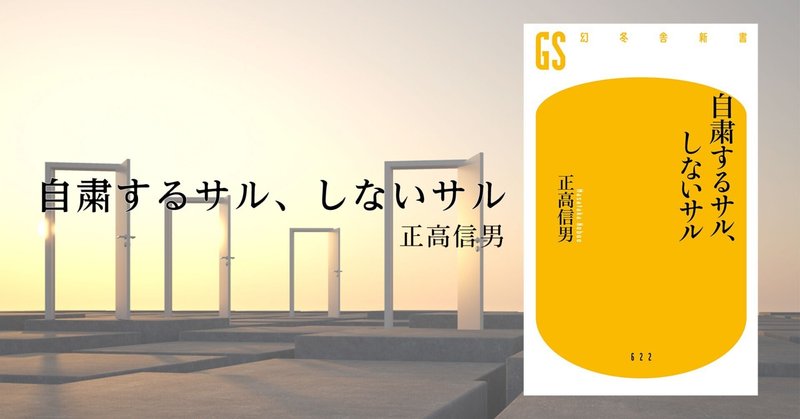
なぜ感染リスクが低い人ほど「Go To」に反対するのか? #4 自粛するサル、しないサル
新型コロナ危機で生まれた、「自粛派」「反自粛派」の対立。霊長類学者の正高信男さんによれば、前者は本能的に感染症を怖がる「サル的」で、後者は理屈で恐怖感を抑制できる「ヒト的」だそう。「ヒト的」のほうが進化形ですが、命を守るうえでは「サル的」のほうが合理的とも……。
そんな正高さんの『自粛するサル、しないサル』は、霊長類学の観点から新型コロナをめぐるできごとを考察したユニークな「コロナ文化論」。なぜ対立は生まれるのか、はたして両者はわかり合えるのか、ぜひ本書で考えてみてください。
* * *
多くの批判にさらされた「Go To」
「Go Toトラベル」キャンペーンをめぐる騒動にも、それは反映されています。周知の通り、コロナ禍で冷え込んだ観光事業を活性化するため、政府が景気回復の目玉として打ち出した政策です。

旅先で宿泊すると、宿泊代が値引きされ、なおかつ現地で現金代わりに使えるクーポンをもらえたりする。評判になる半面、旅行客の移動がコロナの感染拡大を助長しているという批判にも、さらされることとなりました。
政府は最初から一貫して、拡大を助長しているという批判はあたらないというスタンスで、政策を進めました。ところが2020年11月から感染の第3波が激しくなり、12月を迎えます。感染者は減るどころか増加を続け、年末年始が見えてきました。
そして12月14日、突然に12月28日から2021年1月11日までの、「Go To」の中断が宣言されることとなったのでした。
その理由はいたって明白。直前に発表されたマスコミ各社の世論調査での、内閣支持率の急落が原因でした。どこの発表をとってみても、約60%であった数値が40%台にまで落ち込んだのです。
「Go To」に対する批判であることは明らかなように見えました。少なく見積もっても、1000万人の日本国民が批判に回ったと推測される数字です。
むろん、「Go To」を使って旅行しようと考えている人々が、政策推進に反対するはずがありません。使うつもりのない人々が反対しているのでしょう。では、「Go To」の何がそんなによくないのか?
渦中にいる人ほど冷静に対処できる
旅行客の移動によって、感染が拡大するというのです。日本で感染者が集中しているのは東京や大阪という大都市圏です。「Go To」を利用するのは、金銭的かつ時間的にもゆとりのある富裕層で、これまた東京や大阪という大都市圏に、多くは居住している人々にほかなりません。

つまり、そういうところの住民が観光地をかかえる地方へ行くと、ウイルスをうつすのではないか、だから移動するな(来るな)というのが批判のメッセージと解釈できます。これはつまるところ、他都道府県ナンバーの自動車を見て、抗議の文書を貼り付けるのと大差ありません。
そもそも、鉄道車内や飛行機機中での感染リスクは低いとされています。旅行客が観光地をめぐったところで、地元の人々とどれだけ接触の機会があるのか、それによってどれだけ地元にウイルスが持ち込まれるのか、大変疑問です。しかも地元でも、接触するのはたいていは観光に携わる人々ではありませんか。
私は今、この文章を2020年末に沖縄で書いています。沖縄県は、感染がかなりおさまりつつあるというのが、地元のおおよその印象です。観光業の人々は年末年始に東京から、大挙して旅行客がやってくると期待していました。
ところが「Go To」を止めるという。「なんで」というのが、おおよその感想です。感染リスクの高い人が、かまわないと考えているのに、当事者でないリスクの低い人が、けしからんというのです。
自分自身はコロナ禍の渦中にいないという人、つまりそれほど感染する機会がないという人ほど、コロナ感染への嫌悪は強いのです。感染のリスクを背負わないと生きていけない人ほど、冷静に現実を直視できます。
かたやリスクから逃れていると、ひょっとすると地元の観光業に携わる人々をすら、内心では、いまいましく感じるようになるかもしれないのです。
それが、サルとしてのヒトに備わった天敵への嫌悪の本来のあり方なのです――君子危うきに近寄らず――。他所者に愛想を振りまきやがって……となる。
◇ ◇ ◇
連載はこちら↓
自粛するサル、しないサル

