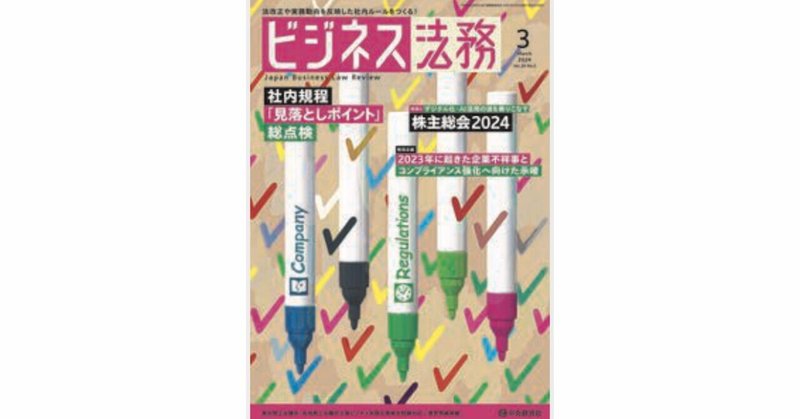
ビジネス法務・2024年3月号
2024年3月号のビジネス法務では、企業内弁護士として知っておくべき重要なトピックが多数取り上げられています。この記事では、その中から特に注目すべきポイントをピックアップし、企業法務の仕事にどのように活かせるかについて考えたいと思います。
【地平線】法務部員はなぜ自社事業を把握すべきか
2024年3月号で、普段私が社内弁護士として働く際に最も意識していることを言語化している記事がありました。
『地平線:法務部員はなぜ自社事業を把握すべきか』という記事です。
この記事では、執筆者(少徳彩子氏)の所属する法務部門の事例を通じて、自社事業を理解し、事業部門に寄り添うことの重要性が説かれています。
私自身、法律事務所の弁護士と比較して、企業内弁護士としての仕事の最も面白さと重要性を、「自社のビジネスに最も精通した弁護士になることができる」という点に感じています。
世間には独占禁止法や労働法専門の弁護士、刑事事件専門を謳う法律事務所が溢れています。
一方で、「特定のビジネスに最も精通した弁護士」になれるのは、その企業に所属する企業内弁護士をおいてほかにいません。
どれだけ外部の顧問弁護士として顧客企業に密接に関わっても、企業内弁護士以上にその事業を深く理解することは不可能です。なぜなら事業は「人」が作るものである以上、内部の複雑な人間関係や他部門を含めた組織の役割まで理解しなければならないからです。
そして、法務部員という組織の一員としてビジネスを事業部門とともに成長させることに貢献できることが、企業内弁護士の醍醐味だと感じています。
そのためには、企業法務に関する幅広い法律知識や組織人としての成熟した振る舞いが求められることになります。
最も重要なのは、以下で筆者が述べるようなマインドであると感じました。
担当する部門や事業を正しい方向に導くために必要なのは、①その健全な成長へのコミットメント、②その部門の仲間との強固な(耳障りなことでも聞いてもらえる)安心感、そして、③戦略や方向性、その実現に向けた課題や対策についての圧倒的な理解である。
【特別企画】2023年に起きた企業不祥事とコンプライアンス強化に向けた示唆
特別企画では、「2023年に起きた企業不祥事とコンプライアンス強化に向けた示唆」が取り上げられています。
この記事では、昨年大きなスキャンダルとなった「ビッグモーター社の保険金不適切請求(過剰修理)事件」、「旧ジャニーズ事務所の創業者性加害事件」、「日大アメフト部員による大麻取締法違反事件」を参考に、前2社の事例では、問題の企業だけでなくその取引先企業(ビッグモーター社と取引を続けた保険会社や性加害を知りつつタレントを起用したメディア各局)のコンプライアンス問題や社会からの批判、日大の事案では、学生の薬物使用に加えて日大執行部の後ろ向きな姿勢に批判が集まったことが指摘されていました。
昨今では、企業不祥事が起きた場合には、当該不祥事とその当事者だけでなく、むしろ不祥事に対する経営陣のスタンスや取引先にまで社会の目が向けられることに注意しなければならないことがわかります。
それ以外にも、連結子会社の不祥事に関連してグループガバナンスや、資本効率性の向上のため自己株式の取得に関する法令規制違反といった事例、さらに、生成AI規制にまつわるリスクといった幅広いトピックが取り上げられています。
このように、企業法務に携わる者として押さえておくべきコンプライアンスリスクが事例とともにまとまっており、大変参考になりました。
余談ですが、筆者が最初に以下のような注釈を加えているのが個人的には印象に残りました。
なお、本校作成にあたり、下書きを含めてChatGPTは一切使用していないこと付言する。
これからは、不正リスク管理の観点からも、文章の書き手は生成AI利用の有無を宣言すべき時代が来るのでしょうか(笑)
※ちなみにこのブログ記事は校正にChatGPTを利用しているのでご注意ください。
【特集2】デジタル化・AI活用の波を乗りこなす 株主総会2024
2024年3月号では、AI技術を含むデジタル化がすすむ中で、株主総会の今と未来について特集が組まれていました。
その中で特に面白いと思ったのは、「生成AIがもたらす株主総会実務への影響」(生方紀裕氏・著)です。
ChatGPTをはじめとする生成AIは、我々法務の仕事と親和性が高いといわれています。
私自身も、情報検索(業界情報や文献の検索)・情報の整理(収集した情報の取捨選択や複雑なビジネスのカテゴライズ)・情報の生成(契約書や規程、メモランダムの作成)といった法律業務は、生成AIをうまく使うことによって大きく生産性が向上することを実感しています。
この記事では、株主総会実務に焦点を当てて、どのように生成AIを使うことができるか、そして将来の可能性について、株主総会の事前準備、総会対応の場面において、活用例や注意点が解説されています。
私もChatGPT4を業務に活用していますが、重要な点は、生成AIの有用性だけではなくその限界に常に注意を払うこと、そして、アウトプットの正確性を自身で確認し、その活用には人間である「自分自身」が責任を持つことだ、と考えています。
例えば、よく言われるように、生成AIは虚偽と真実の情報の区別に弱く、アウトプットされる情報のソースや真実性を常に確認しなければなりません。
そのためにも、生成AIそれ自体に精通することだけでなく、活用する分野(例えば法律実務や判例知識)において、自分自身も生成AIによるアウトプットの真偽を確認できるだけの十分な知見を蓄えることが非常に大切だと感じています。
この記事は、株主総会準備・運営という場面において、どのように生成AIが活用できるか、一方で、その限界と注意点をわかりやすく解説されており、法務の生成AIの活用についての一般的な示唆が得ることができます。
2024年3月号のビジネス法務・まとめ
今回は、2024年3月号のビジネス法務から気になった記事をピックアップしました。
今回取り上げたトピック以外にも、企業法務の仕事において重要な『社内規程「見落としポイント」総点検』といった特集も組まれており、実務において参考になる記事が多くありました。
生成AIといった最新のトピックは書籍を待つよりも、ビジネス法務といった専門誌の方がタイムリーに情報に触れることができます。
ビジネス法務を定期的にチェックすることは法改正情報、ビジネス法に関する知識のアップデートにおすすめです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
