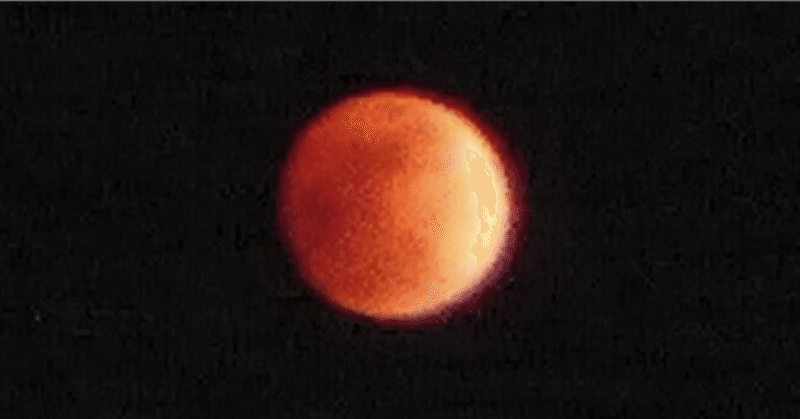
小説 月に背いて 9
私達は家の中に入った。冷え切った空気が全く動かない部屋に、風の音だけがごうごうと鳴り響いていた。
「勝手に来て悪かった。返事がないなんて初めてだったから、心配になって」
先生はダウンジャケットを脱ごうとしなかった。ダウンの下は黒のジャージを着ている。いくら彼がいつも学校でジャージを着ているとはいえ、この時間にこの格好で私の家に来ているところを見られたら、もはやなんの言い訳も出来ない。
「今日、美希達と飲んでたの。恭子の結婚式の二次会で井川くんに会って、また皆で集まることになって」
うつむいて微動だにしない彼は、じっと床を見つめたまま何も言わなかった。
「ラインの返事が出来なくてごめんなさい」
そう言うと、顔を挙げて私をまっすぐ見た。
「別に謝ることないだろう」
全く抑揚のない声だった。彼の目はまた透明になっている。もう私の姿も見えていないに違いない。
「怒らないの?」
再びうつむいて目を閉じた彼は、深いため息をつく。
「何を怒ればいいのかわからない」
なんの感情も籠っていないその言葉を聞いて、ひどく悲しい気持ちになった。
「私達付き合ってるんでしょう?だったら普通怒るでしょう?どうして怒らないの!?」自分でも驚くくらいの大声を出していた。
痛いくらいぴんと張り詰めた空気が流れ、沈黙が続いた。外の風の音が私の耳元で響き、窓がコツコツと鳴る音はまるで誰かがノックをしているように大きくなっていく。
私は自分の気持ちを洗いざらい全てぶつけてしまいたい衝動に駆られた。私の事だけを見て欲しい。でもそんな事を言ってどうなるというのだろう。この人は真面目だから、きっと私の気持ちを正面から受け止めようとして、真剣に向き合ってはくれるだろうけど、重すぎて受け止めきれずに、さらに自分を追い込むのが目に見えている。余計に苦しめるだけだ。本当は私のことが好きなのではなくて、ただ私に逃げているだけなのだから。
涙が溢れ落ちた。頬を伝う涙をぬぐうこともしないでただ先生の顔を見つめていた。
彼は両腕を伸ばして私の頭を抱き、「ごめん」とつぶやいた。
「どうして何も言ってくれないの?私の事を好きじゃないの?」
自分が放った言葉が空しく虚空を漂った。嘘でもいいから私のことを好きだと言って欲しい。もうなんでもいい。なんでもいいから、胸にぽっかりとあいた空洞を満たして欲しかった。
「好きだから会いに来てる」と彼は言った。とても苦しそうな、かすれた声だった。
こうして抱き合えば、お互い何もなかったことにしてしまえる。そうやってやり過ごすしかこの関係を維持する方法はないのだろうか。行き場のない苦しさが胸を巣食ってこのまま消えてしまいたくなった。どうする事も出来ないくらいこの人に魅かれるのは何故だろう。好きでなければ、これほど好きでさえなければ、苦しまずに済むのに。もっと上手くやれるのに。
結局先生はその晩家に泊まった。私は彼の肌がいつもより熱く感じられて何も考えられなくなった。そんな自分が怖かった。それでもお互いの温もりを感じ合うと何かが満たされて、心の中の熱風は過ぎ去ったけれど、それと同時に冷たい虚しさが塊になって胸の奥に残った。
夜中に夢を見た。夢の中で私は自分の家の和室に寝ている。カーテンの隙間から淡い月の光が差し込み、不思議な輝きを放っていた。隣には先生が横たわっている。寝息もたてずに死んだように眠っている彼の首に、私はそっと両手をかけた。どうしてこんな事をしているのか自分でもわからない。わからないけれども、どうしてもそうしないわけにはいかなかった。すると彼は目を開けて「殺せ」と言った。そこで目が覚めた。
飛び起きて周囲を見回した。冬なのに全身に汗が滲んでいて、鼓動は激しく呼吸も苦しかった。隣に横たわる彼はやはり寝息もたてずに死んだように眠っている。枕元の目覚まし時計を見るとまだ朝の四時だった。夜中に何度も目が覚めて全く眠った気がしない。頭が重くて目の奥がひどく痛む。
再び彼の寝顔を見た。私が飛び起きても全く目を覚まさない。胸の奥にある塊をはっきりと自覚し、憎悪に似た感情がどこかから湧き上がった。それが全身に広がり、骨身にまでじわじわと侵食していくのを感じていた。
なんとなく彼の首に触れると、頸動脈がどくどくと脈打っている。その時風が大きく窓を叩きつけた。ノックをするようなその音は、それから朝までずっと規則的に続いていた。何かが私達を迎えに来ているように思えてならなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

