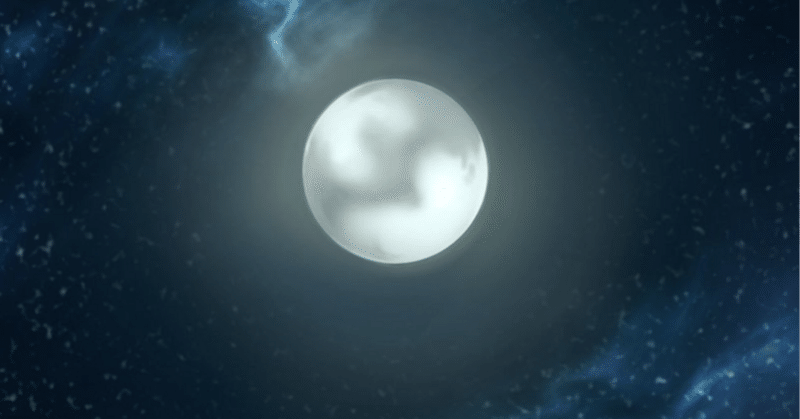
小説 月に背いて 11
井川くんと神社へ行った翌週、佐田先生が車の衝突事故にあった。一時停止をせずに優先道路に進入してきた車に助手席側から衝突されたようだ。車は廃車となるほど損壊したが、彼自身は軽い打ち身だけで済んだ。私はそれから全く事故を目撃しなくなった。
しばらく会わないようにしようと先生に伝えなければならない。そうしないとさらに悪いことが起こるという予感が頭に纏わりついた。とりあえず今は会うのをやめよう。次に会った時必ず伝えよう。そう自分に言い聞かせながらも私は、彼が今ひとりで何を考えているのか想像し、寒さに震えていないだろうかと心配した。
二月最後の土曜日の午後、先生が家に来た。私はその日夜勤明けで、午前中はずっと眠っていた。
私達はダイニングテーブルを挟んで向かい合い、温かい紅茶を飲んでいた。夕食は何を食べたいかと彼は言った。
「話があるの」
人生の終焉かと思うほど色彩を欠いた景色を眺めた。
「私達はしばらく会わないほうがいいと思う。もう連絡してこないで」
背筋が寒くなるくらい冷酷な沈黙が続く。もうどれだけ時間が流れたのかわからない。重苦しい空気が部屋中に充満し、壁掛け時計に目を向けることも出来なかった。
「わかった」
彼は立ち上がり、コートとショルダーバッグを持ってドアの方向へ歩き出した。
ああ、これでいい。これで私と彼の運命はひとりでに決まる。振り返ってはいけない。絶対に振り返るな。私はそう思った。
足音が止まり部屋は再び静寂な空気に包まれた。
「どうして急にそんな事を言うのか教えて欲しい」
驚いてつい振り返ると、彼はドアの前に立っていた。
「お前は本当は何を思っているのか教えてくれ」
冷たい漆黒の瞳が私を貫いた。私はその目を見つめたまま黙っていた。
「言ってくれ!」
先生は大声を出すと同時に右手の拳を壁に強く叩きつけた。ドンという大きな音が鳴り響き、その振動が部屋全体を包んだ。彼がこんな風に感情的になるのは初めてで、思わずその姿を上から下まで眺めた。
「言ってくれないのは先生のほうでしょう!?」
私は大声を出した。
「先生は何も話してくれないじゃない!だから私も自分の気持ちを言えない。私はただ先生が好きなだけなの。でも私達が一緒にいると良くないことが起こる。だから今は距離を置いたほうがいいと思う」
もう自分でも何を言っているのかわからなかった。
彼は両目に悲しい色を浮かべたあと、うつむきながら右手を額に当て、ゆっくりと目を閉じた。私にはその仕草が子供が泣いているように見えた。「良くないことが起こる」とはどういう意味なのか、聞きただそうとする気配は見られなかった。
「家にいると、相変わらず足音や話し声が聞こえる。もう俺は頭がおかしくなってるんだと思う」
「今もずっと続いてるの?」
彼は小さく頷いた。
「俺は、……お前に会いたくなった時だけ連絡するわけじゃない。自分の頭が正常に働いてると感じた時にここに来てる。今なら大丈夫だと思える時だけ来てる。毎回、もう二度とここには来ないと言おうと思うんだ。お前を巻きこみたくないから。俺と一緒にいたってお前は苦しいだろう?」
私は黙って彼の顔を見つめていた。
「何もかも全部放り出して、今までの事を全部忘れて、家も処分して、仕事も責任も棄てて、お前に甘えられたらどんなにいいだろうと思う。でも俺には出来ない。どうしても出来ない。たとえ今の状況が落ち着いたとしても、俺が俺でいる限り、一生出来ないかもしれない。俺はお前を大切にしたいと思うんだ。お前を失いたくない。それなのにどうして、……」
彼は目を閉じ、苦悶に満ちた表情で大きく息を吸い込んだ。
「こんなに苦しいんだろう」
「それは私が生徒だったから?」
「わからない」
彼から視線を逸らした。涙は流していないけれども、私には泣いているように見えた。胸が潰れそうで、もうその姿を見ていられなかった。
「お前がさっき言ったのと同じようなことを妻にも言われ続けた。愛していると言っても信じてもらえないんだ。俺は何かが決定的に欠けているんだな。俺は……」
「先生」私は彼の言葉をさえぎった。
「海に行きたい。これから一緒に行こう」
「今から?」彼は驚いたような声を出した。
「うん」
先生は視線を動かして壁掛け時計をしばらく見つめたあと、私に目を戻して「わかった」と言った。時計は15時を差していた。ここから海までは高速道路を使っても1時間半かかる。今から出発すれば、日没までにはなんとか間に合うだろう。厚手のセーターを着込み、ジーンズを履いて、一番温かいダウンジャケットとマフラーと手袋を準備した。
先生の車で家を出た。彼はもう少し温かい格好をしてくると言い、まず自分の家に向かった。車で15分ほど走ると彼の家に着いた。その家は結婚した時に購入したのであろう、グレーのタイルに覆われた二階建ての一軒家だった。駐車場の隣には小さな庭があり、花壇もあったが何も植えられてはいなかった。家の中に入るのは気が引けたので私は車で待っていた。
ぼんやりと家の外観を眺めていると、懐かしいような、それでいて悲しいような、不思議な感情に囚われた。心の中に流れ込んでくるこの泣きたい気持ちは何なのだろう……、そう思いながら目を閉じた。目を閉じると私は家の中にいた。どうやらリビングのようだ。南側には庭に面した大きな窓があり、中央に座卓が置かれていて、カーテンもカーペットも深い緑色だった。テレビがあって、ベージュの布張りのソファがあって、北側には台所があって……ふと冷蔵庫へ目を向けると、その横から白い猫が姿を現した。
「おまたせ」
車のドアが開く音と先生の声が同時に聞こえた。私は慌てて目を開けた。
「大丈夫か?顔色が悪いけど」
そう言う彼も血の気を失った顔をしていた。
「なんでもない」
車は高速道路を走っている。彼はいつも通り無表情で運転していた。
「先生、事故の痛みは大丈夫?運転しようか?」
「いや、車は派手に壊れたけど俺は案外大丈夫だよ。相手がすぐに自分の非を認めてくれたから示談もスムーズだった。新しい車もすぐに見つかったし、不幸中の幸いだな」
毎日のように事故現場を目撃したことを伝えようか迷ったが、どうしても言えなかった。日没までに海にたどり着かなければいけないと考えている私達は、まるで何かから逃げているような気持ちだった。
高速道路のどこまでも真っ直ぐな車線をじっと見つめていると、瞼が重くなってきた。そのうちに強烈な眠気に襲われて目を開けていられなくなった。
「夜勤明けで疲れてるんだろう。いいよ眠って。着いたら起こすから」
彼の声を頭の片隅で聞きながら、助手席で眠りに落ちた。
浅い眠りのなか夢を見た。
私は知らない家のリビングにいた。いや、でも見覚えがある。ここはさっき見た先生の家だ。窓からの優しい日差しが部屋中を温かく包んでいた。台所に目を向けると、30代くらいの黒髪の女性が白い猫を抱いて立っている。胸の辺りまであるその髪は光沢を放ちとても美しい。この人は誰だろう。じっと見つめていると、彼女も私を見た。瞳の色はぞっとするくらい漆黒で、肌の血色は失われていた。私はゆっくりと目を閉じて、深く深呼吸をした。目を開けると、彼女の美しい黒髪はほとんど抜け落ちていた。まだらに残った髪の隙間に、肌色の頭皮が見えている。私はその姿を漫然と眺めていた。
「着いたよ」
先生の声で私は飛び起きた。
「え?」
目を覚ました時、涙を流していた。私は随分と遠くの景色を見てきたのだろう。もう少しで掴めそうだったのだ。夜の底の正体を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

