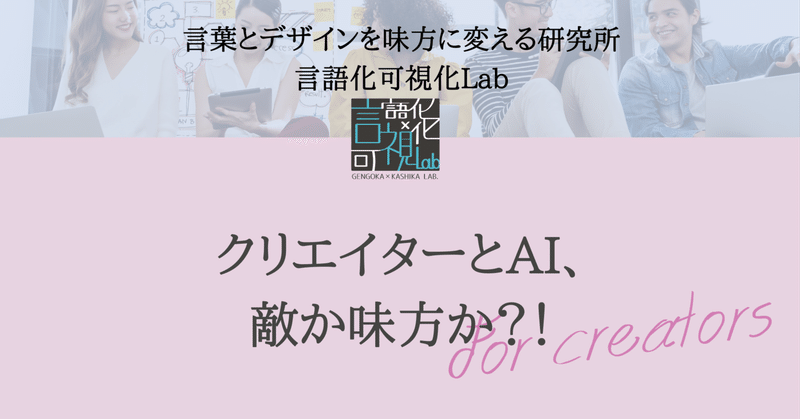
クリエイターとAI、敵か味方か?!
今回のテーマは、今話題の「AI」について。
AIの進化はめざましく、私たちの生活のあらゆる場面で活用されつつあります。さらに、クリエイティブな分野においても、AIはすでに大きな影響を与え始めています。
AIは、クリエイターにとって敵か、それとも味方となるのか。
AIがクリエイターに与える影響について、さとみともみじのフリートークでお届けします。

言語化可視化ラボは、デザイナー岩崎さとみとライター本田もみじの「ブランディングとマーケティングの研究所」。クリエイターメンバーと一緒に、日々ブランディングとマーケティングの研究を行っています。
◆2人主宰のスクールはこちら
AIはクリエイターにどう影響する?
さとみ:
今日はクリエイターとAIの関係についてお話していきましょう。
もみじ:
絵や漫画、文章を自動で生成できるAIが登場したことは、クリエイターの仕事にも大きく影響するのではないでしょうか。
さとみ:
AIといってもいろいろな種類があるので、使いこなせないといけませんね。
もみじ:
私は今のところ使っていませんが…。
正直なところ、自分の手元の仕事よりも、AIが社会に与える影響の方が気になります。特にクリエイターの仕事や、世界のビジネスのあり方がどう変わるかに興味があります。AIがクリエイターの仕事を奪ってしまうのか、それとも新たな表現を生み出すのか…、時代がどう変わるのかを俯瞰的な視点で考えていきたいです。
さとみさんはAIを使っているのですか?
さとみ:
新しいツールは少し苦手なので、あまり積極的に使ってはいません。でも、中には「これはすごい!」と思うものもあるので、少しずつ使い始めています。
もみじ:
どんなに素晴らしい技術でも、使われなければ廃れてしまうこともよくありますよね。生成系AIのChatGPTなどは、ビジネス利用が期待されています。
いずれにせよ、商業クリエイターにとっては大きな影響を与えるでしょう。今後、どのように関わっていくかを考えていく必要がありそうです。
AIを活用した新たな価値の提供が必要
さとみ:
AIは学習によって発達していきます。ですから、初期段階では理解が不十分な場合や、指示の出し方によって回答が異なる場合があります。人間の脳も、良い質問をすれば良い答えが返ってきます。
AIに質問するのも、人間に質問するのも同じですね。
たとえば、化粧品販売のLPを作成する場合。ペルソナである40代女性の肌の悩みをChatGPTに尋ねると、一般的な悩み事を知ることができます。さらに、その悩みを40代女性の口調を用いてLPの文章を書いてもらうこともできます。
今まで時間をかけてネットで調べたり、自分で考えて書いていたりしたものに、瞬発力よく応えてくれます。ChatGPTはうまく活用すれば、LP作成の経験が浅い人や、時間をかけずにLPを作成したい人にとって、便利なツールとなります。
もみじ:
すごい技術ですよね。
ところで、AIを使ってLPを作成する人はクリエイターと呼べるのでしょうか?
善し悪しは別として、新しい肩書きが必要だと私は思います。
さとみ:
単にAIを使うだけではオペレーターではないでしょうか。
AIを使って何かを生み出してはじめてクリエイターだと私は考えます。
もみじ:
今までのクリエイターは、センスによって評価されていた部分がありましたよね。そのセンスは、AIが担っていく部分と人間にしかできない部分に分かれていくのでは?
さとみ:
その通りだと思います。
クリエイターの対応ジャンルは、時代によって大きく変化します。紙の媒体が減ったことで、グラフィックデザイナーの需要が減少したように、今後もデジタル化や自動化の進展にあわせてクリエイターの職業は変化していくでしょう。
クリエイターは時代に抗うのではなく、AIを活用して新たな価値の提供を考えるべきです。AIではできないようなオリジナリティや感性、人間ならではの表現力などを磨くことが大切なのではないでしょうか。
生き残るためには、時代の変化に対応し、新たな価値を提供していくための努力が必要です。
AIの進化は新たなチャンス!
もみじ:
AIの進化でクリエイティブな作業のコストが下がるため、クリエイターへの報酬も一時的に下がる可能性があると考えています。
さとみ:
AIを使えば誰にでも簡単に制作できる程度のデザインや文章にはお金を払わなくなるでしょうね。AIに代替される可能性がある仕事に携わっているクリエイターは、新たな価値創造について急ぎ考えないと…。
先ほどのLPを例にあげると、AIによって誰でも簡単に、ある程度のクオリティのLPが作成できるのですから、マーケティングの知識や経験が豊富なライターでない限り、LPの仕事獲得は難しくなります。
もみじ:
うーん、確かにクリエイターの仕事がなくなるという懸念もありますが、AIの質問力が未熟な段階では、そのようなことは起こらないと思っています。
AIがクリエイターの仕事を引き受けるには、顧客のニーズや要求を正確に理解し、顧客へ適切な質問ができなければなりません。AIはまだそのレベルに達していません。
ですから、ヒアリング型のクリエイターの仕事は、なくなるどころか、ますます重要になっていくと思います。
ただしAIの進化次第で、今後1年以内に代替される可能性もある。AIが顧客の潜在ニーズを掴み取る力をつけ始めると、少し怖いなと思っています。
さとみ:
AIの進化は速いので、今からしっかりと準備しておきたいですね。
人間ならではの感性や表現力を磨いたり、AIと連携して顧客の潜在ニーズをより深く理解したりするなどの取り組みが必要になります。また、AIの最新技術を学び、柔軟な対応力を身につけていくことも求められるでしょう。
また、新たな価値を創造できる仕事も存在します。自分の強みやスキルを分析し、AIとどう連携していくのか検討することが大切です。
AIの進化は、クリエイターにとって危機であると同時に新たなチャンスでもあります。AIをうまく活用できれば、クリエイターはこれまで以上に社会に貢献できるようになるのではないでしょうか。
AIの登場は自分の価値を見出す良い機会
もみじ:
クリエイターは自分がどういう立ち位置で仕事をしていきたいのか、しっかりと考えておくことが大切ですね。
さとみ:
AI自体のクオリティも高くなっていくでしょうから、絵が得意だったり、文書を書くのが好きなだけでは、仕事として成立しなくなるでしょう。
もちろん好きなことを仕事にしたい場合は、AIの進化に対応しながら自分の強みを活かして、新たな価値を創造していけばよいのです。
ただしビジネスとして成功したい場合は、AIの進化に対応して、効率的に、質の高いクリエイティブを提供することが重要になっていきます。
もみじ:
クリエイターは自分の仕事の価値を、より明確に伝える必要が出てきますね。AIと何が違うのか、何を効率化できるのか、どのようなスタイルで仕事に取り組んでいるのかを言語化しないといけません。ただ言われた通りの仕事をしているだけでは、AIに負けてしまいます。
さとみ:
言われた通りの仕事しかしていないクリエイターは淘汰されるでしょうね。
もみじ:
私は、AIを使わないことに価値を見出していきたいと思っています。もちろん、AIは便利で、私自身も日常生活ではよく使っていますが…。
たとえばフードプロセッサーや電子レンジなど便利な道具があるのに、それを使わないプロ料理人っていますよね。彼らの料理は、コンビニで買える料理とは異なる価値を持っています。
私はAIを使わないクリエイターとして、そのような価値を目指したいですね。AIを使わずにクリエイティブなものを生み出すためには、人間ならではのセンスと技術が必要です。AIでは実現できないようなオリジナリティや温かみのあるアウトプットにこだわりたいです。
さとみ:
結構な職人気質ですね(笑)
もみじ:
AIの進化によって、クリエイティブの生成が効率化されることは間違いありませんから…。クリエイターはAIと共存しながら、自分の強みを活かして仕事をしていくことが求められるでしょう。
さとみ:
その通りだと思います。自分の価値を考えられないと、それを提供できなくなり、仕事の機会を失ってしまいます。
私は、さっさとAIを使いこなしていくことをおすすめします。
もみじ:
どっちにしても、のんびりしてはいられない、ということですね。
いい機会なので、クリエイターさんは自分の立ち位置とできることを考えていきましょう!
このnoteは、Facebook非公開グループ「言語化×可視化ラボコミュ」のライブ配信からクリエイターさん向けの内容をピックアップして記事化したものです。
【この記事を書いた人】
言語化×可視化ラボ コンテンツ開発チーム さとう れいこ
大阪在住のフリーランスライター。取材・インタビュー記事執筆など「書く」だけでなく、撮影、BtoB企業のデジタルマーケティング支援、SEOコンサルなど、コンテンツ制作をトータルサポートしています。カメラマンとしても活動中。
https://twitter.com/reikosatou10111
https://note.com/reikosato/
【クリエイターの皆さまにお知らせ】
さとみ&もみじのペアで、「商業クリエイターのためのオンラインスクール バリューアップカレッジ」を開講中!詳細は以下ページでご覧ください。
【Twitterでは、もみじがライター / クリエイター向けに発信しています】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
