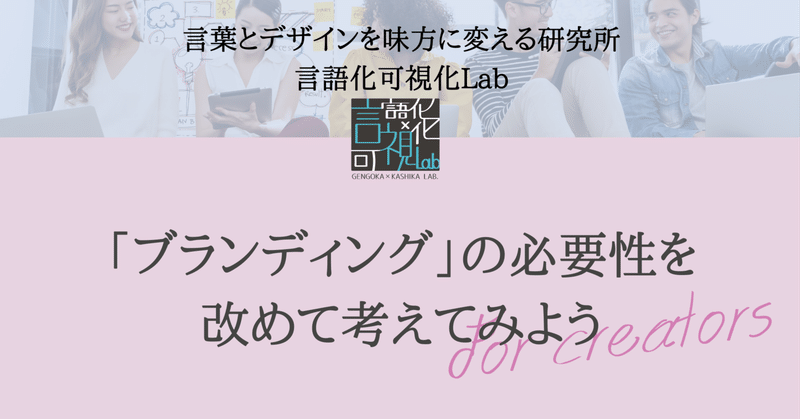
「ブランディング」の必要性を改めて考えてみよう
今回のテーマは「ブランディング」について。
ブランディングとは、提供するサービスや商品のターゲットであるお客さまに共通のイメージを形成するための施策です。
ブランディングのプロであるさとみとマーケティングのプロであるもみじが、ブランディングの必要性について、混同されがちなマーケティングとの違いも交えながら語ります。

言語化可視化ラボは、デザイナー岩崎さとみとライター本田もみじの「ブランディングとマーケティングの研究所」。クリエイターメンバーと一緒に、日々ブランディングとマーケティングの研究を行っています。
◆2人主宰のスクールはこちら
ブランディングは3つの要素で構成されている
さとみ:
今回はブランディングについてです。
まず、私が考えるブランディングの定義について簡単にお話ししますね。

私が普段お伝えしているブラディングとは、代替のきかないものや、商品・サービスの価値が世界観として現れているもの。また、それを普及していく行為そのものです。そして、こちらが意図したイメージをお客さまにも共通の認識として持ってもらえることとしています(図1)。

「世界観」とは、自分のキャラクターやビジネス・ブランド・会社・事業などのブランド化したいものに対する、ビジョンや指針、使命、価値観などマインドに関すること(図2 中心の黄色部分)です。
これをしっかりと言語化し、デザインやライティングなどで、ホームページ・SNS・名刺・ロゴ・書籍などのコンテンツを通じて形にしていきます(図2 緑色部分)。そして、その世界観を行動や発信、広告などの普及活動を通して広げていきます(図2 水色部分)。
普及活動が一貫して行われていると、信頼・信用が積み重ねられていきます。一貫性があれば、人は安心するんですよ。
反対に、普段「世界平和は大事だ」と熱く語っておきながらいつも誰かと揉めているなど、発言と行動にズレがある方は信頼されませんよね。
もみじ:
どんなに立派なことを言っていても「いやいや、平和どこいった?」ってなりますね。
さとみ:
ブランディングでは、発言と行動を合わせていく必要があります。
ビジョン・使命・価値観など自分の軸となるものを決めてから、ブランドイメージに反映させていくことを「自分軸ブランディング」と呼んでいて、お客さまに「お金を払うに値する」「信頼できる」と思っていただけたり、「他のものではだめ」と、お客さまの中で代替がきかないポジションを確立できたりすれば、自分軸ブランディングは成功であると考えています(図3)。

ブランディングとマーケティングは似て非なるもの
もみじ:
マーケティングとブランディングは、混同されていますよね。
言葉は知っているけど実態が分からない、とよくいわれます。
さとみ:
そうですね。混同されがちですが、マーケティングとブランディングは似て非なるものです。端的にいえば、ブランディングはマーケティングを不要にするもの、マーケティングはセールスを不要にするもの。
先ほどの図2でいえば、外側から内側へ向かって考えていくのがマーケティング、内側から外側に向かって考えていくのがブランディング。
作っていくコンテンツをどちらに寄せるかによって、結構テイストが変わるんですよ。そのため、2つを混同してしまっていると難しいです。
もみじ:
でも、どちらかだけではダメなんです。マーケティングにも信頼が必要ですし、ファン化もしたいでしょうし。
さとみ:
そうですね。ブランディングだからといって、マーケティングをおろそかにしていいわけではありません。マーケティングはブランディングの一環として存在するもので、逆も然りです。ですから、双方の考え方をしっかり取り入れていかなければなりません。
ブランディングの進め方
もみじ:
想いや発信に一貫性を持たせることがブランディングにおける1つ目のハードルだと思います。どうしても、その時々の考えであったり、その都度製作したコンテンツであったりと、統一感のないものになってしまいがちですよね。
さとみ:
そうですね。実は私のところにリブランディングに来てくださるお客様には、そういう方も多いんです。
たとえば、新しく事業を始めたのだけど既存事業と近い内容ではないからコーポレートサイトをうまくつくれないというお悩みです。でも、そういう方って根っこの価値観は同じであることが多いです。確固たる価値観をもって、つまり自分軸に従って選んだ新事業なので、そこをしっかりと言語化できれば一貫性が出せるのです。
言語化できていなければ単なる散らかった人になってしまうのが困り処ですが…。
もみじ:
一貫性って本当に大切ですよね。
他人にとってわかりにくいものを、伝わるようにまとめる必要がありますが、そもそも自分で決められていないと難しいです。
さとみ:
そうですね。自分のなかで形が決まらないのは単なる情報不足なので、行動量で解決できるケースが多いんですよ。自分で確認する意味も含め、たくさん試し打ちをして、たくさん失敗を経験するのがいいと思います。
もみじ:
自分軸ブランディングのステップはこのステップであっていますか?
1.「私はこういう人だ」という軸を決める
2.自分の軸に合う行動をとる
3.自分の軸を言語化する
4.人にわかってもらえるようにアウトプットする
さとみ:
そのステップであっています。
自分軸は、自分が一番わかりやすく自分の気持ちにフィットした言葉にするとよいでしょう。
また、一度方向性を決めても、自分も成長するしたくさんの言葉に出会いますよね。自分の成長とともに自分の想いや軸も成長するんです。その都度ブラッシュアップしていってくださいね。
成長スピードを上げたければプロに頼ろう
もみじ:
先ほどの統一感の話とも重なるのですが、小さなビジネスを始めたときは時間もお金もありませんから、行きあたりばったりで販促物を作るケースが90%を占めるのではないでしょうか。
フリーランス始めの“あるある”
・500円で安かったから、とりあえず名刺をつくった
・知り合いが安く引き受けてくれるというのでチラシをつくった
・営業をかけられた業者さんでホームページをつくった
・講演会のプロフィールを自分で一生懸命書いた
もみじ:
お金がないからという事情もあるとは思うのですが、ブランディングやマーケティングについて理解度が低いせいで将来のお金を失っている節もあると思うんですよ。
さとみ:
多少無理してでも頑張ったほうがいいところってありますよね。
もみじ:
「自分でできないところはプロにお願いする」という経験を初期にやっておくことで、1年かかることが1か月で実現できるかもしれないんです。
さとみ:
今は無料のデザインツールも沢山あるので、プロでなくてもそこそこのものはつくれます。でも、無料でそこそこのクオリティを出そうと思うとかなり勉強しないといけません。ホームページ制作をプロに依頼すると50〜100万はかかりますが、1年程度で費用を回収できるのであればプロに頼む方が安上がりという考えもできます。
もみじ:
何でも自分でやってみたほうがいいという話を聞くと思うのですが、それは自分が主導してPDCAを回すという意味であって、自分が完成品をつくるという意味ではないので誤解しないようにしましょう!
名刺をつくる場合、500円でつくって、デザインを1ヶ月で5回見直せるのであれば自分でやるのもよいでしょう。しかし1回つくったら1年は使おう、というのであれば、ブランディングやマーケティングに沿ってつくった名刺でない限り、ライバルに遅れを取ってしまうので注意してくださいね。
さとみ:
スピードを上げたければプロに頼んだほうがいいです。その時は、自分がビジネスで成長していくときに誰と一緒に走りたいかを考えるといいと思います。誰に手伝ってもらうかで結果が変わるから、その辺の相性も含めて自分のビジネスを応援してもらう相手を考えましょう。
制作スタッフサイドを巻き込むと、自分よりビジネスのことをわかっている外部の方と繋がりができます。ブランディングは信用が一番なので、スタッフや周りの手伝ってくれる方、協力会社なども自分のブランドを守ってくれるメンバーに巻き込んだほうがいいのです。内側がぐちゃくちゃなのに外側だけ取り繕っていても、いずれボロが出ます。ブランディングは内側から、気持ちからです!
もみじ:
すてきなプロフィール写真を撮ることだけがブランディングではありませんね。
この話は時間内では収まりそうにありません…。
続きはお酒を飲みながら語りましょう(笑)!
このnoteは、Facebook非公開グループ「言語化×可視化ラボコミュ」のライブ配信からクリエイターさん向けの内容をピックアップして記事化したものです。
【この記事を書いた人】
言語化×可視化ラボ コンテンツ開発チーム しまこ
2021年、会社員の傍ら複業ライターとして活動開始。
“自分のことばで誰にでもわかりやすく”をモットーに、ペット・インテリア・エンタメジャンルで執筆中。最近WEBデザインの勉強をはじめました。無類の猫好き。
https://twitter.com/simarisucco
【クリエイターの皆さまにお知らせ】
さとみ&もみじのペアで、「クリエイターのビジネススキルをアップさせる オンライン講座 バリューアップカレッジ」を開講中!詳細は以下ページでご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
