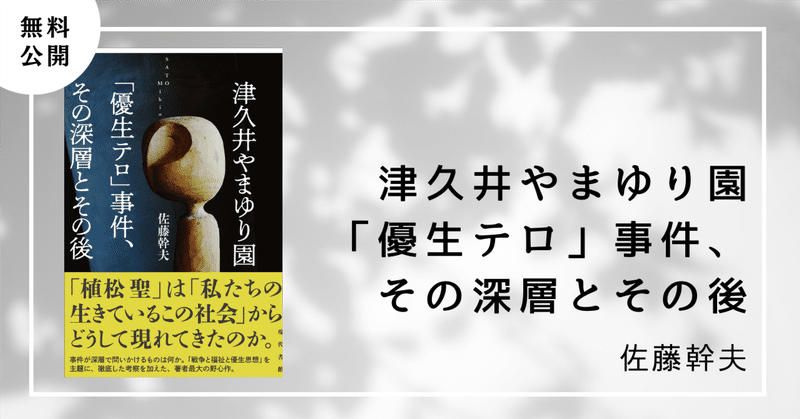
プロローグ 植松被告の短い手紙から読み解く三つのこと(佐藤幹夫)|津久井やまゆり園「優生テロ」事件、その深層とその後
【編集担当者より】2020年3月、津久井やまゆり園事件の犯人に死刑判決が言い渡されてから2年余り、ジャーナリストの佐藤幹夫さんはこの重すぎるテーマをどう描くのか、迷い続けたと言います。「植松聖」は「私たちの生きるこの社会」からどうして現れてきたのか。事件が深層で問いかけるものは何か。浮かび上がったのは、「福祉と戦争と優生思想」という主題でした。そうして書き上げた『津久井やまゆり園「優生テロ」事件、その深層とその後』は、法と精神医学の問題、犯罪論や戦後の犯罪史など、著者が20数年にわたり取り組んできたテーマの集大成とも言える一冊です。2023年7月26日で7年を迎える今日、本書の「プロローグ」を公開いたします。
1 なぜ「疲れ切った母親の表情」なのか
拘置所の植松被告に手紙を出したこと
一度だけ、横浜拘置所に収監中だった植松聖被告・現死刑囚(注1)に、手紙を書いたことがあります。
植松死刑囚については多言を要さないでしょうが、二〇一六年七月二六日未明、神奈川県相模原市の障害者施設、津久井やまゆり園に侵入し、利用者と職員四五名を殺傷したという「戦後最悪」の事件の加害者その人です。
私はこれまで、犯罪加害者の取材にあって、面会に行ったり手紙を書いたりするという、直接交流の機会を設けることをしてきませんでした。最初の本がたまたまその機会をもつことがないまま書かれ、それが私のスタイルになってきた、とでも言う他ないところがあります。
ところが今回、初めて手紙を送ってみることにしました。私は個人編集・発行の小さな雑誌(『飢餓陣営』)を作っているのですが、そこでは津久井やまゆり園事件に関する記事が集中的に掲載されており、手紙を添えて送ったのです。どうして突然そんなことを思い立ったか、理由を簡単に書けば次のようになります。
公判が近くなるにつれて、植松被告が精神的に不安定になっていると報道されるようになりました。たとえば読売新聞の、二〇一九年七月二六日の記事。「植松被告『死にたくない』」と見出しが打たれ、「裁判を気にするそぶりも見せている」と書かれています。記事によれば、初公判の日程が決まった六月には、死刑判決が出ても控訴はしないというそれまでの発言から、「死刑は避けたい、一審で判決が出ても確定ではない」と、その内容を変えたともいいます。
この記事が考えるきっかけになりました。というのは、彼はそれまで多くの報道関係者や識者・学者と面会をし、一つとして揺らぐことなく、自身の「使命感」や「信念」を饒舌に語り続けてきました。面会が可能になって以来、多くのメディアや識者による「接見合戦」の観を呈していましたが、私はそこから窺うことのできる植松死刑囚に対して疑念を抱いていました。
彼はあれほど多くの人の命を奪い、また深い傷を負わせた人間です。「使命感」がいかに強固だったとしても、心が無傷なままで済むはずはありません。人の命を奪うという行為は、それを行った者にもなんらかの心的外傷を負わせることは、これまでの戦争心理学などの研究で明らかになっています。
また大谷恭子弁護士は『死刑事件弁護人――永山則夫とともに』(悠々社、一九九九年)のなかで、次のように書いています。
被告人は時に事実を語らないし、語れないこともある。自己の犯してしまった結果の重大さに打ちのめされ、言葉を失ってしまうのである。思い出すことがつらい、忘れてしまいたい、できたら消してしまいたい事実なのである。(略)あの連合赤軍の気丈な永田洋子さんも、病気のせいもあるが、事実関係の話になると嘔吐した。十数年も経ってからである。(五〇頁)
ここに書かれている姿が、いかに「凶悪犯」といえども、私にとっての通常の、ありうるはずの姿でした。彼もまた、わずかなりともこうした苦悶に襲われているのではないか。そう考えていたのですが、接見した記者たちが報じる植松死刑囚には、そうした様子がまったく窺われません。それが不思議でした。
私が拘置所の彼の元に手紙を入れたのは、読売新聞の記事の一カ月後の八月三〇日、気弱になっているかどうかを確かめたい、そう考えたからでした。少しでも後悔を覚えているのなら、それをこのさい認めてしまったらどうか。余計なこととは知りつつ、そんなことも書き加えていたはずです。しかし、私の疑念は一蹴されることになります。
なぜ「母親」なのか
思いもよらぬことに植松死刑囚から返信が寄せられたのですが、それは以下のようなものでした。
佐藤幹夫様
御手紙を拝読致しました。
家族会の大月和真会長はとても良い人だと知っているので一概に云えませんが、「障害児の家族と話し合いはできない」と考えております。
大変恐縮ですが、佐藤さんの母親、大月さんの奥様は重度障害者と関わり、過労で亡くなったと考えるのが自然ではないでしょうか。
乱文乱筆、失礼致します。お体どうぞご自愛下さいませ。
二〇一九年九月八日 植松聖
これで全文です。そして手紙はこの一通だけです。これだけでは分かりにくいかもしれませんので、必要なことのみを補足しておきます。
私が同封した『飢餓陣営』には、障害をもつ子の父親たちによるシンポジウムの記事が掲載されていました(注2)。シンポジストとして登壇した津久井やまゆり園の親の会の会長である大月氏は、そこでご自身の奥様をがんで亡くしたことを語っており、植松死刑囚の文面の「大月さんの奥様」云々はそのことを指しています。
また「佐藤さんの母親」云々とは、同じ号に掲載した私の父親による手記を指しています。詳細は後述しますが、そこでは重い障害を負って生誕することになった弟をめぐって、両親による懸命の看病と介護、早すぎる母親の死、弟が東京の島田療育園へ入所し他界するまでの経緯などが書かれています。一九六〇年代、重い障害のある子どもをもった家族がどんなふうに生きなくてはならなかったか、その実情にも触れているのですが、手記についての植松死刑囚の感想が、「大変恐縮ですが」以降の件です。
たった一回だけ交わされた、便箋一枚ほどの短い手紙です。何十回と手紙のやり取りや接見をした人たちから見れば、まるで話にならないものでしょう。しかし短い文面に、重要なことが書かれています。それは三点あります。
一つは、「重度障害者と関わり、過労で亡くなったと考えるのが自然」であるとされ、しかもその対象が、私と大月氏ともに「母親」である点です。「重度の障害者は、家族に不幸しかもたらさない」と彼はくり返しました。そのときに引かれる例が、決まったように「疲れ切った母親の表情」でした。
つまりは「重度障害者」と「不幸」と「疲れ切った母親」とは、切っても切り離せない関係になっているのです。「重度障害者の最大の犠牲者となるのは母親である」という見解は、彼の持論中の持論です。なぜ「母親」なのか。なぜそこまでこだわるのか。しかし植松死刑囚自身はこれ以上のことを述べていません。
本人の手紙を読んでも、接見した記者や識者たちの記録を読んでも、「疲れ切った母親」問題は出てきません。この事件についての書籍は山のように出版されていますが、やはり一つとして触れられていません。関心が向けられていないようなのです。裁判にあっても、この問題についての質問がなされると、本人と弁護人によって、たちどころに拒絶されました。傍聴していていささか異様な印象を受けたほどです。
このことが、短い返信の中にはっきりと書かれています。
2 「障害児・者の家族とは話ができない」のはどうしてか
平行線は解消できるのか
二つ目は、「障害児の家族と話し合いはできない」と考えていることです。障害をもつ人の家族は、自分(植松死刑囚)の考えを理解しないだろうし、受け入れるはずもない、だから話しても無駄である、話す必要もない。そういう明確な意思表明です。ここには重要で、とても厄介な問題があります。
事件後、「障害をもっていようとも自分たちも同じ人間であり、懸命に生きているのだ」という当事者本人による訴えがありました。家族や彼らにかかわる人間からの「彼らによってこそ自分たちはたくさんのことを学び、勇気づけられ、支えられている」という声がメディアに溢れました。その訴えが、「障害児の家族と話し合いはできない」と考えている植松死刑囚(とその賛同者たち)にとって、どこまで通じるのかという問題です。
もちろん私は、こうした主張が社会に広く行きわたっていくことの重要性を誰よりも理解しているつもりです。この二〇年にわたって私が書き続けてきたものは、そのことに費やされてきたと言っても言いすぎではないほどです。しかし植松死刑囚(たち)に向けた言葉として、どこまで力をもつことができるのか、心もとなさを感じていました。
同様の問題意識を明瞭に示したのは、ただ一人、立命館大学大学院教授の立岩真也氏(社会学・障害学)だけでした。立岩さんは次のように書いていました(注4)。
相模原での事件についての本で、自らの(その子の)肯定性によって自ら(その子)の生命・生活の正当性を言う必要などないのだと言った人たちのことを紹介し、そちらの側を私は支持すると述べた。/(略)/
それは、その容疑者〔植松死刑囚〕のように語ったり感じたりする人たちに、そして自分たちに、どのようにものを言うのかということでもある。例えば、美しい言葉が、この事件、その容疑者に「効く」だろうかということだ。例えばその容疑者(のような人)は、「そのようにあなたが(自分の子を)言いたい気持ちは理解はできるが」「あなたがそう思うあるいはそう言いたいその事実は否定しないが」と言い、「私にはそう思えない」「きれいごとを信じようとしている」と言う。「世の光〔糸賀一雄〕」と思う人にもさらに言い分はあるだろうが、話は平行線を辿ることになるだろう。(二〇八頁)
慎重に、幾重にも防波堤を施した立岩氏らしい書きぶりですが、ここでの主旨を私なりに端的に言い直せば、「障害者は「世の光」である」といった類の言葉を何度くり返しても、植松死刑囚たちには届かない、平行線をたどることになる、ということです。
この平行線の問題をもう少し一般的な場所へ連れ出せば、次のような議論として現れることになります。『生命倫理学と障害学の対話――障害者を排除しない生命倫理へ』(注5)から引用してみます。
生命倫理学は医療において、十分な情報を得た上での個人の選択を優先する。たとえその選択が患者の死につながるものであるような場合であってもそのことに変わりはない。それに対して、障害学者や障害者運動の活動家は、一つの集団としての障害者たちを守ることを優先する。たとえ、そうした障害者のコミュニティーにとっての利害が、障害をもった個々のメンバーの選択と相容れないような場合においても、前者を優先するのが彼のやり方である。(二一―二二頁)
こんなふうに、生命倫理学と障害学者・障害者運動とは、ことごとく対立するというのです。生命倫理学者の代表的な一人がピーター・シンガーです。障害学者や障害者コミュニティの側の人間は、生命倫理学者に対して強い不信感をもっているといいます。双方がどんな主張をし、なぜそれほど深い対立を見せるのか、第Ⅳ部で詳述しますが、植松死刑囚の「障害児の家族と話し合いはできない」という言葉は、ここに通じていく内容を含んでいます。
3 『帰還兵はなぜ自殺するのか』、「植松聖」はなぜ自殺しないのか
「人は人を殺せない」というシステム
手紙から窺えることの三つ目は、植松死刑囚に、心理的ダメージがいささかも感じられない、というそのことです。
裁判の傍聴の目的の一つはこの点だったのですが、公判での応答を見聞きした限り、「加害者であることによって生じるPTSD」という類の動揺は、一切窺うことはできませんでした。裁判で証言台に立った精神鑑定医からも、そのような可能性の示唆は皆無でした。
印象はむしろ逆で、公判廷での彼は、傍聴人に向かって(とくに顔なじみとなったメディア関係者に向かって)、生涯で最大の「晴れ姿」を誇示するような、そんな様子さえ見せていたのです。私のこれまでの傍聴経験にあって、あのように晴れがましく公判に臨み、手柄話でも語るように質問に答えていく被告人は皆無でした。
先ほど大谷弁護士の文章を引用しましたが、もう一つ、戦時における兵士たちの心理を詳細に解剖した、デーヴ・グロスマンの『戦争における「人殺し」の心理学』(注6)から紹介します。グロスマンは米国陸軍に二三年間所属し、陸軍士官学校で心理学と軍事社会学の教鞭をとったという、戦闘の実際と、軍事というシステムと社会の関係と、兵士の心理という問題に通暁した人物です。その彼が「人間のうちには、自分自身の生命を危険にさらしても人を殺すことに抵抗しようとする力がある」と言い、銃剣戦のような至近距離での「殺し合い」には重要な三つの心理的要因が加わってくる、と次のように書いています。
第一に、銃剣距離まで敵に接近した場合、兵士のほとんどは敵を串刺しにしようとはせず、銃床またはその他の手段によって敵を戦闘不能にしたり、負傷させたりする。第二に、銃剣を使用した場合、それが近距離で生じる行為であるために、その状況には深刻なトラウマの可能性がひそんでいる。そして第三に、銃剣で人を殺すことの抵抗感は、そんな殺されかたにたいする恐怖と完全に等価である。(二一五頁)
相手に銃剣を突き刺すときの泣くような悲鳴や、口から噴き出す血、飛び出す目、「そのすべてが、死ぬまで抱えてゆかねばならない記憶の一部になるのだ。これが刃物による殺人」というものであるといいます。しかし植松死刑囚にはこのようなためらいは皆無です。
戦争の銃撃戦において、多くの兵士が狙いを外して撃っている、敵兵に照準を向けて撃てる兵士は一割半に満たなかった、という事実が明らかになったといい、次のような記述があります。
兵士の訓練/条件づけ(マーシャルの研究に基づくアメリカ陸軍訓練プログラムは、第二次大戦時に五~二〇パーセントだった個々の兵士の発砲率を、朝鮮戦争で五五パーセント、ベトナム戦争では九〇~九五パーセントに向上させた)。(三〇七頁)
しかしそのことによって兵士たちが帰還後、どれだけの戦場トラウマに苦しめられることになったか。社会的不適応、凶悪犯罪、精神失調、自殺といった事態がヴェトナム戦争後に生起し、帰還兵たちのケアという問題が深刻な社会的課題となり、そこからアメリカで本格的なPTSDの研究が始まったといいます。しかし、指摘したように、植松死刑囚の手紙にはトラウマの可能性はわずかも見られません。
人間はめったに「人を殺せない」、もともとそのようなシステムが内在しており、生育の過程でそれがより確かなものとなっていく。私はそう考えるようになっていったのです。発達の過程とは、共感力や共有する力を獲得していくプロセスでもあるわけですが、「人を殺さないシステム」とはまさにこのことです。
植松死刑囚は衝動に駆られ、あるいは偶発的な出来事をきっかけとして犯行に及んだのではありません。入念に計画し、準備を整え、ほぼ計画どおりに行動しています。しかも一時間以上にもわたって集中力を持続させていることが、公判での証言から分かります。実行時、あるいはその前後、「人を殺すことに抵抗しようとする力」は、植松死刑囚にあってはまったく作動していません。
あるいは『帰還兵はなぜ自殺するのか』(注7)というイラク・アフガン戦争の兵士たちを主題にしたノンフィクションがあります。著者によれば、帰還兵士二〇〇万人のうち五〇万人(およそ四人に一人です)が精神に深い傷を負っており、毎年二五〇人以上が自殺しているといいます。いかに深いダメージを負うことになるか、通常の市民生活に戻ることがどれほど困難か、その現状を伝えるべく兵士や家族に取材をして書かれた本です。
そんなわけで、人は人をなかなか殺せない、そのようなシステムを本来はもっている。もしそのシステムを破壊するような人格改造が加えられるならば、社会生活が不可能になるほど、人格そのものが深い傷を負ってしまう。この事情は「植松聖」といえども同様のはずである。しかし「人を殺すことに抵抗しようとする力」が、植松死刑囚にあってはまったく働いていない。その後の心理においても、動揺や外傷の痕跡がまるで見られない。この点をどのように考えればよいのか、私には重要な問いでした。
もちろん、「殺人者の心理」など、まして植松死刑囚のような桁外れの殺人を犯した人間の心理など、凡人の理解が及ぶものではないことは承知していますが、こんなことが、あの一通だけの短い手紙から私が考え続けてきたことでした。
グロスマンの著書では、「兵士の二パーセントは」「殺人行動にともなうトラウマを経験しないらしい」といい、その一群を「攻撃的精神病質者」と名付けています。グロスマンに倣えば植松死刑囚もここに該当するのかもしれませんが、この本の目的は心理学的な診断名を付すことではなく、「植松聖」という人間を、私自身の言葉で掘り下げることはできないかということです。あえて言えば「人間学的犯罪論」とでもいうべき試みであり、本書の第Ⅲ部で、さまざまな角度からその検討を加えています。
この事件の深層に流れる「戦争」という主題
もう一つ、次のことも書き添えておきましょう。事件の決行前に衆議院議長に宛てたという例の手紙についてです。
政治が戦争の「顔」を強く現し始めたときに、戦争の「顔」を剝き出しにした男が、自分は優秀なコマンドだ、いつでも戦争をする用意があるという手紙を持って、政治の中枢に乗り込んでいった。しかもそれが福祉のなかから現れた。これはいったいなんだろう。……植松死刑囚の手紙を読んだときの衝撃と困惑は、次第にそんな言葉になっていきました。
「戦争と福祉と優生思想」。これがこの事件の主題のようだと私は受け取ったのですが、どこからどう切り込んでいけばいいのか、しばらく身動きの取れない状態が続きました。第Ⅰ部のようなかたちでまとめられるまでには、二年ほどの歳月を要しました。
そして本書の草稿を書き終える直前になって、ほんとうに戦争が始まったのです。ロシアによるウクライナへの侵攻です。すぐさま、ロシア‒プーチンのおよそ時代錯誤的な蛮行を非難する報道が溢れました。砲弾をのがれて逃げまどうウクライナの人々の姿に釘付けになりながら、何度見ても言葉が詰まって出てきませんでした。やがて、ロシア兵による民間人の虐殺、拷問、レイプなどが次々と明らかになっていきます。そんな最中の二〇二二年四月二八日、突然、拘置所にいる植松死刑囚が「再審請求」を出したと報じられたのです。報道は今のところそれだけで、続報はありません。戦争の渦中にあることを見計らったかのような再審請求。この符合はまったくの偶然なのか、何かしらの思惑があるのか。皆目見当はつかないのですが、偶然だとしてもいかにも「植松聖」らしいと感じさせます。
そして五月一二日には、戦争犯罪人として法廷に呼び出されたロシア兵の初公判が開かれたと報じられました。民間人を背後から射殺したとされた兵士は二一歳だといい、子どものような顔立ちをしていました。いったん戦争が始まれば、兵士たちを人間ではない別の生きものに変えてしまう、それが、人と人とが殺し合う戦争の本質なのだ、と改めて思い知らされる報道が続きました。
多くの人にとって、津久井やまゆり園事件はほんとうに遠い過去の出来事になったのでしょうか。二〇一六年七月二六日に、降って湧いたように私たちの前に現れて衝撃を与えた津久井やまゆり園事件。コロナ禍の渦中にある二〇二二年二月二四日、突然始まって世界中を震撼させているロシア‐ウクライナ戦争。私がこの六年間を事件と「植松聖」という存在にどっぷりと浸かりきって過ごしてきたから、余計そう感じるのかもしれませんが、ひとつながりの出来事のように思えてならないのです。
それにしても、なぜこれほどまでに社会は「明るい無関心」を隠そうとしないのでしょうか。もはや、抗議することを忘れてしまっているのでしょうか。本書への入り口としてこのようなことも記しておきたいと思います。
注
1 この時期はまだ被告人でしたが、現在は死刑囚であり、こちらを用いました。
2 『飢餓陣営49』(二〇一九年七月)所収、「父親たちは語る―なぜ施設を望むのか、あるいは望まないのか」(「津久井やまゆり園事件を考え続ける対話集会」より。発言者:大月和真、尾野剛志、神戸金史、岡部耕典)
3 私が入手した限りの単行本だけでも、次のようになります(出版年月順)。
立岩真也・杉田俊介『相模原障害者殺傷事件』(青土社、二〇一六年一二月)、朝日新聞取材班『妄信 相模原障害者殺傷事件』(朝日新聞出版、二〇一七年六月)、堀利和編著『私たちの津久井やまゆり園事件』(社会評論社、二〇一七年九月)、月刊『創』編集部編『開けられたパンドラの箱』(創出版、二〇一八年七月)、河東田博『入所施設だからこそ起きてしまった相模原障害者殺傷事件』(現代書館、二〇一八年七月)、井原裕『相模原事件はなぜ起きたのか』(批評社、二〇一八年七月)、渡辺一史『なぜ人と人は支え合うのか』(ちくまプリマー新書、二〇一八年一二月)、阿部芳久『障害者排除の論理を超えて』(批評社、二〇一九年三月)、高岡健『いかにして抹殺の〈思想〉は引き寄せられたか』(ヘウレーカ、二〇一九年四月)、雨宮処凛編著『この国の不寛容の果てに』(大月書店、二〇一九年九月)、堀利和編著『私たちは津久井やまゆり園事件の「何」を裁くべきか』(社会評論社、二〇二〇年三月)、月刊『創』編集部編『パンドラの箱は閉じられたのか』(創出版、二〇二〇年六月)、朝日新聞取材班『相模原障害者殺傷事件』(朝日文庫、二〇二〇年七月)、神奈川新聞取材班『やまゆり園事件』(幻冬舎、二〇二〇年七月)、雨宮処凛『相模原事件裁判傍聴記』(太田出版、二〇二〇年七月)、森下直貴・佐野誠編著『新版「生きるに値しない命」とは誰のことか』(中公選書、二〇二〇年九月)、森達也『U 相模原に現れた世界の憂鬱な断面』(講談社現代新書、二〇二〇年一二月)、小松美彦・聞き手今野哲男『増補決定版「自己決定権」という罠』(現代書館、二〇二〇年一二月)
4 立岩真也『病者障害者の戦後――生政治史点描』(青土社、二〇一八年)。
5 アリシア・ウーレット著、安藤泰至・児玉真美訳『生命倫理学と障害学の対話――障害者を排除しない生命倫理へ』(生活書院、二〇一四年)
6 デーヴ・グロスマン著、安原和見訳『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫、二〇〇四年)
7 デイヴィッド・フィンケル著、古屋美登里訳『帰還兵はなぜ自殺するのか』(亜紀書房、二〇一五年)
関連書籍
津久井やまゆり園事件 関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
